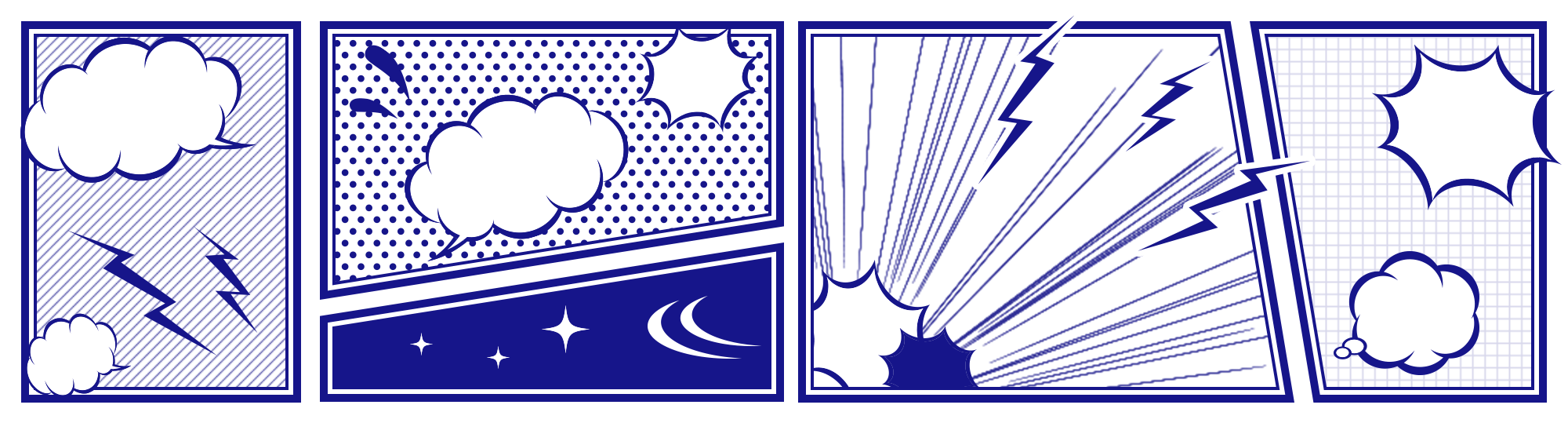友達の距離
おなまえ
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
「みょうじさんって王馬くんと付き合ってるの?」
そんな質問をされるのはもう何度目だろうか。
たまたま同じクラスになって、たまたま席が前後になって、たまたま仲良くなった王馬くんと私。
私たちのお年頃で男女がよく一緒にいるとなると、どうしても恋愛的な発想になる人は少なくない。
本科生の間では変わり者として通っている王馬くんだが、予備学科生達からは妙に人気があってファンクラブのようなものまであるらしい。
今も私の目の前にいる予備学科生の名前も知らない女子生徒たちは、鋭い敵意の籠った視線を私に向けている。
多分、彼女らはその王馬くんファンクラブなるものの人達なんだろう。
「付き合ってないよ?」
「…そうなの?だったらあんまりベタベタしないでよ、紛らわしい」
「そんなことしてないと思うけど…」
「してるから!…ちゃんと気をつけてよね」
キッと私を睨みつけながら、彼女らはそんな捨て台詞と共に退散して行った。
そんなに好きなら告白でもすればいいのに。
そう思ったけれど、これに関しては私が言えたことではないからと思考を心の奥底に引っ込めた。
「うわー、女の子の怖いとこ見ちゃったなー」
どこから見ていたのか、こうなった元凶である王馬くんが影からひょっこり現れた。
居合わせたなら助けてよと思ったが、変に出てこられても余計ややこしい事態になっていたかもしれない。
付き合ってるなんて嘘をつくくらいのことは、引っかき回したがりの彼ならやりかねないだろうから。
「みょうじちゃんお疲れー」
誰のせいだ思っているのかと嫌味とひとつでも言ってやりたくなるが、今この瞬間の彼の笑顔は私にだけ向けられたものなのだと思うとそれだけで満足してしまいそうだ。
惚れた弱みとは本当に恐ろしいものである。
「にしても、なんで毎回みょうじちゃんにばっか来るんだろうねー?直接オレのとこに来ればいいのに」
「なんだか私たちのこと勘違いしてるみたいだよ」
「ふーん、勘違いって?」
「その…付き合ってると思われてたっぽい」
そっかー、なんて王馬くんはなんでもない事のように呟いた。
私は口に出すのも少しドキドキしたのに、こんな風に些細なことで心を乱しているのは私だけなんだな…と分かりきっていたことに落ち込む。
「なるほどね、それでベタベタするな!なんて言われてたんだ」
「ベタベタなんかしてないのにね」
「そう?結構してると思うけどなー」
「えー、どこが?」
「こういうとことか」
言葉の意味が分からずにいると、王馬くんは一歩私に近づいて手を伸ばしてくる。
距離が近いことは時々あるけれど、その手はどこに向かっているのか。
緊張を悟られないよう注意しながらその行動の行く末を見守っていると、王馬くんは小さく笑って私の頭をぽんぽんと撫でた。
嬉しいような恥ずかしいような、むずむずとした気持ちになったけど、生憎こういった行動を日常的に行っていた記憶はない。
「…こういうとこも何も、別に普段こんなことしてないじゃん」
「にしし、バレた?」
じゃあこれからはしてもいい?なんて聞かれても、どう返せばいいか分からずに沈黙が流れる。
ただのからかい目的の冗談だと思い至るのに遅れてしまい、私が対応するよりも王馬くんが吹き出す方が早かった。
「ぷっ…くく、なんて顔してんの」
「べ、別になんでもないよ!」
「へー、じゃあなんでそんなに顔赤いの?」
ハッとして手を頬に当てると、手のひらから伝えられる熱が傍から見た自分の状況を教えてくれる。
多分きっと、顔が赤いのは本当のことなんだと。
「う…これは、その」
「んー?」
「き、急に近くに来たからびっくりしただけ!」
「あは、びっくりしたなら仕方ないね!」
王馬くんはそう言って、にししと笑った。
「とりあえず、明日からみょうじちゃんを1人にしないように頑張るね」
「どうして?」
「そうすればきっと、今日みたいなことにはならないでしょ?」
「うーん…でも、それだと卒業するまで毎日一緒にいなきゃいけなくなるかもしれないよ」
「いいじゃん、それはそれで!それとも、みょうじちゃんはオレと毎日一緒は嫌?」
顎を引いてわざとらしい上目遣いを作る彼の策略にまんまと引っかかりそうになる。
思わず息を飲んでしまった時点で引っかかったも同然な気もするけれど。
「な、何言ってんの…。もう、そうやってすぐからかうんだから」
「にしし、好きな子にはちょっかいかけたくなるのが男のサガってやつでしょ?」
「私は男じゃないからわかんない…ってちょっと待って、今なんて言った!?」
「んー?男のサガの話?」
「そうだけどそれより前の話!」
「オレと毎日一緒は嫌?」
「戻りすぎだから!」
「じゃあ…好きな子にちょっかいの話?」
王馬くんはふっと息を吐いて静かに微笑んだ。
私がどう返事するのかを試しているような余裕たっぷりの表情が癪だ。
それでも改めて好きな子というワードを聞いてしまうと、どうしても胸がざわざわして落ち着かない。
今の話の流れだと、その好きな子がまるで私なんじゃないかと思わずにはいられないから。
「正解?」
「…うん。そう、だけど…その」
「にしし、分かってるくせに分かんないふり?相変わらず嘘つくの下手だなー。今度オレが直々に嘘のつき方教えてあげよっか?なーんて嘘だけど!」
「や、違うから!そんな分かってるって言えるほど確信持てないだけで…」
「ふーん、オレは確信持ってるけどね」
「そりゃあ王馬くんのことなんだから当然でしょ」
「違う違う。みょうじちゃん、オレのこと好きなんだろうなーって」
「…え?」
なかなか告白してくれないから待ちくたびれちゃった、なんて言われてしまって頭が真っ白になる。
そのくせ顔だけはぽーっと熱くなってきて、多分きっと真っ赤なんだろうなと思うといたたまれない気持ちになった。
ついには「なんで知ってるの?」なんて、もう誤魔化しのきかない一言を自ら発してしまう始末。
「むしろなんで知らないと思ったの?」と逆質問されて、脳内はもうパニック状態だ。
というか、こういう恋愛イベントはもっとロマンチックなムードと一緒にやって来るものじゃないのだろうか。
恋愛経験が未熟であるが故の淡い妄想と現実の温度差の違いは予想以上だった。
「大丈夫?」
「大丈夫じゃないよ…」
「あらら…でも大丈夫じゃないとこ悪いんだけど、オレから一言だけいい?」
「…なに?」
「好きだよ」
ロマンなんて欠片もないシチュエーションだったはずなのに、そのたった四文字の言葉によって目の前に少女漫画のようなキラキラしたエフェクトがかかった気がする。
あれ、王馬くんってこんなに格好よかったっけ?なんてお決まりのセリフを心の中で呟いた。
「ちょっとー、無視?なんとか言ってよ」
王馬くんが口を尖らせてぶーぶー文句を言ってきたところで、ようやく現実に戻ってくることが出来た。
そうか、今私は告白されたんだ。
王馬くんが私に告白をして、それに私は何か対して返事を…。
王馬くんが?私に?告白??
やっと帰ってこられた現実では信じ難いようなことが起こっていたらしい。
喜びがじわじわと胸の内を侵略し始めたところではたと気付く。
王馬くんってこういう嘘でも平気でつきそうだよなぁ…と。
だって、これが現実なのだとしたらあまりにも都合が良すぎる。
喜ばせたところで実は嘘でしたと突き落とされる方がありがちな展開だと思った。
「あ、あははー、ありがとう嬉しいなー」
「何その棒読み。はいはい、どうせ信じてないんでしょ?あーあ、さすがのオレも傷ついちゃうなー」
「またまた…そうやって油断させてやっぱり嘘でしたって展開なんじゃないの?」
「ふーん、みょうじちゃんがそう思いたいならそういうことにすればいいじゃん。いたいけなオレのガラスのハートは今バキバキに粉砕されてるところだけどね」
「わ、大変だ。お医者さんに診てもらわないと」
「医者に治せるわけないじゃん。これはみょうじちゃんにしかどうにもできないの!」
王馬くんにしては珍しく1つの嘘に固執している。
いつもなら嘘だとバレた時点であっさりとネタばらしして次の嘘に備えてくるのに。
何かがおかしいと思いつつも、あくまで茶化したような物言いをする彼は普段の冗談を言い合っている時の様子と変わらない。
本当はどっちなの?さっきのは嘘?本当?
そう聞いて100%嘘偽りのない答えが返ってくる保障があるなら私は迷わず質問しているところだ。
今の一連の流れの目的が私を惑わせることだったなら、それはもう大成功をおさめている。
「はぁ、そんなに信じられない?」
「………え、もしかして本当なの?」
「ずっとそう言ってるじゃん!オレがみょうじちゃんに嘘つくと思う?」
「思うよ」
「たはー!そうだよね、実際つくもんね!」
「じゃあやっぱりさっきのも嘘なんだ…」
「だからー、今回のは嘘じゃないんだってば!」
「嘘だ」「嘘じゃない」のやり取りが何度か続き、やっぱり普段の王馬くんならここまでしないのではないかと思えてきた。
もしかすると今回の嘘に特別力を入れているだけ…ということなのかもしれないが、それだけの力作ならそもそも私に嘘と見抜かせないようにしてくるだろうし…。
嘘だなんだと言いつつ、私は王馬くんが好きなわけだから、やっぱり嘘ではなかったという真実の方が嬉しい。
そんな欲もあって私は「嘘だ」という自分の回答が正しいのか揺らぎ始めていた。
「も、もしかして本当に嘘じゃない…?」
「どっちだと思う?」
「うわ、ずるい」
「冗談だってば。…嘘じゃないよ、今回はホントに」
見たこともないような優しい笑顔を向けられて、思わず身体が固まってしまう。
そうかと思えば次の瞬間にはその表情をいつもの意地悪な笑みに変えて、彼は再度口を開く。
「それとも、みょうじちゃんにとっては嘘だった方がよかったの?」
答えなんて聞かなくても分かっているだろうに。
でも、きっと答えなかったらうるさいし。
心の中でそう自分に言い聞かせながら、分かりきった答えを告げるために私も口を開く。
「う、嘘じゃない…方がいい」
「にしし、知ってたけどね」
王馬くんが続けて何かを言おうとする素振りを見せた時、校舎中に下校を促すチャイムの音が鳴り響いた。
私たちはきょとんとした顔でしばし見つめ合い、どちらからともなく笑い声を上げる。
「あは、すっごいタイミング。…さて、そろそろ帰ろっか」
「うん」
寮までの帰り道を並んで歩く。
今までとは少しだけ違う距離感で。
そんな質問をされるのはもう何度目だろうか。
たまたま同じクラスになって、たまたま席が前後になって、たまたま仲良くなった王馬くんと私。
私たちのお年頃で男女がよく一緒にいるとなると、どうしても恋愛的な発想になる人は少なくない。
本科生の間では変わり者として通っている王馬くんだが、予備学科生達からは妙に人気があってファンクラブのようなものまであるらしい。
今も私の目の前にいる予備学科生の名前も知らない女子生徒たちは、鋭い敵意の籠った視線を私に向けている。
多分、彼女らはその王馬くんファンクラブなるものの人達なんだろう。
「付き合ってないよ?」
「…そうなの?だったらあんまりベタベタしないでよ、紛らわしい」
「そんなことしてないと思うけど…」
「してるから!…ちゃんと気をつけてよね」
キッと私を睨みつけながら、彼女らはそんな捨て台詞と共に退散して行った。
そんなに好きなら告白でもすればいいのに。
そう思ったけれど、これに関しては私が言えたことではないからと思考を心の奥底に引っ込めた。
「うわー、女の子の怖いとこ見ちゃったなー」
どこから見ていたのか、こうなった元凶である王馬くんが影からひょっこり現れた。
居合わせたなら助けてよと思ったが、変に出てこられても余計ややこしい事態になっていたかもしれない。
付き合ってるなんて嘘をつくくらいのことは、引っかき回したがりの彼ならやりかねないだろうから。
「みょうじちゃんお疲れー」
誰のせいだ思っているのかと嫌味とひとつでも言ってやりたくなるが、今この瞬間の彼の笑顔は私にだけ向けられたものなのだと思うとそれだけで満足してしまいそうだ。
惚れた弱みとは本当に恐ろしいものである。
「にしても、なんで毎回みょうじちゃんにばっか来るんだろうねー?直接オレのとこに来ればいいのに」
「なんだか私たちのこと勘違いしてるみたいだよ」
「ふーん、勘違いって?」
「その…付き合ってると思われてたっぽい」
そっかー、なんて王馬くんはなんでもない事のように呟いた。
私は口に出すのも少しドキドキしたのに、こんな風に些細なことで心を乱しているのは私だけなんだな…と分かりきっていたことに落ち込む。
「なるほどね、それでベタベタするな!なんて言われてたんだ」
「ベタベタなんかしてないのにね」
「そう?結構してると思うけどなー」
「えー、どこが?」
「こういうとことか」
言葉の意味が分からずにいると、王馬くんは一歩私に近づいて手を伸ばしてくる。
距離が近いことは時々あるけれど、その手はどこに向かっているのか。
緊張を悟られないよう注意しながらその行動の行く末を見守っていると、王馬くんは小さく笑って私の頭をぽんぽんと撫でた。
嬉しいような恥ずかしいような、むずむずとした気持ちになったけど、生憎こういった行動を日常的に行っていた記憶はない。
「…こういうとこも何も、別に普段こんなことしてないじゃん」
「にしし、バレた?」
じゃあこれからはしてもいい?なんて聞かれても、どう返せばいいか分からずに沈黙が流れる。
ただのからかい目的の冗談だと思い至るのに遅れてしまい、私が対応するよりも王馬くんが吹き出す方が早かった。
「ぷっ…くく、なんて顔してんの」
「べ、別になんでもないよ!」
「へー、じゃあなんでそんなに顔赤いの?」
ハッとして手を頬に当てると、手のひらから伝えられる熱が傍から見た自分の状況を教えてくれる。
多分きっと、顔が赤いのは本当のことなんだと。
「う…これは、その」
「んー?」
「き、急に近くに来たからびっくりしただけ!」
「あは、びっくりしたなら仕方ないね!」
王馬くんはそう言って、にししと笑った。
「とりあえず、明日からみょうじちゃんを1人にしないように頑張るね」
「どうして?」
「そうすればきっと、今日みたいなことにはならないでしょ?」
「うーん…でも、それだと卒業するまで毎日一緒にいなきゃいけなくなるかもしれないよ」
「いいじゃん、それはそれで!それとも、みょうじちゃんはオレと毎日一緒は嫌?」
顎を引いてわざとらしい上目遣いを作る彼の策略にまんまと引っかかりそうになる。
思わず息を飲んでしまった時点で引っかかったも同然な気もするけれど。
「な、何言ってんの…。もう、そうやってすぐからかうんだから」
「にしし、好きな子にはちょっかいかけたくなるのが男のサガってやつでしょ?」
「私は男じゃないからわかんない…ってちょっと待って、今なんて言った!?」
「んー?男のサガの話?」
「そうだけどそれより前の話!」
「オレと毎日一緒は嫌?」
「戻りすぎだから!」
「じゃあ…好きな子にちょっかいの話?」
王馬くんはふっと息を吐いて静かに微笑んだ。
私がどう返事するのかを試しているような余裕たっぷりの表情が癪だ。
それでも改めて好きな子というワードを聞いてしまうと、どうしても胸がざわざわして落ち着かない。
今の話の流れだと、その好きな子がまるで私なんじゃないかと思わずにはいられないから。
「正解?」
「…うん。そう、だけど…その」
「にしし、分かってるくせに分かんないふり?相変わらず嘘つくの下手だなー。今度オレが直々に嘘のつき方教えてあげよっか?なーんて嘘だけど!」
「や、違うから!そんな分かってるって言えるほど確信持てないだけで…」
「ふーん、オレは確信持ってるけどね」
「そりゃあ王馬くんのことなんだから当然でしょ」
「違う違う。みょうじちゃん、オレのこと好きなんだろうなーって」
「…え?」
なかなか告白してくれないから待ちくたびれちゃった、なんて言われてしまって頭が真っ白になる。
そのくせ顔だけはぽーっと熱くなってきて、多分きっと真っ赤なんだろうなと思うといたたまれない気持ちになった。
ついには「なんで知ってるの?」なんて、もう誤魔化しのきかない一言を自ら発してしまう始末。
「むしろなんで知らないと思ったの?」と逆質問されて、脳内はもうパニック状態だ。
というか、こういう恋愛イベントはもっとロマンチックなムードと一緒にやって来るものじゃないのだろうか。
恋愛経験が未熟であるが故の淡い妄想と現実の温度差の違いは予想以上だった。
「大丈夫?」
「大丈夫じゃないよ…」
「あらら…でも大丈夫じゃないとこ悪いんだけど、オレから一言だけいい?」
「…なに?」
「好きだよ」
ロマンなんて欠片もないシチュエーションだったはずなのに、そのたった四文字の言葉によって目の前に少女漫画のようなキラキラしたエフェクトがかかった気がする。
あれ、王馬くんってこんなに格好よかったっけ?なんてお決まりのセリフを心の中で呟いた。
「ちょっとー、無視?なんとか言ってよ」
王馬くんが口を尖らせてぶーぶー文句を言ってきたところで、ようやく現実に戻ってくることが出来た。
そうか、今私は告白されたんだ。
王馬くんが私に告白をして、それに私は何か対して返事を…。
王馬くんが?私に?告白??
やっと帰ってこられた現実では信じ難いようなことが起こっていたらしい。
喜びがじわじわと胸の内を侵略し始めたところではたと気付く。
王馬くんってこういう嘘でも平気でつきそうだよなぁ…と。
だって、これが現実なのだとしたらあまりにも都合が良すぎる。
喜ばせたところで実は嘘でしたと突き落とされる方がありがちな展開だと思った。
「あ、あははー、ありがとう嬉しいなー」
「何その棒読み。はいはい、どうせ信じてないんでしょ?あーあ、さすがのオレも傷ついちゃうなー」
「またまた…そうやって油断させてやっぱり嘘でしたって展開なんじゃないの?」
「ふーん、みょうじちゃんがそう思いたいならそういうことにすればいいじゃん。いたいけなオレのガラスのハートは今バキバキに粉砕されてるところだけどね」
「わ、大変だ。お医者さんに診てもらわないと」
「医者に治せるわけないじゃん。これはみょうじちゃんにしかどうにもできないの!」
王馬くんにしては珍しく1つの嘘に固執している。
いつもなら嘘だとバレた時点であっさりとネタばらしして次の嘘に備えてくるのに。
何かがおかしいと思いつつも、あくまで茶化したような物言いをする彼は普段の冗談を言い合っている時の様子と変わらない。
本当はどっちなの?さっきのは嘘?本当?
そう聞いて100%嘘偽りのない答えが返ってくる保障があるなら私は迷わず質問しているところだ。
今の一連の流れの目的が私を惑わせることだったなら、それはもう大成功をおさめている。
「はぁ、そんなに信じられない?」
「………え、もしかして本当なの?」
「ずっとそう言ってるじゃん!オレがみょうじちゃんに嘘つくと思う?」
「思うよ」
「たはー!そうだよね、実際つくもんね!」
「じゃあやっぱりさっきのも嘘なんだ…」
「だからー、今回のは嘘じゃないんだってば!」
「嘘だ」「嘘じゃない」のやり取りが何度か続き、やっぱり普段の王馬くんならここまでしないのではないかと思えてきた。
もしかすると今回の嘘に特別力を入れているだけ…ということなのかもしれないが、それだけの力作ならそもそも私に嘘と見抜かせないようにしてくるだろうし…。
嘘だなんだと言いつつ、私は王馬くんが好きなわけだから、やっぱり嘘ではなかったという真実の方が嬉しい。
そんな欲もあって私は「嘘だ」という自分の回答が正しいのか揺らぎ始めていた。
「も、もしかして本当に嘘じゃない…?」
「どっちだと思う?」
「うわ、ずるい」
「冗談だってば。…嘘じゃないよ、今回はホントに」
見たこともないような優しい笑顔を向けられて、思わず身体が固まってしまう。
そうかと思えば次の瞬間にはその表情をいつもの意地悪な笑みに変えて、彼は再度口を開く。
「それとも、みょうじちゃんにとっては嘘だった方がよかったの?」
答えなんて聞かなくても分かっているだろうに。
でも、きっと答えなかったらうるさいし。
心の中でそう自分に言い聞かせながら、分かりきった答えを告げるために私も口を開く。
「う、嘘じゃない…方がいい」
「にしし、知ってたけどね」
王馬くんが続けて何かを言おうとする素振りを見せた時、校舎中に下校を促すチャイムの音が鳴り響いた。
私たちはきょとんとした顔でしばし見つめ合い、どちらからともなく笑い声を上げる。
「あは、すっごいタイミング。…さて、そろそろ帰ろっか」
「うん」
寮までの帰り道を並んで歩く。
今までとは少しだけ違う距離感で。
1/1ページ