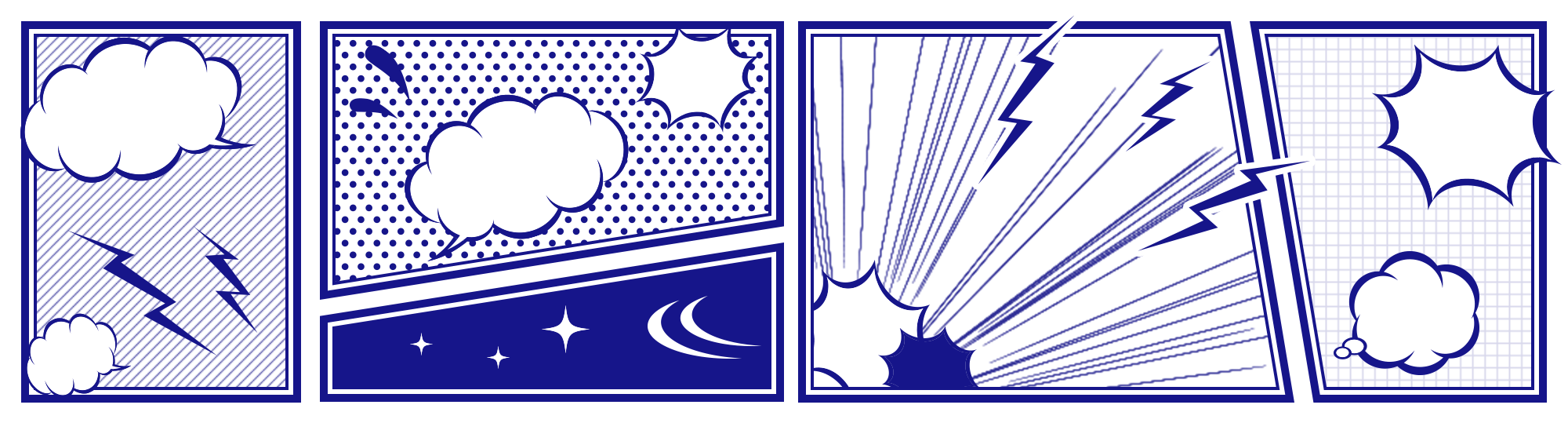お願いを聞いた理由
おなまえ
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
「ねぇ、お願い!」
大量のプリントの束を挟んで向かい合い、王馬くんを拝むように両手を合わせて頭を下げる。
彼は私とプリントとを何度か交互に見つめた後、大きなため息をついてから口を開いた。
「…あのさ、どう考えてもオレより茶柱ちゃんかゴン太の方が適任だと思わない?」
「ぐっ…」
本当にその通り、としか言いようがなかった。
このプリントの束を運ぶのを手伝って、という紛うことなき肉体労働には、誰が聞いたって王馬くんの言う2人の方が適任だ。
もちろん、それは私にだって分かっている。
それでも彼にお願いをしたのは、なんというか…日直でもないのにこんな手伝いを押し付けられたのだから、せめて好きな人と過ごす大義名分にしてやろう、等という100%邪な思いからだ。
「…どうしても、だめ?」
これでダメなら、諦めて茶柱さんに声をかけてみよう。
きっと、彼女なら快く受け入れてくれるんだろうな。
そう思いつつも、やっぱり王馬くんと一緒だったらなぁ、という願いも捨てきれず、半ば呆れ顔の彼としばし目を合わせる。
なんとなく、先に目を逸らすと負けになるような気がして耐えていると、彼は意外にもその我慢比べには乗ってこず、大きなため息とともに視線を逸らした。
「はぁ…。これ、分かっててやってんのかなぁ…」
「ん?えっと…?」
「あーもう、なんでもない!いいよ、運ぶの手伝うから。それでいいんでしょ?」
「王馬くん、ありがとう!」
王馬くんはぼそぼそと何かを呟いたかと思えば、なんでもない!と大声を出してから雑にプリントの束を手に取った。
半分より少し多めの束を抱えながら「どこまで運ぶの?」と不機嫌顔な彼に続いて、私も残りの束を手に取る。
「理科準備室!」
「はいはい。じゃあさっさと行くよ」
すたすたと歩き始めた王馬くんを追いかけて教室を出る。
隣に並ぼうと足を早めてみるが、思ったよりも歩くスピードが違うらしい。
自分なりの精一杯の早歩きをもってして、ようやく斜め後ろの位置をキープできるか…という速度だった。
少し歩いたところで、必死に追いつこうと足を動かす私に気がついたのか、王馬くんはまた小さくため息をついて歩みを遅くした。
「……みょうじちゃんさ」
「う、うん?」
「茶柱ちゃんと仲良いじゃん?」
「まぁ…そうだね」
「なんでオレに頼んだの?」
「…なんでってこともない、けど」
「ふーん、そっか」
王馬くんは呟くようにそう言うと、それきり黙り込んでしまった。
放課後の廊下に、私と彼の足音だけが響き渡る。
もしかして迷惑だっただろうか。
そもそも、ただの雑用に巻き込んでしまって嬉しいと思う人なんてそういないだろうけど。
…やっぱり、1度断られた時点で潔く諦めるべきだったのかもしれない。
無言で足音ばかりを聞いているとどんどん不安が広がって、謝らなければと足を止めた。
「ご、ごめん!…怒った?」
「え?あー、別に。…っていうか、怒るくらいならそもそも引き受けないでしょ」
一瞬きょとんとした顔でこちらを見ていた王馬くんが、「みょうじちゃんはバカだなぁ」と言っていつものように笑う。
それだけで先程までの不安はどこへやら、たまにはこんな雑用も悪くないかもしれない、なんて調子のいいことを思ってしまった。
「よし、終わりー!」
「ふぅ…ありがとう、王馬くん。ほんと助かったー」
「にしし、別にいいよ。お礼期待してるねー」
「えぇっ!?う、うーん…今月金欠だから手加減してもらえると…」
「はぁ、嘘に決まってるでしょ?ホント、みょうじちゃんはバカだなぁ」
いい加減、簡単な嘘くらい見抜いてよ。
王馬くんはそう言って笑う。
そんなの出来るわけないでしょ、と抗議すれば、それもそうだね、とまたバカにしたように鼻で笑われた。
「王馬くん、すぐそうやって意地悪言う」
「何言ってんの。そんなオレをわざわざ狙い撃ちしてきたのはみょうじちゃんでしょ」
「そっ…そんなことないよ。暇そうにしてたから声掛けただけで」
「えー、ホントかなー?怪しいなー?」
後ろめたさしか感じないことを言われ、咄嗟に顔を逸らした。
王馬くんはニヤニヤとした表情で私の顔を追うように視界に入ってくる。
また顔を逸らして、それを追いかけてきて、というのを何度か繰り返し、不意に目が合った瞬間私たちは同時に吹き出してしまった。
「ぷっ…あははは!」
「あはは、もう…ふふ、意味分かんない!」
「みょうじちゃんのせいでしょ!…あー、笑った笑った」
「えー、私のせいなの?」
「そうだよ?みょうじちゃんがオレに手伝わせるから」
「そんなに遡るんだ!?」
意味の分からないやりとりにお腹が痛くなるほど笑い合ってから、荷物を取りに教室へと戻り始める。
今度は最初からずっと歩く速度が同じくらいで、置いていかれそうになることはなかった。
「王馬くんって意外と優しいよね」
「意外と、の部分要る?」
「そこが重要なポイントでしょ」
「うわ、心外ー。みょうじちゃん、オレのこと優しくないと思ってたんだ」
「お、思ってない!思ってないよ!?」
「…じゃあどう思ってんの?」
並んで廊下を歩いていた王馬くんの足が止まる。
反応が遅れて数歩先へ進んでしまった私が振り返ると、回答を促すように彼の視線が送られてきた。
「どう…って、優しくて面白い人?…あ!あとは個性的とか」
「ふーん、それだけ?」
「それだけってことはないけど」
「じゃあ、他に思ってること教えてよ」
王馬くんが一歩踏み出すと、私たちの間の距離が少し縮まった。
教えて、なんて言われても。
大事なクラスメイトだとか、実は頭が良いだとか、本当に心の真ん中にある二文字の言葉をわざと避けるようにして、彼に対しての自分の中のイメージを伝えてみる。
「…やっぱだめか」
王馬くんは小さな声でそう言って、「なんでもない!」と笑ってまた歩き出す。
「えっ?ねぇ、なんだったの今の?」
「なんでもないよー」
「本当に?もしかして、私の回答ズレてた?」
「そんなことないない」
「うわ、絶対嘘だ…!ねぇ、ちょっと待って」
歩き出した王馬くんはプリントを運び始めた時と同じくらい早くて、早歩きというよりは小走りに近い状態になりながら彼を追いかける。
「ね、王馬くんってば」
「なに」
「なんで、「なんでもない」って嘘つくの」
「…嘘ついてるのはさ、みょうじちゃんも同じでしょ?」
「えっ…ひゃあ!?」
ぴたりと足を止めた王馬くんの背中に勢い余ってぶつかってしまった。
前のめりになった彼がなんとか踏みとどまってくれたおかげで、私も転ばずには済んだようだ。
「いったー…もう、何やってんの」
「ご、ごめんね?」
「鈍いのは身体能力の方もなの?はぁ、勘弁してよねー」
「すみません……って、私別に鈍くないし!それに、「も」って何よ!」
「何って、どこもかしこも鈍いなーってこと」
いいから帰るよと、王馬くんはまた教室に向かって歩き始める。
それを追いかけて、私も彼の少し後ろを歩く。
言葉少なに教室までたどり着き、それぞれ荷物を取るために自席へと向かう。
先に荷物を回収し終えた王馬くんが教室を出ようとしているのを見つけて、私はその背中に声をかけた。
「王馬くん!今日はありがとう、嬉しかった!」
「はいはい。…あ、そうだみょうじちゃん」
「えっ、なに?」
「オレ、今日はみょうじちゃんのお願いだから聞いてあげたんだよ」
「えっ…え?」
「にしし。じゃ、また明日ね!鈍感女のみょうじちゃん」
王馬くんがひらひらと手を振って教室から出ていった後も、私はしばらくその場から動けずにいた。
彼の言葉の全てを都合良く解釈してしまいそうで、どこからが嘘でどこまでが本当なのかを必死に考える。
ああ…もう、明日どんな顔して学校に来ればいいのよ…。
今日の出来事を思い出しては赤くなる頬を押さえつけながら、明日への不安とほんの少しの期待を胸に帰路に着いた。
大量のプリントの束を挟んで向かい合い、王馬くんを拝むように両手を合わせて頭を下げる。
彼は私とプリントとを何度か交互に見つめた後、大きなため息をついてから口を開いた。
「…あのさ、どう考えてもオレより茶柱ちゃんかゴン太の方が適任だと思わない?」
「ぐっ…」
本当にその通り、としか言いようがなかった。
このプリントの束を運ぶのを手伝って、という紛うことなき肉体労働には、誰が聞いたって王馬くんの言う2人の方が適任だ。
もちろん、それは私にだって分かっている。
それでも彼にお願いをしたのは、なんというか…日直でもないのにこんな手伝いを押し付けられたのだから、せめて好きな人と過ごす大義名分にしてやろう、等という100%邪な思いからだ。
「…どうしても、だめ?」
これでダメなら、諦めて茶柱さんに声をかけてみよう。
きっと、彼女なら快く受け入れてくれるんだろうな。
そう思いつつも、やっぱり王馬くんと一緒だったらなぁ、という願いも捨てきれず、半ば呆れ顔の彼としばし目を合わせる。
なんとなく、先に目を逸らすと負けになるような気がして耐えていると、彼は意外にもその我慢比べには乗ってこず、大きなため息とともに視線を逸らした。
「はぁ…。これ、分かっててやってんのかなぁ…」
「ん?えっと…?」
「あーもう、なんでもない!いいよ、運ぶの手伝うから。それでいいんでしょ?」
「王馬くん、ありがとう!」
王馬くんはぼそぼそと何かを呟いたかと思えば、なんでもない!と大声を出してから雑にプリントの束を手に取った。
半分より少し多めの束を抱えながら「どこまで運ぶの?」と不機嫌顔な彼に続いて、私も残りの束を手に取る。
「理科準備室!」
「はいはい。じゃあさっさと行くよ」
すたすたと歩き始めた王馬くんを追いかけて教室を出る。
隣に並ぼうと足を早めてみるが、思ったよりも歩くスピードが違うらしい。
自分なりの精一杯の早歩きをもってして、ようやく斜め後ろの位置をキープできるか…という速度だった。
少し歩いたところで、必死に追いつこうと足を動かす私に気がついたのか、王馬くんはまた小さくため息をついて歩みを遅くした。
「……みょうじちゃんさ」
「う、うん?」
「茶柱ちゃんと仲良いじゃん?」
「まぁ…そうだね」
「なんでオレに頼んだの?」
「…なんでってこともない、けど」
「ふーん、そっか」
王馬くんは呟くようにそう言うと、それきり黙り込んでしまった。
放課後の廊下に、私と彼の足音だけが響き渡る。
もしかして迷惑だっただろうか。
そもそも、ただの雑用に巻き込んでしまって嬉しいと思う人なんてそういないだろうけど。
…やっぱり、1度断られた時点で潔く諦めるべきだったのかもしれない。
無言で足音ばかりを聞いているとどんどん不安が広がって、謝らなければと足を止めた。
「ご、ごめん!…怒った?」
「え?あー、別に。…っていうか、怒るくらいならそもそも引き受けないでしょ」
一瞬きょとんとした顔でこちらを見ていた王馬くんが、「みょうじちゃんはバカだなぁ」と言っていつものように笑う。
それだけで先程までの不安はどこへやら、たまにはこんな雑用も悪くないかもしれない、なんて調子のいいことを思ってしまった。
「よし、終わりー!」
「ふぅ…ありがとう、王馬くん。ほんと助かったー」
「にしし、別にいいよ。お礼期待してるねー」
「えぇっ!?う、うーん…今月金欠だから手加減してもらえると…」
「はぁ、嘘に決まってるでしょ?ホント、みょうじちゃんはバカだなぁ」
いい加減、簡単な嘘くらい見抜いてよ。
王馬くんはそう言って笑う。
そんなの出来るわけないでしょ、と抗議すれば、それもそうだね、とまたバカにしたように鼻で笑われた。
「王馬くん、すぐそうやって意地悪言う」
「何言ってんの。そんなオレをわざわざ狙い撃ちしてきたのはみょうじちゃんでしょ」
「そっ…そんなことないよ。暇そうにしてたから声掛けただけで」
「えー、ホントかなー?怪しいなー?」
後ろめたさしか感じないことを言われ、咄嗟に顔を逸らした。
王馬くんはニヤニヤとした表情で私の顔を追うように視界に入ってくる。
また顔を逸らして、それを追いかけてきて、というのを何度か繰り返し、不意に目が合った瞬間私たちは同時に吹き出してしまった。
「ぷっ…あははは!」
「あはは、もう…ふふ、意味分かんない!」
「みょうじちゃんのせいでしょ!…あー、笑った笑った」
「えー、私のせいなの?」
「そうだよ?みょうじちゃんがオレに手伝わせるから」
「そんなに遡るんだ!?」
意味の分からないやりとりにお腹が痛くなるほど笑い合ってから、荷物を取りに教室へと戻り始める。
今度は最初からずっと歩く速度が同じくらいで、置いていかれそうになることはなかった。
「王馬くんって意外と優しいよね」
「意外と、の部分要る?」
「そこが重要なポイントでしょ」
「うわ、心外ー。みょうじちゃん、オレのこと優しくないと思ってたんだ」
「お、思ってない!思ってないよ!?」
「…じゃあどう思ってんの?」
並んで廊下を歩いていた王馬くんの足が止まる。
反応が遅れて数歩先へ進んでしまった私が振り返ると、回答を促すように彼の視線が送られてきた。
「どう…って、優しくて面白い人?…あ!あとは個性的とか」
「ふーん、それだけ?」
「それだけってことはないけど」
「じゃあ、他に思ってること教えてよ」
王馬くんが一歩踏み出すと、私たちの間の距離が少し縮まった。
教えて、なんて言われても。
大事なクラスメイトだとか、実は頭が良いだとか、本当に心の真ん中にある二文字の言葉をわざと避けるようにして、彼に対しての自分の中のイメージを伝えてみる。
「…やっぱだめか」
王馬くんは小さな声でそう言って、「なんでもない!」と笑ってまた歩き出す。
「えっ?ねぇ、なんだったの今の?」
「なんでもないよー」
「本当に?もしかして、私の回答ズレてた?」
「そんなことないない」
「うわ、絶対嘘だ…!ねぇ、ちょっと待って」
歩き出した王馬くんはプリントを運び始めた時と同じくらい早くて、早歩きというよりは小走りに近い状態になりながら彼を追いかける。
「ね、王馬くんってば」
「なに」
「なんで、「なんでもない」って嘘つくの」
「…嘘ついてるのはさ、みょうじちゃんも同じでしょ?」
「えっ…ひゃあ!?」
ぴたりと足を止めた王馬くんの背中に勢い余ってぶつかってしまった。
前のめりになった彼がなんとか踏みとどまってくれたおかげで、私も転ばずには済んだようだ。
「いったー…もう、何やってんの」
「ご、ごめんね?」
「鈍いのは身体能力の方もなの?はぁ、勘弁してよねー」
「すみません……って、私別に鈍くないし!それに、「も」って何よ!」
「何って、どこもかしこも鈍いなーってこと」
いいから帰るよと、王馬くんはまた教室に向かって歩き始める。
それを追いかけて、私も彼の少し後ろを歩く。
言葉少なに教室までたどり着き、それぞれ荷物を取るために自席へと向かう。
先に荷物を回収し終えた王馬くんが教室を出ようとしているのを見つけて、私はその背中に声をかけた。
「王馬くん!今日はありがとう、嬉しかった!」
「はいはい。…あ、そうだみょうじちゃん」
「えっ、なに?」
「オレ、今日はみょうじちゃんのお願いだから聞いてあげたんだよ」
「えっ…え?」
「にしし。じゃ、また明日ね!鈍感女のみょうじちゃん」
王馬くんがひらひらと手を振って教室から出ていった後も、私はしばらくその場から動けずにいた。
彼の言葉の全てを都合良く解釈してしまいそうで、どこからが嘘でどこまでが本当なのかを必死に考える。
ああ…もう、明日どんな顔して学校に来ればいいのよ…。
今日の出来事を思い出しては赤くなる頬を押さえつけながら、明日への不安とほんの少しの期待を胸に帰路に着いた。
1/1ページ