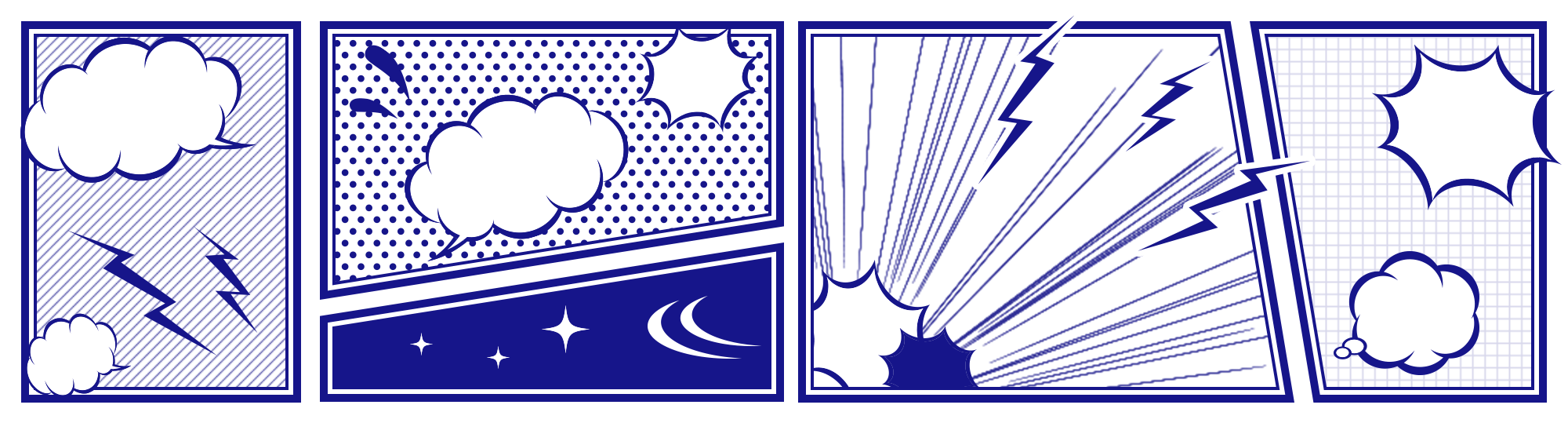前髪を切った日
おなまえ
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
前髪越しに見る世界は、まるで優しいフィルターがかけられたみたいに安心できた。
昔から人見知りで内気で、全然友達なんて出来たこともなかった私は、不運なことに超高校級なんてものに選ばれて世間の目に晒されて、完全に人との関わり方を知らないまま生きてきた。
すっかり鼻の辺りまで伸びてしまった前髪越しでなければ、もう他の人の目を見る勇気すらない。
「ねぇみょうじちゃん、見て見て!」
「な、なんですか…?」
「えっちな本」
「きゃああ…!?や、やめてください、もう」
そんな私は才囚学園に来てからも相変わらず1人で過ごしていた…わけではなく、何故かこの王馬小吉くんという男子生徒と共にいることが多くなった。
…と言っても、一方的に連行されているだけで、私から望んで彼と過ごしたことはないのだけれど。
「あ、ねぇねぇ。なまえちゃんって呼んでもいい?」
「え…嫌ですよ。私たち、そんなに仲良くないですし…」
「ひ、ひどい…オレはもう仲良しだと思っ…思っでだのに…!」
仲良し…か。
そんなこと言われたの初めてだな。
変な人だと思って引き気味になっていたけど、ちゃんと向き合えばお友達になれるのだろうか…などと思えていたのも束の間のこと。
「う、うわぁぁあああん!!ひどいよぉおおおお!!!」
鼓膜が裂けるんじゃないかと思えるほどの泣き声が図書室に響き渡る。
けれども「図書室ではお静かに」なんて注意してくれる司書さんはここにはいなくて、彼の叫びを止めるには私がアクションを起こすしかないらしい。
「ご、ごめんなさい…いいですから、もう…名前で呼んでも…」
とにかく先程の王馬くんの申し出を受け入れることしか思いつかず、どうにでもなれという気持ちでそう言った。
小さな声しか出なかったのに彼はそれを聞き逃すことはなく、それと同時に大粒の涙も鼻水も途端に消えていく。
「あ、ホント?じゃあ次から名前で呼ぶね」
ケロッとした笑顔でそう言えば、何事も無かったかのようにまた本棚で何かを探し始める。
王馬くんの切り替えの早さについていけず、一瞬ぽかんとしてしまったが、気を取り直して読み進めていた本に目を移した。
お互いにペラペラとページを捲る音だけが室内に響く。
そのまま少し時間が経った頃、その音が私の手元からしか鳴らなくなった。
ちらり、と視線を本から外し上に向けてみる。
すると王馬くんは思っていたよりも私の近くにいて、じっと私の顔を見ていたことに初めて気がついた。
「ひゃっ…!?な、なんですか…何か付いてますか…?」
「ううん、別に。…っていうかなまえちゃん、前髪長すぎない?ちゃんと見えてるの、それ?」
「えっ……あ、み、見えてます、よ」
聞き慣れない「なまえちゃん」の響きに戸惑いながらもそう返事をする。
自分から聞いてきたくせに、彼は「ふーん?」と興味無さげに言ってまたどこからか見つけてきたらしいマンガのページを捲り始めた。
やっぱり、変な人。
お友達になれそう、なんて思い違いだったかもしれない。
少しだけ落ち込みそうになった心に蓋をして、これまで通りだと自分に言い聞かせながら私も視線を本に戻した。
*****
この日はAVルームに連れてこられて、王馬くんの趣味で選ばれたコメディ映画を鑑賞していた。
自分ではあまり見たことがなかった分新鮮な気持ちだったが、さほど大きくないソファに隣同士という距離感にむず痒い落ち着かなさを覚える。
王馬くんの方は全くそんなことは感じていないようで、背もたれに肘をついたり、時折伸びをしたりと至って普通な様子だ。
「…やっぱりさー」
突然声をかけられて彼の方を向くと、前と同じように私の顔をじっと見つめる紫の瞳が視界に入った。
慌てて重心を後ろに向ける私を気に留めるでもなく、彼は続けて口を開く。
「前髪長すぎ。ねぇ、切っちゃえば?」
そんな言葉と共に、ごく自然な動作で王馬くんの左手が私の髪に触れる。
さらりと前髪を横に流されて、初めて何か越しではない彼の姿を目にした。
「な、な、な、何やってるんですか…!」
同い年の男の子に髪を触られたことや、至近距離でばっちりと目が合ってしまったことへの動揺で、たったそれだけの言葉を言うのにも口が回らなくなる。
一拍遅れてから、「ごめんごめん」なんて軽い口調と笑顔を浮かべた彼が私の髪を手放した。
「オレが切ってあげよっか」
「い、いりません」
「えー、残念。オレ結構得意だよ、髪切るの。…嘘だけどね!」
手ぐしで髪を戻しながら、王馬くんのいつもの軽口を適当に受け流す。
彼の様子は本当に普段通りに見えて、どうして私ばかりこんなに余裕が無いのだろうかと、誰に向けたものかも分からない不満を心の中に漂わせていた。
それが、対人スキルに関する経験値の差だということは目に見えていたけれど。
「切った方が可愛いと思うんだけどなぁ。なまえちゃん」
王馬くんはいつもより抑揚のない声で、独り言のようにそう呟く。
「これも嘘だけど!」なんて茶化した言葉を待ち構えていたのに、それは一向に聞こえてこなくて。
また私のリアクションを見て遊ぼうとしてるのだろうか。
そう考えて視線をそちらへ向けてみたが、意外にもあの紫色の瞳はそこになくて、代わりにあったのは何故かそっぽを向いている王馬くんの姿だった。
「…あの、王馬くん?」
「何?」
「映画…見ないんですか?」
「見てるよ」
「でも…」
「なまえちゃんは知らないだろうけど、オレは側頭部にも目があるんだよ!だから心配しなくてもばっちり見えてるよ!」
そんなわけないでしょうに。
いつもの嘘だと片付けてしまおうとした時、ふと彼の髪の隙間から赤く染った耳がチラリと見えた。
さっきのは本心、だったんだろうか。
意図せず本心を口にして、誤魔化すことも忘れて、それでただ照れているだけ?
憎たらしく悪趣味な冗談ばかり吐くと思っていた王馬くんの、年相応で普通な部分を知れた気がした。
「…似合う、でしょうか」
「え?」
「前髪…です。切っても、似合うでしょうか?」
「知らなーい。…けど、似合うんじゃない?」
その晩、鏡の前で少しずつ、ゆっくりと、自分の手で前髪を切った。
すごく変だけど、意外と普通なところもある同い年の男の子。
フィルター無しのあなたの姿を、もっと見てみたいと思ったから。
昔から人見知りで内気で、全然友達なんて出来たこともなかった私は、不運なことに超高校級なんてものに選ばれて世間の目に晒されて、完全に人との関わり方を知らないまま生きてきた。
すっかり鼻の辺りまで伸びてしまった前髪越しでなければ、もう他の人の目を見る勇気すらない。
「ねぇみょうじちゃん、見て見て!」
「な、なんですか…?」
「えっちな本」
「きゃああ…!?や、やめてください、もう」
そんな私は才囚学園に来てからも相変わらず1人で過ごしていた…わけではなく、何故かこの王馬小吉くんという男子生徒と共にいることが多くなった。
…と言っても、一方的に連行されているだけで、私から望んで彼と過ごしたことはないのだけれど。
「あ、ねぇねぇ。なまえちゃんって呼んでもいい?」
「え…嫌ですよ。私たち、そんなに仲良くないですし…」
「ひ、ひどい…オレはもう仲良しだと思っ…思っでだのに…!」
仲良し…か。
そんなこと言われたの初めてだな。
変な人だと思って引き気味になっていたけど、ちゃんと向き合えばお友達になれるのだろうか…などと思えていたのも束の間のこと。
「う、うわぁぁあああん!!ひどいよぉおおおお!!!」
鼓膜が裂けるんじゃないかと思えるほどの泣き声が図書室に響き渡る。
けれども「図書室ではお静かに」なんて注意してくれる司書さんはここにはいなくて、彼の叫びを止めるには私がアクションを起こすしかないらしい。
「ご、ごめんなさい…いいですから、もう…名前で呼んでも…」
とにかく先程の王馬くんの申し出を受け入れることしか思いつかず、どうにでもなれという気持ちでそう言った。
小さな声しか出なかったのに彼はそれを聞き逃すことはなく、それと同時に大粒の涙も鼻水も途端に消えていく。
「あ、ホント?じゃあ次から名前で呼ぶね」
ケロッとした笑顔でそう言えば、何事も無かったかのようにまた本棚で何かを探し始める。
王馬くんの切り替えの早さについていけず、一瞬ぽかんとしてしまったが、気を取り直して読み進めていた本に目を移した。
お互いにペラペラとページを捲る音だけが室内に響く。
そのまま少し時間が経った頃、その音が私の手元からしか鳴らなくなった。
ちらり、と視線を本から外し上に向けてみる。
すると王馬くんは思っていたよりも私の近くにいて、じっと私の顔を見ていたことに初めて気がついた。
「ひゃっ…!?な、なんですか…何か付いてますか…?」
「ううん、別に。…っていうかなまえちゃん、前髪長すぎない?ちゃんと見えてるの、それ?」
「えっ……あ、み、見えてます、よ」
聞き慣れない「なまえちゃん」の響きに戸惑いながらもそう返事をする。
自分から聞いてきたくせに、彼は「ふーん?」と興味無さげに言ってまたどこからか見つけてきたらしいマンガのページを捲り始めた。
やっぱり、変な人。
お友達になれそう、なんて思い違いだったかもしれない。
少しだけ落ち込みそうになった心に蓋をして、これまで通りだと自分に言い聞かせながら私も視線を本に戻した。
*****
この日はAVルームに連れてこられて、王馬くんの趣味で選ばれたコメディ映画を鑑賞していた。
自分ではあまり見たことがなかった分新鮮な気持ちだったが、さほど大きくないソファに隣同士という距離感にむず痒い落ち着かなさを覚える。
王馬くんの方は全くそんなことは感じていないようで、背もたれに肘をついたり、時折伸びをしたりと至って普通な様子だ。
「…やっぱりさー」
突然声をかけられて彼の方を向くと、前と同じように私の顔をじっと見つめる紫の瞳が視界に入った。
慌てて重心を後ろに向ける私を気に留めるでもなく、彼は続けて口を開く。
「前髪長すぎ。ねぇ、切っちゃえば?」
そんな言葉と共に、ごく自然な動作で王馬くんの左手が私の髪に触れる。
さらりと前髪を横に流されて、初めて何か越しではない彼の姿を目にした。
「な、な、な、何やってるんですか…!」
同い年の男の子に髪を触られたことや、至近距離でばっちりと目が合ってしまったことへの動揺で、たったそれだけの言葉を言うのにも口が回らなくなる。
一拍遅れてから、「ごめんごめん」なんて軽い口調と笑顔を浮かべた彼が私の髪を手放した。
「オレが切ってあげよっか」
「い、いりません」
「えー、残念。オレ結構得意だよ、髪切るの。…嘘だけどね!」
手ぐしで髪を戻しながら、王馬くんのいつもの軽口を適当に受け流す。
彼の様子は本当に普段通りに見えて、どうして私ばかりこんなに余裕が無いのだろうかと、誰に向けたものかも分からない不満を心の中に漂わせていた。
それが、対人スキルに関する経験値の差だということは目に見えていたけれど。
「切った方が可愛いと思うんだけどなぁ。なまえちゃん」
王馬くんはいつもより抑揚のない声で、独り言のようにそう呟く。
「これも嘘だけど!」なんて茶化した言葉を待ち構えていたのに、それは一向に聞こえてこなくて。
また私のリアクションを見て遊ぼうとしてるのだろうか。
そう考えて視線をそちらへ向けてみたが、意外にもあの紫色の瞳はそこになくて、代わりにあったのは何故かそっぽを向いている王馬くんの姿だった。
「…あの、王馬くん?」
「何?」
「映画…見ないんですか?」
「見てるよ」
「でも…」
「なまえちゃんは知らないだろうけど、オレは側頭部にも目があるんだよ!だから心配しなくてもばっちり見えてるよ!」
そんなわけないでしょうに。
いつもの嘘だと片付けてしまおうとした時、ふと彼の髪の隙間から赤く染った耳がチラリと見えた。
さっきのは本心、だったんだろうか。
意図せず本心を口にして、誤魔化すことも忘れて、それでただ照れているだけ?
憎たらしく悪趣味な冗談ばかり吐くと思っていた王馬くんの、年相応で普通な部分を知れた気がした。
「…似合う、でしょうか」
「え?」
「前髪…です。切っても、似合うでしょうか?」
「知らなーい。…けど、似合うんじゃない?」
その晩、鏡の前で少しずつ、ゆっくりと、自分の手で前髪を切った。
すごく変だけど、意外と普通なところもある同い年の男の子。
フィルター無しのあなたの姿を、もっと見てみたいと思ったから。
1/1ページ