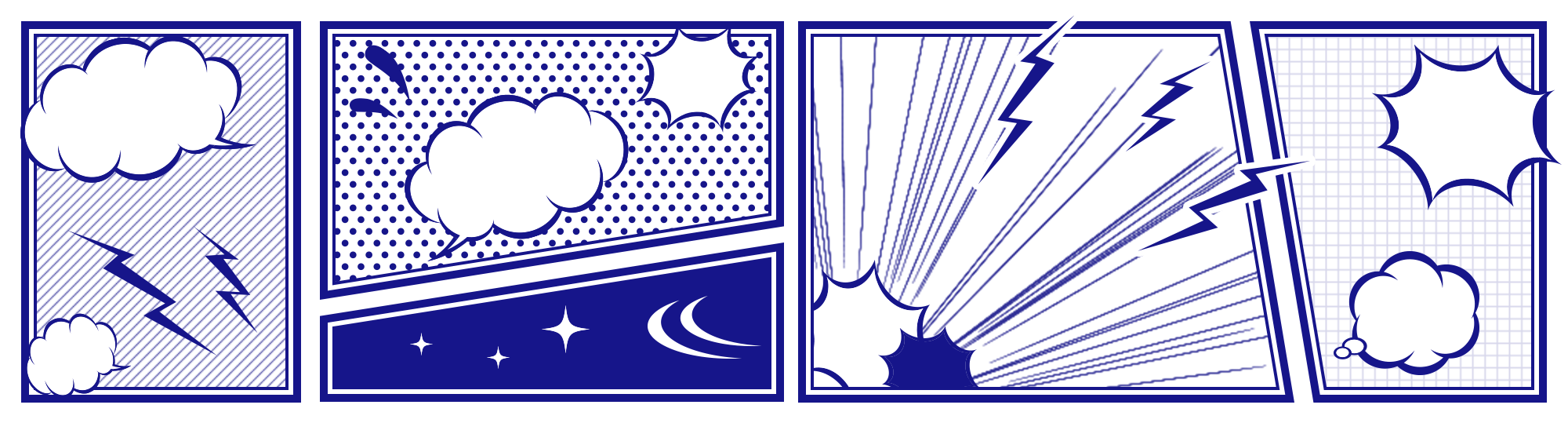擬似告白
おなまえ
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
「王子様…私もあなたの事がスキデス…」
「…ねぇ、やる気あんの?」
放課後の教室。
ここ数日、私は王馬くんと2人居残りの日々を過ごしている。
もちろん本意ではないが、なんというか仕方なくだ。
事の発端は、文化祭の出し物で私たちのクラスは劇をしようということになり、何故かヒロイン役に私が選ばれてしまったことだ。
演技の経験も自信もないくせに、投票で選ばれた手前断りきれずに承諾してしまったのだ。
で、いざ練習を始めてみて驚いた。
私には演技の才能がまるでなかったらしい。
大根役者どころの騒ぎではない、とは王馬くん談。
ロボットであるはずのキーボくんの方がまだ情緒があるのでは…と。
散々な言われようだが、正直自分でもそう思う。
「もう棒読みなのは一旦置いとくけどさ、肝心なところでカタコトになるのはなんなの?イヤイヤ言わされてる感あるし、オレが王子の立場だったら絶対姫にしたくないって思うね」
「う…そこまでいわなくても…」
「そこまで言われたくないならもうちょっとマシなもの見せてよ」
「…返す言葉もございません」
普通に思ったことを話す時に嘘くさいとか、カタコトになってるとか、そんなことを言われた覚えはない。
どうして決められた台詞を言おうとするとここまで棒読みになってしまうのか。
数日間の王馬くんのスパルタレッスンの最中、そんなことの答えを探し続けていた。
「例えば目の前にいるのはずーっと好きだった人…とか思ったりさ、もうちょっと想像力働かせながらやってみなよ」
「そう言われてもなぁ…私好きな人いないし…」
思えばまともに恋愛をしてこなかった私には、恋焦がれるという感情を全くイメージできない。
「王馬くんはいるの?好きな人」
何の気なしに口にした、ちょっとした世間話の延長線のような質問のつもりだった。
自分の中には答えがなかったから、他の人の話を参考にしたいと、ただそれだけ。
「いないよ」
彼は意外とすんなり答えてくれた。
いるいないに関わらず、どうでしょう?とか無駄に秘密にしたがりそうなイメージだった。
とはいえ完全に参考にはならないことが分かってしまい、私はふぅとため息をつく。
王馬くんはそんな私を見て、何かを思いついたように声を上げる。
やけに楽しそうな顔をしているから、きっとろくでもないことなんだろうな。
「とりあえずさ」
「うん?」
「一旦オレのこと好きになってみて」
「はぁ!?」
突拍子もない提案に素っ頓狂な声が出る。
何を言っているんだこの人は。
「だからさー、一旦そういう事にしてみたら何か掴めるかもしれないでしょ?ほら、オレに好きって告白してみなって。本気のやつ」
「そ、そんなこと言われても何のきっかけもなく好きになれると思う!?…っていうか、さっきも台本とはいえ告白じみたこと言ってたじゃん!」
「あれはみょうじちゃんとして言った言葉じゃないからね。ほら、言霊?ってあるらしいし1回やってみようよ。何事も経験でしょ?オレもいい加減、演技指南飽きてきちゃったしさー」
本当にそんなことをして意味はあるのか?と思わずにはいられないが、ここ最近毎日のように放課後付き合ってくれているだけにそう言われてしまうと返す言葉がない。
仕方ない、一度だけ。
好きです。と、さっきみたいに言うだけだから。
そう思って王馬くんの方を見ると、さっきまでのおちゃらけた雰囲気はどこへやら、彼は小首を傾げつつも妙に落ち着いた表情でこちらを見つめていた。
「…す、…」
「んー?」
だめだ、なんかちょっと良い雰囲気っぽいなと思ったら緊張が止まらない。
いつもだったら憎たらしく「聞こえませーん」とでも言ってきそうなところ、何を優しく聞き返してくれてるんだこの男は。
「どうかした?」
「べ、別に!」
「じゃあほら、早く言ってみなよ」
王馬くんは優しく促すようにそう言った。
いつもと違う…多分、これは演技なんだろうけど。
戸惑いつつも、時間をかけすぎても不自然に思われる。
ごくりと息を飲んで、私はまた口を開いた。
「…す、好き、です……」
言えた…。
私はばくばくと音を立てている心臓を労わるように、そっと手を胸に当てて息をつこうとした。
「オレもだよ」
「へっ!?」
突如聞こえてきた、予定されていなかった告白の返事に戸惑い顔を上げる。
机に片肘をついてこちらを見ていた王馬くんと目が合う。
今のはどういう…?
戸惑う私の様子をしばし観察していたかと思うと、王馬くんの口角が意地悪く上がった。
「あは、本気にしちゃった?」
「し、してないから!」
「はいはい。で、さっきの感じは結構良かったんじゃない?…あれが演技なら、の話だけどね」
「演技です!」
じっと目を細めて私を見る王馬くんは、なんだか心の内まで見透かしているんじゃないかという気がしてくる。
実際のところ、普通に緊張してしまった私にはあれを演技とは言い難い。
「にしし、じゃあ次の練習もその感じで頑張ってね!…ってことで今日は解散!」
じゃーね!と手を振り教室を後にする王馬くんを確認し、私はへなへなとその場にへたりこんだ。
またドキドキと高鳴る胸を押さえながら、そんな、まさか…と一人教室の隅で呟いていた。
「…ねぇ、やる気あんの?」
放課後の教室。
ここ数日、私は王馬くんと2人居残りの日々を過ごしている。
もちろん本意ではないが、なんというか仕方なくだ。
事の発端は、文化祭の出し物で私たちのクラスは劇をしようということになり、何故かヒロイン役に私が選ばれてしまったことだ。
演技の経験も自信もないくせに、投票で選ばれた手前断りきれずに承諾してしまったのだ。
で、いざ練習を始めてみて驚いた。
私には演技の才能がまるでなかったらしい。
大根役者どころの騒ぎではない、とは王馬くん談。
ロボットであるはずのキーボくんの方がまだ情緒があるのでは…と。
散々な言われようだが、正直自分でもそう思う。
「もう棒読みなのは一旦置いとくけどさ、肝心なところでカタコトになるのはなんなの?イヤイヤ言わされてる感あるし、オレが王子の立場だったら絶対姫にしたくないって思うね」
「う…そこまでいわなくても…」
「そこまで言われたくないならもうちょっとマシなもの見せてよ」
「…返す言葉もございません」
普通に思ったことを話す時に嘘くさいとか、カタコトになってるとか、そんなことを言われた覚えはない。
どうして決められた台詞を言おうとするとここまで棒読みになってしまうのか。
数日間の王馬くんのスパルタレッスンの最中、そんなことの答えを探し続けていた。
「例えば目の前にいるのはずーっと好きだった人…とか思ったりさ、もうちょっと想像力働かせながらやってみなよ」
「そう言われてもなぁ…私好きな人いないし…」
思えばまともに恋愛をしてこなかった私には、恋焦がれるという感情を全くイメージできない。
「王馬くんはいるの?好きな人」
何の気なしに口にした、ちょっとした世間話の延長線のような質問のつもりだった。
自分の中には答えがなかったから、他の人の話を参考にしたいと、ただそれだけ。
「いないよ」
彼は意外とすんなり答えてくれた。
いるいないに関わらず、どうでしょう?とか無駄に秘密にしたがりそうなイメージだった。
とはいえ完全に参考にはならないことが分かってしまい、私はふぅとため息をつく。
王馬くんはそんな私を見て、何かを思いついたように声を上げる。
やけに楽しそうな顔をしているから、きっとろくでもないことなんだろうな。
「とりあえずさ」
「うん?」
「一旦オレのこと好きになってみて」
「はぁ!?」
突拍子もない提案に素っ頓狂な声が出る。
何を言っているんだこの人は。
「だからさー、一旦そういう事にしてみたら何か掴めるかもしれないでしょ?ほら、オレに好きって告白してみなって。本気のやつ」
「そ、そんなこと言われても何のきっかけもなく好きになれると思う!?…っていうか、さっきも台本とはいえ告白じみたこと言ってたじゃん!」
「あれはみょうじちゃんとして言った言葉じゃないからね。ほら、言霊?ってあるらしいし1回やってみようよ。何事も経験でしょ?オレもいい加減、演技指南飽きてきちゃったしさー」
本当にそんなことをして意味はあるのか?と思わずにはいられないが、ここ最近毎日のように放課後付き合ってくれているだけにそう言われてしまうと返す言葉がない。
仕方ない、一度だけ。
好きです。と、さっきみたいに言うだけだから。
そう思って王馬くんの方を見ると、さっきまでのおちゃらけた雰囲気はどこへやら、彼は小首を傾げつつも妙に落ち着いた表情でこちらを見つめていた。
「…す、…」
「んー?」
だめだ、なんかちょっと良い雰囲気っぽいなと思ったら緊張が止まらない。
いつもだったら憎たらしく「聞こえませーん」とでも言ってきそうなところ、何を優しく聞き返してくれてるんだこの男は。
「どうかした?」
「べ、別に!」
「じゃあほら、早く言ってみなよ」
王馬くんは優しく促すようにそう言った。
いつもと違う…多分、これは演技なんだろうけど。
戸惑いつつも、時間をかけすぎても不自然に思われる。
ごくりと息を飲んで、私はまた口を開いた。
「…す、好き、です……」
言えた…。
私はばくばくと音を立てている心臓を労わるように、そっと手を胸に当てて息をつこうとした。
「オレもだよ」
「へっ!?」
突如聞こえてきた、予定されていなかった告白の返事に戸惑い顔を上げる。
机に片肘をついてこちらを見ていた王馬くんと目が合う。
今のはどういう…?
戸惑う私の様子をしばし観察していたかと思うと、王馬くんの口角が意地悪く上がった。
「あは、本気にしちゃった?」
「し、してないから!」
「はいはい。で、さっきの感じは結構良かったんじゃない?…あれが演技なら、の話だけどね」
「演技です!」
じっと目を細めて私を見る王馬くんは、なんだか心の内まで見透かしているんじゃないかという気がしてくる。
実際のところ、普通に緊張してしまった私にはあれを演技とは言い難い。
「にしし、じゃあ次の練習もその感じで頑張ってね!…ってことで今日は解散!」
じゃーね!と手を振り教室を後にする王馬くんを確認し、私はへなへなとその場にへたりこんだ。
またドキドキと高鳴る胸を押さえながら、そんな、まさか…と一人教室の隅で呟いていた。
1/1ページ