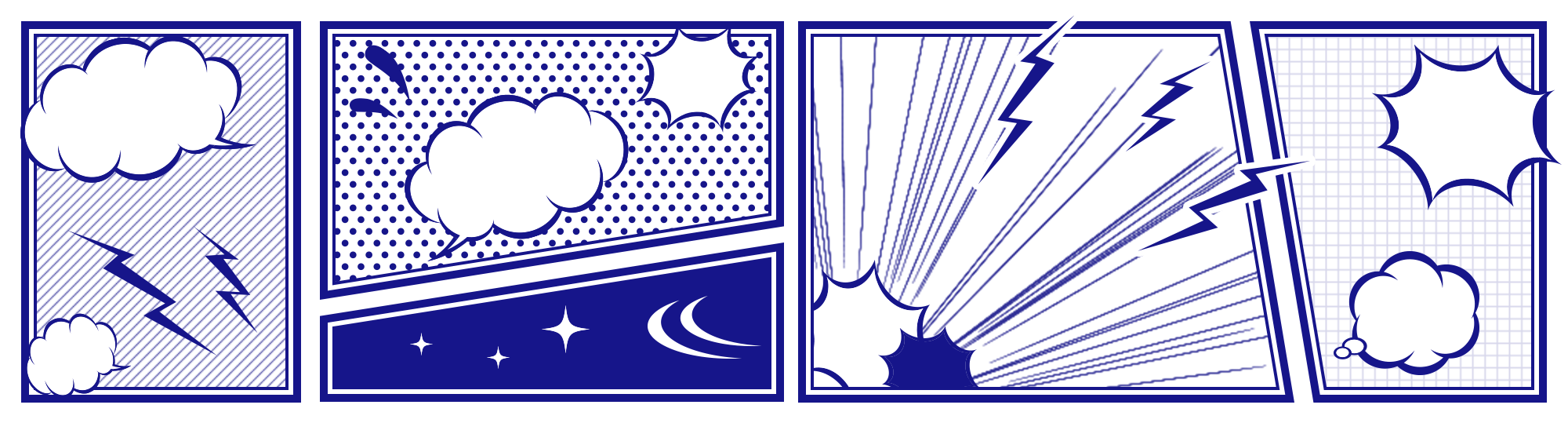ジンクスか迷信か
おなまえ
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
クラスメイトの女の子から聞いた、ちょっとした恋のおまじないみたいな話。
どこの学校にだってありがちなものだけど、いつの時代も恋する青少年はこういうジンクスには目がないものだ。
かくいう私も…その口なんだけど。
「文化祭、誰と回るか決めた?」
「決まってない。…というか、まだ誘えてない」
「もー、なまえちゃんってばうじうじしすぎ!もう来週だよ?早くしないと予定埋まっちゃうかもしれないのに」
好きな人と後夜祭の間をずっと一緒に過ごせたら結ばれる。
嘘か本当かは誰にも分からないけど、学生の間では割と有名な噂だ。
昔はどうだったのか知らないが、現在はいきなり「後夜祭を共に過ごしましょう」なんて誘ってしまうとあからさま過ぎるということから、これを実践したい人は文化祭の自由時間から約束をするのがスタンダードなやり方になっている。
と言ってもこんなカムフラージュも有名になってしまえば意味が無くなるもので、もはや「文化祭を見て回ろうと誘う=そういうつもり」の図式が出来上がっているのもまた事実。
結局のところ、後夜祭に誘おうがその前段階から誘おうがハードルの高さは変わらないように思う。
「返す言葉もございません…。ところで、楓ちゃんはどうなったの?」
「ふふん…ちゃんと約束取り付けました!」
「えっ、マジで!?すごい…さすが楓様…」
私より何倍もしっかり者で行動力のある友人は、既に意中の相手との約束にこぎつけたらしい。
そして、当日は私も一緒にいられないんだからね、と半分脅しのような励ましを受けてしまう。
そうだよなぁ、そろそろ頑張らないと本当に後がなくなるよなぁ。
どうやって誘えばいいだろうかと考えつつ、移動教室のため廊下を歩いていると後ろから誰かに名前を呼ばれた気がして振り返る。
「え、王馬くん…?」
思い浮かべていた意中の相手その人が立っていて戸惑う。
幻覚…じゃないよね、さすがに。
目をぱちぱちさせながら現実かどうか見極めていると、王馬くんは笑いながらこちらに近づいてきた。
「あはは、変な顔ー。ほら、これ落としてったよ」
「あ、ありがとう…」
彼の手の上には確かに私が持ち歩いていたものがある。
考え事に夢中で落としたことに気が付かなかったみたい。
お礼を言って受け取ろうとすると王馬くんがその手をひょいっと上に持ち上げ、私の手はただ何も無い空間に残される。
「えっ…?」
「誰もタダであげるとは言ってないよ!」
「そ、そんな…私、お金とかあんまりもってないよ?」
「そんなカツアゲみたいな真似するわけないでしょ、どこの不良漫画?」
王馬くんはニコニコと楽しげな笑顔を浮かべながらそう言った。
考えてみればこんなに近くで顔を見るのは初めてで、自分の状況も忘れてドキドキしてしまう。
「返して欲しかったらさ、文化祭一緒に遊ぼうよ」
発せられた言葉の意味がよく分からず固まった。
文化祭、一緒に、遊ぶ?
それってつまりは…一緒に過ごそうって、そういうこと?
「え、ぇええ!?」
「あれ、もしかして先約あった?」
「う、ううん…それはないけど」
「にしし、じゃあ決まりだね。みょうじちゃんも店番は前半組に立候補よろしく!当日終わったらそっち迎えに行くから待っててねー」
「えっ…えっ?」
口をぱくぱくさせながら声にならない声を上げていると、宙に取り残されていた私の手に王馬くんが拾ってくれた落し物をぽんと乗せ、そのままどこかへ行ってしまった。
嘘だよって言われなかった。
本当ってこと?そんなまさか…でも。
もしかして当日になっていきなりネタバラシがあるとか?それはちょっと嫌だな…。
でもでも、少しくらいは夢見てても罰は当たらないかも…。
考えても何もまとまらないまま、とにかく教室へと向かって今しがた起こった夢か現実か分からない出来事を友人に話す。
良かったじゃん、と満面の笑みで祝福されて、そんなすんなり受け入れていいものなの?と疑問に思いつつ、当日が楽しみで浮かれてしまう気持ちと共に文化祭までの期間を過ごした。
*****
「どうしよう、実はやっぱり嘘でしたとかそういう展開ないかな?そんなこと言われたら私もう再起不能になるかも」
「大丈夫だって、さすがの王馬くんでもそんなことは…ない…と、思う。多分。…あっ、ほらそろそろ来るんじゃない?早く戻らないと」
「ねぇ、楓ちゃんもちょっと自信なくなってるじゃん!う~~~…どうしよう、怖くなってきた…」
文化祭当日の店番交代の時間。
私たちのグループは喫茶店を開いていて、メイドさんのような衣装から制服に着替えるため更衣室へとやって来ていた。
既に着替え自体は終わっているのだが、心の準備は一向に出来ていない。
自分のクラスに戻ったら、もしかすると既にあの人が待ってるかも。
そう考えただけでもうキャパオーバー。
さらにはドッキリの可能性も残されているなんていうおまけ付き。
良い方に転んでも悪い方に転んでも、どちらにせよ私の心臓には大打撃だ。
「あ、向こうも終わったみたい。じゃあ…私そろそろ行かなきゃだから、後は頑張って!ちゃんと行かないとダメだよ?可能性は0じゃないんだから!」
「う、楓ちゃん……」
友人はスマホを見て慌てて出ていってしまった。
なんとまぁ連絡先まで交換してるのか…さすが、抜かりない。
なんて考えてる場合じゃない。
とにかく行ってみないと…。もしダメだったらその時は、今日帰ってから好きなお菓子をたくさん食べよう。うん、そうしよう。今日だけはカロリーのことも忘れて自分を甘やかそう。
ほとんどダメ寄りな思考で自分のクラスの教室へと戻ると、幸か不幸か王馬くんは普通にそこにいた。
「ご、ごめん…待たせちゃった?」
「みょうじちゃん遅すぎ、めちゃくちゃ待ったよー。…なんて、嘘だけどね!ホントはさっき来たとこ」
嘘……その嘘っていうのは、早く来たことが嘘…ってことなんだよね。
じゃあやっぱり一緒に過ごすっていう約束は本当?
いやいや、そもそも嘘ならこの場に来てないはずだし…このまま一緒に見て回る流れってことでいいんだよね?
ぐるぐると考え事をしていると、王馬くんは不思議そうな顔で私の目を覗き込んできた。
「聞いてる?ねぇ、みょうじちゃんってばー」
「へ?ご、ごめん考え事してた…」
「ふーん、まぁいいけど。あっ!ねぇねぇ、オレここのお化け屋敷行きたいんだよね!ほら行こうよー」
「えっ…わ、分かったから手を…!」
「ぼさっとして迷子になられたらつまんないし、このまま!」
ぼーっとしてた罰、と言って笑いながら王馬くんが私の手を取り歩き出す。
嘘でしょ…いきなりこんなの、ただでさえ緊張してるのにもっと緊張しちゃうよ。
ずんずん進んでいく彼に手を引かれて、各クラスの教室を回る。
西園寺さんのクラスのお化け屋敷は死ぬほど怖くて、王馬くんに縋りながら叫びまくった。そんな私の様子が面白かったのか、彼は少しも怖がることなくずっと笑っていた。
七海さん主催のゲーム大会ブースでは色んなジャンルのゲームを楽しんだ。でも対戦相手が王馬くんか七海さんだから、私では全然歯が立たなかったんだけど。
他にも食べ物の屋台を回ったり、展示物を見に行ったり、想像していたよりも楽しい時間を過ごした。
手を繋がれていることも気がつけば慣れていて、もちろん少しは緊張するけどさほど違和感もなくなって、素直に今の状況を喜ぶ余裕も出て来た時にはもうすぐ文化祭も終わろうかと言う頃だった。
「もうすぐ終わっちゃうんだ…」
「そうだねー。でも、なかなかつまらなくない文化祭だったと思うよ」
「ふふ、そうだね。こんなに楽しい日になると思ってなかったな…王馬くん、今日は誘ってくれてありがとう」
「にしし、どういたしまして!…あ、そろそろ後夜祭始まるんじゃない?グラウンド行こ!」
王馬くんの中では当然のように後夜祭まで一緒に過ごす予定になっていたらしい。
さっきまでと同じように彼に手を引かれながら、その事実を噛み締めて口元が綻んだ。
「そういえばさ、みょうじちゃんは文化祭にまつわる噂話…聞いたことある?」
「噂ってあの、好きな人と後夜祭を一緒に過ごしたらってやつ?」
「そうそう!なーんだ、やっぱり知ってたんだ」
好きな人と後夜祭を過ごせば結ばれる。
そもそも私が王馬くんを誘おうと思っていたのはこの噂話が原因だった。
でも、なんで改まってそんなことを聞くんだろう。
そう思っていると、突然王馬くんの足がすぐそばの空き教室へと方向を変えた。
よく分からないまま誰もいない教室に足を踏み入れる。
窓の外にはグラウンドで後夜祭の準備をしている先生たちの姿が見えた。
「みょうじちゃんは信じてるの?ああいうの」
「えっ、うーん…どうだろう。分からないけど、信じたいって気持ちはあるかも」
「そっかー、ちなみにオレは全然信じてないよ!そんなことで人の気持ちが簡単に変わるわけないし、あんなのただの迷信だよねー!」
確かに王馬くんはそう思ってそうだけど、つまりは何が言いたいんだろうか。
彼の言動の真意が分からず戸惑っていると、繋がれていた手をそっと引き寄せられて距離が近づく。
今までよりもずっと近くに体温を感じて、きっと少しでも顔を上げたらそこには王馬くんの顔があるんだと思うと身動きが取れない。
「にしし、固まっちゃった」
「だ、だって…どうしたらいいか分かんなくて」
「別にどうもしなくていいよ、そのままで」
思っていた通りの場所から王馬くんの声が聞こえる。
どういう状況?なんでこんなことに?
嬉しいけど、これから何が起こるのか…素直に喜んでいいものなのかもよく分からない。
そう思っていると、またすぐ近くから王馬くんの声が聞こえ始めた。
「みょうじちゃん、オレのこと好きでしょ」
「…はい!?な、何言って…」
「あれ違った?…なんて、そんなわけないよね。好きでもないならこんなことされて抵抗しない理由がないし」
「う…」
全部見透かされていたようで言葉に詰まる。
今日を一緒に過ごすことも、手を繋ぐことも、こんな風に近くにいることも、全部嫌じゃないどころか嬉しいと思っている。
私は王馬くんが好きだから。
そういう気持ちが表面に滲み出ていたってことなのかな、そう思うと全てが恥ずかしくなってくる。
あわあわと口ごもっていると、王馬くんはそんな私の様子を見てか楽しげに笑った。
「あは、ホント分かりやすいよねー。顔も真っ赤になってリンゴみたい」
「か、からかわないでよ…」
「別にからかってないよ?可愛いなーと思っただけ」
「か、かわ…?」
今、何を言われたんだろう。
いよいよ私の情報処理能力が限界を迎えている。
からかってないの?本当に?
だったらどうしてこんなことを?
「オレもね、みょうじちゃんのこと好きだよ」
まさかここにきて都合のいい幻聴が聞こえているんじゃないだろうか。
だって、そんなことありえる?
好きな人に文化祭に誘われて、あまつさえ私のことを好きだと言われるなんて。
夢なんじゃないかと思って頬を抓ってみても、ただ普通に痛みを感じただけだった。
「ゆ、夢じゃない…!?」
「あっははは!夢でも嘘でもない現実だよ。それじゃあもう1回聞くけどさ、みょうじちゃんはオレのこと好き?」
「えっと…す、好き…です」
よくできました。そんな声がして、王馬くんが私の頬に手を当てて顔をあげさせる。
思っていたよりもずっと近くにあった王馬くんの顔が私の視界を埋めつくした。
それと同時に、唇に触れ合う何か。
ちゅ、と音を立ててそれは離れていき、また目の前には彼の笑顔が広がる。
「ほら、やっぱり迷信だったでしょ?」
「え?」
「だってまだ後夜祭は始まってもないじゃん。それなのにちゃんと結ばれたんだから、あの噂は迷信」
「ふふ…なにそれ」
得意気に笑う王馬くんが可愛くて、思わず私も笑ってしまった。
ひとしきり笑いあった後またそっと彼の顔が近づいてきて、さっきと同じ感触がまた。
「後夜祭、ここから眺めてよっか」
「…うん」
窓の外で始まるキャンプファイヤーを眺めながら、私たちはまたそっと顔を寄せ合った。
1/1ページ