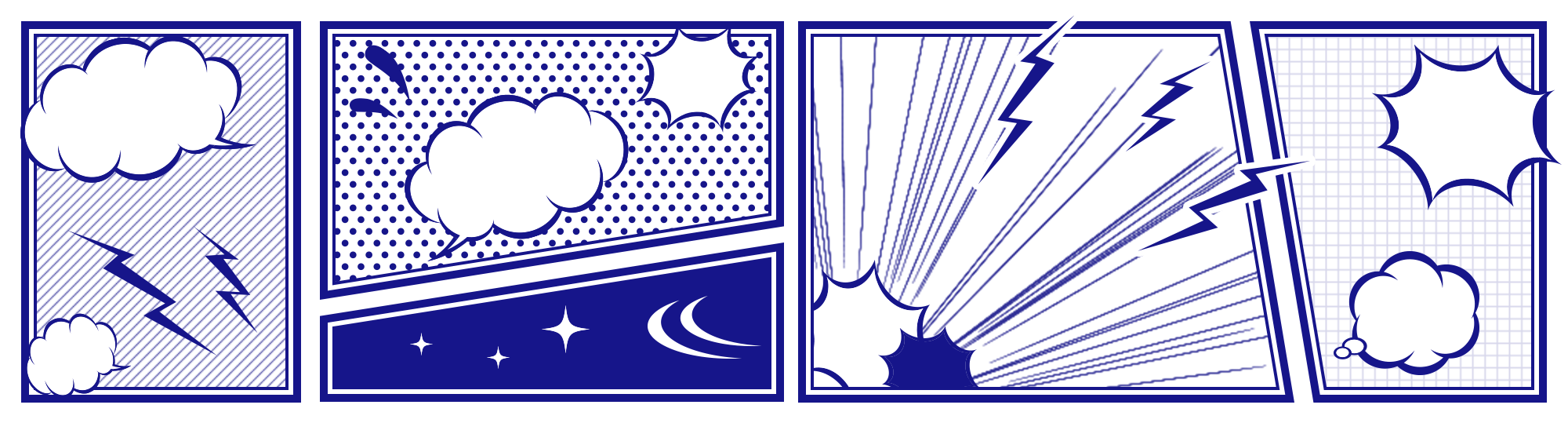嘘色ラブストーリー
おなまえ
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
※夢主の片思いスタート
希望ヶ峰学園に入学して早くも1年が経った。
なんとなく日々を過ごしてるだけでも案外周囲とは打ち解けられるもので、1年前と比べて学校に行くのが楽しいと感じるようになった。
みんなが面白くていい人だからというのももちろんあると思うけど、それだけじゃないのかもしれない。
ここは誰も来ない穴場だと教えられた、校舎の一番端の階段の影にある小さな物置部屋。
物置と言う割にはほとんど何も置かれていなくて、特に誰にも使われていないんだなということが分かる。
きっと昔応接室か何かで使っていたのであろう古びた高級そうなソファに腰掛けながら、この穴場を発見してきた人物と昼休みを過ごすのももはや恒例のこと。
そんななんでもないような時間が、今の私にはかけがえのないものになっていた。
「ねぇ、何読んでるの?」
「んー?えっちな本」
「絶対嘘だ」
「にしし…バレた?」
私の膝を我が物顔で枕に使いながら、王馬くんは教室から持ってきたらしい本を仰向けに寝転びながら読んでいる。
いいご身分だこと。
キミはどこかの王様か何か?とでも言いたくなるが、実際彼は1万人規模の秘密結社の総統らしいので上に立つ者と言う意味では近い部分があるのかもしれない。
もちろん、それももしかすると彼の嘘なのかもしれないけど。
手に持った本にはご丁寧に藍色のブックカバーが掛けられていて、私からは結局何を読んでいるのか知る術はなかった。
「…みょうじちゃんってさー、好きな人いるんだね」
「ぶっ…!?」
ペラペラと興味なさげにページを捲りながら、まるで独り言にみたいに王馬くんが呟く。
丁度水筒のお茶を口に含んでいたタイミングだったので、危うく吹き出してしまうところだった。
ごほごほと咳き込む私に対して、ギリギリセーフだね!なんて言いながら彼は笑う。
「…はぁ、びっくりした」
「にしし…大丈夫ー?本がびしょ濡れにならなくて良かったよー」
「もう、誰のせいだと思ってるの」
「オレのせい、でしょ?」
手に持った本の位置をずらして、王馬くんがチラリと私の目を見た。
本の背表紙に隠れて口元は見えないけど、多分今ニヤッと笑ったんだろうなと思う。
「で、誰なの?」
「何が?」
「決まってるじゃん、好きな人の話」
「…教えない」
「えー、ひどいよー!赤松ちゃんには教えてたのにオレは仲間外れ?」
「な、なんでそれ知って…!?」
「さぁ?なんでだと思う?みょうじちゃんが好きな人教えてくれたらオレも教えてあげる!」
赤松さんとは確かにそんな話をしたことがあったけど、それは家で電話をしてる時だったはず。
状況的に考えて盗み聞きはありえない。
もし赤松さんが言ってしまったのなら、それはそれで本人からそのことについて何かしら知らせてきそうだし…。
記憶を振り返りながらどんな可能性があるのかを考えていると、王馬くんが楽しげに笑った。
「ぷっ…あはは!適当なこと言っただけなのに、もしかして全部当たってた?」
「え…適当…?」
「そうだよ?オレがそんなこと知るわけないじゃん」
ホントに好きな人いるんだね、とくつくつと肩を揺らしながら今も笑い続ける王馬くんに、私は脱力してため息をついた。
「王馬くんの嘘つき」
「そうだよ、オレは嘘つきだよ」
ちょっとした抵抗の気持ちを込めて放った言葉にも、王馬くんはなんでもないようにさらっと返事をしてくる。
まぁ確かに、嘘つきを自称している彼にとってはなんてことないだろうけど。
弄ばれたことが不服でじろりと彼を見つめると、その視線はまた本の背表紙で遮られてしまった。
「みょうじちゃんは、オレが嘘つきだって思ってるんだよね」
「う、うん」
少しの沈黙の後、ぽつりとそう言われて身構える。
さっき言ったこと、気に触ったんだろうか。
でもいつも自分でも言ってることなのに。
どうして、と思っても彼の表情は未だに隠れていてそこから推し量ることは出来ない。
「じゃあ、もしオレがみょうじちゃんに好きって言ったとしたら…それは嘘だって思う?」
ドクンと心臓が鳴った。
声が震えそうになるのをこらえて、なんでもないような態度を心がけながら口を開く。
「…分かんないよ。その時の状況とか、色々あるし」
「うーん、それもそっか」
そしてまた、沈黙。
ページを捲る音だけが室内に響く。
何だったんだろう、今のは。
ドキドキと鳴り止まない心臓の音が王馬くんに聞こえませんようにと祈っていると、彼は突然パタンと本を閉じて身体を起こした。
何事かと彼を見れば、いつになく真剣な表情を浮かべた彼もまたこちらを見ていた。
「ど、どうしたの?」
「好きだよ」
「…え?」
「好きだよ、みょうじちゃんのことが」
驚いて固まっている私をよそに、王馬くんは私の耳元に口を寄せて何かを囁く。
「ねぇ。嘘かホントか、どっちだと思う?」
まるで私にその選択肢を委ねるような、そんな言い方。
ずるいなぁと思う。でも同時に、それはすごく彼らしい表現だとも思った。
嘘になるのは嫌だな、と答えると王馬くんは満足気に笑った。
予鈴のチャイムの音が聞こえる。
もうじき昼休みが終わることを認識しながら、どうやってこの熱を持って赤くなった顔を冷まそうかと考えていた。
*****
「腐川ちゃん、この本返すね。ありがとー」
藍色のブックカバーを外しながら、王馬は一冊の本を腐川に手渡した。
腐川は訝しげに彼を見ながらその本を受け取り、雑に扱われて傷んでやしないかと本の状態を確かめつつ口を開く。
「な…なによ……もう読んだのね。…それにしても、どういう風の吹き回しよ?あんた…あたしの小説に興味なんかなさそうなのに…」
「にしし…そうだね。全然、全く、これっぽっちも興味無いね!」
サラリと笑顔で言ってのける王馬に嫌気が差す。
嘘ばかりつくこの男の相手は疲れるし、さっさと会話を終わらせてしまおう。
腐川はそう思ったが、興味が無いと言うならどうして突然本を貸せと言ってきたのかと疑問が湧いてきた。
「あんた…興味なんかないなら、なんであたしの小説読もうと思ったのよ?読書したいだけなら図書室にでも行けばよかったじゃない」
「んー…別に深い意味なんかないよ?ただ、いっつも陰気な腐川ちゃんが書く恋愛小説ってどんなのなのかなーって思っただけだよ!」
「そ、その割には細かくシチュエーション指定してきたじゃない…。主人公が学生で、2人きりの教室で男から告白するシーンが入ってる話…なんて」
貸した時はとにかく早く王馬にどこかへ行って欲しい一心でそれらしいシーンのある本を渡したが、よくよく考えれば不可解だ。
まるで、興味が無いと断言する恋愛小説でなければ意味がなかったとでも言いたげな…。
「にしし…次のイタズラにでも使えるかなぁと思ったんだけど、全然役に立ちそうもなかったよー。やっぱり他人の言葉なんて借りちゃダメだよね!」
「はぁ…分かってたことだけど、あんたと話すのは疲れるわね」
「奇遇だね!オレもそろそろ腐川ちゃんの珍奇な匂いに鼻が限界を迎えるところだったんだ!」
「誰がドブ臭いですって!?…も、もういいわ。これ以上無駄な時間を過ごすのはごめんよ」
ばいばーい、と明るい声を背中に受けながら腐川は自分の教室へと戻った。
1/1ページ