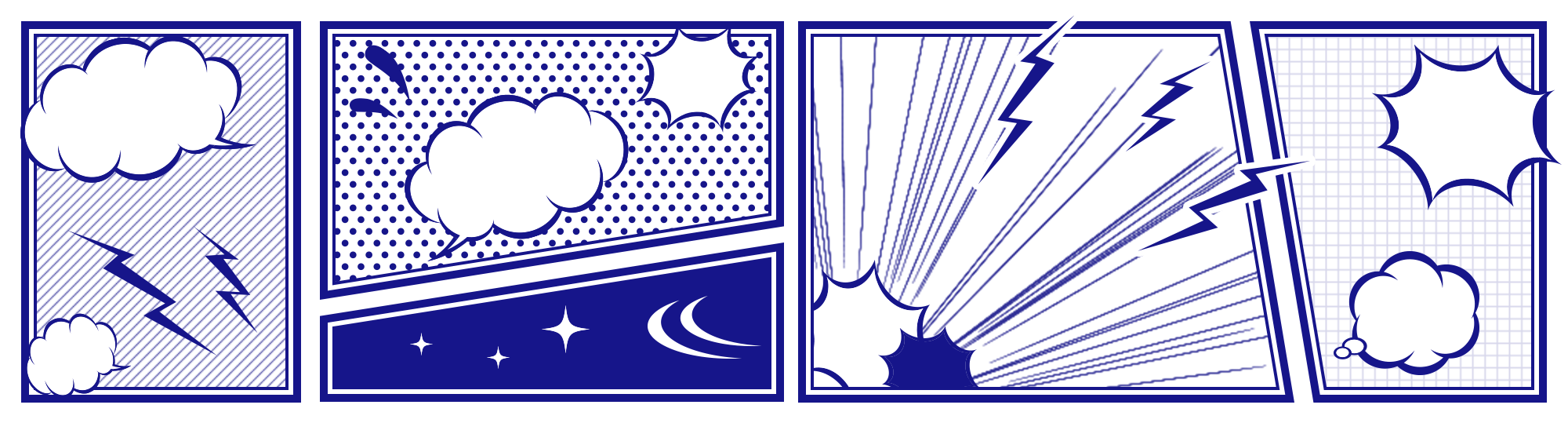同窓会
おなまえ
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
高校生の頃、いつも賑やかに色んな人を惑わせていた彼。
見る度にくるくる変わる表情と、何をするのか予測もできないあの人から目が離せなくなっていた。
仲が良かったわけでもないし、なんならまともに会話をした覚えもない。
あの頃もう少し勇気を出していれば…今になってこんな後悔することもなかったのかな。
大人になって月日の経過とともに多少の恋愛経験はしてきたつもりだけど、ふとした瞬間に思い出すのは彼の事ばかりで。
結局、私の一方的な思い出が美化されて拗らせてるだけなのかな。
「あれ、これって…」
ある夜の帰宅時、普段はチラシくらいしか入っていないポストに白い封筒が入っていた。
『同窓会のお知らせ』と書かれたそれは、久しぶりに高校生の頃の同級生達と会うきっかけをくれるものだった。
*****
「みょうじさん、久しぶりだね」
「もしかして最原くん…?ふふ、なんだか大人っぽくなってて一瞬誰か分からなかったよ」
緊張しながら足を運んだ同窓会会場で、あの頃よく話をしていた最原くんに声をかけられた。
高校生の頃は中性的美少年って感じだったけど、線の細さは変わってないもののすっかり大人の男性だ。
相変わらず、顔立ちは美人なままだけれど。
「そりゃあ…実際、もう僕らは大人なんだから。みょうじさんも、その…綺麗になったね。あ、いや、…あの頃も綺麗…だったけど」
「あはは、ありがとう。お世辞でも嬉しいよ」
「そんな…お世辞じゃ…」
「王馬クン!キミは相変わらずロボット差別がひどいですよ!!」
キーボくんの悲鳴にも近い声が聞こえて、呼ばれていた名前にハッとする。
来てるんだ、王馬くんも…。
心のどこかで期待はしていたけど、悪の総統であるらしい彼がこんなところに来るはずない…なんて思っていたから、意識した途端また緊張に襲われる。
いや、でも…私の事なんてきっと覚えてない。
ぐるぐると色んな感情が渦巻く中、声のした方へと視線を移す。
「えー?いーじゃん別に!キー坊は歳とらなくていいなーって話しただけじゃんかー」
「さっきの言い方だとそうは思えませんでしたけどね!ゴン太クンだってそう思いませんか!?思いますよねぇ!?」
「えぇっ?うーん、ゴン太にはよく分からないけど…キーボ君が傷ついてるなら、王馬君はちゃんと謝らなきゃダメだよ!」
腕を頭の後ろで組んで、必死なキーボくんに少しも悪びれる様子もなくあの頃と変わらない表情でにしし、と笑う王馬くん。
少しだけ背が伸びて、全てが変わってないわけではないんだけど。
彼の纏う雰囲気が…思い出の頃のあのままだった。
「…みょうじさん?大丈夫?」
「へっ?あっ…うん、大丈夫!ごめんね、ちょっとぼーっとしちゃって」
気がつけば王馬くんに気を取られすぎていたみたいで、最原くんに心配されてしまった。
「おーい終一!久しぶりだなぁ!…お、オメーはみょうじだろ!なんつーか…女って数年会わねーだけで随分雰囲気変わるもんだよなぁ」
「ふふ、百田くん久しぶり。大人になったら化粧したり服装が変わったり色々あるからね」
その後も懐かしい面々がやって来て、代わる代わる会話をしながら時間が過ぎていく。
見た目は変わっても中身は変わってないなぁ…とか、そんなことを考えながら昔の思い出話に花を咲かせて楽しい一時だった。
でも、あの人とは1度も話が出来ていないまま。
結局私が一番成長できてないのかも、なんて思いつつ少し酔いを覚ますためにその場を抜け出して外の風に当たる。
「…また、帰ってから後悔するのかなぁ」
街灯に照らされているせいか微かにしか見えない星空に向かってそんなことを呟いた。
こんなところで感傷に浸って、ちょっと痛い子みたいだなと思う。
「みょうじちゃん、何やってんの?一人でドラマ撮影ごっこ?」
「…お、王馬くん…?」
後ろから思い描いていたその人の声が聞こえて慌てて振り返る。
独り言を聞かれていたかもしれないこともあって、気恥しさから顔を直視出来なかった。
「あっはは!みょうじちゃんってホント変わってないよねー、あの頃のままって感じ」
「あの頃って……王馬くんと私、そんなに接点なかったじゃない」
「そう?だってずっとオレのこと見てたじゃん、今日と一緒でさ」
かぁ、と顔に熱が集まってくるのを感じる。
気づかれてたんだ、ずっと。
もしかしたら私の心の内までも知られているんじゃないか、なんて気すらしてくる。
どう答えればいいか…と言い淀んでいると、王馬くんは私に向かってニヤリと笑った。
「へぇ、ホントにずっと見てたんだ。カマかけたつもりだったけど、その反応だと大当たりみたいだね!」
「なっ…!?」
すぐに否定しておけばよかった、もうとにかく恥ずかしくて俯いて口を噤む。
これじゃ私、まるでストーカー気質な女みたいじゃないか。
「なーんて、嘘だよー!ホントはずっと知ってたよ。いつ話しかけてくれるのかなー…なんて思いながら見てるだけなのはオレも一緒だったからさ」
予想もしなかった言葉に顔を上げると、王馬くんはさっきまでの意地悪な笑顔をやめて、ふわりと優しい微笑みを浮かべていた。
「…さっきは変わってないって言ったけど、それも嘘かもね。だってさ、みょうじちゃんはあの頃よりも…綺麗になったと思う」
王馬くんの手がゆっくりと私の頬に伸びる。
ドキドキと胸が高鳴る。
都合のいい夢を見てるんじゃないかなんて考えがよぎったが、しっかりと頬に触れた手の温もりが現実だということを私に伝えてくる。
「オレはみょうじちゃんのこともっと知りたいって思ってるけど、みょうじちゃんはどう?」
「わ、私も知りたい…けど」
「けど、何?」
「これって…嘘じゃない、よね?」
「んー…みょうじちゃんが嘘ってことにしたいならそうしてあげるよ?」
彼は私の頬からそっと手を離し、自分の唇に人差し指を押し当てて挑発的に笑った。
本当に、次から次へと表情が変わって目が離せない人。
やっぱり私の気持ちはずっと、あの時のままだ。
「嘘には…してほしくないな」
「にしし、そもそも最初から嘘じゃないけどね!」
私が一歩踏み出していれば、あの頃ももしかしたら何かが変わっていたのかもしれない。
でも、今この瞬間のこの人の嬉しそうな笑顔を近くで見られたことは、今の私じゃないと体験できなかったことなのかな…と思った。
1/1ページ