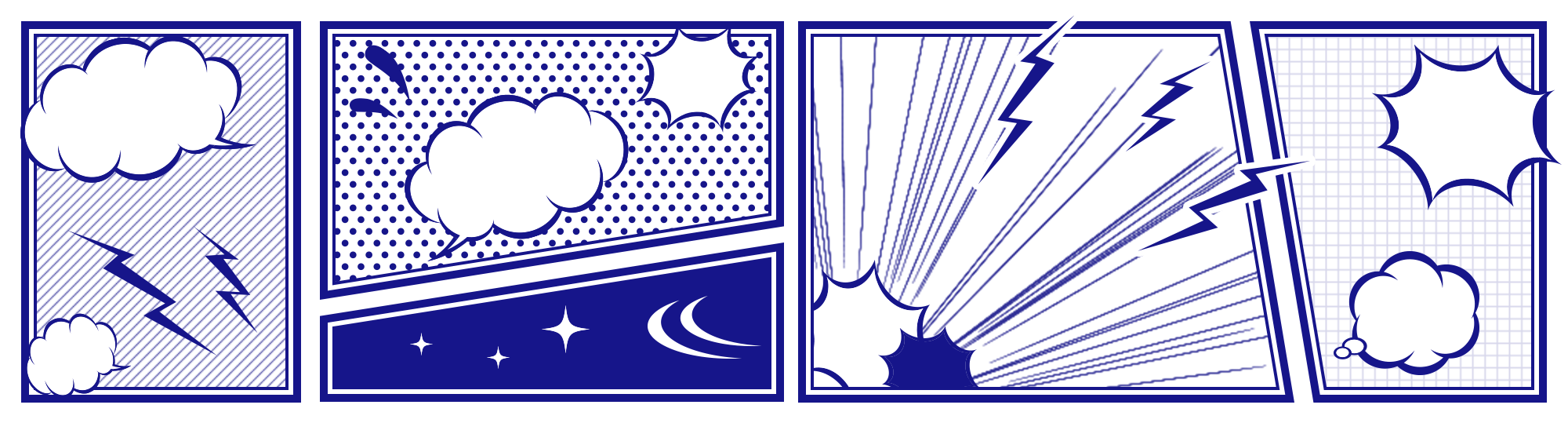すれ違い
おなまえ
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
スマホの着信音が聞こえて画面に目を落とす。
メッセージの差出人は…小吉くん。
なんとなく予想はできているものの、一応内容を確認してみる。
「…はぁ」
これで何回目だろう、前日に約束をキャンセルされるのは。
最後に会ったのっていつだっけ、なんて考えてもすぐには思い浮かばないほどの期間があいている。
今後私との結婚を私の家族に認めてもらえるようにするため、と彼は1年ほど前に会社を立ち上げた。
一応その会社は、彼が総統を務める秘密結社の隠れ蓑としての役割もあるらしい…けど。
なんだか最近は表の顔の部分が軌道に乗り始めたようで、あまり家にも帰っていないらしい。
忙しいのは分かってる。分かってる、けど。
「やっぱり、寂しいな…」
浮気なんてする気はさらさらないけど、少しだけ寂しくて他の人の愛を求める気持ちが分かるような。
そんなこと絶対しないし、できないけど。
他の人に揺らいじゃう時ってきっとこういう時なんだろうな…なんて。
モヤモヤした気持ちのまま目を閉じて、その日は無理やり眠りについた。
*****
「あ、なまえちゃんこっちこっちー!」
「ごめん、お待たせ!」
「大丈夫だよー」
ぽっかり予定が空いてしまって何をしようかと思っていたら、タイミング良く楓ちゃんからのお誘い連絡があった。
ほんと、ありがたいタイミングだったな。
一人でいたらきっと悶々としちゃって、もしかしたら不安定な気持ちのまま小吉くんに当たってたかもしれない。
「魔姫ちゃんもごめんね、待たせちゃって」
「別に、遅刻じゃないんだから気にしなくていいよ」
先に取っていてくれた席に座り、オーダーを取りにきた店員さんに紅茶を注文する。
2人の前にもまだ飲み物はまだ来ていないことから、そこまで待たせていたわけではないようで安心した。
女友達にありがちな最近どう?なんて話をしながら、なんだか高校生の頃を思い出して楽しい気持ちになる。
2人とも仕事も恋愛も順調みたい。…なんだか羨ましいな。
「なまえ、なんかあったの?いつもより元気ないけど」
「それ私も思ってた!…もしかして、王馬くんと何かあったの?」
「あー…うん、ちょっと。喧嘩したわけではないんだけどさ」
誰かに聞いて欲しいという気持ちがどこかにあったのかもしれない。
結局私はここ最近のことを2人に話してしまった。
もうしばらく会えていないこと。
…もしかしたらこのまま自然消滅するのかも、なんて考えていること。
「そっかぁ、それは確かに…ちょっと不安になるかも」
「でも、仕事なんでしょ?仕方ない部分はあるんじゃないの」
「うん…仕方ないのはもちろん分かってるんだけどね。その、実は今日も元々約束してたのをキャンセルされてて。…記念日くらいは、なんて勝手に思ってたからちょっと悲しくてさ」
記念日、という言葉に楓ちゃんと魔姫ちゃんは顔を見合わせる。
楓ちゃんのあちゃー、と言いたげな顔が見えて、やっぱりそういう反応になるよねと苦笑してしまう。
「男性って、そういうの疎い人多いって言うもんね…」
「まぁ…1回ちゃんと話し合ってみたら?どっちにしろ、今のままじゃなまえの方からダメになるよ」
「うん…そうだね。聞いてくれてありがと」
2人に励まされて少し気は紛れた。
その後も色々な話をして、結局自宅の最寄り駅に着いたのは夜10時を回った頃だった。
お酒を呑んだ余韻もあって、気分良く駅から家までの道を歩く。
マンションの玄関から中へ入り、自分の部屋のある階へと上がってもうすぐそこ、という時だった。
あれ、ドアの前に誰かいる?
暗くてよく見えないけれど、誰かが私の部屋の前にしゃがみこんでいた。
どうしよう、不審者なのかな。
怯えながら目を凝らして、やっとその人が誰なのかに気がつく。
「……小吉くん?」
「あ、おかえり」
疲れた顔でにしし、と笑う彼はずっと会いたかったその人だった。
急いで近くに駆け寄ると、そのまま抱きとめられて私の体が腕の中に収まる。
「どうしたの、こんな時間に」
「どうしても会いたかったから来ちゃった」
あまり休めていないのは本当らしく、いつもより声に覇気がない気がした。
「そっか…私も、会いたかった」
本当はもっと言いたいことがあったはずなのに、それだけしか言葉に出来なかった。
自然と目から涙がこぼれて、小吉くんがそれを指で拭う。
「寂しい思いさせてごめん」
「…うん」
「ちょっと話したいことがあるんだけど、中入れてくれる?」
鍵を開けて中へ入り、小吉くんをリビングに通す。
飲み物を何にするかと聞いたけど、後でいいからとそばに来るように言われた。
「話って、何?」
「うん…仕事、今日でひと段落ついたから。明日からはもっと時間取れると思う」
「そうなんだ」
「だからさ、なまえさえ良ければなんだけど。…家、探さない?2人の」
「それって…」
「もっとなまえと一緒にいたいから、オレと住まない?ってこと。…もちろん、結婚前提で」
ちゃんと色々、私のこと考えてくれてたんだ。
小吉くんも私と同じ気持ちでいてくれてたんだ。
そうであって欲しいと思っていたことが現実だと分かって、嬉しくてまた涙が出る。
「ホント、なまえは大人になっても泣き虫だね」
「だって、嬉しくて…小吉くんも、私と一緒がいいって思ってくれてたんだって…」
「そんなの当たり前じゃん。オレがどれだけなまえのこと好きか、まだ分かってないわけ?」
小吉くんが私の頬に手を当てて、顔を上げさせるように力を込める。
目の前には優しい笑顔を向けてくれる彼がいた。
「なーんか、思い出すなぁ」
「え…何を?」
「数年前の今日、なまえがオレに告白してきた日のこと。あの時も今みたいに嬉し泣きしてたよね」
「…ふふ、そうだったね。覚えてたんだ」
「そりゃあね。人生変わった日だもん」
そっと彼の顔が近づいて、唇が触れ合った。
「そういえばさっきの返事、まだ貰ってないけど」
「あっ、…私も、小吉くんともっと一緒にいたい!」
「にしし、だよねー!」
満足そうに笑う小吉くんにぎゅっと抱き寄せられる。
寂しかった気持ちはいつの間にかどこかへ消えていて、今あるのは安心感と充足感。
先のことは分からないけれど、それでもきっと私の隣にはこの人がいるんだろうなと思った。
1/1ページ