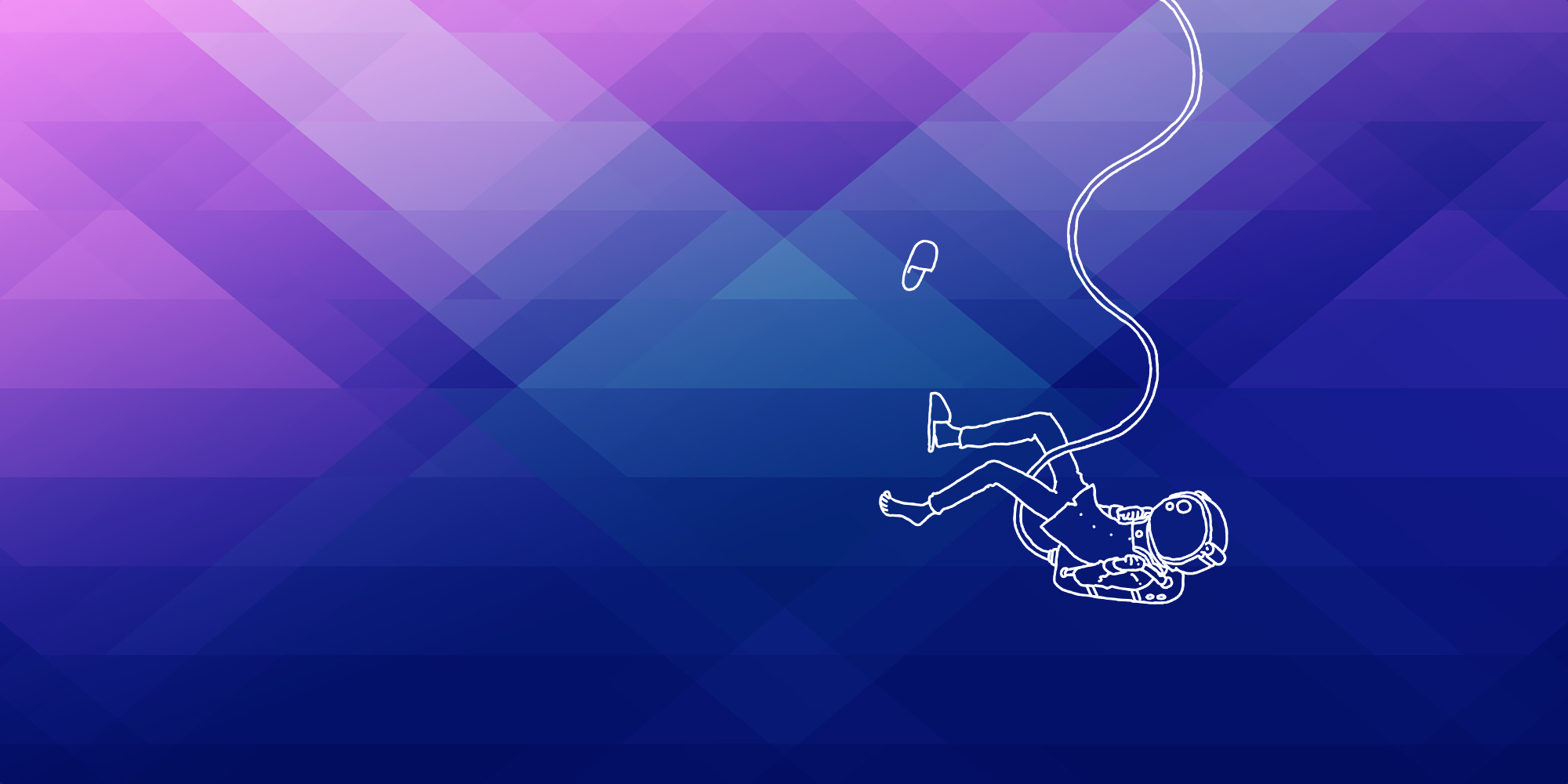二、死んでいく世界
私は大きな商家に生まれた。
三人兄妹だった。双子の兄と、末っ子の私。
私たちは仲が良かった。上の兄の鷹久お兄様も、下の兄の鴨太郎お兄様も、一見気難しそうだがどちらも優しくて、私は小さい頃からしょっちゅう遊んでもらったものだ。
私は学道も、芸道も、武道も好きだった。
特に、女に似合わず武道が一番楽しかった。
剣に長けた鴨太郎お兄様と一緒に道場に通い、男の子に混じってよく剣術を教わった。
始めは男の子の力に圧倒されるばかりだったけれど、いつしか私には誰も適わなくなり、免許皆伝にまでなった。
その頃には、そうやって何かに熱中するしか生きるよすがが無くなっていた。
私は、お父様やお母様から全く相手にされなかった。
朝目が覚めてから、食事、習い事、夜眠るまで全てに至るまで女中に任され、家族の誰とも顔をあわせることがない日も多かった。
いつしか、大好きなお兄様達とも会えなくなっていた。
元々病弱だった鷹久お兄様は、私が十五になる頃にはほとんど寝たきりになってしまっていた。
襖はぴったりと閉ざされ、私が気晴らしに覗くのも許されなかった。
そして、鴨太郎お兄様の方は、いつからか怖くて話しかけることも出来ないような気難しい兄になっていた。
子どもの頃は幸せだった。
「あの子は学問も出来すぎてしかも武道なんて……。あんなに隙の無い子にはいい婿どころか男も寄ってこないでしょうよ」
そうお母様が漏らしていたのを聞いてしまった時、私は、この家に幸せになるには決定的に何かを間違ってしまったのだと気づいた。
そして私は、今まで自分がいた世界と、この窮屈で憂鬱な世界と、居場所のない世界と、さよならすることに決めたのだ。
私は手元にあっただけのお金と、少しのパンと、それから、蔵の中にあった一振りの刀を持って、家出をした。
だけどその一夜は、これまでの私の人生の中で最悪の一夜になった。
家を抜け出したまではよかったものの、私はその夜寝る場所の当てもないことに気づいた。
歩き疲れて真夜中の道をふらふらしていると、色んな人に声をかけられた。
始めは、夜中見廻りをしている奉行所の人。
小さな荷物だけを持ってふらふらと歩いている私はどう見ても家出少女だったのだろう。
「未成年がこんな夜中に出歩いちゃダメだよ?お嬢ちゃん、いくつ?家は?」
「な……なんでもないです!大丈夫ですから……!」
補導されたら家に連れて帰られると思った私は、そのおじさんの手を振りほどいてなんとか逃げた。
安心したのも束の間、その次は、着物をだらしなく気崩した三人の男の人に絡まれた。
「あれ~?珍しいな、こんなところに女の子がいる」
「お嬢ちゃん、どうしたの?こんな怪しいところに一人で」
「帰るとこが無いんなら、俺たちが拾ってあげようかぁ?なんて。ギャハハ」
酒臭い息に、下卑た笑い声。
同じ男の人のはずなのに、どうしてこんなにお兄様達と違うのだろう、と思いながら、私は、どうしようもできずに怯えた。
「なんか答えてよぉ、お嬢ちゃん。なに、もしかして家出?」
「ち、ちがいます…っ」
「じゃあ、なんで出歩いてんの?ホラ、辻斬りとか、こわーい人が出るから帰らなきゃ」
三人の男の人に、じりじりと距離を詰められた。
私は、無意識のうちに抱きかかえた刀をぎゅっと握りしめていた。
「ほらほら、こっちおいでよー」
そのうちの一人に、腕を掴まれた。
「きゃあ!!」
全身に鳥肌が立って、気がつくと私はその人を思いっきり突き飛ばしていた。
そして、慌てて逃げ出す。
「お、おい、待てよこら!!!」
路地裏から大通りに出て、明かりの下をひたすら逃げた。
お願いだから、追いかけてこないで。
私は、転びそうなくらい、無我夢中でひたすらに走った。
浪士さんは、追いかけてこなかった。
それがわかって少しだけ安心すると、私の目からは次々に涙がこぼれてきた。
なんで。お兄様、助けて。怖い…。
「…………兄さま、鷹久兄さまぁ……っ、ひっく…」
こらえきれなくて、私はそのまま声を上げて泣いた。
「兄さま、鴨太郎兄さま………っ…ぐすっ…」
帰りたい。
うちに帰りたい。怖い………。
「兄さま、助けて………母さま、父さま……っ」
気が付くと私は、あれほど嫌いだったはずの母さまと父さまの名前を呼んでいた。
私には、家族しか頼る人がいなかった。
この時にはもう、私は気づいていたのだ。
世界は、こんな小さな私一人には広すぎる。
いくら家という小さな檻から逃げ出したって、私には、どこにも行くあてがないんだと。
結局、私はこの世のことを何一つ知らなかったのだ。
だけど、それを知るのが遅すぎる。
私は、ふらつく足取りで家に帰ろうとした。
いくら叱られてもいい。
家出しようとしても、私には一晩すらできないと分かったから。
私は涙で溢れかえった目をこすりながら、来た道を戻ろうとした。
……だけど。
なぜかはわからないけど、悪いことはとことんまで続くらしい。
神様は残酷だった。
「きゃ………!」
暗闇の中で私は、誰かとぶつかってしまう。
その拍子にバランスを崩して、尻もちをついて転んでしまった。
「ごめんなさい!」
私は、慌ててぶつかったその人に謝る。
そうして、起き上がろうとした瞬間――――――、
「ひひひ………」
不気味な笑い声が聞こえてきた。
怪しいその声に、一瞬で私の体は硬直した。
「え……?」
目の前の男の人は、さっきの怖い三人の人たちみたいに、素浪人のような格好をしていた。
腰には刀を差して。笠の下の目が、私の抱きかかえていた刀を見た―――気がした。
逃げなきゃ。
そう思ったのに、怖くて体が動かなかった。
目の前の男の人が、ふいに持っていた刀を抜いて――――――、
大きく振りかざした。
“辻斬り”
さっきあの浪士さんが言っていた言葉が、鮮明によみがえってきた。
「いや…いや、やめて…っ!」
殺される。
そう思った瞬間、私は何とか立ち上がってその場から逃げようとした。
それよりも早く、目のすぐ横に刀が降ってきた。
「きゃあ!」
すんでのところで避ける。
けど、その一撃で私はすっかり腰を抜かしてしまった。
「誰か、誰か助けてっ!」
私は冷たい道をひた走る。
だけど、その人はどこまでも追いかけてきた。
辻斬りさんが、もう一度刀を振った。
その瞬間、背中に鋭い痛みが走った。
「あっ………!」
冷たい、何かに貫かれたような感覚だった。
だけど、それはすぐに熱くなる。
皮膚全体をえぐられた様な痛みが走って、ああ、これが斬られた痛みなんだ、と思うと同時に、地面に顔を殴りつけられた。
斬られたところがどくどくと脈打っている。全身が心臓になったみたいだ。
もう、私には泣く力が残っていなかった。
ただ、ぼんやりと私、死ぬのかな、と思う。
それを恐れる元気さえもう残っていなくて、死んでしまう前にお兄様に会いたかったな、家出なんてした罰だな、なんて途方もないことしか頭に浮かばなかった。
上も下も分からず、身体中が痺れて溶けていくような感覚に襲われ、やがて、私は意識を失った。
.
1/1ページ