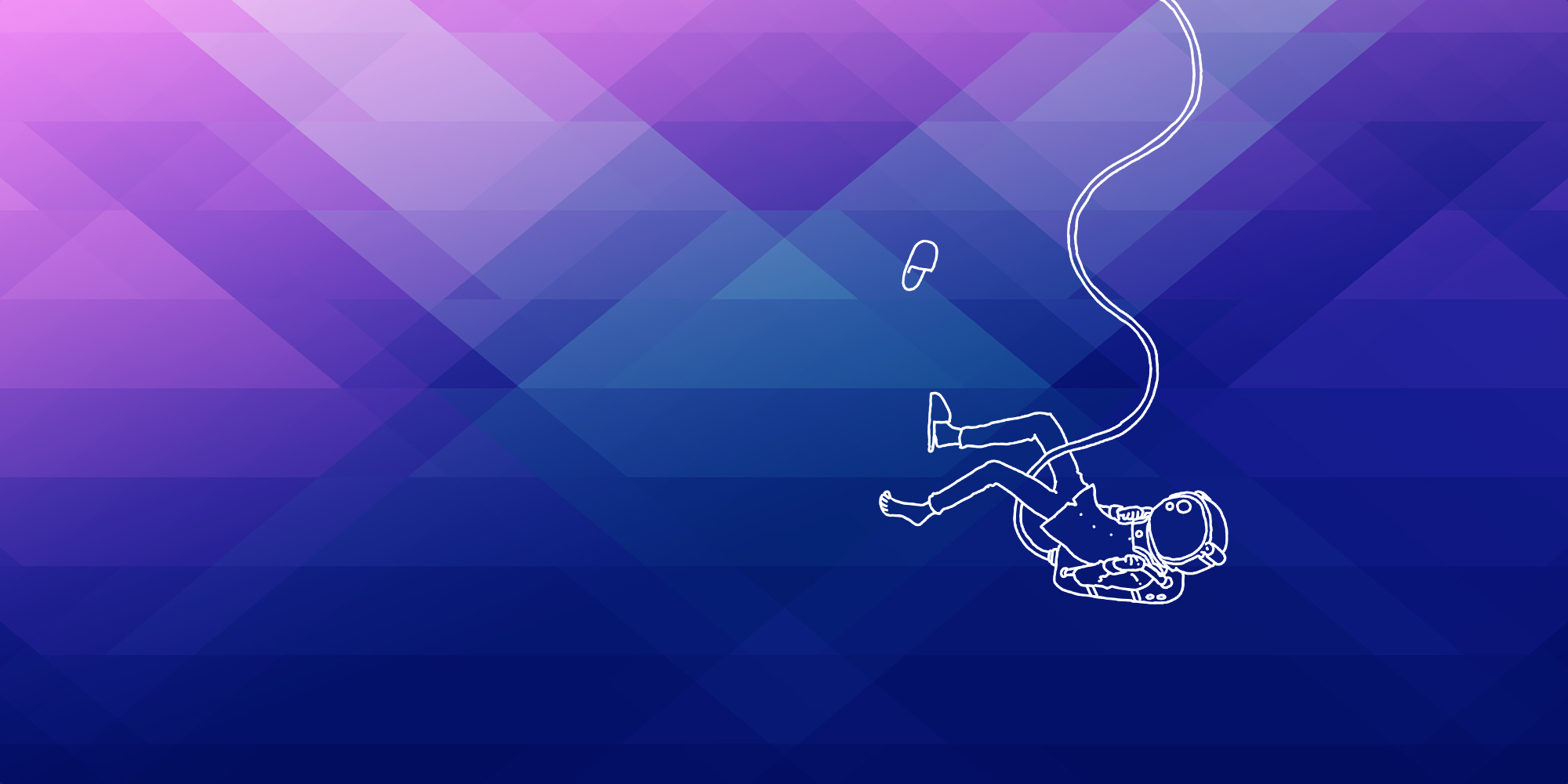一、ふたたびはじまり
真っ青な絵の具が滲んだキャンパスに、筆で牛乳を流したみたいな空。
「晋助、どこ行くの?」
私は前を歩いている彼に訊ねた。
「ん?」
彼は僅かに振り返った。
長い前髪からのぞく、翡翠色の瞳。
この瞳が本当は暖かいことを私は知っている。
「…あの港に船を停めてある」
「え、あそこ?」
「ああ」
私はなんだか嬉しくなった。
彼がそう言ってしばらく経たぬうちに、大通りから段々裏道や暗い路地を抜けていくと、ある寂れた、小さな港に出た。
汚れたコンクリートの波止場、その背後には、トタンとレンガが崩れそうなボロ倉庫。
この鬼兵隊が始まった場所。
元々ここは、ある大財閥と取引をしている商社が専用していた港だ。
…私が生まれた、あの伊東家と。
最も、私が家を出る前からその商社は潰れてしまって、(伊東家に潰されてしまって)それ以来倉庫などが取り壊されることもなく廃墟化している。
だから出会ったばかりの私たちは、ここで追手から息を潜めて逃げ暖をとったのだった。
晋助の言った通り、船はそこに停泊して、波にあわせて僅かにゆらゆら揺れていた。
乗船口が開く。
「…懐かしくなったのか」
いつまでも水面を眺めている私を見て晋助が言った。
「うん」
晋助は私の隣に立って同じように海を眺めた。
水の底は、妖しい深緑。
「俺も」
あの時も、同じようにこうして二人で海を眺めていた。
凍るように冷たい夜風を、麻痺した感覚で冷たいとも思わず頬に感じながら。
冷たい家が嫌になって、身一つで家出しただけの私に、本当にいいのかと彼は訊いた。
私は間髪なく頷いたのだ。
この人に出会った時から、心は決まっていた。もう何年も前の話。
.