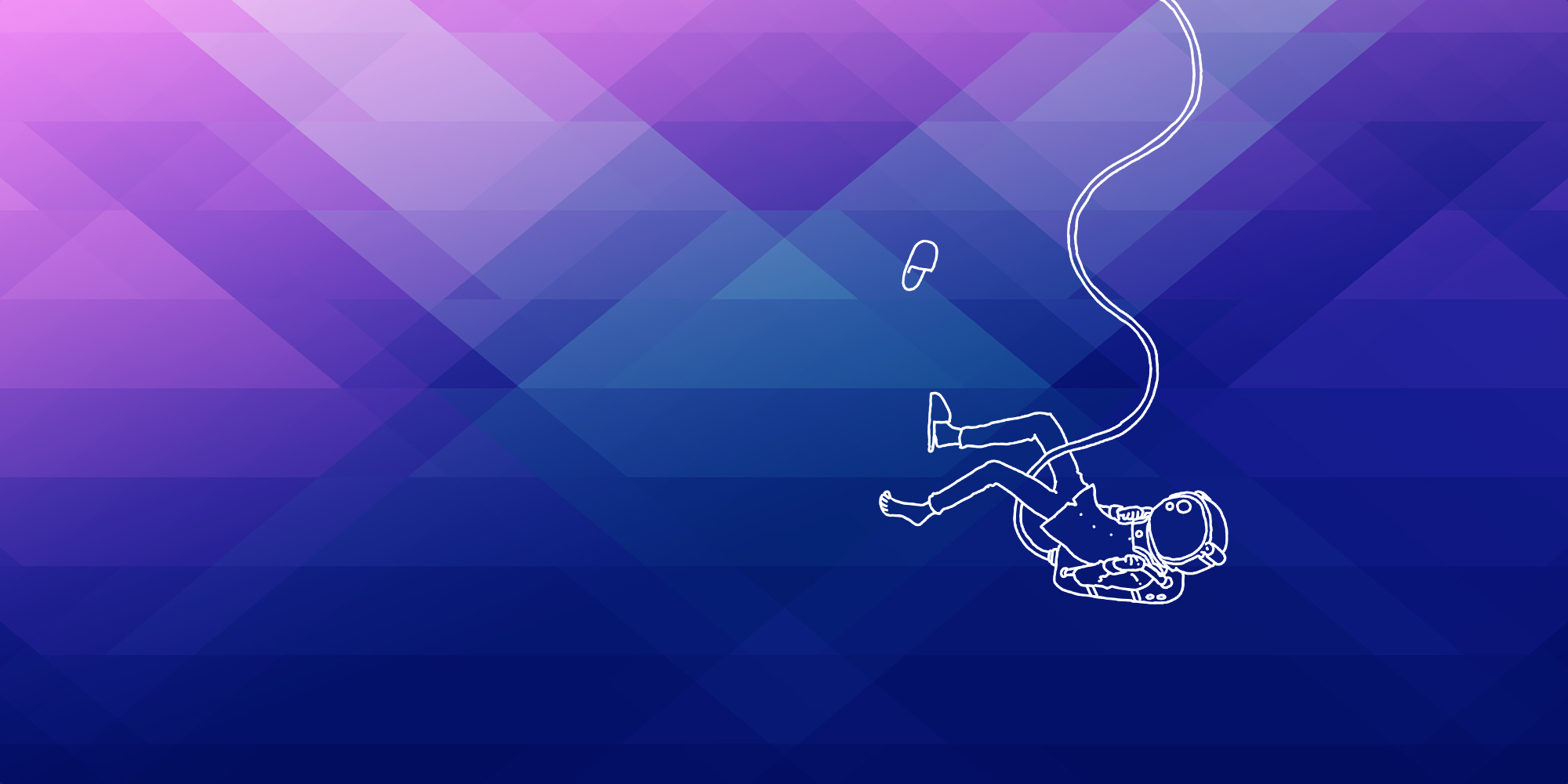一、ふたたびはじまり
『侍の国』。この国がそう呼ばれていたのは、今は遥か昔の話。
いつからかそう揶揄されるようになった、その象徴が、この江戸の街の中心にそびえたつターミナル。
瓦屋根と白い漆喰の壁の長屋が連ねる江戸の街には不釣り合いな、超高層の銀色の塔。
そのターミナルを編笠の下から見上げながら、町人と天人が行き交う街を歩いている一人の男がいた。
蝶々が踊る着流しに、指では煙管を弄び、紫がかった黒髪の下には包帯が覗いている。
彼、高杉晋助は、冷たい瞳で江戸の青空を眺めながら、そっと唇の端をつり上げた。
高杉はターミナルに着いた。
裏口の前に伸びる、川とも言えない小さな水路の上にかかった小さな木造の橋。
その欄干の上に、一人の女が腰掛けて、水路を下に足を投げ出してパンをかじっている。
薄桃色の小袖に長い髪を高く結って、女は静かに流れる水を物憂げに見つめていた。
高杉が近づく、と、示し合わせたように彼女は振り返った。
「晋助!」
彼女は花が開いたように笑って、ひょいと欄干から降りた。
「おかえり、由紀、会合おつかれさん」
「ありがと、迎えに来てくれたの?」
「気が向いたからな」
由紀と呼ばれた彼女は笑って、「いる?」と手にしていたパンを半分ちぎって高杉に差し出す。
「いらねえよ、んな甘ったるいもん」
「えー、チョコクロ美味しいのにい」
由紀はそう言ってクロワッサンを全て口の中に放り込んだ。
「お前、その着物似合ってない」
「えっ、うそ。女子にそんなこと言っちゃう?晋助ひっどーい」
「髪の色と合ってねえんだよ」
由紀は自分の着物と括った髪の先を交互に見て、うーんと顔をしかめた。
由紀の髪は、不思議な色をしている。絹糸のように滑らかな髪は、墨を流したように深い黒なのに、光が当たった部分だけに底光するように青が見える。
「似合わないのかあ。晋助いる?どうせ身長一緒じゃん」
「一緒じゃねえよ黙れ」
あはは、と笑う由紀に、彼女が背中に掛けていた笠を被せて、行くぞ、と高杉は言った。
二人は江戸の街を歩き出す。
「どうだった、春雨とは」
「んー、交渉は予定通りだった、けど、」
「けど?」
「なんか面倒なことになったかもしれない」
「面倒なこと?」
うん、と由紀は頷いた。
「なんか、第七師団?の団長っていう、多分夜兎の男の子に絡まれて」
「ほお」
「よく分かんないけど気に入られたぽいんだけど、また別のことに巻き込まれそうだなあって」
「へえ、まあいいんじゃねえの?第七師団って、春雨でも最も武闘派の連中だろ。そいつらを利用できたらこっちのもんじゃねえか」
「うーん、まあ細かい事情帰ってから話すね」
そう言いながら、由紀はふと振り返った。
相変わらず賑やかな江戸の街。
下町らしく長屋が数多く並び、着物の袖をたすきでくくった商人たちが行き交う通り。
その一つに、赤い壁のひときわ目立つ長屋があった。
二階の看板には『万事屋銀ちゃん』、一階には『スナックお登勢』の看板と縹色の暖簾…。
「どうした?」
先を歩いていた高杉が立ち止まる。
「ううん、なんでもない」
由紀は彼に続いた。
.