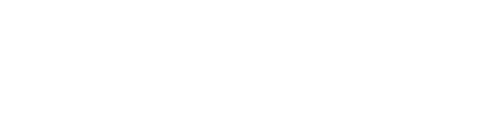冬空と二人
いつもなら、ソファでパルシュキを食べながら少女マンガを読んでたはずなのに。
”ヴァルシュ”ことワルシャワ市の体現は、電話先が通話を終了させたのを確認してから大きなため息を漏らした。
なんだって「特別な日の式典から帰らずスーツ姿で酒屋に向かい他人の家にまで上がりこんで眠っていたポーランドを回収して食事と身支度を手伝って国際会議に出席するための交通手段を手配して彼を送り出す」のが、東欧最大の都市である自分の仕事なのだ、オレだって昨日お祝いに日本料理店で働く知り合いのサクラに貰った漫画を読むのを楽しみにしてたのに。今だって、次から次へとかかってくるポーランドの遅刻に関する苦情と質問にいちいち説明して謝罪しているのは自分なのだ。迷惑ったらありゃしない。
「気晴らしねぇ...」
ひとしきり自分の部屋を漁っても、スマートフォンを弄っても、これといって楽しいことは見当たらない。再びため息を漏らしたヴァルシュはふわふわもこもこの青いパジャマからお気に入りの民族衣装に着替えると、意外と難しい旧市街までの瞬間移動に意識を集中させた。
いつもなら、ポーランドちゃんと並んで座ってるはずのお洒落なカフェ。
いつもなら、ポーランドちゃんと一緒に歩いてるはずの公園。
いつもなら、ポーランドちゃんと笑って過ごしてるはずのこの時間。
11月12日、ポーランドの国祭日である”民族復興記念の日”の翌日という日におとずれたワルシャワ旧市街は静寂に包まれて、物語に出てくるような、もしくは再び「北のパリ」が目の前に現れたかのような感動をもたらした。昨日は夜ふかしをしたからみんなまだ寝ているのかしら。それとも敬虔なカトリック国家だから、安息日の今日は教会にいるのかも。未だ彼とギクシャクした関係が続く中で昨日のセレモニーに出席したウクライナは、先に国へと帰った上司に休暇を取りたいと申し出、喧嘩したばかりの相手と仲直りできるわけでもなくこの街を歩いていたのだった。
「友達だと思っとったのに...もうお前のことなんか嫌いだし!」
1か月前に引きとめる間もなくウクライナの家を後にしたポーランドは、WW2に関する資料の公開を求めに来ていた。しかし聞き入れてしまうと各方面でのウクライナ共和国の安全が脅かされるから、と丁重に謝りながら断ったウクライナだったが、戦争で最も打撃をうけた国のひとつであるポーランドにとっては信じられない決断だったらしくそれ以来彼とはまともに会話できていない。会議場であってもお互いに目をそらしてしまうし、ウクライナの方から話しかけようとしてもすぐにリトアニアやアメリカ、ハンガリーなど友好な関係を結んでいる国がポーランドの周りに集まる。ほんの先月までは私もあの中にいたのに、と寂しいような悔しいような思いを感じるウクライナであった。
ひとりぼっちで歩く街では特に寄り道することもなく、冬が近づいて数がめっきり減った観光客に交じって旧市街広場に出た。交通量が多い道路の上を橋でわたったところにあるこの広場は、パステル調の歴史的建造物が立ち並ぶ観光名所だ。ウクライナはこの場所が大好きで、この国に来るたび仕事の後に時間を取ってポーランドと遊びに来ていた。ああ、あれもこれもポーランドちゃんと一緒だったらもっとずっと楽しいのに___。沈んだ気分のまま、人目も気にならず広場の中心にある人魚像の影に座りこむ。すると突如、
「お姉さん、せっかく此処に来たんだから悲しい顔するなよ。寂しいならオレが案内するから」
像の反対側から少年が姿を現した。ワルシャワ近辺に伝わる黒とオレンジを基調とした民族衣装に身を包んだその姿からして近隣の住民なのだろうが、美しいクイーンズイングリッシュを話している。キャラメル色の髪にココア色の瞳をしたその少年は、立ってみるとウクライナよりも背が高いかもしれないくらいだった。顔にはあどけなさが残り、中学の第2学年くらいかな、とウクライナは心の中で予測を立てる。初対面の相手ではあるが第六感に訴える物もない、ここは案内してもらってもいいだろう。
「そうね、ひとりぼっちはちょっと寂しかったし、お言葉に甘えてお願いしちゃおうかしら。私はソフィヤっていうの」
「会えて嬉しいよ、オレはヴァルシュ」
互いの目をみて握手を交わすと、二人は歩きだした。
「どういうとこが見たい?」
そうヴァルシュがきいてくるので速攻でスイーツ食べに行こう、と答えると驚いた様子だったが、クラクフ郊外通りにあるロディ専門店に連れて行ってくれた。突然のわがままだったので代金を払おうとする彼をとめて二人分のチョコレートアイスを購入し、通りをひとつずつ歩いて行くことにした。アイスを渡す時に見たヴァルシュの顔は、髪型や色のバランスこそ違うがどこかポーランドの面影があった。やっぱり国民と体現は似てるわ、とあらためて思うと、面白い。
ヴァルシュはいろいろな話を聞かせてくれた。ワルシャワと、彼について。
夏には旧王宮を見学するためにポーランド中から子どものサマーキャンプが来ること。クリスマスが近づくと街全体がイルミネーションのカタマリになること。ウクライナの首都キエフがワルシャワの姉妹都市であること。クラクフ郊外通りは、途中から新世界通りへと名前を変えること。意外にもポーランドの人口はワルシャワに集中しているわけではないということ。
もちろん、隣国であるウクライナにとってはデータとして知っていたことが殆どだったが、実際にその街に住む人に語ってもらうというのは何か自分の興味と知識が認められたような気がして嬉しかった。
ヴァルシュ自身のことと言えば、先程の人魚像のモデルとなった伝説の人魚を助けたとされている夫婦の夫がヴァルシュという名前で、それが彼のニックネームだということとか。親は居らず、一つ上の女の子と一緒にある青年の家に住んでいるということも。そして、その青年が近頃大切な友達と喧嘩をしてしまい、仲直りのタイミングがつかめず困っているということだった。
「あら、私もなのよぉ... 私も大切な友達と喧嘩しちゃって。彼はワルシャワに住んでいるのだけれど、私はウクライナから来たの」
ウクライナが思わずポーランドのことを口にすると、ヴァルシュは目を輝かせた。
「ああ、それならいい相談相手を知ってる!結構歩き回ったし、会いに行くついでにお昼にしよう。ポーランド料理はあとで御馳走するよ」
そう言ってヴァルシュが向かった先は、イェロゾリムスキェ通りとマルシャウコフスカ通りという二つの大通りが交差する場所のすぐ近くにある日本料理店だった。「NIPPON-KAN SUSHI」と書かれた看板の下をくぐると、そこにあったのはきっちりとスーツを着た中年のアジア人男性たち数人の姿だった。皆同じ言語を話しているようなので、日本人だろう。ヴァルシュは客席の間を縫って空いている席に座ると、オーダーを取りに来た若い店員にCześć!と笑いかけ、ウクライナには想像もつかない”ギョーザ”だの”ウードン”だのを注文し、最後にあとで話があるんだけど、と付け加えた。店員はまた相談しに来たんですね、と楽しそうにほほ笑むと伝票を持ってキッチンへと戻っていった。一体何なのだろうか。
しばらくして例の店員が腕いっぱいに料理を抱えてやってくると、彼女はなぜかエプロンを外してウクライナの横に座り込んだ。ウクライナがあっけにとられている間にも、ヴァルシュと店員の会話は進んでゆく。
「それで今日はどんなご相談なんですか?」
「こちらソフィヤ、ウクライナから来たんだけど、ワルシャワにいる友人と喧嘩しちゃったらしいんだ」
「喧嘩...ですか...」
ハーイ、ソフィヤよ、とすかさず言うウクライナに店員は、はじめましてサクラと申しますとしとやかな笑みを返した。うっかり出てしまったアメリカンな作法に驚いたのか、はたまた喧嘩についての相談はあまり自信がないのか、顔は曇っている。
「ちなみに、相手は男だぞ~」
慌ててそうヴァルシュが付け加えると、サクラの表情が一変した。
「そういうことでしたか!それなら少女漫画発祥の地、日本国で生を受けました私を是非お頼り下さいっ!」
「それなんだけど、相手がポーランド人の男なら、ハグとキスだけじゃ難しいから...」
「そこはですね...」
なんだか話が変だ。”大切な友達で、性別は男だ”とは言ったが、恋人だとも意中の人だとも口にはしていない。どうやらこの二人は所謂「恋バナ」が好きなクチなのだろう、今止めなくてはどんどん暴走してしまう。
「あのね、そ、そういう関係じゃないのよ、ほんとに。ただ、幼馴染っていうか、いままでこんな大きな喧嘩したことなかった子っていうか」
二人とも、ウクライナの言葉を受けてはっと我に返ったようだった。ごめんな、すみません私としたことが、と口々に謝られ、また困る事になるのだったが。
サクラはしばらく考え込んだ後にヴァルシュに何やら耳打ちした。彼がそれに対して頷くと安心したようにウクライナに向き直り、
「そうですね、パワースポットの力を借りてみてはいかがでしょうか」
と言った。パワースポット?と聞き返すソフィヤに、サクラはワルシャワの地図を見せた。街の東寄りを流れるヴィスワ川に架かるシフィェントクシスキ橋の袂には”人魚像”の文字が。人魚像って一つじゃなかったのね、と目を見張るウクライナに実は3つあるんですよ、期待通りの反応有難う御座います!とサクラが答える。
「そして...」
「その人魚像の西側、つまり人魚の背中側に立って相手と待ち合わせすれば、相手と願った通りの関係になれるっていう伝説があるんだ」
そうして今ウクライナは、ヴィスワ川の対岸に見える街並みと自然を眺めている。彼女の背後では人魚が盾と剣を青空に振りかざしていた。手元に水色のスマートフォンを握りしめ、肩の震えが止まらない。早く電話しないと、日が暮れちゃうのに___
「ソフィヤさん、頑張ってください!」
「相手だって絶対に仲直りしたいと思ってるよ、大丈夫」
サクラとヴァルシュが口々に送る声援も耳に届かないまま、ウクライナは「もう、当たって砕けるわ!」と叫び画面をプッシュした。
すぐにコール音が鳴り始め、黒い背景に浮かび上がる”ポーランドちゃん”の文字。
プルルルルルルルル…
「お願いポーランドちゃん、応えて…!」
携帯を両の手に包み、瞼に押し当てる。1回、2回、3回… 機械的なコールが続いたあと、突然に間延びした英語がスピーカーから聞こえてきた。
「ポルスカ様だしー、お前、ポーランド語通じる人ー?」
一瞬の間も開けずにウクライナは答えた。
「ポーランドちゃん、私…」
ポーランドちゃんに会いたい。そう声を絞り出した途端、人魚像に反射したオレンジ色の夕日が眩しくて、目を閉じれば涙が溢れてきた。もし大切な友達だって思ってるのが私だけだったらどうしよう。もしも今ここで”嫌だ”って言われたら?そう思うだけで心がちぎれてしまいそうになって、気がついたらポーランドの声を聞くことなく電話を切ってしまっていた。
「そんな、私、」
ウクライナは、いつの間にかホーム画面が表示されているスマートフォンを呆然と眺めていた。このままではポーランドはウクライナがどこにいるのか知らないままになるが、もう一度電話などしたら彼の気分を害してしまわないだろうか。
「ソフィヤ…」
桜の声にも答える気力が無いまま、ソフィヤはその場に立ち尽くした。
ポーランドは、ワルシャワ中の至るところに瞬間移動を繰り返していた。わかる。人々の好奇と恐怖の視線は自分に向けられているのが分かるのだ。地元の人ともなればきっと「また歩かないで瞬間移動ばっかりして、少しは運動しなさい」なんて事をいつ彼に忠告できるのかタイミングを伺っていることまで想像がつく。それもこれもウクライナらしき電話の相手が、場所も告げないで「会いたい」だの言って切ってしまうからだ。いきなり呼び出すからにはせめてワルシャワに居るだろうと検討をつけてあちこち飛び回る自分もお人好しである。それとも、相手がウクライナだと思うからだろうか。彼女とは先月喧嘩をしてしまい未だに話せてこそいないが、本来とても大切な友達なのだ。
その時、2世紀差の弟のようなワルシャワのことが頭に浮かんだ。色々と不思議な趣味を持つ彼が以前していたおまじないだのパワースポットだのの話に、”ヴィスワ川の岸辺に立つ人魚像の影に立って相手と待ち合わせするとその人と自分が望む関係になれる”と言うものがあった。もしかしたら、ウクライナもその話を知っているかもしれない。ポーランドは人々の視線を振り切って、像の少し手前へと瞬間移動した。
ヴァルシュはウクライナのことを慰めながらも、内心では自信を持っていた。ポーランドは来る。彼に以前この場所についてを話したことがあるのだ。ワルシャワという街を愛し人並み以上の記憶力を持つフェリクスのことだから、きっと覚えているだろう。その時、
「やっぱり、ここにいたんね」
背後から声がした。そこに居たのはポケットに両手を入れたポーランドで、口調から分かったのかウクライナが人魚像の陰から顔を出す。ポーランドは何も言うことなく、ただウクライナのことを見つめた。ウクライナも彼女の大きな碧い瞳を開き、見つめ返した。
サクラもワルシャワも息を潜めて傍らから見守った。像の陰にいる男女二人を木の陰から覗いている男女二人とはどういう図でしょう、とサクラの妄想も盛り上がってきた頃。
「ポーランドちゃん、ごめんねぇ!!!」
「ウクライナ、俺も寂しかったし!!!」
突然叫び声を上げて二人は目に涙を浮かべ、互いに駆け寄った。
「わがまま言ってごめんだし!」
「私こそ勝手なこと言ってごめんね!」
「いや、悪いのは感情的になった俺だし!」
「ううん、ポーランドちゃんの気持ちを無視した私が悪かったのよぉ!!」
うわあああああ、と盛大な泣き声をあげてしっかりと抱き合う二人に、驚きながらもサクラは歩み寄った。
「良かったです、お二人が仲直りできて」
彼女の言葉にポーランドとウクライナはぴたりと泣きやみ、互いの手を握った。
「私たち、また親友に戻れる...?私を許してくれるの?」
「もちろんだし、俺のことも許してほしいんよ」
「当り前じゃない!」
零れる涙を拭いて、二人は再びハグを交わす。
いつの間にか彼らの傍にいたヴァルシュは二人を祝福すると、ポーランドに向き直った。
「ポーランド、今日はマゾフシェと三人でクリスマスの飾りつけをする約束でしょ、もう帰らないと」
彼の言葉にサクラとウクライナは目を見開いたが、貴方にこの先を説明する必要は恐らくないだろう。そしてウクライナが次にワルシャワを訪れたときの出迎えが一人増えていたことも、言うまでもないことである。
”ヴァルシュ”ことワルシャワ市の体現は、電話先が通話を終了させたのを確認してから大きなため息を漏らした。
なんだって「特別な日の式典から帰らずスーツ姿で酒屋に向かい他人の家にまで上がりこんで眠っていたポーランドを回収して食事と身支度を手伝って国際会議に出席するための交通手段を手配して彼を送り出す」のが、東欧最大の都市である自分の仕事なのだ、オレだって昨日お祝いに日本料理店で働く知り合いのサクラに貰った漫画を読むのを楽しみにしてたのに。今だって、次から次へとかかってくるポーランドの遅刻に関する苦情と質問にいちいち説明して謝罪しているのは自分なのだ。迷惑ったらありゃしない。
「気晴らしねぇ...」
ひとしきり自分の部屋を漁っても、スマートフォンを弄っても、これといって楽しいことは見当たらない。再びため息を漏らしたヴァルシュはふわふわもこもこの青いパジャマからお気に入りの民族衣装に着替えると、意外と難しい旧市街までの瞬間移動に意識を集中させた。
いつもなら、ポーランドちゃんと並んで座ってるはずのお洒落なカフェ。
いつもなら、ポーランドちゃんと一緒に歩いてるはずの公園。
いつもなら、ポーランドちゃんと笑って過ごしてるはずのこの時間。
11月12日、ポーランドの国祭日である”民族復興記念の日”の翌日という日におとずれたワルシャワ旧市街は静寂に包まれて、物語に出てくるような、もしくは再び「北のパリ」が目の前に現れたかのような感動をもたらした。昨日は夜ふかしをしたからみんなまだ寝ているのかしら。それとも敬虔なカトリック国家だから、安息日の今日は教会にいるのかも。未だ彼とギクシャクした関係が続く中で昨日のセレモニーに出席したウクライナは、先に国へと帰った上司に休暇を取りたいと申し出、喧嘩したばかりの相手と仲直りできるわけでもなくこの街を歩いていたのだった。
「友達だと思っとったのに...もうお前のことなんか嫌いだし!」
1か月前に引きとめる間もなくウクライナの家を後にしたポーランドは、WW2に関する資料の公開を求めに来ていた。しかし聞き入れてしまうと各方面でのウクライナ共和国の安全が脅かされるから、と丁重に謝りながら断ったウクライナだったが、戦争で最も打撃をうけた国のひとつであるポーランドにとっては信じられない決断だったらしくそれ以来彼とはまともに会話できていない。会議場であってもお互いに目をそらしてしまうし、ウクライナの方から話しかけようとしてもすぐにリトアニアやアメリカ、ハンガリーなど友好な関係を結んでいる国がポーランドの周りに集まる。ほんの先月までは私もあの中にいたのに、と寂しいような悔しいような思いを感じるウクライナであった。
ひとりぼっちで歩く街では特に寄り道することもなく、冬が近づいて数がめっきり減った観光客に交じって旧市街広場に出た。交通量が多い道路の上を橋でわたったところにあるこの広場は、パステル調の歴史的建造物が立ち並ぶ観光名所だ。ウクライナはこの場所が大好きで、この国に来るたび仕事の後に時間を取ってポーランドと遊びに来ていた。ああ、あれもこれもポーランドちゃんと一緒だったらもっとずっと楽しいのに___。沈んだ気分のまま、人目も気にならず広場の中心にある人魚像の影に座りこむ。すると突如、
「お姉さん、せっかく此処に来たんだから悲しい顔するなよ。寂しいならオレが案内するから」
像の反対側から少年が姿を現した。ワルシャワ近辺に伝わる黒とオレンジを基調とした民族衣装に身を包んだその姿からして近隣の住民なのだろうが、美しいクイーンズイングリッシュを話している。キャラメル色の髪にココア色の瞳をしたその少年は、立ってみるとウクライナよりも背が高いかもしれないくらいだった。顔にはあどけなさが残り、中学の第2学年くらいかな、とウクライナは心の中で予測を立てる。初対面の相手ではあるが第六感に訴える物もない、ここは案内してもらってもいいだろう。
「そうね、ひとりぼっちはちょっと寂しかったし、お言葉に甘えてお願いしちゃおうかしら。私はソフィヤっていうの」
「会えて嬉しいよ、オレはヴァルシュ」
互いの目をみて握手を交わすと、二人は歩きだした。
「どういうとこが見たい?」
そうヴァルシュがきいてくるので速攻でスイーツ食べに行こう、と答えると驚いた様子だったが、クラクフ郊外通りにあるロディ専門店に連れて行ってくれた。突然のわがままだったので代金を払おうとする彼をとめて二人分のチョコレートアイスを購入し、通りをひとつずつ歩いて行くことにした。アイスを渡す時に見たヴァルシュの顔は、髪型や色のバランスこそ違うがどこかポーランドの面影があった。やっぱり国民と体現は似てるわ、とあらためて思うと、面白い。
ヴァルシュはいろいろな話を聞かせてくれた。ワルシャワと、彼について。
夏には旧王宮を見学するためにポーランド中から子どものサマーキャンプが来ること。クリスマスが近づくと街全体がイルミネーションのカタマリになること。ウクライナの首都キエフがワルシャワの姉妹都市であること。クラクフ郊外通りは、途中から新世界通りへと名前を変えること。意外にもポーランドの人口はワルシャワに集中しているわけではないということ。
もちろん、隣国であるウクライナにとってはデータとして知っていたことが殆どだったが、実際にその街に住む人に語ってもらうというのは何か自分の興味と知識が認められたような気がして嬉しかった。
ヴァルシュ自身のことと言えば、先程の人魚像のモデルとなった伝説の人魚を助けたとされている夫婦の夫がヴァルシュという名前で、それが彼のニックネームだということとか。親は居らず、一つ上の女の子と一緒にある青年の家に住んでいるということも。そして、その青年が近頃大切な友達と喧嘩をしてしまい、仲直りのタイミングがつかめず困っているということだった。
「あら、私もなのよぉ... 私も大切な友達と喧嘩しちゃって。彼はワルシャワに住んでいるのだけれど、私はウクライナから来たの」
ウクライナが思わずポーランドのことを口にすると、ヴァルシュは目を輝かせた。
「ああ、それならいい相談相手を知ってる!結構歩き回ったし、会いに行くついでにお昼にしよう。ポーランド料理はあとで御馳走するよ」
そう言ってヴァルシュが向かった先は、イェロゾリムスキェ通りとマルシャウコフスカ通りという二つの大通りが交差する場所のすぐ近くにある日本料理店だった。「NIPPON-KAN SUSHI」と書かれた看板の下をくぐると、そこにあったのはきっちりとスーツを着た中年のアジア人男性たち数人の姿だった。皆同じ言語を話しているようなので、日本人だろう。ヴァルシュは客席の間を縫って空いている席に座ると、オーダーを取りに来た若い店員にCześć!と笑いかけ、ウクライナには想像もつかない”ギョーザ”だの”ウードン”だのを注文し、最後にあとで話があるんだけど、と付け加えた。店員はまた相談しに来たんですね、と楽しそうにほほ笑むと伝票を持ってキッチンへと戻っていった。一体何なのだろうか。
しばらくして例の店員が腕いっぱいに料理を抱えてやってくると、彼女はなぜかエプロンを外してウクライナの横に座り込んだ。ウクライナがあっけにとられている間にも、ヴァルシュと店員の会話は進んでゆく。
「それで今日はどんなご相談なんですか?」
「こちらソフィヤ、ウクライナから来たんだけど、ワルシャワにいる友人と喧嘩しちゃったらしいんだ」
「喧嘩...ですか...」
ハーイ、ソフィヤよ、とすかさず言うウクライナに店員は、はじめましてサクラと申しますとしとやかな笑みを返した。うっかり出てしまったアメリカンな作法に驚いたのか、はたまた喧嘩についての相談はあまり自信がないのか、顔は曇っている。
「ちなみに、相手は男だぞ~」
慌ててそうヴァルシュが付け加えると、サクラの表情が一変した。
「そういうことでしたか!それなら少女漫画発祥の地、日本国で生を受けました私を是非お頼り下さいっ!」
「それなんだけど、相手がポーランド人の男なら、ハグとキスだけじゃ難しいから...」
「そこはですね...」
なんだか話が変だ。”大切な友達で、性別は男だ”とは言ったが、恋人だとも意中の人だとも口にはしていない。どうやらこの二人は所謂「恋バナ」が好きなクチなのだろう、今止めなくてはどんどん暴走してしまう。
「あのね、そ、そういう関係じゃないのよ、ほんとに。ただ、幼馴染っていうか、いままでこんな大きな喧嘩したことなかった子っていうか」
二人とも、ウクライナの言葉を受けてはっと我に返ったようだった。ごめんな、すみません私としたことが、と口々に謝られ、また困る事になるのだったが。
サクラはしばらく考え込んだ後にヴァルシュに何やら耳打ちした。彼がそれに対して頷くと安心したようにウクライナに向き直り、
「そうですね、パワースポットの力を借りてみてはいかがでしょうか」
と言った。パワースポット?と聞き返すソフィヤに、サクラはワルシャワの地図を見せた。街の東寄りを流れるヴィスワ川に架かるシフィェントクシスキ橋の袂には”人魚像”の文字が。人魚像って一つじゃなかったのね、と目を見張るウクライナに実は3つあるんですよ、期待通りの反応有難う御座います!とサクラが答える。
「そして...」
「その人魚像の西側、つまり人魚の背中側に立って相手と待ち合わせすれば、相手と願った通りの関係になれるっていう伝説があるんだ」
そうして今ウクライナは、ヴィスワ川の対岸に見える街並みと自然を眺めている。彼女の背後では人魚が盾と剣を青空に振りかざしていた。手元に水色のスマートフォンを握りしめ、肩の震えが止まらない。早く電話しないと、日が暮れちゃうのに___
「ソフィヤさん、頑張ってください!」
「相手だって絶対に仲直りしたいと思ってるよ、大丈夫」
サクラとヴァルシュが口々に送る声援も耳に届かないまま、ウクライナは「もう、当たって砕けるわ!」と叫び画面をプッシュした。
すぐにコール音が鳴り始め、黒い背景に浮かび上がる”ポーランドちゃん”の文字。
プルルルルルルルル…
「お願いポーランドちゃん、応えて…!」
携帯を両の手に包み、瞼に押し当てる。1回、2回、3回… 機械的なコールが続いたあと、突然に間延びした英語がスピーカーから聞こえてきた。
「ポルスカ様だしー、お前、ポーランド語通じる人ー?」
一瞬の間も開けずにウクライナは答えた。
「ポーランドちゃん、私…」
ポーランドちゃんに会いたい。そう声を絞り出した途端、人魚像に反射したオレンジ色の夕日が眩しくて、目を閉じれば涙が溢れてきた。もし大切な友達だって思ってるのが私だけだったらどうしよう。もしも今ここで”嫌だ”って言われたら?そう思うだけで心がちぎれてしまいそうになって、気がついたらポーランドの声を聞くことなく電話を切ってしまっていた。
「そんな、私、」
ウクライナは、いつの間にかホーム画面が表示されているスマートフォンを呆然と眺めていた。このままではポーランドはウクライナがどこにいるのか知らないままになるが、もう一度電話などしたら彼の気分を害してしまわないだろうか。
「ソフィヤ…」
桜の声にも答える気力が無いまま、ソフィヤはその場に立ち尽くした。
ポーランドは、ワルシャワ中の至るところに瞬間移動を繰り返していた。わかる。人々の好奇と恐怖の視線は自分に向けられているのが分かるのだ。地元の人ともなればきっと「また歩かないで瞬間移動ばっかりして、少しは運動しなさい」なんて事をいつ彼に忠告できるのかタイミングを伺っていることまで想像がつく。それもこれもウクライナらしき電話の相手が、場所も告げないで「会いたい」だの言って切ってしまうからだ。いきなり呼び出すからにはせめてワルシャワに居るだろうと検討をつけてあちこち飛び回る自分もお人好しである。それとも、相手がウクライナだと思うからだろうか。彼女とは先月喧嘩をしてしまい未だに話せてこそいないが、本来とても大切な友達なのだ。
その時、2世紀差の弟のようなワルシャワのことが頭に浮かんだ。色々と不思議な趣味を持つ彼が以前していたおまじないだのパワースポットだのの話に、”ヴィスワ川の岸辺に立つ人魚像の影に立って相手と待ち合わせするとその人と自分が望む関係になれる”と言うものがあった。もしかしたら、ウクライナもその話を知っているかもしれない。ポーランドは人々の視線を振り切って、像の少し手前へと瞬間移動した。
ヴァルシュはウクライナのことを慰めながらも、内心では自信を持っていた。ポーランドは来る。彼に以前この場所についてを話したことがあるのだ。ワルシャワという街を愛し人並み以上の記憶力を持つフェリクスのことだから、きっと覚えているだろう。その時、
「やっぱり、ここにいたんね」
背後から声がした。そこに居たのはポケットに両手を入れたポーランドで、口調から分かったのかウクライナが人魚像の陰から顔を出す。ポーランドは何も言うことなく、ただウクライナのことを見つめた。ウクライナも彼女の大きな碧い瞳を開き、見つめ返した。
サクラもワルシャワも息を潜めて傍らから見守った。像の陰にいる男女二人を木の陰から覗いている男女二人とはどういう図でしょう、とサクラの妄想も盛り上がってきた頃。
「ポーランドちゃん、ごめんねぇ!!!」
「ウクライナ、俺も寂しかったし!!!」
突然叫び声を上げて二人は目に涙を浮かべ、互いに駆け寄った。
「わがまま言ってごめんだし!」
「私こそ勝手なこと言ってごめんね!」
「いや、悪いのは感情的になった俺だし!」
「ううん、ポーランドちゃんの気持ちを無視した私が悪かったのよぉ!!」
うわあああああ、と盛大な泣き声をあげてしっかりと抱き合う二人に、驚きながらもサクラは歩み寄った。
「良かったです、お二人が仲直りできて」
彼女の言葉にポーランドとウクライナはぴたりと泣きやみ、互いの手を握った。
「私たち、また親友に戻れる...?私を許してくれるの?」
「もちろんだし、俺のことも許してほしいんよ」
「当り前じゃない!」
零れる涙を拭いて、二人は再びハグを交わす。
いつの間にか彼らの傍にいたヴァルシュは二人を祝福すると、ポーランドに向き直った。
「ポーランド、今日はマゾフシェと三人でクリスマスの飾りつけをする約束でしょ、もう帰らないと」
彼の言葉にサクラとウクライナは目を見開いたが、貴方にこの先を説明する必要は恐らくないだろう。そしてウクライナが次にワルシャワを訪れたときの出迎えが一人増えていたことも、言うまでもないことである。
1/1ページ