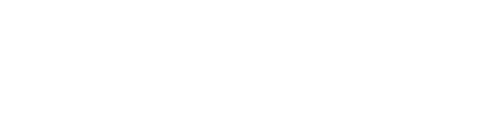ヴトゥカの夜
秋も暮の11月11日が終わろうとしていたその頃、ワルシャワの街外れにある小さなバルには黄色い明かりが煌々と灯っていた。祝賀ムードを湛えた人々が眠りに就いた途端に寒さと疲労感に襲われたポーランドは、吸い寄せられるようにその明るみへと向かって行ったのだった。
「後一年で百年目か...マジ波乱の1世紀だったし。波蘭ポーランドだけに」
「おっ、兄ちゃんやるねぇ」
色彩豊かなラベルが貼られたビール瓶を掴みながらその場で浮かんだ駄洒落を口にすれば、店主も周りの客も一緒になって笑ってくれる。早九十九度目になる”民族復興記念の日”は、毎年恒例のレッドスモークの中で政府の要人が演説し、その後広場にいた国民要人そして他国からの客人全員で国歌斉唱といういつにも増して大規模なものだった。
隣国であり親友であるリトアニアからはピンク色の生クリームでデコレーションが施された巨大センカチュ(リトアニア語ではシャコティスと呼ぶらしい)が贈られ、ロシアからはピンク一色の世界地図の中心に「R o s j a」と大きく書かれたカードを添えてポニーのぬいぐるみを貰った。オーストリアは体調不良で欠席したようだが、先月の終わりに情報を隠蔽しただので喧嘩してしまい未だにギスギスした関係が続いているウクライナでさえも、ポーランドの国花である紫パンジーと彼女の家のそれである向日葵を上手く合わせた花束をうつむきながら渡してくれた。ポーランドが上司の目を気にしながらも彼女に微笑み返したのがちょうど7時間前だ。
「兄ちゃんの後ろにあるでっかい鞄、どうしたんだい?」
ポーランドが”兄ちゃん”と呼ぶに相当する年齢を1000年近く前に卒業していることを知る由もない客の一人に聞かれ、今日は自分の誕生日でもあったと答える。名前はフェリクスで、このすぐ近くに住んでいると続ければ国内で長く伝わるバースディ・ソングをヴトゥカが回った赤ら顔で披露してくれた。インテリアの一部として壁に飾られていた調理器具の数々からフライパンや大振りのスプーンなどを両手にとり、賑やかな金属音のリズムを店内に響かせた。
“Sto lat! Sto lat!
Niech zyje, zyje nam.
Sto lat! Sto lat!
Niech zyje, zyje nam.
Jeszcze raz! Jeszcze raz!
Niech zyje, zyje nam.
Niech zyje nam. “
___百年、百年、我らに囲まれて彼等は生きる!
「彼『ら』か」
例外を除いて一カ国に一人しかいない国家の体現としては、自分と”同じ国”にルーツを持つ誰かが百年以上生きてくれることは稀である。それが孤独で心を閉ざした数えきれないほどの日々を打ち消すようにかつて一つの国家であった親友の顔を思い出したその時、
「でも私たちの祖国さまは一人で千年近く生きてきたんだよな...」
ポーランドの左隣の男がしみじみとそう口にした。同意を求めているのかポーランドに視線をよこすが、立場上下手な答えをしてはならないと適当に相槌を打っておく。するとあら、一人なんかじゃないわ、と店主を挟んで向かい側に座る女性が腰まで届くダーティブロンドをかきあげながら反論した。店内というのに黒く鍔の大きい古風な帽子を深く被り、上品さと神秘的な雰囲気を醸し出している。
ところが彼女までもが帽子を左手で軽くつまみ上げ、ポーランドの目をじっと覗きこんできたのだ。
(これはまずいし...)
正体が見抜かれてしまったかと一瞬警戒したポーランドだったが、気がつけば女性のほうは既に別のことを考えているという風にワインの輝きを (もしくはグラス越しに壁の調理器具の辺りを) 見つめている。ひとまず安心したところで自分の手元の空のグラスが視界に入り、今夜くらいはとアルコール度数がほぼ100%の地酒スピリタスを注文すれば周りの客も彼に続いた。
ああ、眠い。けど今日という日を眠ったまま終えてしまうのは勿体無い。そう頭の中で繰り返し、何杯目かも覚えていないグラスを飲み干して周りの会話に調子を合わせる。ヴトゥカとスピリタスを生み出した国の体現が酒に酔うことなど不可能に等しいので、上機嫌でどんちゃん騒ぎ状態の他の客に素面で付き合っているのだ。世界中の美女と話がしたいだの、俺の前世は英雄ユゼフ・ピウスツキの従兄だの____
もう一人先程から外国のワインばかりを飲んでいる例のダーティブロンドの女性だけが彼の演技に気がついたようで、私もなのよと言わんばかりに苦笑いを受かべてきた。それにしても眠い。
次にポーランドが目をあけると、聞き慣れた自国の国歌がクラシック風にアレンジされたものが響いていた。不意にピアノの音がやみ、「お下品ですよ、静かになさい!」とどこかで聞いたことがある声が隣の部屋から聞こえてくる。ほんの間もなく激しい足音が二つ聞こえたかと思うと、ポーランドが普段何んとなく距離をとっているプロイセンとそれを鬼の形相で追うハンガリーが。
「な、なんでお前がエリザの部屋にいるんだよポーランド!? しかもなんで寝てるんだよ!」
ポーランドを見るなり勢いでそう叫んだプロイセンだったが、取り敢えずウザいので無視した。
「...喋ってる余裕なんかあんの?」
ふと見上げると確かにハンガリーはプロイセンのすぐ背後に迫って来て、彼女のお気に入りのフライパンを振り上げている。護身用の武器とはいえ主にプロイセンを殴るためだけに一番出来が良いフライパンを用意するだけ、殴られて完敗するとわかっていて毎回ちょっかいを掛けに来るだけ、この二人はある意味仲が良いように見えるのだが、そんなポーランドの考えはお構いなしにハンガリーの一方的な攻撃は続く。
ガンッ!
“ショパン”という名字の由来であるともされる「強烈な一撃」がプロイセンの頭部に直撃し、そのまま彼はダウンした。よく見かけることながら間近で目撃し怯えているポーランドに、ハンガリーは先程までとは違う人物ではないかと疑うほどの柔らかな笑顔を浮かべて振り返りながら見苦しいところをごめんねと謝った。
「別にいいんけど、どうして俺今此処にいるんよ?」
そう問いかけたポーランドだったが、脳裏に昨日のダーティブロンドの女性が思い浮かぶ。トカイワインを好み、酒に強く、(恐らくだが)調理器具に見とれていて、ポーランドに対して興味を示していたのだ。もしや、と思って改めて彼女の瞳を見上げる。
「うふふ、たった今気付いたみたいね。昨日ポーちゃんったらバルで突然眠りこんじゃったから、偶然出会った友人だって言って連れて来たのよ」
彼女が話すところによると此処は二重帝国時代に彼女が住みこんでいたオーストリア邸にある部屋らしく、今も頻繁に訪れるため彼女好みの大人メルヘンチックな内装と清潔感が保たれていた。今までずっと横になっていたことに気がついたポーランドは、ソファの上に体を起こす。
「えっと、ありがとうだし!あのままバルで寝ちゃってたら今頃ワルシャワの奴に発見されてニヨニヨ笑われてたし。取り敢えず今は俺ん家帰らなきゃいかんけど、後で絶対最高においしい蜂蜜とピエル二キどっさり送るんよ!」
ソファの隅に掛けてあったジャケットを羽織ってエリザと握手をしようと彼女に歩み寄ると、彼女のほうから顔を近づけてきた。何やら耳元でささやくことがあるらしい。彼女の茶色がかった金髪がポーランドの肩に触れる。
「あのね、昨日お店に入ってきてすぐ言ってたじゃない、波乱の一世紀だったって。私もそう思うけどね、でもね... きゃあっ!?」
ハンガリーが突如足元を見下ろしたかと思うと、地面で伸びていたプロイセンが彼女のスカートを掴みながら起き上がってポーランドに云った。
「...でもな、まだ一世紀終わってないぜ。あと1年残ってんだろ?今までが波乱の99年だったんなら今年を最高に平和な年にすればいいじゃねえか!」
「人のセリフ取ってんじゃないわよー!!!」
「ぐあっ!」
再び彼にフライパンの一撃をくらわせたハンガリーだったが、それ以上の攻撃はしなかった。ポーランドから不意に笑みがこぼれる。
「ははっ、二人して同じこと考えるとか、お前ら仲良過ぎだし!それでもメッセージありがとうだし、マジその通りだと思うんよ~」
ちょうどそのとき、昨日貰ったばかりの透明ピンクに濃い桃色のポニーがプリントされたケースを付けたスマートフォンがポケットの中で振動した。画面には「ワルシャワ」の文字。ああヴァルシュ、すぐ帰るから上司に言いつけるのは勘弁して欲しいんよ!と能天気な声で言い終えてから電話を一方的に切り、じゃあなとオーストリアの家を後にした。門を出るころには丁度、上品さを好む家主の演奏であろうクラシック風ポーランド国歌のサビが聞こえてきた。
進め、進め、ドンブロフスキ、イタリアの地からポーランドへ
汝の指揮下で、我らは再び国家の一部となるのだ!
ポーランド共和国の独立を望み祝い讃えるこの歌は、昨日のセレモニーを欠席したオーストリアからの贈り物かもしれない。
「みんなマジでありがとうだしー!」
ふわふわと雪が降り始めた11月の東欧の空は、白く美しかった。
「後一年で百年目か...マジ波乱の1世紀だったし。波蘭ポーランドだけに」
「おっ、兄ちゃんやるねぇ」
色彩豊かなラベルが貼られたビール瓶を掴みながらその場で浮かんだ駄洒落を口にすれば、店主も周りの客も一緒になって笑ってくれる。早九十九度目になる”民族復興記念の日”は、毎年恒例のレッドスモークの中で政府の要人が演説し、その後広場にいた国民要人そして他国からの客人全員で国歌斉唱といういつにも増して大規模なものだった。
隣国であり親友であるリトアニアからはピンク色の生クリームでデコレーションが施された巨大センカチュ(リトアニア語ではシャコティスと呼ぶらしい)が贈られ、ロシアからはピンク一色の世界地図の中心に「R o s j a」と大きく書かれたカードを添えてポニーのぬいぐるみを貰った。オーストリアは体調不良で欠席したようだが、先月の終わりに情報を隠蔽しただので喧嘩してしまい未だにギスギスした関係が続いているウクライナでさえも、ポーランドの国花である紫パンジーと彼女の家のそれである向日葵を上手く合わせた花束をうつむきながら渡してくれた。ポーランドが上司の目を気にしながらも彼女に微笑み返したのがちょうど7時間前だ。
「兄ちゃんの後ろにあるでっかい鞄、どうしたんだい?」
ポーランドが”兄ちゃん”と呼ぶに相当する年齢を1000年近く前に卒業していることを知る由もない客の一人に聞かれ、今日は自分の誕生日でもあったと答える。名前はフェリクスで、このすぐ近くに住んでいると続ければ国内で長く伝わるバースディ・ソングをヴトゥカが回った赤ら顔で披露してくれた。インテリアの一部として壁に飾られていた調理器具の数々からフライパンや大振りのスプーンなどを両手にとり、賑やかな金属音のリズムを店内に響かせた。
“Sto lat! Sto lat!
Niech zyje, zyje nam.
Sto lat! Sto lat!
Niech zyje, zyje nam.
Jeszcze raz! Jeszcze raz!
Niech zyje, zyje nam.
Niech zyje nam. “
___百年、百年、我らに囲まれて彼等は生きる!
「彼『ら』か」
例外を除いて一カ国に一人しかいない国家の体現としては、自分と”同じ国”にルーツを持つ誰かが百年以上生きてくれることは稀である。それが孤独で心を閉ざした数えきれないほどの日々を打ち消すようにかつて一つの国家であった親友の顔を思い出したその時、
「でも私たちの祖国さまは一人で千年近く生きてきたんだよな...」
ポーランドの左隣の男がしみじみとそう口にした。同意を求めているのかポーランドに視線をよこすが、立場上下手な答えをしてはならないと適当に相槌を打っておく。するとあら、一人なんかじゃないわ、と店主を挟んで向かい側に座る女性が腰まで届くダーティブロンドをかきあげながら反論した。店内というのに黒く鍔の大きい古風な帽子を深く被り、上品さと神秘的な雰囲気を醸し出している。
ところが彼女までもが帽子を左手で軽くつまみ上げ、ポーランドの目をじっと覗きこんできたのだ。
(これはまずいし...)
正体が見抜かれてしまったかと一瞬警戒したポーランドだったが、気がつけば女性のほうは既に別のことを考えているという風にワインの輝きを (もしくはグラス越しに壁の調理器具の辺りを) 見つめている。ひとまず安心したところで自分の手元の空のグラスが視界に入り、今夜くらいはとアルコール度数がほぼ100%の地酒スピリタスを注文すれば周りの客も彼に続いた。
ああ、眠い。けど今日という日を眠ったまま終えてしまうのは勿体無い。そう頭の中で繰り返し、何杯目かも覚えていないグラスを飲み干して周りの会話に調子を合わせる。ヴトゥカとスピリタスを生み出した国の体現が酒に酔うことなど不可能に等しいので、上機嫌でどんちゃん騒ぎ状態の他の客に素面で付き合っているのだ。世界中の美女と話がしたいだの、俺の前世は英雄ユゼフ・ピウスツキの従兄だの____
もう一人先程から外国のワインばかりを飲んでいる例のダーティブロンドの女性だけが彼の演技に気がついたようで、私もなのよと言わんばかりに苦笑いを受かべてきた。それにしても眠い。
次にポーランドが目をあけると、聞き慣れた自国の国歌がクラシック風にアレンジされたものが響いていた。不意にピアノの音がやみ、「お下品ですよ、静かになさい!」とどこかで聞いたことがある声が隣の部屋から聞こえてくる。ほんの間もなく激しい足音が二つ聞こえたかと思うと、ポーランドが普段何んとなく距離をとっているプロイセンとそれを鬼の形相で追うハンガリーが。
「な、なんでお前がエリザの部屋にいるんだよポーランド!? しかもなんで寝てるんだよ!」
ポーランドを見るなり勢いでそう叫んだプロイセンだったが、取り敢えずウザいので無視した。
「...喋ってる余裕なんかあんの?」
ふと見上げると確かにハンガリーはプロイセンのすぐ背後に迫って来て、彼女のお気に入りのフライパンを振り上げている。護身用の武器とはいえ主にプロイセンを殴るためだけに一番出来が良いフライパンを用意するだけ、殴られて完敗するとわかっていて毎回ちょっかいを掛けに来るだけ、この二人はある意味仲が良いように見えるのだが、そんなポーランドの考えはお構いなしにハンガリーの一方的な攻撃は続く。
ガンッ!
“ショパン”という名字の由来であるともされる「強烈な一撃」がプロイセンの頭部に直撃し、そのまま彼はダウンした。よく見かけることながら間近で目撃し怯えているポーランドに、ハンガリーは先程までとは違う人物ではないかと疑うほどの柔らかな笑顔を浮かべて振り返りながら見苦しいところをごめんねと謝った。
「別にいいんけど、どうして俺今此処にいるんよ?」
そう問いかけたポーランドだったが、脳裏に昨日のダーティブロンドの女性が思い浮かぶ。トカイワインを好み、酒に強く、(恐らくだが)調理器具に見とれていて、ポーランドに対して興味を示していたのだ。もしや、と思って改めて彼女の瞳を見上げる。
「うふふ、たった今気付いたみたいね。昨日ポーちゃんったらバルで突然眠りこんじゃったから、偶然出会った友人だって言って連れて来たのよ」
彼女が話すところによると此処は二重帝国時代に彼女が住みこんでいたオーストリア邸にある部屋らしく、今も頻繁に訪れるため彼女好みの大人メルヘンチックな内装と清潔感が保たれていた。今までずっと横になっていたことに気がついたポーランドは、ソファの上に体を起こす。
「えっと、ありがとうだし!あのままバルで寝ちゃってたら今頃ワルシャワの奴に発見されてニヨニヨ笑われてたし。取り敢えず今は俺ん家帰らなきゃいかんけど、後で絶対最高においしい蜂蜜とピエル二キどっさり送るんよ!」
ソファの隅に掛けてあったジャケットを羽織ってエリザと握手をしようと彼女に歩み寄ると、彼女のほうから顔を近づけてきた。何やら耳元でささやくことがあるらしい。彼女の茶色がかった金髪がポーランドの肩に触れる。
「あのね、昨日お店に入ってきてすぐ言ってたじゃない、波乱の一世紀だったって。私もそう思うけどね、でもね... きゃあっ!?」
ハンガリーが突如足元を見下ろしたかと思うと、地面で伸びていたプロイセンが彼女のスカートを掴みながら起き上がってポーランドに云った。
「...でもな、まだ一世紀終わってないぜ。あと1年残ってんだろ?今までが波乱の99年だったんなら今年を最高に平和な年にすればいいじゃねえか!」
「人のセリフ取ってんじゃないわよー!!!」
「ぐあっ!」
再び彼にフライパンの一撃をくらわせたハンガリーだったが、それ以上の攻撃はしなかった。ポーランドから不意に笑みがこぼれる。
「ははっ、二人して同じこと考えるとか、お前ら仲良過ぎだし!それでもメッセージありがとうだし、マジその通りだと思うんよ~」
ちょうどそのとき、昨日貰ったばかりの透明ピンクに濃い桃色のポニーがプリントされたケースを付けたスマートフォンがポケットの中で振動した。画面には「ワルシャワ」の文字。ああヴァルシュ、すぐ帰るから上司に言いつけるのは勘弁して欲しいんよ!と能天気な声で言い終えてから電話を一方的に切り、じゃあなとオーストリアの家を後にした。門を出るころには丁度、上品さを好む家主の演奏であろうクラシック風ポーランド国歌のサビが聞こえてきた。
進め、進め、ドンブロフスキ、イタリアの地からポーランドへ
汝の指揮下で、我らは再び国家の一部となるのだ!
ポーランド共和国の独立を望み祝い讃えるこの歌は、昨日のセレモニーを欠席したオーストリアからの贈り物かもしれない。
「みんなマジでありがとうだしー!」
ふわふわと雪が降り始めた11月の東欧の空は、白く美しかった。
1/1ページ