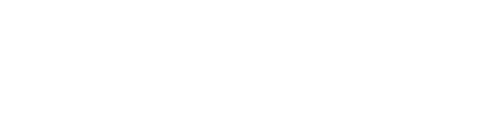繋がるキャロル
1795年10月24日、誇り高きポーランド人が築いた王国は長い長い戦いの末ついに消滅した。ロシア・プロイセン・オーストリアの三国がその領土を全て奪い去り、帝政ロシアの元でポーランド民族は自らの言語を話すことさえ許されなかった。
(俺は、戻ってくるし)
新年が明けた街を行くマゾフシェは、王国の消滅とともに姿を消したその体現が最後に言い残した言葉を何度も思い返していた。あれから何十回のクリスマスを過ごしてきただろうか。ロシアに対する反乱計画の談合には彼女も頻繁に参加するが、もしその計画が明るみに出たらと考えるだけで視界が真っ白になるほど恐ろしい。だって、消滅する前のポーランドはもっと平和で、富のある国だったのだから。その時、
「ママぁ、生誕祭は1月7日だよ、どうしてこないだもお祝いしてたの?」
道行く幼子のロシア語がマゾフシェの耳に入り、虚ろな彼女の心を鋭く差した。ポーランドのクリスマスは12月の25日だから_______。
「ピョトル!お願い、そんなこと言わないのよ、いい子だから...!」
「奥さん、何をいつ祝ったって?お聞かせ願いたいね...刑務所で」
我に返ったマゾフシェが振り返った時には既に間に合わなかった。黒い制服に黒い帽子をかぶった秘密警察が子供の母親を金色のステッキで取り押さえ、周りにいたスーツの男たちも一斉に彼女へと歩みを進めてくる。見てはいけない。見つめてはいけないのだ、自分の命が惜しければ。
「ママ、ママぁ!? いやだよ、ママを連れてかないで!」
「ピョトル...!!!」
「ママ!」
ああ、可哀そうな男の子は一人この寒い通りに残されてしまっただろう。何もできない自らの非力さに悔しさと怒りが込み上げてくる。マゾフシェは涙を人から隠すように、足早にワルシャワが待つ家へと向かった。
「ただいま」
門の鍵を開け家に入ると、ワルシャワが作ったクリスマス料理とジンジャーブレッドの香りが漂ってきた。立派なツリーの横を通り抜け居間へ足を踏み入れるとそこには誰の姿も無い。家の外の通りからは無邪気にロシア語でクリスマスを祝う子供たちの声が聞こえてくる。マゾフシェは木でできた狭い階段を上り、ドアが開いたままのワルシャワの部屋を覗いた。
「本当に昼寝が好きなんだから」
ワルシャワは真冬の寒さも気にせず、薄い青色の掛け布団の上に寝っ転がりすやすやと寝息を立てていた。柔らかいキャラメル色の髪と睫毛が穏やかな息に合わせて静かに動く。まるで普段の悲しみなど全て忘れたかのように眠る彼に、マゾフシェは心から安心した。
(夜の静けさの中、声は響く...)
もう、ワルシャワにはこの言葉の意味がわからないだろう。大切な弟のような彼に苦しみを背負わせたくないが為に、蜂起の話は全てマゾフシェが秘密下に引き受けていたからだ。今のワルシャワがロシア語しか知らないのは、自らの人民よりも他の体現を守ることを選んだマゾフシェへの罰。それでも、彼女は囁いた。
「...Wesołych Świąt」
誰にも、自分にも聞こえないほどの小さな声で、愛する家族の耳元で。