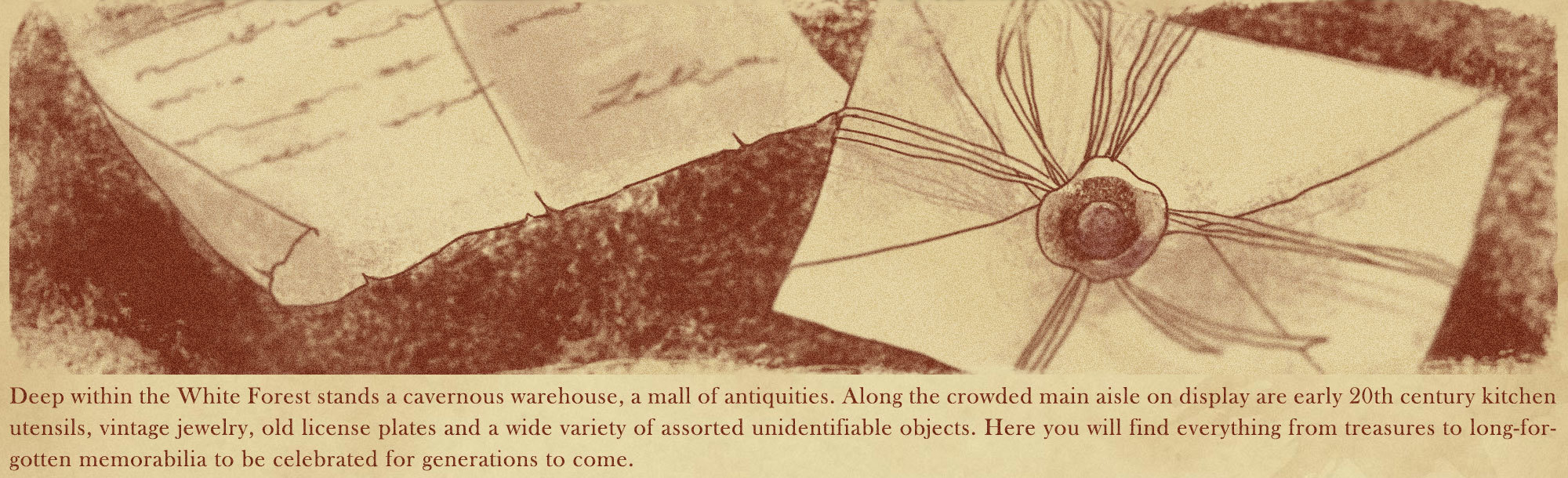福音
泣き声が聞こえる。
おそらくは女の人。直感的に私の母だと思った。
霞む視界の中で掴むように上げた手はふくふくとして小さい。どこか冷静な頭で私は今赤子なのだろうと悟った。
胸元に何か重みがあるブランケット以外の。何か置かれているのだろうか。口から高い声が漏れる。小さな籠の中で私は泣いた。精一杯手を伸ばして。だってそうしないと捨てられると思ったから。
私の考えは不幸にもあたり、とある春の晩ウール孤児院という英国の首都、ロンドンにある小さな孤児院へと捨てられたのだった。
ヴィクトリア─『勝利の女神』の名とともに。
─────
私はきっと一度死んで、そして生まれ変わったはずだ。死んだときの記憶は残念ながら無いけれど。
小さな体でずっとぼんやりとそんなことを考えていた。
私は第一次世界大戦終結からおおよそ八年後、まだまだ戦後の残り香がする時代に生まれ変わった。生まれ変わり先が元々生きていた時代よりも過去の戦後で……それも第二次世界大戦目前に孤児として生まれ変わるだなんてどんな不運だと思った。
私の生きていたのはもっと遠い未来の話。第二次世界大戦終結後の世界。日本という国で生まれ、幸福も不幸も重なりながら、それでも日々を生きていた……はずだ。
そんな世界で私は海外の児童書に夢中になっていた。その児童書はこの英国にて生まれ世界中で大ヒットし世界でもっとも売れた本トップ10の常連となり、そして映画となった。とある一人のシングルマザーが書いた本は世界中の子供や大人に夢を抱かせたのだ。
しかし、ヴィクトリアはそれ以外の記憶を何も思い出せないでいた。ハリポタという児童書が好きだった。ただそれだけ。
けれど、別に良いかと思った。構わなかった。だって私は私だから。例え前世がどうでも。年の割りに大人びた思考回路。不意に出る癖。既視感や憧れによる感動。そういったものは確かにあるし、前世の自分であろう自我もふと自覚する。けれど、どこまでいっても私は私だ。
前世での暮らしは何も覚えていないのに理解して話せる日本語。これから先のおおまかな世界情勢。文字の書き方。そんなものは知っている。
しかし、どうしよう。私はあくまでもおそらくだが義務教育レベルの英語能力しかないのである。
私は職員の話からしておよそ生後数ヵ月程度の小さな赤ちゃんだった。
赤ちゃんというのは不便なもので体に不快感を感じれば泣き叫ぶのだがなかなか意図が伝わらない。泣いて泣いて泣いて抱っこされておむつをおろされミルクを口につけられる。それを私はもう食べられないと拒否しても無理やりに口につけ続けられたらいやおうなしに吸うしかなかった。
そうして虚無になっているヴィクトリアにお腹が空いていたから食べたのだろう、満腹になったから泣き止んだのだろう、と考えた職員は疲れきった様子でヴィクトリアをゆりかごにおろしたのだ。
ヴィクトリアにはふわふわとした知識はあれど確固たる前世の人格はなかったので屈辱で憤死することはなかった。けれど、不便には違いないのだ。
私はかなり頑丈な体をしているらしく、殆ど熱を出したりして体調を崩すことなくすくすくと育っていく。
不安の種である英語力も生まれた頃から周りは英語で溢れており、前世の記憶があるといってもしょせんそれだけが私ではなく私はあくまでも育ち盛りで周りから様々なものを吸収する赤ん坊であったのもあいまってなんなら同年代でもっとも話せるようになった。
……あと必然性にかられたら案外人間なんとでもなる、というのもあるかもしれない。
存外に孤児院での暮らしというのも悪くはなかった。プライバシーが首の皮ほど薄いけど衣食住は常に提供された。1年経つ頃から支給された古風なグレーのチュニックも嫌いではない。お下がりだけど。支給されたものには色褪せてくたくたになっているものもあった。
仲良くなった子が引き取られ去っていくのは悲しいけれどその子の未来が明るいものであるように祈った。
単語をおぼえて話して絵本を何人かで囲んで読んで文字をおぼえてそんな日々を過ごしていったら私の英語力もめきめきと育てられたものだ。
─────
物心がついたばかりのある日私は院長室に来るよう院長であるミセスコールに呼ばれた。
何か懲罰を受けるのではと心配する歳上の少女ににっこりと笑って心配しないように手を振りミセスコールのもとへ向かう。
だって悪いことをした覚えはないから。いったい何で呼び出されたのやら。……ああ、でも。もしもあいつのせいで呼ばれたんだったらいやだなーとふわりとある幼児の顔を浮かべ考えながら呼びにきた職員に続いてまだまだ小さな体をひょこひょこと動かし階段を降りる。
跳ねるようにおりるものだから肩ほどの髪が揺れる。ふわり、ふわりと振動にあわせて膨らんだ。ぴょん、ぴょんと。そうやって降りると呆気なく院長室の前へとついた。小さな孤児院であるため必然である。職員が扉をノックする。
「ミセスコール、ヴィクトリアを連れてきました」
「お入りなさい。」
その言葉に扉が人一人入れるほど開かれた。職員が開いたのだ。背中を押された上目遣いで職員の顔を浮かがうと顎をかすかに動かし入室するように促す。
小さな孤児院ゆえに院長ともそこそこ接する機会があるとはいえやっぱり職員室や校長室に訪れるような緊張がある。
ヴィクトリアは恐る恐ると足を踏み入れる。室内は一見清潔に保たれているがカビ臭くじめじめとしていた。埃っぽいとまでは言わないが。掃除が行き届いていないのだろう。院長室には来客用の椅子と小さな机。そして古びた木製の書斎机があった。いくつかの書類の上に文鎮替わりにか万年筆が転がされており横にある本棚にはいくつかの実用書と10何冊かのバインダーが納められていた。
「お呼びですかー?」と尋ねる私にミセスコールはメッセージカードと小さな品物がいくつかを机の上の小物置きに並べた。「あなたはこれと共に捨てられていたのだ」と、淡々とした声音でこの孤児院の院長殿は私に告げた。
捨てられただなんてまだ3歳を越したばかりのちいちゃな子供にはなかなかに酷な話である。まあ孤児院で育つ者なんて、ほとんど親が死んだか親に捨てられたかの二択だけど。院長からそのときの物だと受け取ったメッセージカードを光にかざしぼーと眺めたあと、また先生に返した。一緒に入れられていた品物と共に。
私には適切に保管できる自信がなかったから。
流麗な線の細い字だった。筆記体だけど詠みやすかった。けど震えたようにがくがくとしていて最後の文字に至っては変な方向にはねていた。
染みたあとのようなものがあった。捨てられた日は特別暑くなく雪も雨も降っていなかったからおそらくは……これは涙なのだろう。
そう思って厚い紙の少し凹んだところを指でたどった。
先生はせめてこれだけでも持っていなさいと私の首に十字架をかける。確かにこれは捨てられたときにも持っていた気がする。
胸の重みを、憶えている。
ずしりとした重みをたたえる金属製の十字架は明るいゴールドに輝いていた。歩けるようになってから、それが当然のように毎日通いつめる礼拝堂にいる牧師さまがつけているもののように立派だった。
首を擦れる革ひもにしっくりきた。孤児院で他とは違う特定のものを持つことは顰蹙を買うからと考え躊躇う心がぬぐい去られた。
これは私のものだ。誰のものでもなく、私だけの。
______
「トリア、それ、何?」
ヴィクトリアの愛称であるトリアと呼ばれて、ヴィクトリアは視線を向けた。黒くさらりとした髪と黒い双眸のあどけない少年が興味深そうに尋ねる。ヴィクトリアの胸元にかけられた金の十字架を指し示しながら。瞳にうつるのは純粋なる好奇心。幼いながらに整った顔立ちは未来への有望さがうかがえた。
この少年は私と同い年であり私が捨てられる数ヵ月前にここで生まれここで暮らしていたらしい。彼の名前はトム・リドル。そう、あのトム・リドルである。
ハリー・ポッターというイギリス生まれの大人気児童書の最強で最恐のラスボス、ヴォルデモートの過去の姿である。
そう、ここウール孤児院はトム・リドルが生まれ育った孤児院であった。
ヴィクトリアは初めてこいつがトム・リドルでここがウール孤児院であると気づくと驚いた。あまりに驚いて初めて寝返りをし、そのままごろごろと転がり、床へと落ちかけたほどである。しかし、そんなことはどうでもいい。
私ははっきり言うとこいつが好きではない。
だってこいつはこの世界のラスボスで、何よりも……大がつくほどの問題児なのである。
あさっぱらから癇癪を起してこの不況の時代に窓を割るわ、電球をショートさせるわ。ついにはミセスコールが悪魔祓いを呼ぶまでにいたったほどである。
けれど、こいつはどこまでもきっと寂しい子供だった。小さくて不安げでどこか朧だった。
そしてまだまだこいつは無垢で無邪気な幼子であった。
私が捨てられてからほとんど私はこいつと共に育った。しかしこいつは幸いにも_なぜかはわからないが私が傍にいるときに問題を起こすことは殆どなかった。うまれてたいして経たぬほどから傍に居たから同族感でも感じているのだろう。
理由不明で周りで問題や事故が起こる人物の前にお互い同い年の赤ちゃんとはいえ赤ちゃんを置くってどんな神経しているんだ、と思いながら過ごしたものだ。いつ何が起こるかと恐々としながら。
だからか、別に私たちの仲は悪くない、良くもないが。
いやむしろ悪くて良いのほうが正しいのかもしれない。
私とこいつは根本的に合わないのである。
こいつはわずか3歳ほどで大問題児の一人として孤児院内で名をはせているトムかたや私は聞き分けの良い良い子として周知されつつあるのである。そりゃ合わない。
ヴィクトリアは話しかけてきたトムに対して顔を歪め話をそらした。なぜだか知られたくなかった。私に様々なをものを託し捨てた母親のことを。
「聞いたよ、トム。昨日いらした老夫婦の旦那さんのベルトをへびに変えたんだって?ほんとう?」
「さあ?違うんじゃない?どうやってやるというんだ」
肩を竦ませて告げるトムは胡散臭いことこのうえない。ヴィクトリアは思わず半眼になる。
「大人しくしていたら……あなた、顔も頭も良いんだからすぐ貰われるだろうに」
小さく溜息をつきながらヴィクトリアはぼやいた。ヴィクトリアの呆れが滲んだ声に反してトムは鼻で笑う。
「ハッお断りだね、そういう君はどうなんだ?」
今度はヴィクトリアが渋い顔になった。どうにも縁がないのだ。
ヴィクトリアは少々珍しい容姿をしているのがあってどれほど優等生であろうが"引き取りたい"と告げられることはなかった。
こいつほど整った顔立ちをしているなら話は別だろうが。
でも少しでも興味をもたれたなら話は早かった。幼いながらに真面目で従順なその姿を見てヴィクトリアを気に入る者は少なくはなかった。とんとん拍子に進む話に不安と共に期待をヴィクトリアが抱いているとその話はすぐさま破談となるのだ。いっそ呆気ないほどに。
そんな日々が続いていてヴィクトリアはもうすっかり期待しなくなってしまった。
この孤児院にいられるだけ恵まれている。それも健康体で。
捨てられる子は多いけれど引き取られる子は少ない。そして貧しい孤児院では病になり亡くなる子も少なくはなかった。
19世紀ほどに話題となりいくぶんか姿を消したが第一次世界大戦の影響もあってかロンドンでもまだ少し暗い路地へと入れば身寄りのない浮浪児がさ迷っている。
大人の保護下にいない状況で生きていけるほどこの国はまだまだ甘くはない。探せば子供の死体など転がっているだろう。
私は運がいい。捨てられた晩すぐに孤児院の職員が見つけてくれて。捨てられた孤児院が貧しく事務的な面が強いとはいえ善良かつマトモで。
下手な家に引き取られるよりはよほどいい。けれど…………
黙りこくった様子のヴィクトリアにトムは何を思ったのか先ほどのつん、として人を小馬鹿にしたような声とはうってかわりいくぶんか優しい声を出した。慰めるような宥めるような声。怒った母を、悲しむ妹を。
「……まあ、トリア。孤児院での生活もそこまで悪くはないだろうし……変なやつに引き取られるよりはだいぶマシさ……。ずーっと誰も僕らを引き取りに来なければ出ていってしまおうよ」
最後は提案するような声音だった。子供の無邪気さと果てのない全能感を由来とする、無鉄砲なひらめき。それをもっとも良案だといいたげな声音にヴィクトリアは(どうやって生きていくのだろうか、でもこいつならやっていけそうだ)と思わず微笑んだ。
おそらくは女の人。直感的に私の母だと思った。
霞む視界の中で掴むように上げた手はふくふくとして小さい。どこか冷静な頭で私は今赤子なのだろうと悟った。
胸元に何か重みがあるブランケット以外の。何か置かれているのだろうか。口から高い声が漏れる。小さな籠の中で私は泣いた。精一杯手を伸ばして。だってそうしないと捨てられると思ったから。
私の考えは不幸にもあたり、とある春の晩ウール孤児院という英国の首都、ロンドンにある小さな孤児院へと捨てられたのだった。
ヴィクトリア─『勝利の女神』の名とともに。
─────
私はきっと一度死んで、そして生まれ変わったはずだ。死んだときの記憶は残念ながら無いけれど。
小さな体でずっとぼんやりとそんなことを考えていた。
私は第一次世界大戦終結からおおよそ八年後、まだまだ戦後の残り香がする時代に生まれ変わった。生まれ変わり先が元々生きていた時代よりも過去の戦後で……それも第二次世界大戦目前に孤児として生まれ変わるだなんてどんな不運だと思った。
私の生きていたのはもっと遠い未来の話。第二次世界大戦終結後の世界。日本という国で生まれ、幸福も不幸も重なりながら、それでも日々を生きていた……はずだ。
そんな世界で私は海外の児童書に夢中になっていた。その児童書はこの英国にて生まれ世界中で大ヒットし世界でもっとも売れた本トップ10の常連となり、そして映画となった。とある一人のシングルマザーが書いた本は世界中の子供や大人に夢を抱かせたのだ。
しかし、ヴィクトリアはそれ以外の記憶を何も思い出せないでいた。ハリポタという児童書が好きだった。ただそれだけ。
けれど、別に良いかと思った。構わなかった。だって私は私だから。例え前世がどうでも。年の割りに大人びた思考回路。不意に出る癖。既視感や憧れによる感動。そういったものは確かにあるし、前世の自分であろう自我もふと自覚する。けれど、どこまでいっても私は私だ。
前世での暮らしは何も覚えていないのに理解して話せる日本語。これから先のおおまかな世界情勢。文字の書き方。そんなものは知っている。
しかし、どうしよう。私はあくまでもおそらくだが義務教育レベルの英語能力しかないのである。
私は職員の話からしておよそ生後数ヵ月程度の小さな赤ちゃんだった。
赤ちゃんというのは不便なもので体に不快感を感じれば泣き叫ぶのだがなかなか意図が伝わらない。泣いて泣いて泣いて抱っこされておむつをおろされミルクを口につけられる。それを私はもう食べられないと拒否しても無理やりに口につけ続けられたらいやおうなしに吸うしかなかった。
そうして虚無になっているヴィクトリアにお腹が空いていたから食べたのだろう、満腹になったから泣き止んだのだろう、と考えた職員は疲れきった様子でヴィクトリアをゆりかごにおろしたのだ。
ヴィクトリアにはふわふわとした知識はあれど確固たる前世の人格はなかったので屈辱で憤死することはなかった。けれど、不便には違いないのだ。
私はかなり頑丈な体をしているらしく、殆ど熱を出したりして体調を崩すことなくすくすくと育っていく。
不安の種である英語力も生まれた頃から周りは英語で溢れており、前世の記憶があるといってもしょせんそれだけが私ではなく私はあくまでも育ち盛りで周りから様々なものを吸収する赤ん坊であったのもあいまってなんなら同年代でもっとも話せるようになった。
……あと必然性にかられたら案外人間なんとでもなる、というのもあるかもしれない。
存外に孤児院での暮らしというのも悪くはなかった。プライバシーが首の皮ほど薄いけど衣食住は常に提供された。1年経つ頃から支給された古風なグレーのチュニックも嫌いではない。お下がりだけど。支給されたものには色褪せてくたくたになっているものもあった。
仲良くなった子が引き取られ去っていくのは悲しいけれどその子の未来が明るいものであるように祈った。
単語をおぼえて話して絵本を何人かで囲んで読んで文字をおぼえてそんな日々を過ごしていったら私の英語力もめきめきと育てられたものだ。
─────
物心がついたばかりのある日私は院長室に来るよう院長であるミセスコールに呼ばれた。
何か懲罰を受けるのではと心配する歳上の少女ににっこりと笑って心配しないように手を振りミセスコールのもとへ向かう。
だって悪いことをした覚えはないから。いったい何で呼び出されたのやら。……ああ、でも。もしもあいつのせいで呼ばれたんだったらいやだなーとふわりとある幼児の顔を浮かべ考えながら呼びにきた職員に続いてまだまだ小さな体をひょこひょこと動かし階段を降りる。
跳ねるようにおりるものだから肩ほどの髪が揺れる。ふわり、ふわりと振動にあわせて膨らんだ。ぴょん、ぴょんと。そうやって降りると呆気なく院長室の前へとついた。小さな孤児院であるため必然である。職員が扉をノックする。
「ミセスコール、ヴィクトリアを連れてきました」
「お入りなさい。」
その言葉に扉が人一人入れるほど開かれた。職員が開いたのだ。背中を押された上目遣いで職員の顔を浮かがうと顎をかすかに動かし入室するように促す。
小さな孤児院ゆえに院長ともそこそこ接する機会があるとはいえやっぱり職員室や校長室に訪れるような緊張がある。
ヴィクトリアは恐る恐ると足を踏み入れる。室内は一見清潔に保たれているがカビ臭くじめじめとしていた。埃っぽいとまでは言わないが。掃除が行き届いていないのだろう。院長室には来客用の椅子と小さな机。そして古びた木製の書斎机があった。いくつかの書類の上に文鎮替わりにか万年筆が転がされており横にある本棚にはいくつかの実用書と10何冊かのバインダーが納められていた。
「お呼びですかー?」と尋ねる私にミセスコールはメッセージカードと小さな品物がいくつかを机の上の小物置きに並べた。「あなたはこれと共に捨てられていたのだ」と、淡々とした声音でこの孤児院の院長殿は私に告げた。
捨てられただなんてまだ3歳を越したばかりのちいちゃな子供にはなかなかに酷な話である。まあ孤児院で育つ者なんて、ほとんど親が死んだか親に捨てられたかの二択だけど。院長からそのときの物だと受け取ったメッセージカードを光にかざしぼーと眺めたあと、また先生に返した。一緒に入れられていた品物と共に。
私には適切に保管できる自信がなかったから。
流麗な線の細い字だった。筆記体だけど詠みやすかった。けど震えたようにがくがくとしていて最後の文字に至っては変な方向にはねていた。
染みたあとのようなものがあった。捨てられた日は特別暑くなく雪も雨も降っていなかったからおそらくは……これは涙なのだろう。
そう思って厚い紙の少し凹んだところを指でたどった。
先生はせめてこれだけでも持っていなさいと私の首に十字架をかける。確かにこれは捨てられたときにも持っていた気がする。
胸の重みを、憶えている。
ずしりとした重みをたたえる金属製の十字架は明るいゴールドに輝いていた。歩けるようになってから、それが当然のように毎日通いつめる礼拝堂にいる牧師さまがつけているもののように立派だった。
首を擦れる革ひもにしっくりきた。孤児院で他とは違う特定のものを持つことは顰蹙を買うからと考え躊躇う心がぬぐい去られた。
これは私のものだ。誰のものでもなく、私だけの。
______
「トリア、それ、何?」
ヴィクトリアの愛称であるトリアと呼ばれて、ヴィクトリアは視線を向けた。黒くさらりとした髪と黒い双眸のあどけない少年が興味深そうに尋ねる。ヴィクトリアの胸元にかけられた金の十字架を指し示しながら。瞳にうつるのは純粋なる好奇心。幼いながらに整った顔立ちは未来への有望さがうかがえた。
この少年は私と同い年であり私が捨てられる数ヵ月前にここで生まれここで暮らしていたらしい。彼の名前はトム・リドル。そう、あのトム・リドルである。
ハリー・ポッターというイギリス生まれの大人気児童書の最強で最恐のラスボス、ヴォルデモートの過去の姿である。
そう、ここウール孤児院はトム・リドルが生まれ育った孤児院であった。
ヴィクトリアは初めてこいつがトム・リドルでここがウール孤児院であると気づくと驚いた。あまりに驚いて初めて寝返りをし、そのままごろごろと転がり、床へと落ちかけたほどである。しかし、そんなことはどうでもいい。
私ははっきり言うとこいつが好きではない。
だってこいつはこの世界のラスボスで、何よりも……大がつくほどの問題児なのである。
あさっぱらから癇癪を起してこの不況の時代に窓を割るわ、電球をショートさせるわ。ついにはミセスコールが悪魔祓いを呼ぶまでにいたったほどである。
けれど、こいつはどこまでもきっと寂しい子供だった。小さくて不安げでどこか朧だった。
そしてまだまだこいつは無垢で無邪気な幼子であった。
私が捨てられてからほとんど私はこいつと共に育った。しかしこいつは幸いにも_なぜかはわからないが私が傍にいるときに問題を起こすことは殆どなかった。うまれてたいして経たぬほどから傍に居たから同族感でも感じているのだろう。
理由不明で周りで問題や事故が起こる人物の前にお互い同い年の赤ちゃんとはいえ赤ちゃんを置くってどんな神経しているんだ、と思いながら過ごしたものだ。いつ何が起こるかと恐々としながら。
だからか、別に私たちの仲は悪くない、良くもないが。
いやむしろ悪くて良いのほうが正しいのかもしれない。
私とこいつは根本的に合わないのである。
こいつはわずか3歳ほどで大問題児の一人として孤児院内で名をはせているトムかたや私は聞き分けの良い良い子として周知されつつあるのである。そりゃ合わない。
ヴィクトリアは話しかけてきたトムに対して顔を歪め話をそらした。なぜだか知られたくなかった。私に様々なをものを託し捨てた母親のことを。
「聞いたよ、トム。昨日いらした老夫婦の旦那さんのベルトをへびに変えたんだって?ほんとう?」
「さあ?違うんじゃない?どうやってやるというんだ」
肩を竦ませて告げるトムは胡散臭いことこのうえない。ヴィクトリアは思わず半眼になる。
「大人しくしていたら……あなた、顔も頭も良いんだからすぐ貰われるだろうに」
小さく溜息をつきながらヴィクトリアはぼやいた。ヴィクトリアの呆れが滲んだ声に反してトムは鼻で笑う。
「ハッお断りだね、そういう君はどうなんだ?」
今度はヴィクトリアが渋い顔になった。どうにも縁がないのだ。
ヴィクトリアは少々珍しい容姿をしているのがあってどれほど優等生であろうが"引き取りたい"と告げられることはなかった。
こいつほど整った顔立ちをしているなら話は別だろうが。
でも少しでも興味をもたれたなら話は早かった。幼いながらに真面目で従順なその姿を見てヴィクトリアを気に入る者は少なくはなかった。とんとん拍子に進む話に不安と共に期待をヴィクトリアが抱いているとその話はすぐさま破談となるのだ。いっそ呆気ないほどに。
そんな日々が続いていてヴィクトリアはもうすっかり期待しなくなってしまった。
この孤児院にいられるだけ恵まれている。それも健康体で。
捨てられる子は多いけれど引き取られる子は少ない。そして貧しい孤児院では病になり亡くなる子も少なくはなかった。
19世紀ほどに話題となりいくぶんか姿を消したが第一次世界大戦の影響もあってかロンドンでもまだ少し暗い路地へと入れば身寄りのない浮浪児がさ迷っている。
大人の保護下にいない状況で生きていけるほどこの国はまだまだ甘くはない。探せば子供の死体など転がっているだろう。
私は運がいい。捨てられた晩すぐに孤児院の職員が見つけてくれて。捨てられた孤児院が貧しく事務的な面が強いとはいえ善良かつマトモで。
下手な家に引き取られるよりはよほどいい。けれど…………
黙りこくった様子のヴィクトリアにトムは何を思ったのか先ほどのつん、として人を小馬鹿にしたような声とはうってかわりいくぶんか優しい声を出した。慰めるような宥めるような声。怒った母を、悲しむ妹を。
「……まあ、トリア。孤児院での生活もそこまで悪くはないだろうし……変なやつに引き取られるよりはだいぶマシさ……。ずーっと誰も僕らを引き取りに来なければ出ていってしまおうよ」
最後は提案するような声音だった。子供の無邪気さと果てのない全能感を由来とする、無鉄砲なひらめき。それをもっとも良案だといいたげな声音にヴィクトリアは(どうやって生きていくのだろうか、でもこいつならやっていけそうだ)と思わず微笑んだ。
2/2ページ