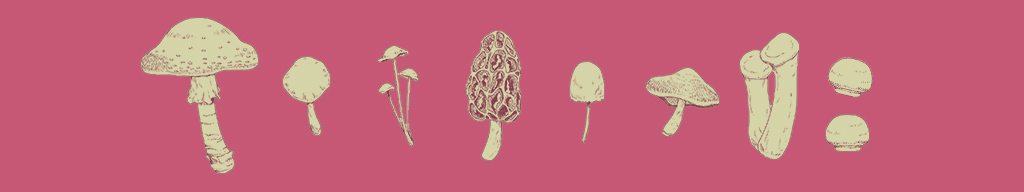私の太子様
「はぁ…」
太陽が沈み、常闇が訪れる夜
ランプに灯された小さな火が、唯一辺りを小さく照らし続けている。
ゆらゆらと揺れる火を見つめながら、[#dn=1#]は小さなため息を吐いた。
「太子様…」
小さく呟いた名前こそ、[#dn=1#]にため息を吐かせる人物である。
先日、太子により自分との交際宣言もとい婚約宣言をしたことがきっかけで、
自分から可愛い愛娘を奪った太子が気に入らなくて、嫌がらせをしたい[#dn=1#]の父と
日頃から太子への不満を募らせていた馬子を始めとした朝廷の役人により
摂政である太子自らが、遣隋使として遠く離れた隋の国へ赴くことになった。
それを、[#dn=1#]は自分のせいだと自らを責めていた。
優秀な部下である妹子がいるとはいえ、二人だけで隋に行くなんて危険すぎる。
だが、自分の立場上何も出来ない。
その上、愛する人を危険な目に遭わせておいて、自分だけは何のお咎めもない。
「せめて、私が殿方なら太子様をお守りできたのに…」
「それだと、私が困るでおま」
「え!?だ、誰!?」
「誰って失礼だな!私は摂政だぞ!!」
誰に聞かれることもなく消える筈だった[#dn=1#]の呟きに、
返事が返ってきたことに驚き、振り向くと室の扉の前に太子が立っていた
「太子様、お戻りになられたんですね」
「あぁ、明日からの旅の用意もしないとだからな」
「明日…」
明日、という単語を聞いて[#dn=1#]は思い出した。
明日が、隋への旅立ちの日であることを。
「…そんな顔するな、[#dn=1#]」
「っ…でも!私のせいで、…太子様が…」
[#dn=1#]の目から、堰を切ったように大粒の涙が零れ始めた。
もしかしたら、今夜が最後の日かもしれない。
[#dn=1#]は、太子のジャージの裾を力なく掴む
「行かないで…」
「[#dn=1#]、大丈夫、私は必ず戻ってくるから。」
「だから、戻ったら私と夫婦になってくれないか。」
太子の言葉に、[#dn=1#]は太子、そういうのを死亡フラグって言うんですよ。
と、敢えておどけた様に言ってみせた。