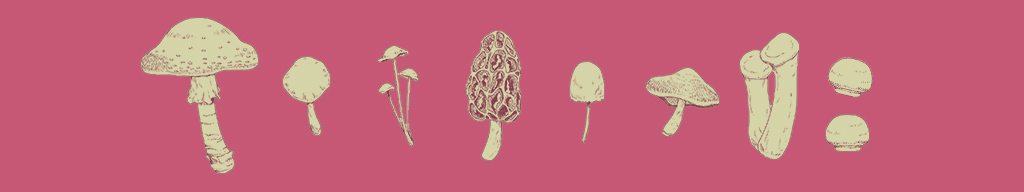遊戯王ゴーラッシュ!!の男主攻め
夢小説設定
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
「ゆめお、今週末私の家に遊びに来ないか?」
きっかけは、フェイザーからゆめおに送られてきたメッセージだった。文末には、お前の好きなお茶菓子もあるぞ、まるで子どもに対する誘い文句付きのフェイザーからのメッセージに対してお菓子が大好きなゆめおは深く考えないまま二つ返事で返した。
そして迎えた翌日、フェイザーは約束通り食べ切れない程のお茶菓子を用意してゆめおを迎えてくれた。
特別な事はなく、2人でお菓子を食べながらフェイザーの部屋でデュエルをしていたのだが、楽しい時間はあっという間に過ぎていき、気付けば窓の外は陽が沈み始めていた。
「ごめん、フェイザーそろそろ俺帰るわ」
「…もうそんな時間か」
まだ学生の身分であるゆめおには、門限が課せられている為、時間までに帰らねばならない。だが、ゆめおの言葉を聞いたフェイザーは、分かりやすいぐらい表情を沈ませた。もっとゆめおといたい、帰らないでほしい。言葉にこそ出さないが、その悲しそうな表情が言葉の代わりにフェイザーの心情を雄弁に語りかけてくる。
いつでも会える関係であるのにそんな顔をするのはズルすぎるとゆめおは考えた末にある事を思いついた。
「ちょっと、親に連絡していい?」
ゆめおは、フェイザーに一言伝え部屋の外に出た。
母親に泊まりの許可を得る為の電話をかけることにしたのだ。数度のコールの後に繋がり、開口1番にフェイザーの家に泊まっていいかと持ち掛けた。
ゆめおの母親はフェイザー宅ならばと許可しつつ、あまり羽目を外しすぎるなと釘を差してきた。日頃から模範的な息子をやっていて良かった、ゆめおはほっと胸を撫で下ろしながら部屋に戻る。
「今日、泊まって良いって」
「本当か」
「うん」
「…なら、今日は私の部屋で寝泊まりしてくれ。必要なものは直ぐに用意させる」
ゆめおが泊まると分かった時のフェイザーの変わりように、思わずニヤケてしまうゆめおであった。
*************
「やっぱ、風呂もでかいんだな」
目の前に広がるのは、まるで高級スパの様な立派な浴室であった。こんなに広々とした風呂に入るのは修学旅行の温泉旅館以来だ、ゆめおは感動と驚きを抱えつつはゆっくり浴室の中へ入った。そして、壁側に設置されたシャワースペースに行き椅子に腰掛ける。
「このシャワー、痛くない…」
水圧が強い自宅のシャワーヘッドと比較し感心していると浴室の扉が開く音がした。おかしいな、この時間はゆめおの貸し切りにしてあるというフェイザーの言葉を思い出していると、湯気と共にある男性のシルエットが現れた。
「あ、すみません。お邪魔しています…」
「ゆめお、私だ」
「ん?…って、ちょ!なんでお前がいるんだよ!!!」
少しの気まずさを感じながら声を掛けると返ってきたのはゆめおの名を呼ぶフェイザーの声であった。浴室の湯気が晴れると同時に現れたのは、フェイザーの引き締まった肢体であった。初めて見る恋人の裸にゆめおの脳内は混乱を極める。しかし、フェイザーは普段と変わらない話しぶりで口を開いた。
「折角だからお前の背中を流してやろうと思ってな」
「なんで!?」
「お前は今日私にとっての大切なゲストだからな、丁重にもてなさなければならないだろう」
「お前のおもてなし、背中を流すことなの!?」
フェイザーはゆめおの事等お構いなしと言わんばかりにマイペースに事を進めようとするので、突っ込みが追いつかない。あれよこれよと言う前にゆめおは、フェイザーによって椅子に座らされた時ゆめおは全てを諦めた。この男は夜な夜な龍の姿で反物を織り、毎朝全裸で寝ている男だ。きっと裸に対しての抵抗がないのだろう。だから、風呂に入ってきたのも純粋にもてなそうと思っての事なのだろう。そうだ、そうに違いない。変に意識する方がおかしいのだ。そう必死にゆめおは自身に言い聞かせる。
「じゃあ、洗っていくぞ」
フェイザーは身体を洗う為のスポンジにお湯を染み込ませてから、石鹸で泡立て始めゆめおの背中に宛がう。スポンジの柔らかさと、背中に触れるフェイザーの細い指が何とも言えないむず痒さとを生み出す。ただ、背中を洗っているだけだというのにこの奇妙な感覚は何だ。やけに下半身が熱い気がする。ゆめおが自身の足元に目線を落とした時、ソレと目が合った。
「!?!?」
ゆめおの股下にて自身の分身である性器がそそり立っていた。しかも、普段1人でオナニーする時よりも明らかに質量が増しており、血管も浮き立っている。
何故なのか、いや答えは明白だ。フェイザーと共に風呂に入っているからだ。恋人の裸を見て、あまつさえ身体を触れられているのだから健全な男子なら反応するのも無理はない…とは言うものの肥大しきった自身の性器の大きさにゆめおは内心引いてしまった。
「どうした、ゆめお?」
「!?あ、いや!なんでもない!」
ゆめおはフェイザーにバレないように、それまで広げていた足を閉じ前かがみの姿勢を取ることにした。
幸いにもフェイザーはゆめおの背後にいるので上手いこと隠せばバレない。その間に気持ちを落ち着かせれば大丈夫だ。しかし、そんな彼の思惑をこの男は簡単に破ってみせた。
「じゃあ、次は前を洗うとするか」
「はぁ????」
「ゆめお、こちらを向け」
「いやいやいや!いい!前は自分で洗うから!!」
「そう、遠慮するな。私達の仲だろう」
「いい!まじで大丈夫!俺、自分で洗える!」
「ゆめお…そんなに私に洗われるのが嫌なのか?」
「うぐっ!!」
全力で首を横に振りながら拒むゆめおに対して、フェイザーはまたしても悲しそうな表情を浮かべた。恐らく本人は意図しての行為ではないのだろうが、それはゆめおには効果てきめんである。フェイザーの厚意を優先して自身の恥を捨てるか、それとも自身のプライドを優先しするか。悩んだ末前者を選ぶごとにした。男ならば恋人を泣かせるような事はしてはいけない、と静かに首を縦に振り、椅子ごとフェイザーの方を向いた。
「ゆめお、これは…」
「や、あの、違う。これは、その〜生理現象であって!」
フェイザーの前に現れたのは、立派にそそり立つゆめおの性器。彼の意志と反してまるで触ってほしいと言わんばかりにピクピクと小刻みに動いている。その姿が、自分とは別の意思を持った生き物の様に見えた。フェイザーは、ゆめおの性器を何も言葉を発さないまま見下ろしている。
「風呂に入るとこうなるんだよね…」
「…」
「温かくなって血流が良くなるのかも…」
「…」
沈黙に耐えきれなくなりゆめおは言い訳を始めた。
しかし、依然としてフェイザーは黙ったままである。
ゆめお自身、これは嫌われてしまったのではないかと徐々に身体の温度が下がっていくのが分かった。
弁明しなければと口を開こうとした時、フェイザーがゆめおの性器に触れ始めた。
「はっ!?何してんだよ!汚えぞ!」
「ここもきちんと洗わねばならいだろう」
フェイザーは右手にボディーソープを垂らしてからゆめおのサオ部分を握り、根本から優しく擦り始める。
「うっ…」
「痛くないか?」
「い、たくはないけど…」
「そうか、なら良かった」
安心したように笑みを浮かべつつ、フェイザーは奉仕を続ける。緩慢な動きと微弱な刺激、泡のぬるぬる加減が気持ちいい。
「あ、っ…くぅ、!」
「…もう少し強くした方がいいか?」
「あぁっ!バカ、やめ…うあぁ!」
フェイザーは性器を握る手の力を込めながら、擦る速度を速めるとそれまでの緩慢な刺激から直接ゆめおに快感を与えるものとなり、ゆめおの身体が大きく跳ねた。息を抜いたら今にも射精してしまいそうなので、ゆめおはバスチェアの縁に手をかけ耐えようとする。それを見たフェイザーはゆめおの性器にシャワーをかけ泡を落としたかと思えば、徐に身体を屈ませゆめおの性器の先端を口で咥え始めた。
「ぅあっ!…っ、ちょ、フェイザー!」
「ふぉうひは?(どうした?)」
「お前、何やってるんだよ!汚えだろ、そんなの!」
「汚ふはいふぉ(汚くないぞ)」
「咥えたまま喋るな!」
フェイザーは、ゆめおの太ももに手を置き、咥えたまま顔を上下させ始める。口内の温かさと潤滑油代わりの唾液が陰茎に絡みつく感覚、そしてあの竜宮フェイザーが自身の性器に奉仕しているという事実がゆめおのなけなしの理性を溶かし始める。
「フェイ、ザー…まじで、も、やばい!」
徐々に頂点に昇りつめてくる感覚、このままではフェイザーの口内で射精してしまう。それは避けねばならないので、ゆめおは押し退けようとするものの、腕に力が入らない為フェイザーの頭を自身の陰茎に押し付けている事にゆめおは気づいていなかった。そして、ついにその時が訪れた。
「う、ぁ…」
「んぅ、…ふふっ、沢山出たな」
ゆめおの男性器から放たれた白濁は、フェイザーの顔目掛けて噴射された。必死に息を整えながら射精の余韻に浸るゆめお、ふとフェイザーを見ると自身の顔の白濁を指で掬い取り、数秒程それを見つめたかと思うと徐に口に含んでいた。
「!?!?お前、何してるんだよ!?」
「精液というのは苦いのだな…」
「…」
その姿に倒錯的な興奮を抱いてしまった。今すぐこの場でフェイザーを犯し、その綺麗な顔を歪まてやりたい男としての本能に自身の理性が吞み込まれかけながらも、だが、それではいけない。一度冷静になろう、そうだこれは熱いせいだ。一度風呂から出て冷たい水でも貰おう。ゆめおは無言で立ち上がり、急いで風呂場から出ようとしたのだが、それはフェイザーにより阻まれた。
「ゆめお、ここは熱いから私の部屋で続きをしないか?」
この状況でそんな事を言われたら断れる人間なんていないだろう、ゆめおは小さく首を縦に振った。