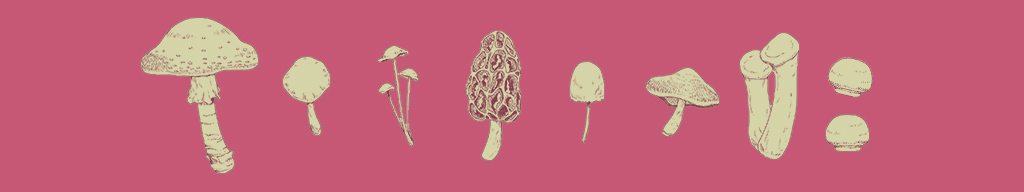遊戯王GXの置き場
夢小説設定
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
僕の恋人は、吸血鬼だ。
言っておくが、別にふざけている訳では無い。
これは紛れもない事実だ。
その証拠に、これから僕は彼女の食事として
その身を捧げに行くのだから。
「ゆめ、お待たせ」
「エド!もう、遅いよ!」
「悪かった、会う前にシャワーを浴びていた」
「別に、私は気にしないのに…」
「いいや、だめだ。エチケットだからな」
僕に抱き着いてきた、この少女こそ
僕の恋人であり、そして吸血鬼だ。
吸血鬼のくせに、日の光の下で堂々と行動したり
ガーリック料理を好み、
あまつさえ僕以外の人間の血は見るのも
苦手等と言うが。
「エドって私のことが大好きなんだね」
微笑む彼女の瞳は、真紅に染まり
口元の端から牙が僕のことを伺う。
「当たり前だ、じゃなければ誰が好き好んで
血を吸わせるんだ」
「たしかに!」
僕の膝の上に座り、甘えるように首に腕を回す。
そして、ゆっくりと首筋に口元を寄せて牙を突き立てた。
皮膚が破ける痛みに眉を顰める。
何回経験してもこればかりは慣れない。
「くっ…」
痛みが徐々に引くかわりに、
次に訪れたのは甘い痺れ。
ゆめ曰く、吸血鬼が血を吸う為に吸血する時に微弱な毒を注入するそうだ。
それにより、痛みが快感に変わることで、
人間側から吸血鬼に血を吸ってくれと 寄ってくるそうだ。
まぁ、初めは僕もそうだったがな。
無性に血を吸って欲しいと考えていた。
だから、過去に吸血鬼に快感の代償として
命を捧げていった人間を侮辱できない。
そもそも、僕達が出会ったのは空腹で倒れてた
ゆめを見つけたからだ。
目の前に倒れているのを無視するほど、
僕は薄情ではないから、助けてやろうとしたら
突然血を吸われた。
ゆめは僕の血が今までで1番美味いと言い、
僕に付き纏うようになった。
陽の光によるダメージを最小限に抑える為に、
小さなコウモリに変化し、僕のスーツの
胸ポケットを住処にした。
最初こそ、迷惑極まりなかったが、
気付けば彼女は僕にとって必要不可欠な存在となった。
「なんで、エドは私に優しくしてくれるの?」
普段は、自由で我儘な癖に、
ゆめは1度だけ僕に尋ねてきた。
どうやら、僕がゆめに優しくするのは、
吸血行為に伴う毒のせいだ、と勘違いしていたらしい。
だから、僕はそれを否定した。
「僕が、君のことを愛してるからだ。」
そうだ、僕のゆめへの想いは偽物ではない。愛しているからこそ、この身を捧げるんだ。
「愛してる、ゆめ」
そして、僕はゆっくりと目を閉じる。
明日は休みだから、ゆっくり休ませてもらおう。