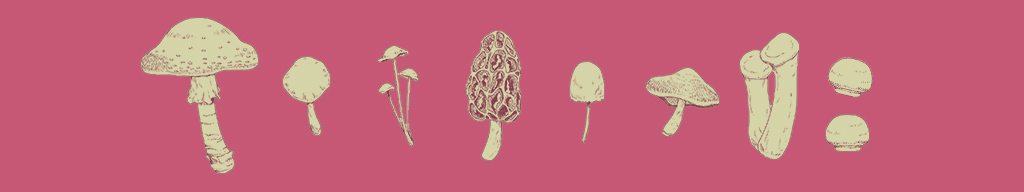女夢主の短編
夢小説設定
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
生きていく為には金が必要だ。
しかし、この国で知識も技量もない小娘に出来る仕事等限られている。
その上、自分の器量の悪さも相まって中々仕事が見つからない。
そんな時に、百獣海賊団の城に住み込みで働く使用人を募集しているというお触れを目にした。
お触れには、主に清掃や食事作り、配膳等がメインと書いてあるので、
これならば、と確信したゆめは思い切って申し込むことにした。
だが、事態は想定外の方向に動き始めた
「お前さん、随分と顔がいいじゃないか。使用人なんかじゃなくてうちの遊郭においで」
偶然、そこにいた身体が大きな女性に声を掛けられて、
気付けば派手な柄の着物に身を包んでいた。
そして、あれよあれよと流され、ついにゆめの遊女デビューの日を迎えてしまった。
だが、ゆめには不安しかなかった。
だが、生きる為には働かねばならない。
それに、折角ならお客様に少しでも楽しんでもらいたい。
ゆめは頬を伝う涙を着物の袖で拭い、客が待つ部屋の障子の前に膝をつく。
「ゆめござりんす」
「お、おぅ…」
恐る恐る開いた障子の先にいた初めての客は、口元を布で隠し
ツノのようなものがついた被り物を被る若い男であった。
男の服装は、着物とは全く異なる外国風である為ゆめは
思わず興味を惹かれた、男をジッと見つめた。
それに気づいた男は、微かに眉をしかめた
「なんだよ」
「あ、…申し訳ございません…じゃなくて、申し訳ございんせん!
お客様のお召し物が珍しくてつい…何のお仕事をしていんす?」
「…海賊」
「海…賊?」
「お前、そんな事も知らねえのかよ」
「はい!生まれてこの方、国の外に出たことがないので」
「…世界中の海を旅して金を稼いでる」
「海を旅するって凄い素敵ですね!」
「別にいいもんじゃねえよ」
男は、その言葉を最後に目線を下に落とし、目の前の食事に手をつけ始める。
それを見て、ゆめは酌をせねばと酒瓶を手に取り男に近付く。
「お飲みになられんすか ?」
「……頼む」
「はい、では…って、あッ!」
「な!?おい、」
「も、申し訳ございません!!ただいま、拭きものを!!ひゃぁああ!!」
「おい、お前落ち着け!!」
ゆめは、酌を注ぐ際に男の着ている服にうっかり酒を零してしまった。
拭き取らねば、と慌てた所を自分の着物の裾を踏みその場に転んだ。
最悪だ、客の目の前でこのような失態。
ゆめは、恥ずかしさと客から怒られるのではという恐怖で視界が滲む
恐る恐る男を見上げると、男は呆れた様子ではあるがゆめに向かって手を差し出した。
「大丈夫か?」
「は、はい…あの、申し訳ございませんでした…!」
「別に、これぐらいなんてことねぇよ」
怪我はねぇか?なんて逆にゆめを気遣う男の言葉を聞いて、
ゆめは胸が温かくなったのを感じた。
ある程度、片付けが終わると男は今日は帰るわ、と
言い残して部屋から出て行った。
こうしてゆめの初勤務は終わりを迎えた。
何とか初日を終えられた安堵と、
男を楽しませられなかったという悔しさの残る1日となった。
きっと、2度とあの男は来ないだろうと考えていたにも関わらず、
次の日も、そのまた次の日も何故かやってきては、必ずゆめを指名した。
それも、大金を積んだのかゆめには自分以外の客をつけるな、と
遊郭の長であるブラックマリアに告げたらしい。
「あ、ページワン様!またいらしてくれたんですね!」
「ゆめ」
「今日もいっぱいお喋りしましょうね」
「あぁ、頼む」
ページワンは、毎日決まった時間に必ずゆめの元を訪れる。
沢山の贈り物を携えて。花束に着物、簪、外の国のお茶菓子等
しかし、ページワンはけしてゆめに触れようとはせず、
ただ隣で一緒に食事をしながらゆめの話を聞いて、時々自分の事も話すだけだ。
「そういえば、今度お城の宴会にお呼ばれしたんですよ。私、お城に行くの初めてなんですよ!」
「あぁ、それなら俺もいるぞ」
「ページワン様って、確か凄く強くて偉い人なんですよね?とび…とんび隊でしたっけ?」
「飛六砲な…」
「あ、そうそうそれ!宴会の日、こっそりページワン様の所に行きますね」
「ん、楽しみにしてる」
2人は、互いに顔を見合って笑いあった。
*******
宴会の当日、「こっそり会いに行く」とは言ったものの
宴会場は想像以上の人数で、ゆめは呆気に取られてしまった。
ブラックマリア並に大きい人?や、身体に動物の被り物?のような物を身につける人等多種多様な人間がいる。
海賊というのは、凄いなと感心していると、隣りにいたお姉さんに声をかけられる。
「ページワン様は見つけられたの?ゆめ」
「あ、いえ…人が多くて」
「そう、まぁ今日は仕事だと思って頑張るしかないわね」
「そうですね、お姉さん」
毎日会っていたからか、ページワンと会えない事に寂しさの様なものを感じるが、
これも仕事だと自分で区切りをつけ、お姉さんと一緒に各お座敷を回り始める。
「おぅ、嬢ちゃんいいケツしてんな!」
「あ、あはは…ありがとうございんす…」
遊女になってから、ページワン以外の男性を知らないからか、
酒に酔った男性陣達に対してどう接すれば良いのか分からない。
とりあえず愛想笑いを浮かべるものの、
時折お尻や太ももを厭らしく撫でる手つきが気持ち悪く感じてしまう。
「なぁ、今夜俺とどうだ?」
「え、あ、あの…」
「いいだろ?」
「い、いやっ!」
男に肩を抱かれ、耳元で囁かれた瞬間
ゆめの全身に鳥肌が立ち、思わず男の手を振り払ってしまった。
男は、一瞬呆然としたものの直ぐに顔を真っ赤にさせ、
ゆめの身体を蹴り飛ばした。床に強く身体を打ち付けた事で、全身に痛みが走る。
「ぅ…いたい…」
「テメエ、ふざけんじゃねえよ!テメエみたいな売女は黙って男にマンコ差し出せば良いんだよ!!」
ギャハハハと周りの男達は、笑い出し口々に下卑た言葉をゆめに投げ掛ける。
本当なら今すぐこの場から逃げたいのに、身体に力が入らない。
自分のが酷く惨めに感じ、彼女の意識とは裏腹に涙が勝手に溢れてきた。
脳裏に浮かぶのはページワンの顔、
「ページワン様…っ、」
誰にも聞こえない程小さく男の名を呟いた時、
遠くから女性の悲鳴が聞こえたと同時にゆめを見下ろしていた男が大きな物音を立てながらどこかへ消えた。
「え、何…?」
困惑するゆめの目の前には、大きな人間の様な、トカゲの様な何かがそこにいた。
それは、ゆめの視線に気付いたのか一瞬目が合うものの直ぐに逸らし、
先程ゆめを蹴り飛ばした男の元に歩みを進めた。
「ぺ、ページワン様!これはですね、その!!」
「うるせぇ」
「申し訳ございません!!ページワン様のご贔屓だとは知らずに、
とんだご無礼を…ぎゃああああ!!!!痛え、痛えぇよおおお!!」
「ページワン、様…?」
男は、トカゲ人間の事を確かにページワンと呼んだ。
まさか、と信じられない想いが芽生えるものの、
ゆめは本能的に男の言葉が真実だと分かった。
このままではいけない、止めなければ。
震える身体に喝を入れゆめは立ち上がり、そして二人の元へ近づく
「ページワン様、駄目です!」
「ゆめ…アブねぇから、どいてろ」
「…私がどいたら、この人をどうする気ですか?」
「んなの決まってるだろ、俺の女に手を出したんだ。その報いを返してやるんだよ」
「そんな事しなくてもいいです!…それより、今はページワン様と二人になりたいです…」
そう言ってゆめは俯いた。
ページワンは、そんなゆめを見て、
ため息を吐き、バツが悪そうに頭を搔く。
「…わーったよ、だから、んな顔するな」
ページワンは、ゆめの前に跪き手を差し出した。
普段よりも何倍も大きな手のひらに一瞬戸惑いながらも手を取ると、
そのままページワンに抱え上げられた。
「掴まってろ」
そして、ざわめく聴衆達等お構いなしに2人は喧騒の中へと消えて行った。
********************
ページワンに抱えられて連れてこられたのは、彼の自室であった。
部屋の障子を開け、ゆめを畳の上に下ろすと、ページワンは普段の姿に戻る。
「あ、…」
その姿を見てゆめは、内心安堵した。
ページワンであることは分かっていたが、万が一違っていたらという不安があったからだ。
彼は、ゆめに一瞬目線を向けるものの直ぐに逸らした。
「ページワン様?」
「…悪い、怖がらせたよな」
「何がですか?」
「…さっき、お前の前で変化してただろ。あれは、俺なんだよ」
「ページワン様は、とかげ人間なんですか?」
「とかげ人間って…まぁ、そりゃあそう思っても仕方ないか」
ページワンは、ゆめに話し始めた。
悪魔の実のこと、自分がその能力者であること、先程の男達は自分の部下であり、そして百獣海賊団がどんな組織であるかを。
「幻滅しただろ?」
ページワンは、ゆめに尋ねた。ゆめは下を俯き何も答えない。
その姿を見て、ページワンは胸が痛んだ
いつかは、こうなる事が分かっていたのに
ゆめに嫌われたくなくて、真実を話せずにいた。だが、もう遅い。今日をもって彼女とは会えない。会えるわけがない。
ページワンの視界が涙で滲む。男の癖に情けないと自嘲していると、ゆめの指先が頬に触れたのが分かった。
「ページワン様、泣いてるんですか?」
「っ、泣いてねえよ!」
「嘘は駄目ですよ」
ゆめは、自身の着物の裾でページワンの目元に溜まる涙を優しく拭き上げた。
そして、ページワンに向けて微笑んだ。
「幻滅なんてしないですよ。だって、ページワン様は私の事を守ってくれたし、あの時駄目って言ったらちゃんと止めてくれたし」
「ゆめ…」
「それに私、ページワン様の女なんですもんね!」
「ばっ、お前!」
「違うんですか?」
「ちが…くはねぇけどよ…」
正式な告白をしないまま、あの場の怒りに任せてゆめの事を自分の女と口走って
しまった自分を恨みがましく感じていると
ゆめが、ページワンの手に自身の手を重ねる。
「私、ページワン様のことが好きです」
「お前、それ嘘とか実はダチとして好きとかそういう意味じゃねえよな…?」
「まさか!一人の殿方として好きって意味でありんす」
「ありんすって…」
「冗談です!あ、好きってのは本当ですよ」
その言葉を聞いたページワンは、それまで少ない理性で留めていた何かが弾け飛んだような感覚に陥る。
そして、ゆめの身体を両手で力いっぱい抱き締めた。
「ページワン様、苦しいです!」
「うるせえ、お、俺の女なんだから抱きしめさせろ!」
両思いなんだから、これぐらいいいだろ
そう呟くページワンは、耳まで真っ赤にさせていた。
次の日から、ゆめは遊郭を辞めて、
ページワンの小姓と職を改めたが、
昨夜の宴会場での出来事を聞いたフーズ・フーとササキに盛大に茶化されるページワンがいた。