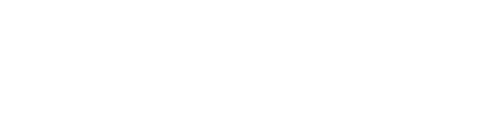引退なんてしてやらないぞ
風見の様子は、取り敢えず初めて見るくらいに、心が弾んでいた。
そこから考えるに“奴ら”とは、僕が潜り込んでいる組織の話だろう。
だから、つい嫌みかと口から漏れてしまった。
そんな喜ばしい展開になっていれば、廊下をこうものんびり歩いてるわけがないだろう。
にしても、何故そんなことを思ったのか。
話の続きを待ったことを、すぐ後悔した。
「いえ、みんなが――」
内容は、こうだった。
今朝、出勤してみると数人が床に泣き崩れていたという。
理由を尋ねる前に聞こえてきたのは――。
『安室じゃぁぁぁんっ!!』
『いんたっ……引退、だなんてっ……!』
それで思うことがあったらしい風見は、すぐさま僕の元に来たらしい。
ニュースを見ていれば、否が応でもそれが僕でないことは明らかだろうに。
溜め息しか出ない僕は、間違っているのか。
何が呆れるって、風見が真剣そのものだからだ。
真っ直ぐなことを悪いとは、言わないが。
「それは、僕のことじゃないぞ」
「……え?!」
本気の反応なのか、もはや僕でも分からない。
そもそも、僕が安室の名を使っていることを知ってる人間は限られている。
今一度、溜め息を吐いては人差し指だけ伸ばした片手を胸元に上げる。
漫画なら、ふわふわとした枠の中にイメージ図でも浮かんでいることだろう。
「流石に知ってるだろ? とても有名な女性アーティストの」
「あー! そういえば、あの人の引退も騒がれてましたね。それで皆あの反応。スッキリしました」
「そうか……良かったな」
本当に気付かなかったのか、もしくは――。
言葉を発さずに、風見に詰め寄る。
本能で危険を察知した動物のように、近づく度に後ろに下がられた。
僕も負けじと、歩みを進める。風見が、壁にぶつかるまで。
怯えた風見の真横に、力強く手を叩きつけてやる。
身長が変わったわけではないのに、何故か見下ろせている心地だ。
「――僕に、そんなに引退して欲しかったか?」
「ひ、ひえっ! し、失言、でした……っ!」
声が裏返った様は、珍しくて笑いをそそられる。
口元にそれが表れたと自覚したとき、風見はより硬直した。
そんな風見の肩に、額を擦り付けた
「僕は、もっと……風見に」
「ふ、降谷さん……?」
そっと、石になっている体の胸の中心に指を添える。
鼓動が速く、逆に息苦しくなっているんじゃないかと思う。
横目に見てみれば、やはり呼吸が浅くなっている。
小さく、今度こそ吹き出して耳元に唇を寄せた。
「――説教、したいんだが?」
「………………あ、そっち、ですか」
「他にどんな選択肢があったのか、じっくり尋問してやろうか?」
「結構です!」
「はは、冗談だ」
心底ホッとしている風見に笑みが深まってしまう。
踵を返し、その表情を引き締め直す。
肩越しに振り返って、風見をもう一度見やる。
まだ、安心したとばかりに胸に手を当てている。
もう速度が通常に戻っているだろうか。
「今夜にでも――」
「え……!」
「なんてな」
「あ、ですよね」
今度は、あからさまにガッカリしている様子。
再び、口角が上がってしまうのは、僕ももうどうしようもない。
「仕方ないだろ。事件は、僕らが睦言に耽るのすら待ってくれないんだからな」
「――はいっ」
何かに気付いたように、風見は姿勢を正して響き渡る返事をする。
早足に近付いてきて、隣に並んだ。
風見の手を取り、覗き込む角度で見つめる。
「けど、その分、長く一緒に居られるな」
「……そうですね」
嬉しそうに笑った風見に、今度は僕が安心させられる。
微笑みが零れ、手を離すと同時にお互い次の現場へと足を向かわせた。
後日に知ったが、あの時、本当に風見は皆の言う安室が僕の事だと思ったらしい。
見ていた人間曰く、必死の形相で駆け出して行った、降谷さんって叫びながら、と。
「まったく、気付かないほど冷静を欠くなんて、後で説教だな」
コーヒーを啜っている僕の唇が緩んでいたことは、誰も知らない。
そこから考えるに“奴ら”とは、僕が潜り込んでいる組織の話だろう。
だから、つい嫌みかと口から漏れてしまった。
そんな喜ばしい展開になっていれば、廊下をこうものんびり歩いてるわけがないだろう。
にしても、何故そんなことを思ったのか。
話の続きを待ったことを、すぐ後悔した。
「いえ、みんなが――」
内容は、こうだった。
今朝、出勤してみると数人が床に泣き崩れていたという。
理由を尋ねる前に聞こえてきたのは――。
『安室じゃぁぁぁんっ!!』
『いんたっ……引退、だなんてっ……!』
それで思うことがあったらしい風見は、すぐさま僕の元に来たらしい。
ニュースを見ていれば、否が応でもそれが僕でないことは明らかだろうに。
溜め息しか出ない僕は、間違っているのか。
何が呆れるって、風見が真剣そのものだからだ。
真っ直ぐなことを悪いとは、言わないが。
「それは、僕のことじゃないぞ」
「……え?!」
本気の反応なのか、もはや僕でも分からない。
そもそも、僕が安室の名を使っていることを知ってる人間は限られている。
今一度、溜め息を吐いては人差し指だけ伸ばした片手を胸元に上げる。
漫画なら、ふわふわとした枠の中にイメージ図でも浮かんでいることだろう。
「流石に知ってるだろ? とても有名な女性アーティストの」
「あー! そういえば、あの人の引退も騒がれてましたね。それで皆あの反応。スッキリしました」
「そうか……良かったな」
本当に気付かなかったのか、もしくは――。
言葉を発さずに、風見に詰め寄る。
本能で危険を察知した動物のように、近づく度に後ろに下がられた。
僕も負けじと、歩みを進める。風見が、壁にぶつかるまで。
怯えた風見の真横に、力強く手を叩きつけてやる。
身長が変わったわけではないのに、何故か見下ろせている心地だ。
「――僕に、そんなに引退して欲しかったか?」
「ひ、ひえっ! し、失言、でした……っ!」
声が裏返った様は、珍しくて笑いをそそられる。
口元にそれが表れたと自覚したとき、風見はより硬直した。
そんな風見の肩に、額を擦り付けた
「僕は、もっと……風見に」
「ふ、降谷さん……?」
そっと、石になっている体の胸の中心に指を添える。
鼓動が速く、逆に息苦しくなっているんじゃないかと思う。
横目に見てみれば、やはり呼吸が浅くなっている。
小さく、今度こそ吹き出して耳元に唇を寄せた。
「――説教、したいんだが?」
「………………あ、そっち、ですか」
「他にどんな選択肢があったのか、じっくり尋問してやろうか?」
「結構です!」
「はは、冗談だ」
心底ホッとしている風見に笑みが深まってしまう。
踵を返し、その表情を引き締め直す。
肩越しに振り返って、風見をもう一度見やる。
まだ、安心したとばかりに胸に手を当てている。
もう速度が通常に戻っているだろうか。
「今夜にでも――」
「え……!」
「なんてな」
「あ、ですよね」
今度は、あからさまにガッカリしている様子。
再び、口角が上がってしまうのは、僕ももうどうしようもない。
「仕方ないだろ。事件は、僕らが睦言に耽るのすら待ってくれないんだからな」
「――はいっ」
何かに気付いたように、風見は姿勢を正して響き渡る返事をする。
早足に近付いてきて、隣に並んだ。
風見の手を取り、覗き込む角度で見つめる。
「けど、その分、長く一緒に居られるな」
「……そうですね」
嬉しそうに笑った風見に、今度は僕が安心させられる。
微笑みが零れ、手を離すと同時にお互い次の現場へと足を向かわせた。
後日に知ったが、あの時、本当に風見は皆の言う安室が僕の事だと思ったらしい。
見ていた人間曰く、必死の形相で駆け出して行った、降谷さんって叫びながら、と。
「まったく、気付かないほど冷静を欠くなんて、後で説教だな」
コーヒーを啜っている僕の唇が緩んでいたことは、誰も知らない。
2/2ページ