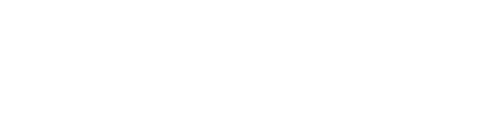星を繋ぐ
「そんなとこに行ってどうするんだ」
これは父が俺に言った言葉だった。不真面目であった俺は、不真面目なだけの結果を大学受験で出した。結果はちゃんと全て駄目だった。本当は映像関係の専門学校を受験したかったのだが、それを許さなかったのは自分自身なのに、何ひとつ合格出来なかった俺に対して酷く落胆してみせたのも父だった。
きっと祖父が生きていたら、父はここまで俺に強気にはなれなかっただろうに。苛立ちが無かったと言えば嘘になる。
最後の不合格発表を前に、落ち込むことも、涙を流すこともできなかった俺に声をかけてきたのが彼だったのだ。
「大丈夫かい、具合が悪そうだけれど」
中肉中背、黒い帽子に、黒いコート、黒いパンツ姿のその男は、柔和な表情でするりと俺の心に入ってくるようであった。
どうでも良かったという気持ちで、彼にいくつも受験した大学全てに落ちたこと、本当は映像関係の専門学校に進みたかったことなどを話した。話しながら、それらの全てが本当はどうでも良くなかったのだとじわじわと思い知らされた。
滲んでくる涙を深呼吸と共に飲み込んだ。
彼はただ、うんうんと余計なことは何ひとつ言わずに相槌を打つだけであった。
彼の相槌は、俺の感情ごとすべてを受け止めてくれるようなそれであった。初対面なのに、不思議と彼に対して諦めていた感情をこぼしていた。
「今からでも遅くないよ、僕が力になるよ」
彼はそういうと耐えきれず頬をつたった俺の涙をそっと指で撫でた。男が男にするようなことでもないだろうし、されて喜ぶようなことでもないだろうと思わないでもなかったけれど、決して嫌な感じがするものでもなかった。
きっとこの時点で、彼という存在にとらわれていたのだと思う。
彼の俺の感情を受け止めてくれるそれにずっぷりと沈んでいって、この短時間で取り返しがつかないほどに、抜け出せないほどに。
その取り返しがつかない分以上のことを彼は俺に対してしてくれた。彼は俺に対して色々な支援を惜しまなかった。
彼は今からでも入学が間に合う専門学校を手配してくれた。そういった学校を探してくれた、紹介してくれただけではない。入学できるようお金まで出してくれていたのだ。
そのことは親に話すことなく家を出た。高校の卒業式のためと家を出てから、俺はそのまま家を出たのだ。
街角で俺のことを探しているポスターを見た。駅前で今まで見たことがないような必死な姿の父親を見た。見ただけで、俺だと名乗り出ることも、家に帰ることもなかった。
そのときは、彼に用意されたものだけで十分だと思っていたから。
これは父が俺に言った言葉だった。不真面目であった俺は、不真面目なだけの結果を大学受験で出した。結果はちゃんと全て駄目だった。本当は映像関係の専門学校を受験したかったのだが、それを許さなかったのは自分自身なのに、何ひとつ合格出来なかった俺に対して酷く落胆してみせたのも父だった。
きっと祖父が生きていたら、父はここまで俺に強気にはなれなかっただろうに。苛立ちが無かったと言えば嘘になる。
最後の不合格発表を前に、落ち込むことも、涙を流すこともできなかった俺に声をかけてきたのが彼だったのだ。
「大丈夫かい、具合が悪そうだけれど」
中肉中背、黒い帽子に、黒いコート、黒いパンツ姿のその男は、柔和な表情でするりと俺の心に入ってくるようであった。
どうでも良かったという気持ちで、彼にいくつも受験した大学全てに落ちたこと、本当は映像関係の専門学校に進みたかったことなどを話した。話しながら、それらの全てが本当はどうでも良くなかったのだとじわじわと思い知らされた。
滲んでくる涙を深呼吸と共に飲み込んだ。
彼はただ、うんうんと余計なことは何ひとつ言わずに相槌を打つだけであった。
彼の相槌は、俺の感情ごとすべてを受け止めてくれるようなそれであった。初対面なのに、不思議と彼に対して諦めていた感情をこぼしていた。
「今からでも遅くないよ、僕が力になるよ」
彼はそういうと耐えきれず頬をつたった俺の涙をそっと指で撫でた。男が男にするようなことでもないだろうし、されて喜ぶようなことでもないだろうと思わないでもなかったけれど、決して嫌な感じがするものでもなかった。
きっとこの時点で、彼という存在にとらわれていたのだと思う。
彼の俺の感情を受け止めてくれるそれにずっぷりと沈んでいって、この短時間で取り返しがつかないほどに、抜け出せないほどに。
その取り返しがつかない分以上のことを彼は俺に対してしてくれた。彼は俺に対して色々な支援を惜しまなかった。
彼は今からでも入学が間に合う専門学校を手配してくれた。そういった学校を探してくれた、紹介してくれただけではない。入学できるようお金まで出してくれていたのだ。
そのことは親に話すことなく家を出た。高校の卒業式のためと家を出てから、俺はそのまま家を出たのだ。
街角で俺のことを探しているポスターを見た。駅前で今まで見たことがないような必死な姿の父親を見た。見ただけで、俺だと名乗り出ることも、家に帰ることもなかった。
そのときは、彼に用意されたものだけで十分だと思っていたから。