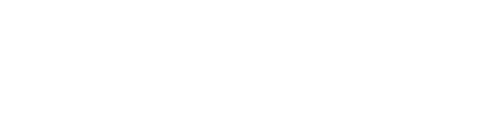星を繋ぐ
それは偶々勉強の手を休めたときだった。
淀んだ空気から逃れるように窓を開けて、ありきたりながら深呼吸でもして気分転換というようなことをしたときだった。
普段なら勉強なんて止めたと、ぽいと放り出して、ベッドにダイブしたうつ伏せのままに朝を迎える。それがいつもの俺だった。
それなのにその日は不思議と勉強を止めようとは思わなかった。
何でだろう。不真面目がベースの俺としては、振り返ってみてもなお不思議で仕方ない感覚であった。
窓を開けて、澄んだ空気がすうっと入ってくるようであった。
本当は窓を開けたところでそんなに変わっていないのかもしれないれど、何事も気分の問題だとひとしりきり呼吸を終えた。
その日は雲ひとつなく晴れていて、満月がどっしりと構えていたと記憶している。
そしてもう窓を閉めてしまおうかとしたときだった、俺の視界いっぱいの眩い光が群れを成して地表に降り注いだのだ。目が眩むような、真昼のような強い光だった。
一瞬何が起こったのか理解は追い付かなったが、それが夜空から注ぐ流星群であるということを次第に理解した。
こんなにも明るく大量の流れ星が降り注ぐ流星群であれば、事前にニュースになっただろうにそんなことは全く聞いたことがなかった。
単に俺が知らないだけだとうことも当然あるだろうから、きっと朝のニュースにはこの流星群の正体がわかるのだろうと思うばかりであった。
そんなことを思いながら明るすぎる夜空を眺めていると、不自然なまでに近づいてくる一筋の光があった。その光があまりにも真っ直ぐ俺の方に向かってくるので、もしかしたらこの家めがけて落ちているのかもしれないと想像したほどだ。
その想像はあたらずとも遠からずで、光は家ではなく俺をめがけて真っ直ぐに落ちてきたのだ。光の直撃を受けた俺のからがは簡単に後ろに飛ばされた。背中や頭を壁に打ち付けた気もするけれど、その痛みは感じられず、なんとも温かいものがからだに吸い込まれていくようであった。
痛みこそ感じないものの、弾き飛ばされたことには変わりなかったので、あわてて自身のからだの状態を確認したけれど、なんともなさすぎて気持ち悪かった。
淀んだ空気から逃れるように窓を開けて、ありきたりながら深呼吸でもして気分転換というようなことをしたときだった。
普段なら勉強なんて止めたと、ぽいと放り出して、ベッドにダイブしたうつ伏せのままに朝を迎える。それがいつもの俺だった。
それなのにその日は不思議と勉強を止めようとは思わなかった。
何でだろう。不真面目がベースの俺としては、振り返ってみてもなお不思議で仕方ない感覚であった。
窓を開けて、澄んだ空気がすうっと入ってくるようであった。
本当は窓を開けたところでそんなに変わっていないのかもしれないれど、何事も気分の問題だとひとしりきり呼吸を終えた。
その日は雲ひとつなく晴れていて、満月がどっしりと構えていたと記憶している。
そしてもう窓を閉めてしまおうかとしたときだった、俺の視界いっぱいの眩い光が群れを成して地表に降り注いだのだ。目が眩むような、真昼のような強い光だった。
一瞬何が起こったのか理解は追い付かなったが、それが夜空から注ぐ流星群であるということを次第に理解した。
こんなにも明るく大量の流れ星が降り注ぐ流星群であれば、事前にニュースになっただろうにそんなことは全く聞いたことがなかった。
単に俺が知らないだけだとうことも当然あるだろうから、きっと朝のニュースにはこの流星群の正体がわかるのだろうと思うばかりであった。
そんなことを思いながら明るすぎる夜空を眺めていると、不自然なまでに近づいてくる一筋の光があった。その光があまりにも真っ直ぐ俺の方に向かってくるので、もしかしたらこの家めがけて落ちているのかもしれないと想像したほどだ。
その想像はあたらずとも遠からずで、光は家ではなく俺をめがけて真っ直ぐに落ちてきたのだ。光の直撃を受けた俺のからがは簡単に後ろに飛ばされた。背中や頭を壁に打ち付けた気もするけれど、その痛みは感じられず、なんとも温かいものがからだに吸い込まれていくようであった。
痛みこそ感じないものの、弾き飛ばされたことには変わりなかったので、あわてて自身のからだの状態を確認したけれど、なんともなさすぎて気持ち悪かった。