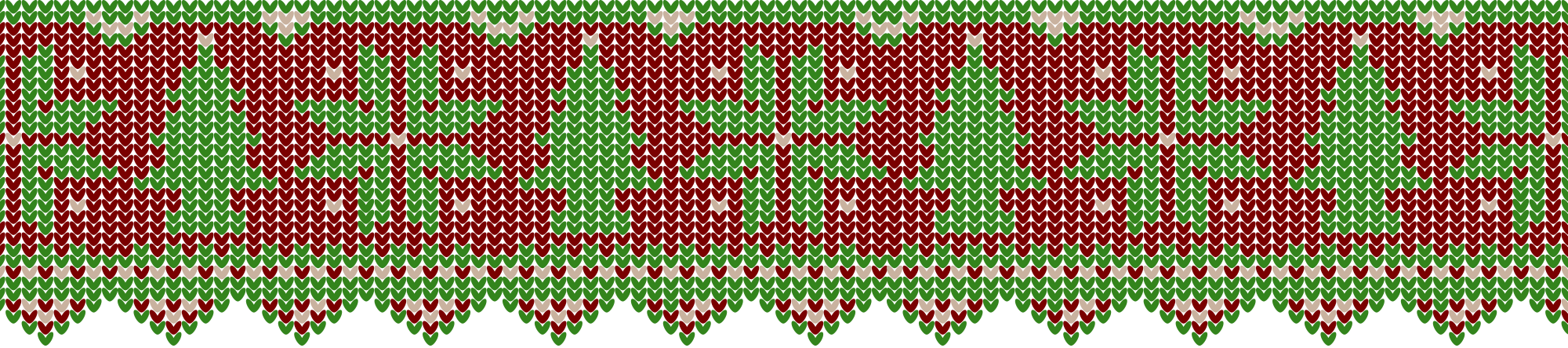📖⛲️SP
いきなり扉が開いたので、寝ずにゲームをしていた俺たちは同時に振り返る。視線の先にはトゥイークの父親の姿があった。朝は一杯のコーヒーからとか何とか訳分からんポエムを呟いている。
「おや。朝のコーヒーを届けに来たんだけど、お楽しみ中だったかな」
彼は俺たちを見下ろして、ねっとりした口調で言った。口は円弧に歪んでいるが目は据わっていて、感情が読み取れない。おちょくっている。
「昨晩は楽しかったかな」
「ええ、楽しかったですよ。ずっとゲームしてました」
毅然と返した。父親が期待しているようなことは本当になくて、ただ夜通しテレビゲームをしていただけだ。しかしなぜ今彼がここに居るんだ? トゥイークコーヒーは既に開店時間のはずなのに。この人はいつだってそうだ。何から何まで不気味すぎる。
「『一晩中ゲーム』かい? ワオ。あんまり夜更かしするのは良くないな」
冷やかすように言われた。返答を探して言い淀んでるうちに、トゥイークのほうが父親に向かって叫んだ。
「ち、違うよ! 僕たちはそういう関係じゃない!」
「じゃあどういう関係なんだ。恋人同士だろう? トゥイーク」
俺の代わりに食い気味に答えたのは父親の方だった。
「……それは……」
トゥイークが消え入りそうな声で呟いた。
俺は何も言わなかった。黙って二人のやりとりを聞いている。リチャードさんはいちおう彼氏の父親だし、息子や4バカとベクトルは違えど紛れもない変人タイプだからあえて喧嘩を売りたいとは思わない。
リチャードさんはそれ以上追求しなかったが、かわりに息子にコーヒーを飲むように言いつけた。そしてご丁寧にもマグカップ二つと個包装の茶菓子を置いて部屋を出ていった。しかしよく見たら、個包装の袋の正体はお菓子じゃなくてコンドームだった。
「クソだな」
「ほんとにね」
二人でベッドに寝そべっていたら、窓から差した朝日が黄金色の前髪を淡く照らしてきた。俺は立ち上がって窓辺に向かい、カーテンを少し開けてやった。それからトゥイークの方を振り返る。色素の薄い、傷んだ毛束は、光を通すときらきら光って見えるのだ。雨の後に雫を垂らした蜘蛛の糸みたいで幻想的に感じる。俺はトゥイークの肉体に偏執しているのかもしれない。特に髪の毛に。
視線に気づいたトゥイークが俺の方を見た。
「……何見てるの、クレイグ。アッ! 僕の髪、何か付いてる?」
ペリドットの瞳をおびえたように細めて、俺の反応を伺っている。俺は黙って首を横に振った。
トゥイークはゲームのコントローラーを床に投げ出して、自分の体を見下ろした。そして両手を広げて、絆創膏の巻きついた指で何度も頭を触ったり頬を引っ張ったりして確認している。強迫症めいて見えた。
確かにこいつの髪は派手だけど、そんなに気にすることだろうか? 彼の髪質は生まれつきらしい。天然パーマだか縮れ毛だか知らないが、とにかく凄いことになっている。寝癖も酷く、こんなんじゃ登校前に鏡を見る気にもならないだろう。しかしトゥイークは若干正気を失っているので、毎朝寝癖もそのままによれたシャツを着て登校しているようだ。
俺は彼の髪の毛が好きだった。ふわふわのブロンドにつぶらな瞳を持った少年がきょろきょろと怯えて縮こまる様は、死にかけの虫みたいでかわいい。どこか小動物を思わせる……実際は凶暴な窮鼠だが。少年らしい顔立ちに陰鬱な影が落ちて不安げに肩をすくめるたび、俺の心はぎゅっと締め付けられ、庇護欲と加害欲求を同時にそそられるのだった。そしてそんなに怯えているのだから気が弱いのかと思えば実際は自我の塊で、暴言と暴力が無軌道に飛び出してくる。それも傍目に見てる分には最高にクールで面白い。いかしたカウンターパンチだと思う。
「僕、変じゃないよね」
不安そうにこちらを見上げるトゥイーク。広い草原で迷子になって困り果てる羊のよう。俺はもう一度首を振る。
「別におかしくない。お前の頭は可愛いと思う」
「ア!? かわっ……可愛いだって! やめてよ、そんなヤオイ同人誌みたいなこと言うの!」
トゥイークは顔を真っ赤にして俺を睨み、枕を抱きしめていた。どうやらお気に召さなかったようだ。まあこんな歯の浮くような台詞言われたら当然か。よく考えたらゲイっぽいかも知れない。
俺はベッドに寝転んで、頭の後ろで腕を組む。一睡もしていないからか思考が上手くまとまらなかった。
「髪の毛以外についてはどうとも言ってないだろ」
「そうだね。君の言う通りだよ。君はいつも正しいんだ。でも僕は可愛くなんかないし、それに君に言われると嫌なんだ。この時間が遠ざかっていくみたいですごく気持ち悪いし怖いよ……」
またパニックを起こしかけている。トゥイークは早口で答えてから泣きそうな顔になって、震えながら俯いた。彼はうつむいて床の一点を見つめていた。明らかに様子がおかしかった。震えていて顔色が悪い。まるで貧血で倒れた後のようだ。
「よしよし、トゥイーク。大丈夫だから落ち着けって。ほら深呼吸しろよ」
俺はベッドから起き上がって、彼を抱き寄せ背中をさすった。トゥイークは無防備に俺の手を受け入れている。その様子に得体の知れない幸福を感じた。きっと優越感とか征服感というやつだ。
「息を吸って、吐いて……」
トゥイークの胸に手を当てて深呼吸させる。パジャマに包まれた平坦なからだが吐息に合わせて上下した。
彼の体は少年らしい厚みがあって、肉が少なくて骨ばっていて、固い。けれどところどころ柔らかくて滑らかでとてもいい匂いがする。まるで硝子でできた人形を抱いているようだ。脆くて繊細、それでいて鋭利。きっとこのまま壊しても罪悪感を感じないだろう。
しばらくすると、トゥイークは落ち着きを取り戻した。俺の腕の中で大人しくしている。もう暴れたりしない。
抱き合ったまま見つめ合う。そしてどちらともなくキスをした。最初は軽く唇を重ねるだけ。それから舌を絡める深いものへと変わっていく。お互いの唾液が混ざり合い、水音を立てて、部屋の中に響いている。俺はその音を耳で聞きながら、頭の中では別のことを思っていた。
(ああ……またか……)
彼の情緒不安定について、最初は馬鹿正直に宥めていたが、最近は愛撫の真似事で黙らせている。いつまでも堂々巡りの慰めをしてやる必要がないし、気持ちいい。少なくとも俺は。
本当はそれだけじゃなくて、もっと複雑な感情が入り混じっているんだけど、言葉にするのは難しい。言うなればこれは一種の儀式のようなものだった。サウスパークという街に祝福された恋人としての義務。愛を確かめあう行為。
彼が俺に向ける感情は、他のクラスメイトに対するものとは全然違う。けれど俺は、この恋人が向けてくる依存と好意の境目がよく分からない。トゥイークは親にコーヒーを与えられすぎて明らかなカフェイン中毒に陥っているが、それでも毎日のようにコーヒーを飲んだり親の店でブレンドを手伝ったりしている。べつに彼が望んでいるわけではないのに、親が与えてくるから。今の状況はそれと似ていると思う。サウスパークに俺を押し付けられて、依存して、俺に縋っている。
俺は目を閉じ、彼の背に回した手に力を込めた。
「うわっ」
突然のことに驚いたのか、トゥイークが声を上げる。俺は構わず彼の体を強く引き寄せた。トゥイークの体がベッドに押し倒される形になり、彼の体重が俺にかかる。ベッドのスプリングが軋む音が聞こえた。
俺は仰向けに横たわったまま、彼に覆いかぶさられている。熱を持った重さが心地よい。
鼻先が触れそうなほど近い距離に顔があった。彼は驚いて目を見開いている。淡い緑色の瞳も好きだった。目の色にフェチズムがある訳じゃない。トゥイークのものだから好きになった。瞳の奥の深緑に吸い込まれるようにゆっくり瞼を閉じる。眠い。
半分寝落ちしかけている俺をトゥイークがつつく。
「クレイグ、クレイグ」
「どうかしたの」
「生きてる? 死んでない?」
「うんうん、生きてる生きてる」
トゥイークはカフェイン中毒だか幻覚病だかで、寝付きも悪ければ眠りも浅い。たまに起き出してはその瞳に俺を映し、安心してまた目を閉じる。一言で言えば電波。
「なんだか怖いんだ……目を開けたら君がいなくなってるんじゃないかって心配になるんだ」
「いなくなったりしないよ」
「不安なんだ! アッ!」
それだけ言って、トゥイークはまた自分の髪を引っ張って喚き始めた。
「クレイグがいなくなっちゃう夢を見ちゃうんだよ!」
「そりゃセンチメンタルだ、俺のキャラじゃない。言っとくけど俺は生きてるよ」
開かれたその目には、薄い涙の膜が張っていた。不安げにこちらを見上げるトゥイークを抱きしめる。軽く抱きしめ、俺の体に彼の頭を押し当てる。
「聞こえるだろ。俺の心臓の音」
「首の近くなら脈の音でしょ……」
トゥイークはぽつんと呟いた。けれど彼の不健康そうな双眸から微弱な不安の色は取り去られていた。彼は黙って身体を預ける。
「……クレイグ、このまんま寝ていい? そしたらきみの生きてる音が聞こえる……」
「いいよ」
気付かれないように彼の頬にキスを落とし、おやすみ、とひとりごちる。もうしばらくは目の前の少年に起こされることは無いだろう。
深く寝息を立てる顔を見つめ、パジャマに包まれた胸に頭を埋めた。素肌の感触、俗物的なぬくもりの隙間から微弱な音が聞こえた。心音だ。触れたら最後、掻き消えてしまうような頼りない心音。規則正しい命のリズム。パニックを起こして叫び散らした後だというのに、彼のそれは落ち着いている。こうして抱き合って目を閉じていると、お互いの存在の境界線が緩やかに溶け合って、やがてひとつの生き物になれる気がした。
朝日に包まれて他人の[[rb:腕 > かいな]]の中で心音を聞けば、彼は安眠を得られるのだろうか。いつも眠っている間どんな夢を見ているのだろう。職場から解雇を言い渡される夢? 家族が死ぬ夢?
――クレイグ、大丈夫? 定期的にそう訊かないと落ち着かない馬鹿。彼がその問いを向ける相手は、俺じゃなきゃいけないんだろうか。
そこまで考えて、俺は思考を打ち切った。これ以上考えたところで意味はない。
俺たち二人の間には、絆創膏で辛うじてつなぎとめられているような特別なきずながあって、それは間違いがない。いつか恋人の好意が依存に転じて重荷に感じたとしても、完全に自分が潰れてしまう前に俺は自分を守れるだろう。そしていつものクールさを取り戻したら、皮肉混じりにハニーと呼んでまたトゥイークのそばにいられる。俺は彼が見ているのと同じ地獄には行けないがそこから手を引くことはできる。それは多分サウスパークが求めている関係だ。そしてそれ以上に、トゥイークにとって必要なことで、俺のやりたいことでもあるんだと思う。
視界がだんだん暗くなってくる。床に転がったままのゲーム機を拾おうかと思ったが、べつに後でいいかと考え直した。トゥイークを起こしたくない。今は彼の安眠を守ってあげたかった。ただ一緒に眠っていたかった。
「おや。朝のコーヒーを届けに来たんだけど、お楽しみ中だったかな」
彼は俺たちを見下ろして、ねっとりした口調で言った。口は円弧に歪んでいるが目は据わっていて、感情が読み取れない。おちょくっている。
「昨晩は楽しかったかな」
「ええ、楽しかったですよ。ずっとゲームしてました」
毅然と返した。父親が期待しているようなことは本当になくて、ただ夜通しテレビゲームをしていただけだ。しかしなぜ今彼がここに居るんだ? トゥイークコーヒーは既に開店時間のはずなのに。この人はいつだってそうだ。何から何まで不気味すぎる。
「『一晩中ゲーム』かい? ワオ。あんまり夜更かしするのは良くないな」
冷やかすように言われた。返答を探して言い淀んでるうちに、トゥイークのほうが父親に向かって叫んだ。
「ち、違うよ! 僕たちはそういう関係じゃない!」
「じゃあどういう関係なんだ。恋人同士だろう? トゥイーク」
俺の代わりに食い気味に答えたのは父親の方だった。
「……それは……」
トゥイークが消え入りそうな声で呟いた。
俺は何も言わなかった。黙って二人のやりとりを聞いている。リチャードさんはいちおう彼氏の父親だし、息子や4バカとベクトルは違えど紛れもない変人タイプだからあえて喧嘩を売りたいとは思わない。
リチャードさんはそれ以上追求しなかったが、かわりに息子にコーヒーを飲むように言いつけた。そしてご丁寧にもマグカップ二つと個包装の茶菓子を置いて部屋を出ていった。しかしよく見たら、個包装の袋の正体はお菓子じゃなくてコンドームだった。
「クソだな」
「ほんとにね」
二人でベッドに寝そべっていたら、窓から差した朝日が黄金色の前髪を淡く照らしてきた。俺は立ち上がって窓辺に向かい、カーテンを少し開けてやった。それからトゥイークの方を振り返る。色素の薄い、傷んだ毛束は、光を通すときらきら光って見えるのだ。雨の後に雫を垂らした蜘蛛の糸みたいで幻想的に感じる。俺はトゥイークの肉体に偏執しているのかもしれない。特に髪の毛に。
視線に気づいたトゥイークが俺の方を見た。
「……何見てるの、クレイグ。アッ! 僕の髪、何か付いてる?」
ペリドットの瞳をおびえたように細めて、俺の反応を伺っている。俺は黙って首を横に振った。
トゥイークはゲームのコントローラーを床に投げ出して、自分の体を見下ろした。そして両手を広げて、絆創膏の巻きついた指で何度も頭を触ったり頬を引っ張ったりして確認している。強迫症めいて見えた。
確かにこいつの髪は派手だけど、そんなに気にすることだろうか? 彼の髪質は生まれつきらしい。天然パーマだか縮れ毛だか知らないが、とにかく凄いことになっている。寝癖も酷く、こんなんじゃ登校前に鏡を見る気にもならないだろう。しかしトゥイークは若干正気を失っているので、毎朝寝癖もそのままによれたシャツを着て登校しているようだ。
俺は彼の髪の毛が好きだった。ふわふわのブロンドにつぶらな瞳を持った少年がきょろきょろと怯えて縮こまる様は、死にかけの虫みたいでかわいい。どこか小動物を思わせる……実際は凶暴な窮鼠だが。少年らしい顔立ちに陰鬱な影が落ちて不安げに肩をすくめるたび、俺の心はぎゅっと締め付けられ、庇護欲と加害欲求を同時にそそられるのだった。そしてそんなに怯えているのだから気が弱いのかと思えば実際は自我の塊で、暴言と暴力が無軌道に飛び出してくる。それも傍目に見てる分には最高にクールで面白い。いかしたカウンターパンチだと思う。
「僕、変じゃないよね」
不安そうにこちらを見上げるトゥイーク。広い草原で迷子になって困り果てる羊のよう。俺はもう一度首を振る。
「別におかしくない。お前の頭は可愛いと思う」
「ア!? かわっ……可愛いだって! やめてよ、そんなヤオイ同人誌みたいなこと言うの!」
トゥイークは顔を真っ赤にして俺を睨み、枕を抱きしめていた。どうやらお気に召さなかったようだ。まあこんな歯の浮くような台詞言われたら当然か。よく考えたらゲイっぽいかも知れない。
俺はベッドに寝転んで、頭の後ろで腕を組む。一睡もしていないからか思考が上手くまとまらなかった。
「髪の毛以外についてはどうとも言ってないだろ」
「そうだね。君の言う通りだよ。君はいつも正しいんだ。でも僕は可愛くなんかないし、それに君に言われると嫌なんだ。この時間が遠ざかっていくみたいですごく気持ち悪いし怖いよ……」
またパニックを起こしかけている。トゥイークは早口で答えてから泣きそうな顔になって、震えながら俯いた。彼はうつむいて床の一点を見つめていた。明らかに様子がおかしかった。震えていて顔色が悪い。まるで貧血で倒れた後のようだ。
「よしよし、トゥイーク。大丈夫だから落ち着けって。ほら深呼吸しろよ」
俺はベッドから起き上がって、彼を抱き寄せ背中をさすった。トゥイークは無防備に俺の手を受け入れている。その様子に得体の知れない幸福を感じた。きっと優越感とか征服感というやつだ。
「息を吸って、吐いて……」
トゥイークの胸に手を当てて深呼吸させる。パジャマに包まれた平坦なからだが吐息に合わせて上下した。
彼の体は少年らしい厚みがあって、肉が少なくて骨ばっていて、固い。けれどところどころ柔らかくて滑らかでとてもいい匂いがする。まるで硝子でできた人形を抱いているようだ。脆くて繊細、それでいて鋭利。きっとこのまま壊しても罪悪感を感じないだろう。
しばらくすると、トゥイークは落ち着きを取り戻した。俺の腕の中で大人しくしている。もう暴れたりしない。
抱き合ったまま見つめ合う。そしてどちらともなくキスをした。最初は軽く唇を重ねるだけ。それから舌を絡める深いものへと変わっていく。お互いの唾液が混ざり合い、水音を立てて、部屋の中に響いている。俺はその音を耳で聞きながら、頭の中では別のことを思っていた。
(ああ……またか……)
彼の情緒不安定について、最初は馬鹿正直に宥めていたが、最近は愛撫の真似事で黙らせている。いつまでも堂々巡りの慰めをしてやる必要がないし、気持ちいい。少なくとも俺は。
本当はそれだけじゃなくて、もっと複雑な感情が入り混じっているんだけど、言葉にするのは難しい。言うなればこれは一種の儀式のようなものだった。サウスパークという街に祝福された恋人としての義務。愛を確かめあう行為。
彼が俺に向ける感情は、他のクラスメイトに対するものとは全然違う。けれど俺は、この恋人が向けてくる依存と好意の境目がよく分からない。トゥイークは親にコーヒーを与えられすぎて明らかなカフェイン中毒に陥っているが、それでも毎日のようにコーヒーを飲んだり親の店でブレンドを手伝ったりしている。べつに彼が望んでいるわけではないのに、親が与えてくるから。今の状況はそれと似ていると思う。サウスパークに俺を押し付けられて、依存して、俺に縋っている。
俺は目を閉じ、彼の背に回した手に力を込めた。
「うわっ」
突然のことに驚いたのか、トゥイークが声を上げる。俺は構わず彼の体を強く引き寄せた。トゥイークの体がベッドに押し倒される形になり、彼の体重が俺にかかる。ベッドのスプリングが軋む音が聞こえた。
俺は仰向けに横たわったまま、彼に覆いかぶさられている。熱を持った重さが心地よい。
鼻先が触れそうなほど近い距離に顔があった。彼は驚いて目を見開いている。淡い緑色の瞳も好きだった。目の色にフェチズムがある訳じゃない。トゥイークのものだから好きになった。瞳の奥の深緑に吸い込まれるようにゆっくり瞼を閉じる。眠い。
半分寝落ちしかけている俺をトゥイークがつつく。
「クレイグ、クレイグ」
「どうかしたの」
「生きてる? 死んでない?」
「うんうん、生きてる生きてる」
トゥイークはカフェイン中毒だか幻覚病だかで、寝付きも悪ければ眠りも浅い。たまに起き出してはその瞳に俺を映し、安心してまた目を閉じる。一言で言えば電波。
「なんだか怖いんだ……目を開けたら君がいなくなってるんじゃないかって心配になるんだ」
「いなくなったりしないよ」
「不安なんだ! アッ!」
それだけ言って、トゥイークはまた自分の髪を引っ張って喚き始めた。
「クレイグがいなくなっちゃう夢を見ちゃうんだよ!」
「そりゃセンチメンタルだ、俺のキャラじゃない。言っとくけど俺は生きてるよ」
開かれたその目には、薄い涙の膜が張っていた。不安げにこちらを見上げるトゥイークを抱きしめる。軽く抱きしめ、俺の体に彼の頭を押し当てる。
「聞こえるだろ。俺の心臓の音」
「首の近くなら脈の音でしょ……」
トゥイークはぽつんと呟いた。けれど彼の不健康そうな双眸から微弱な不安の色は取り去られていた。彼は黙って身体を預ける。
「……クレイグ、このまんま寝ていい? そしたらきみの生きてる音が聞こえる……」
「いいよ」
気付かれないように彼の頬にキスを落とし、おやすみ、とひとりごちる。もうしばらくは目の前の少年に起こされることは無いだろう。
深く寝息を立てる顔を見つめ、パジャマに包まれた胸に頭を埋めた。素肌の感触、俗物的なぬくもりの隙間から微弱な音が聞こえた。心音だ。触れたら最後、掻き消えてしまうような頼りない心音。規則正しい命のリズム。パニックを起こして叫び散らした後だというのに、彼のそれは落ち着いている。こうして抱き合って目を閉じていると、お互いの存在の境界線が緩やかに溶け合って、やがてひとつの生き物になれる気がした。
朝日に包まれて他人の[[rb:腕 > かいな]]の中で心音を聞けば、彼は安眠を得られるのだろうか。いつも眠っている間どんな夢を見ているのだろう。職場から解雇を言い渡される夢? 家族が死ぬ夢?
――クレイグ、大丈夫? 定期的にそう訊かないと落ち着かない馬鹿。彼がその問いを向ける相手は、俺じゃなきゃいけないんだろうか。
そこまで考えて、俺は思考を打ち切った。これ以上考えたところで意味はない。
俺たち二人の間には、絆創膏で辛うじてつなぎとめられているような特別なきずながあって、それは間違いがない。いつか恋人の好意が依存に転じて重荷に感じたとしても、完全に自分が潰れてしまう前に俺は自分を守れるだろう。そしていつものクールさを取り戻したら、皮肉混じりにハニーと呼んでまたトゥイークのそばにいられる。俺は彼が見ているのと同じ地獄には行けないがそこから手を引くことはできる。それは多分サウスパークが求めている関係だ。そしてそれ以上に、トゥイークにとって必要なことで、俺のやりたいことでもあるんだと思う。
視界がだんだん暗くなってくる。床に転がったままのゲーム機を拾おうかと思ったが、べつに後でいいかと考え直した。トゥイークを起こしたくない。今は彼の安眠を守ってあげたかった。ただ一緒に眠っていたかった。
1/2ページ