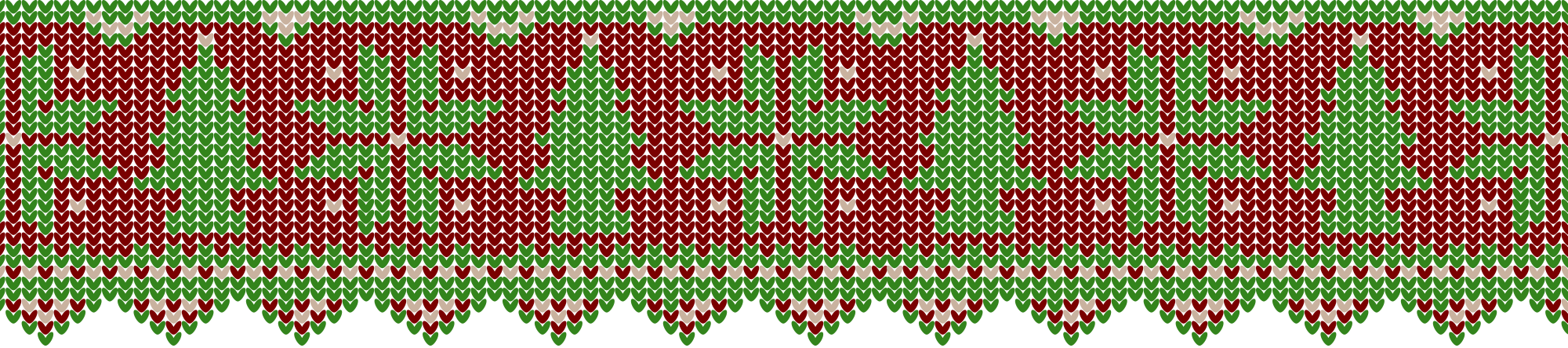📖⛲️SP
A wonder lasts but nine days.
くそったれ。隕石は前触れなしに落ちてくる。俺とトゥイークにおいても、それは同じだった。この町でヤオイアートが流行って、ひっでえイラストが街中に張り出され、俺たちは「恋人」にさせられた。最初、俺はこれでもかと反発していた。メトロセクシャルが流行ってるわけでもないのにゲイなんて冗談じゃない。それに噂の相手はトゥイーク・トゥイーク! やつは一時期スタンたちとつるんでいたがそのうち遊ぶのをやめたようで、俺と付き合うまでは一人でいることが多いようだった。ぶっちゃけあいつは一家まるごとイカレてる。だからこそ喧嘩の前までは俺もあいつを避けていた。だが、イカレたトゥイークに抗うより、イカレたサウスパークに抗う方がずっと難しいと俺は知っていた。そのうち怒る気力もなくなり、俺は街の望み通りトゥイークに手を差し出し、あっちも差し出された手を受け入れた。ドル札や賛辞と引き換えに。
で、それからしばらく経ったわけだが。
サウスパークの朝は冷える。いつもの帽子にすっぽり覆われてロッカーまで向かうと、そいつが立っているのが見えた、
「あ、おはようクレイグっ」
「グッモーニン」
気のない返事を返し、ロッカーから教科書を取り出す。トゥイークは、扉が閉まる音に怯えて小さく身をすくめた。
あの日……俺たちの「恋人記念日」からいくらか経って、俺は震える声にやっと慣れた。ただ厄介なのが、トゥイークはどこにいてもかなり目立つ。コーヒーが欲しい、アーッ、アーッ、アーッ! うんざりだ。
「おはよー」
間延びした声がして振り向いた。現れたのはクライド、それにトークン。クライドは右手でトゥイークの背中を軽く叩いた。
「おはよ、トゥイーク」
「アッ、クライド!」
やつはそのままロッカーにもたれかかった。ジュースをあけて、
「まいったよ。のど渇いたのにジュース持ってきてなくてさ? さっきカフェテリアそばの自販機で買ってきた」
何やってんだか。その自販機、またカートマンに細工されてるかもなとからかうと、やめてよ! とトゥイークが小さく呟いた。
トゥイークのやせた輪郭を視線で撫でる。掻きむしって乱れた短い前髪、怯えがちに細められたペリドットの瞳、絆創膏を何重にも巻いた人差し指。
仲間内で一二を争う問題児、コーヒー中毒、変なやつ(クリーピー)……俺の恋人。与えられた肩書きに関わらず俺とトゥイークの仲は相変わらずで、つまり状況はちっとも良くなっていない。それどころか、最近は「良く」というのがどういう状況を指すのかさえおぼつかなくなっている。俺とトゥイークがむつまじく見つめ合う絵画は壁から外されたが、それはいまでも納屋に眠っているのだ。トリシアはいつまでもそれをネタにして俺をからかうので何度中指を立てたか分からない。やめてほしい。
たまに思う。こんな状況でも、俺は正しい選択を選べているか。この関係は間違いだったのだろうか? 良い悪いの判断すらつかなくなるほど脳がふやけてんのか、渦巻く気持ちに、どうにも名前がつけられない。
そんな焦燥がつぎに襲ってきたのは昼前だった。最近は俺とトゥイーク、クライド、トークンで飯をとることが多い。いつもの様に学校で起きたゴタゴタを話していて、ふと自分の手指が汗ばんでいる気がして繋いだ手を振りほどきたくなった。隣を窺うと、トゥイークの緑の瞳はせわしなく周囲を見渡していた。
こいつは変わらず不安定だ。いっそ、安定してる。俺はひそかにため息を付いた。
「あらゲイのぼくちゃん」
「デートか?」
知らない声が掛かった。見上げると、体格のいい上級生が数人立ち塞がっていた。ムカつくニヤケ面で俺たちを見つめている。
こういうのも、今となっては珍しい事じゃなかった。ほかのカップルが冷やかしを受けるのと同じくらい、いや街ぐるみで「ゲイ」として扱われているぶんその数倍、こうして絡まれる。ただ、サウスパーク全体に俺たちが祝福されている分、今回のように悪意あるケースは稀だが。
クライドたちはこちらをそっと流し見して、くすくす笑って去っていった。あいつら……楽しんでやがる。
「あー、なんか用?」
あくまで気のないふりを装う。上級生達は続けた。
「お前らゲイなんだろ?」
「今からキスしてみろよ」
体がこわばる。そして、その言葉を聞くなり上級生に飛びかかろうとしたトゥイークを慌てて制した。パニックか短気かはこの際どうでも良い。
「堪えろトゥイーク。気持ちはわかるが、こいつら殴ったらめんどくさいことになるぞ」
「アッ、クレイグごめん……」
トゥイークは身をすくめた。
いくら小柄で貧弱そうだとはいえ、ボクシング経験のあるトゥイークから手を出せばあとあとこちらが不利になるだろう。ただでさえイカレポンチなトゥイークのことだ、タガが外れたら何をするか分からない。
「じゃあ従っておいたほうがいい?」
そういう訳じゃない、と言おうとしたが、俺の体は別の反応を返していた。
仕方ない。本来ならこんな見世物みたいなやり方ごめんだ。俺はゲイじゃないし。でもこれは、こんな状況を丸く収めるためなら、仕方ないじゃないか。
ぴりぴりした雰囲気の中トゥイークに目をやった。稲穂を思わせる柔らかいブロンドが揺れる。草原をそのまま刈り取ったような深い色の瞳、傷の多い半開きのくちびるを見て、じわり胸が熱くなる。一瞬が永遠にすら思えた。
今からキスをする。恋人と。
その陶酔感から俺を引き上げたのは、あの野太い怒声だった。
「おい、何してるお前ら!」
「やっべ! 校長だ!」
俺とトゥイークがろくに向き合わないうちに、わりいってきたのはPC校長だった。上級生は蜘蛛の子を散らすように逃げていく。
「どうした、クレイグ、トゥイーク。またケツの穴の問題か?」
「あー……いや、べつに」
校長が俺たちを引っ捕まえて聞いてくるが、もう経緯を説明するのもめんどうだった。それから遅れて、頬に熱が集まるのがわかった。
上級生に煽られたとはいえ何をしようとしてた、俺。いつもみたく中指立てて殴り返せばよかったろ。オーディエンスだってそれを期待してた。
なのにあんな態度、まるで俺が前々からトゥイークとキスしたがってたみたいだろ!
ふざけんなよ!
二
意思とはかかわりなく小刻みに震える手指を、ぼんやり眺めていた。そうするとママが、あなたコーヒーを切らしてるわよって教えてくれた。でもちがうんだ、ぼくはコーヒーが欲しいわけじゃない。少なくとも今は。
どうかしたのかって先に聞いてきたのはパパだった。
「じ、実は。アッ! 今日のランチタイム、上級生がキスしろって煽ってきたんだ。そこでクレイグはぼくにキスしようとしたんだけど、途中で校長先生に止められて、それから様子がおかしくなっちゃって。アッ!」
パパは僕の話を興味深そうに聞いていたけど、すぐに機嫌良い笑みになった。
「それはお前がいやらしいからだぞトゥイーク」
「アッ!? い、いやらしいってどういうこと! ぼく何もしてない!」
「ママの子供なんだからセクシーなのは当然さ。ダメだぞちゃんと気をつけなきゃ。男は好きな子の前では狼になるんだ、ねえママ?」
「あらやだうふふ」
ママは朗らかに笑う。
……じゃあ、クレイグの様子がおかしかったのって、僕のせいってこと?
三
俺とトゥイークが再会したのは、翌日の土曜だった。
「おはよ、クレイグ」
「今日は昼まで寝てた」
「そっか」
「クライドたちは?」
「靴屋の手伝いだって。トークンはデンバーまで家族とショッピング」
いいご身分でいらっしゃる。小さく悪態をつくと、トゥイークが困ったように笑った。
今日は何をしよう、テレビゲーム? と戯れに聞くと、トゥイークは待ってましたとばかりにカルト映画のDVDを差し出した。子供が見るには似つかわしくないグロテスクなパッケージに嗚咽する。流石だぜハニー。
映画を見ていると、ふと二人の手のひらが触れ合った。
もともと俺はこいつと付き合うつもりなんかなかった。予定通りじゃない人生で、予定調和のパニック映画を楽しんでいる。なんなんだよ、これ。……それに、なんだったんだよ、昨日の焦燥は。
映画そっちのけてトゥイークの横顔を見つめていると、ちょうど彼がこちらを見た。
「クレイグ」
切なげに呼ばれた名前。先を促すと、
「昨日の放課後、僕のこと避けてたの、僕のせいなんでしょ」
突拍子もない質問に思わずフリーズする。トゥイークは小刻みに震えながら、
「あれ、なんだったの。この前学校でキスしろって言われた時、ほら、君の……」
トゥイークはそのまま俯いてしまった。耳に熱が集まって真っ赤になっている。
俺のあの焦燥がバレてやがった。どう言い訳しようか思案していると、トゥイークは意を決したように切り出した。
「クレイグはぼくのこと好き?」
「はっ?」
あまりに唐突で声が裏返りそうになった。
「お前はもっとやれるって、クレイグに言われた時嬉しかった。好きだよ、君のことが。でも、この気持ちを恋や愛に絡めて語る決心がまだつかない。君の気持ちが、わからないから……」
トゥイークの指先が震えていた。でもその震えはきっと、いつものカフェイン中毒ではなく彼自身の感情から来るものだろう。
俺はそっとトゥイークを抱きしめる。腕の中で細い体が跳ねるさまは、どこかストライプを思わせた。
「……初めは運命のいたずらだったけど、今は違う」
うん。腕の中でトゥイークの囁きが聞こえる。
少し身を離して、彼の頬にそっと触れた。くちびるに、自分のそれを優しく重ねる。数秒熱を感じ、しかし終わってしまえばあっという間だった。
「……間違いじゃない。これが今の俺の本当の気持ち」
トゥイークは何も返さなかった。瞬きすらしなかった。きらきらと潤んだ大きな瞳に、俺を映り込ませている。照れくさいながら切り出した。
「ちょっとずつ恋人になろう」
■
朝食のチョコレートシリアルを食べながら、休み明けの学校について考えていた。土曜のキスから初めてトゥイークと顔を合わせることになる。つぎ上級生に会ったら、トゥイークの頬に軽いキスの一つでもくれて、これで満足かって笑ってやろう。
そんなことを考えていると、トリシアがやけに笑いながら問いかけてくる。
「ねえねえ、土曜はトゥイークと何したの。コウノトリ呼んだ?」
「うるさいぞトリシア」
中指を立てて応じると、妹も同じようにして返す。彼女は懲りずに、
「ね、お兄ちゃん。恋人のことは、なんて呼ぶんだっけ」
「なんてって、トゥイークだけど」
違うでしょ、トリシアがくすくすと抗議した。俺は若干口篭りながら、
「あー…………、……ハニー?」
「あ、お兄ちゃん照れてる」
うるさい。
くそったれ。隕石は前触れなしに落ちてくる。俺とトゥイークにおいても、それは同じだった。この町でヤオイアートが流行って、ひっでえイラストが街中に張り出され、俺たちは「恋人」にさせられた。最初、俺はこれでもかと反発していた。メトロセクシャルが流行ってるわけでもないのにゲイなんて冗談じゃない。それに噂の相手はトゥイーク・トゥイーク! やつは一時期スタンたちとつるんでいたがそのうち遊ぶのをやめたようで、俺と付き合うまでは一人でいることが多いようだった。ぶっちゃけあいつは一家まるごとイカレてる。だからこそ喧嘩の前までは俺もあいつを避けていた。だが、イカレたトゥイークに抗うより、イカレたサウスパークに抗う方がずっと難しいと俺は知っていた。そのうち怒る気力もなくなり、俺は街の望み通りトゥイークに手を差し出し、あっちも差し出された手を受け入れた。ドル札や賛辞と引き換えに。
で、それからしばらく経ったわけだが。
サウスパークの朝は冷える。いつもの帽子にすっぽり覆われてロッカーまで向かうと、そいつが立っているのが見えた、
「あ、おはようクレイグっ」
「グッモーニン」
気のない返事を返し、ロッカーから教科書を取り出す。トゥイークは、扉が閉まる音に怯えて小さく身をすくめた。
あの日……俺たちの「恋人記念日」からいくらか経って、俺は震える声にやっと慣れた。ただ厄介なのが、トゥイークはどこにいてもかなり目立つ。コーヒーが欲しい、アーッ、アーッ、アーッ! うんざりだ。
「おはよー」
間延びした声がして振り向いた。現れたのはクライド、それにトークン。クライドは右手でトゥイークの背中を軽く叩いた。
「おはよ、トゥイーク」
「アッ、クライド!」
やつはそのままロッカーにもたれかかった。ジュースをあけて、
「まいったよ。のど渇いたのにジュース持ってきてなくてさ? さっきカフェテリアそばの自販機で買ってきた」
何やってんだか。その自販機、またカートマンに細工されてるかもなとからかうと、やめてよ! とトゥイークが小さく呟いた。
トゥイークのやせた輪郭を視線で撫でる。掻きむしって乱れた短い前髪、怯えがちに細められたペリドットの瞳、絆創膏を何重にも巻いた人差し指。
仲間内で一二を争う問題児、コーヒー中毒、変なやつ(クリーピー)……俺の恋人。与えられた肩書きに関わらず俺とトゥイークの仲は相変わらずで、つまり状況はちっとも良くなっていない。それどころか、最近は「良く」というのがどういう状況を指すのかさえおぼつかなくなっている。俺とトゥイークがむつまじく見つめ合う絵画は壁から外されたが、それはいまでも納屋に眠っているのだ。トリシアはいつまでもそれをネタにして俺をからかうので何度中指を立てたか分からない。やめてほしい。
たまに思う。こんな状況でも、俺は正しい選択を選べているか。この関係は間違いだったのだろうか? 良い悪いの判断すらつかなくなるほど脳がふやけてんのか、渦巻く気持ちに、どうにも名前がつけられない。
そんな焦燥がつぎに襲ってきたのは昼前だった。最近は俺とトゥイーク、クライド、トークンで飯をとることが多い。いつもの様に学校で起きたゴタゴタを話していて、ふと自分の手指が汗ばんでいる気がして繋いだ手を振りほどきたくなった。隣を窺うと、トゥイークの緑の瞳はせわしなく周囲を見渡していた。
こいつは変わらず不安定だ。いっそ、安定してる。俺はひそかにため息を付いた。
「あらゲイのぼくちゃん」
「デートか?」
知らない声が掛かった。見上げると、体格のいい上級生が数人立ち塞がっていた。ムカつくニヤケ面で俺たちを見つめている。
こういうのも、今となっては珍しい事じゃなかった。ほかのカップルが冷やかしを受けるのと同じくらい、いや街ぐるみで「ゲイ」として扱われているぶんその数倍、こうして絡まれる。ただ、サウスパーク全体に俺たちが祝福されている分、今回のように悪意あるケースは稀だが。
クライドたちはこちらをそっと流し見して、くすくす笑って去っていった。あいつら……楽しんでやがる。
「あー、なんか用?」
あくまで気のないふりを装う。上級生達は続けた。
「お前らゲイなんだろ?」
「今からキスしてみろよ」
体がこわばる。そして、その言葉を聞くなり上級生に飛びかかろうとしたトゥイークを慌てて制した。パニックか短気かはこの際どうでも良い。
「堪えろトゥイーク。気持ちはわかるが、こいつら殴ったらめんどくさいことになるぞ」
「アッ、クレイグごめん……」
トゥイークは身をすくめた。
いくら小柄で貧弱そうだとはいえ、ボクシング経験のあるトゥイークから手を出せばあとあとこちらが不利になるだろう。ただでさえイカレポンチなトゥイークのことだ、タガが外れたら何をするか分からない。
「じゃあ従っておいたほうがいい?」
そういう訳じゃない、と言おうとしたが、俺の体は別の反応を返していた。
仕方ない。本来ならこんな見世物みたいなやり方ごめんだ。俺はゲイじゃないし。でもこれは、こんな状況を丸く収めるためなら、仕方ないじゃないか。
ぴりぴりした雰囲気の中トゥイークに目をやった。稲穂を思わせる柔らかいブロンドが揺れる。草原をそのまま刈り取ったような深い色の瞳、傷の多い半開きのくちびるを見て、じわり胸が熱くなる。一瞬が永遠にすら思えた。
今からキスをする。恋人と。
その陶酔感から俺を引き上げたのは、あの野太い怒声だった。
「おい、何してるお前ら!」
「やっべ! 校長だ!」
俺とトゥイークがろくに向き合わないうちに、わりいってきたのはPC校長だった。上級生は蜘蛛の子を散らすように逃げていく。
「どうした、クレイグ、トゥイーク。またケツの穴の問題か?」
「あー……いや、べつに」
校長が俺たちを引っ捕まえて聞いてくるが、もう経緯を説明するのもめんどうだった。それから遅れて、頬に熱が集まるのがわかった。
上級生に煽られたとはいえ何をしようとしてた、俺。いつもみたく中指立てて殴り返せばよかったろ。オーディエンスだってそれを期待してた。
なのにあんな態度、まるで俺が前々からトゥイークとキスしたがってたみたいだろ!
ふざけんなよ!
二
意思とはかかわりなく小刻みに震える手指を、ぼんやり眺めていた。そうするとママが、あなたコーヒーを切らしてるわよって教えてくれた。でもちがうんだ、ぼくはコーヒーが欲しいわけじゃない。少なくとも今は。
どうかしたのかって先に聞いてきたのはパパだった。
「じ、実は。アッ! 今日のランチタイム、上級生がキスしろって煽ってきたんだ。そこでクレイグはぼくにキスしようとしたんだけど、途中で校長先生に止められて、それから様子がおかしくなっちゃって。アッ!」
パパは僕の話を興味深そうに聞いていたけど、すぐに機嫌良い笑みになった。
「それはお前がいやらしいからだぞトゥイーク」
「アッ!? い、いやらしいってどういうこと! ぼく何もしてない!」
「ママの子供なんだからセクシーなのは当然さ。ダメだぞちゃんと気をつけなきゃ。男は好きな子の前では狼になるんだ、ねえママ?」
「あらやだうふふ」
ママは朗らかに笑う。
……じゃあ、クレイグの様子がおかしかったのって、僕のせいってこと?
三
俺とトゥイークが再会したのは、翌日の土曜だった。
「おはよ、クレイグ」
「今日は昼まで寝てた」
「そっか」
「クライドたちは?」
「靴屋の手伝いだって。トークンはデンバーまで家族とショッピング」
いいご身分でいらっしゃる。小さく悪態をつくと、トゥイークが困ったように笑った。
今日は何をしよう、テレビゲーム? と戯れに聞くと、トゥイークは待ってましたとばかりにカルト映画のDVDを差し出した。子供が見るには似つかわしくないグロテスクなパッケージに嗚咽する。流石だぜハニー。
映画を見ていると、ふと二人の手のひらが触れ合った。
もともと俺はこいつと付き合うつもりなんかなかった。予定通りじゃない人生で、予定調和のパニック映画を楽しんでいる。なんなんだよ、これ。……それに、なんだったんだよ、昨日の焦燥は。
映画そっちのけてトゥイークの横顔を見つめていると、ちょうど彼がこちらを見た。
「クレイグ」
切なげに呼ばれた名前。先を促すと、
「昨日の放課後、僕のこと避けてたの、僕のせいなんでしょ」
突拍子もない質問に思わずフリーズする。トゥイークは小刻みに震えながら、
「あれ、なんだったの。この前学校でキスしろって言われた時、ほら、君の……」
トゥイークはそのまま俯いてしまった。耳に熱が集まって真っ赤になっている。
俺のあの焦燥がバレてやがった。どう言い訳しようか思案していると、トゥイークは意を決したように切り出した。
「クレイグはぼくのこと好き?」
「はっ?」
あまりに唐突で声が裏返りそうになった。
「お前はもっとやれるって、クレイグに言われた時嬉しかった。好きだよ、君のことが。でも、この気持ちを恋や愛に絡めて語る決心がまだつかない。君の気持ちが、わからないから……」
トゥイークの指先が震えていた。でもその震えはきっと、いつものカフェイン中毒ではなく彼自身の感情から来るものだろう。
俺はそっとトゥイークを抱きしめる。腕の中で細い体が跳ねるさまは、どこかストライプを思わせた。
「……初めは運命のいたずらだったけど、今は違う」
うん。腕の中でトゥイークの囁きが聞こえる。
少し身を離して、彼の頬にそっと触れた。くちびるに、自分のそれを優しく重ねる。数秒熱を感じ、しかし終わってしまえばあっという間だった。
「……間違いじゃない。これが今の俺の本当の気持ち」
トゥイークは何も返さなかった。瞬きすらしなかった。きらきらと潤んだ大きな瞳に、俺を映り込ませている。照れくさいながら切り出した。
「ちょっとずつ恋人になろう」
■
朝食のチョコレートシリアルを食べながら、休み明けの学校について考えていた。土曜のキスから初めてトゥイークと顔を合わせることになる。つぎ上級生に会ったら、トゥイークの頬に軽いキスの一つでもくれて、これで満足かって笑ってやろう。
そんなことを考えていると、トリシアがやけに笑いながら問いかけてくる。
「ねえねえ、土曜はトゥイークと何したの。コウノトリ呼んだ?」
「うるさいぞトリシア」
中指を立てて応じると、妹も同じようにして返す。彼女は懲りずに、
「ね、お兄ちゃん。恋人のことは、なんて呼ぶんだっけ」
「なんてって、トゥイークだけど」
違うでしょ、トリシアがくすくすと抗議した。俺は若干口篭りながら、
「あー…………、……ハニー?」
「あ、お兄ちゃん照れてる」
うるさい。
2/2ページ