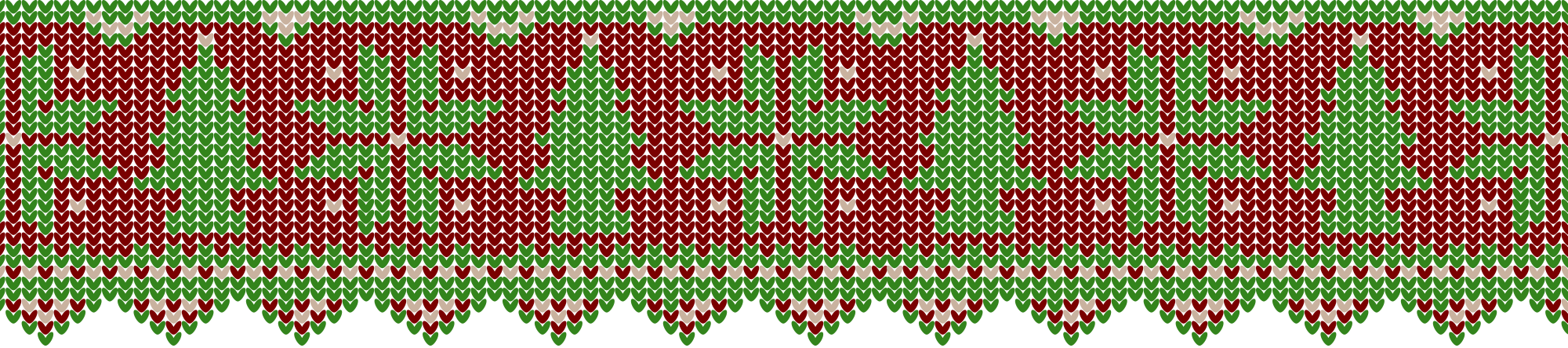📖Log
メルズ・ドライブインは、ネオンの灯りとロックのナンバーで賑わっている。ジョン・ミルナーは愛車の黄色いデュース・クーペに寄りかかり、タバコをくわえながら、通りを鋭い目つきで眺めていた。
彼にしては珍しいことに、レースの気分ではなかった。かといって、スティーブやテリーに会う気にもならない。夏の終わり特有のやや倦怠な雰囲気が、彼の逞しい肉体を柔らかく包み込んでいた。
おもむろに足音が聞こえる。
「ねえ、お兄さん! あたしお腹すいたんだけど!」
そんな風情を完全に無視して歩み寄ってきたのはキャロル・モリソン。淡い茶髪のポニーテールが風に揺れ、生意気な笑顔が向けられる。ショートパンツからは、色気のかけらもない細い脚がのぞいている。年齢相応に小柄な彼女は腕を組んで、わざとらしく唇をとがらせた。
ジョンはタバコを弾き、煙を吐き出しながら彼女を見やる。
「またお前か。姉さんは何してる」
「フォードのクーペ見つけたから乗ってきなって」
あきれた。どうやら『ウザい妹のお守り役』として認識されたらしい。これではおちおちレースもできない。ズベ公、今度会ったら言って聞かせないと。
キャロルは目を輝かせて、ジョンににじり寄った。
「ねっ、何か甘いものが欲しいなあ……バナナスプリットとかさ!」
うるせえガキだ。ジョンはポケットからくしゃくしゃのドル札を取り出した。適当に腹一杯にさせて、送り届ければいい。
ドライブインのカウンターに腰を下ろすと、ブダが腰をくねらせてスケートを滑らせてきた。ブダは、そのぱっちりした瞳で、馴染みの男と連れの子供を見比べる。
「ご注文は? ジョンと……えっと」
「キャロルよ! わたしジョンのステディなの」
「従妹のお守りだ」
「ジョンのバカ! それ止めてっていったでしょ!」
「はいはい。こいつにバナナスプリット一つ。俺は……」
「コークフロートにしなよ!」
「分かったわ。バナナスプリットとコークフロートね」
ブダは子連れのジョンに詮索もせず微笑みかけ、短く返して厨房へ戻って行った。
しばらくすると、巨大なガラスボウルに盛られたバナナスプリットが運ばれてきた。バニラとチョコレートのアイスに、バナナが添えられて、生クリームとチェリーが山盛りだ。ついでにコークフロートも。
キャロルは銀色のスプーンを手に持つなり、目を丸くして声を上げた。
「何だよ、その顔。ガキはバナナスプリットも始めてか」
「だってこんな大きいの見たことないもん。ありがとね!」
キャロルは無邪気に笑い、さっそくアイスにスプーンを突っ込んだ。クリームが口の周りにつくのもお構いなしで幸せそうに頬張る。小さな口の周りは白と茶色の遊園地と化していた。
ジョンは肘をついて、呆れたような、それでいてどこか楽しそうな目でそれを見つめていた。
「なあ、お前、食うならもうちょっと上品に食えよ。顔がベタベタじゃねえか」
ジョンはため息をつきながらそう言った。
タバコを灰皿に押し付けて火を消す。紙ナプキンを取り、化粧もしていないつややかな頬に押し付けた。雑に拭うその手つきに、キャロルは小さく唸りながら身をよじった。
「やだ、ジョン。あたし自分でできるよ!」
彼女はハンカチを奪い取ると、自分の顔をゴシゴシ拭いた。でもその仕草がまた子供っぽい。
「お前、ほんとガキだな」
「あたし、もう14になるもん」
キャロルは頬を膨らませて反論しつつ、スプーンを手に持ったままジョンにぐいっと近づいた。
「それに、ジョンだって大人だけど大人じゃないでしょ? 車と女の子とロックンロールしか頭にないんだから!」
「生意気言うなよ。チビ」
生意気なガキの癖に、こんなところはちゃんと図星を突いてくる。
ジョンはキャロルの頭を軽く小突き、ポニーテールを少し乱した。やめてよと抗議する言葉とは裏腹に、笑顔のままだ。
カウンターの向こうから、ブダが新しい客の注文を取る声が聞こえる。店内を彩るロックの音。
少女はふとスプーンを止め、そして、向かいに座る男を見上げて、ちょっと照れたように切り出した。
「ねえ、ジョン。あたし、今日ずっと一緒にいて楽しいよ。バナナスプリット奢ってくれたのも嬉しいし……あたしのこと、ちゃんと見ててくれるんだなって……」
キャロルは微笑んで、バナナスプリットの最後の一口をスプーンですくい、口元に突き出した。
「はい、あーん! 奢ってくれたお礼!」
ジョンは言われるまま渋々口を開けた。アイスとクリームの冷たさと甘ったるさが口に広がる。糖分過多。いささか甘すぎた。慣れないことは、するもんじゃない。
バナナスプリットを食べ終えたキャロルは、満足そうにスプーンを舐めながらジョンを見上げた。
「ねえ。あたし、もっと一緒にいたいな」
「勘弁してくれよ」
ジョンは低く呟いたが、声にはいつもの威勢がない。彼女はやはりそんな様子を見逃さず、自信たっぷりに笑ってさらに近づいた。
「ジョンってさ、かっこいいし車もすごいし、みんなにモテるでしょ? でもあたしのことちゃんと見てくれるの、嬉しいんだから。バナナスプリット奢ってくれたのだって、あたしが特別だからだよね?」
「お前……調子に乗るなよ」
そう言いながらも、子どもの頭を軽く叩く手は、妙に優しい。彼女はその手を掴んで、自分の頬に押し当てた。
「あたし、ジョンと一緒だと安心するんだもん。ねえ、このままドライブ連れてってよ。またクーペに乗せて!」
子供らしい純真な目を輝かせて、ジョンをまっすぐに見上げる。その瞳に映る自分を見て、ジョンは完全に参ってしまう。
どうせ、こいつを送り届けなければならないのだから、同じか。
「乗せてやるから、そんな目で俺を見るな」
「やったー!」
立ち上がり、デュース・クーペの方へ歩き出した。一歩遅れてキャロルが跳ねるように後をついてきて、助手席に飛び乗ると、シートにちょこんと座って彼を見上げた。
愛車のドアを開け、乗れよと顎で合図する。キャロルはやっとあたしの言うこと聞いてくれた! とばかりに得意げに助手席に飛び乗り、シートに座るなりジョンに絡み始めた。
「ねえ、ジョン! あたしとドライブなんて、最高の夜じゃん! ほらっ早くエンジンかけてよ。あたしのことちゃんと楽しませてよね!」
「うちの車は大声禁止だ」
ドライブインの喧騒を貫く、思わず耳を塞ぎたくなるようなキンキン声。手元でキーを回しながら、太い眉をひそめた。
車がハイウェイに滑り出すと、キャロルは窓から身を乗り出してはしゃいだ。
「風気持ちいいー!」
「落ちんなよ、チビ」
ハンドルを軽く握る手に力がこもる。柔らかい茶髪が風に揺れて、あどけない笑い声が夜空に溶けていった。
それからキャロルは助手席で膝立ちになって、ジョンに顔を近づけた。
「ねえ、ジョン。今夜のあたしのこと、どう思う? 可愛いよね? 絶対可愛いって言えよ!」
「可愛いってよりうるさいガキだ。座ってろ、危ねえから」
ジョンは片手でキャロルの首元を引っ掴み、強引にシートに戻した。キャロルは拗ねたように唇をとがらせて連呼する。
「意地悪! 意地悪、意地悪、意地悪!」
「可愛い」
「やったー!」
そんな単純なやり取りが続く中、車はスピードを落とし、人気のない道に入った。夜空には星が瞬き、遠くの町の灯りが小さく見える。ジョンはタバコに火をつけ、窓から煙を吐き出した。
「何? 急に徐行して」
キャロルが不思議そうに聞くと、ジョンはふっと彼女を見た。
「夜道に怖気付いたの?」
「なわけあるか」
「じゃあどうしたの」
「さっきから騒いでばっかで疲れねえのか? ちょっと黙って、見てみろよ」
彼の声は、いつもと違って低く落ち着いている。彼は細く華奢な肩にそっと手を置いて、星空の方を指さしてみせた。
「ほら。綺麗だろ」
一瞬の戸惑いののち、キャロルは急に静かになった。大人の無骨な手が肩にあたって、その体温にどぎまぎしたのか、彼女の頬が少し赤くなる。先ほどまでの勢いが一瞬でしぼんで、目を丸くしてジョンを見上げた。
「ジョンって……こういうとこ連れてきてくれるんだね。なんか、ロマンティック……じゃん……デートみたいで……」
珍しくしおらしい。
「お前がガキっぽく騒ぐからだろ。大人しくしてりゃ、俺だって優しくするさ」
彼はそう言って、キャロルの頭を軽く撫でた。乱暴に髪を乱す仕草が男前だ。キャロルは言葉に詰まり、顔を真っ赤にして俯く……と思われた。
次の瞬間、彼女はハッと顔を上げて、叩いて笑い出す。
「や、やっぱりジョン、あたしのこと好きなんだー!」
調子を取り戻すのが早すぎる。ジョンはタバコを取り落としそうになりながら、呆れ顔を作った。しかしその表情はどこか弾んでもいた。
慣れないことはするもんじゃない。けれどジョンは、この子供っぽい甘さを存外心地よく感じてしまっていた。二つに分かたれたバナナの間の、甘すぎるクリームのような。
タバコを始末し、ハンドルに手をかける。
さあ、ドライブを続けよう。夜はこれからだ。
(2025/03/08)
彼にしては珍しいことに、レースの気分ではなかった。かといって、スティーブやテリーに会う気にもならない。夏の終わり特有のやや倦怠な雰囲気が、彼の逞しい肉体を柔らかく包み込んでいた。
おもむろに足音が聞こえる。
「ねえ、お兄さん! あたしお腹すいたんだけど!」
そんな風情を完全に無視して歩み寄ってきたのはキャロル・モリソン。淡い茶髪のポニーテールが風に揺れ、生意気な笑顔が向けられる。ショートパンツからは、色気のかけらもない細い脚がのぞいている。年齢相応に小柄な彼女は腕を組んで、わざとらしく唇をとがらせた。
ジョンはタバコを弾き、煙を吐き出しながら彼女を見やる。
「またお前か。姉さんは何してる」
「フォードのクーペ見つけたから乗ってきなって」
あきれた。どうやら『ウザい妹のお守り役』として認識されたらしい。これではおちおちレースもできない。ズベ公、今度会ったら言って聞かせないと。
キャロルは目を輝かせて、ジョンににじり寄った。
「ねっ、何か甘いものが欲しいなあ……バナナスプリットとかさ!」
うるせえガキだ。ジョンはポケットからくしゃくしゃのドル札を取り出した。適当に腹一杯にさせて、送り届ければいい。
ドライブインのカウンターに腰を下ろすと、ブダが腰をくねらせてスケートを滑らせてきた。ブダは、そのぱっちりした瞳で、馴染みの男と連れの子供を見比べる。
「ご注文は? ジョンと……えっと」
「キャロルよ! わたしジョンのステディなの」
「従妹のお守りだ」
「ジョンのバカ! それ止めてっていったでしょ!」
「はいはい。こいつにバナナスプリット一つ。俺は……」
「コークフロートにしなよ!」
「分かったわ。バナナスプリットとコークフロートね」
ブダは子連れのジョンに詮索もせず微笑みかけ、短く返して厨房へ戻って行った。
しばらくすると、巨大なガラスボウルに盛られたバナナスプリットが運ばれてきた。バニラとチョコレートのアイスに、バナナが添えられて、生クリームとチェリーが山盛りだ。ついでにコークフロートも。
キャロルは銀色のスプーンを手に持つなり、目を丸くして声を上げた。
「何だよ、その顔。ガキはバナナスプリットも始めてか」
「だってこんな大きいの見たことないもん。ありがとね!」
キャロルは無邪気に笑い、さっそくアイスにスプーンを突っ込んだ。クリームが口の周りにつくのもお構いなしで幸せそうに頬張る。小さな口の周りは白と茶色の遊園地と化していた。
ジョンは肘をついて、呆れたような、それでいてどこか楽しそうな目でそれを見つめていた。
「なあ、お前、食うならもうちょっと上品に食えよ。顔がベタベタじゃねえか」
ジョンはため息をつきながらそう言った。
タバコを灰皿に押し付けて火を消す。紙ナプキンを取り、化粧もしていないつややかな頬に押し付けた。雑に拭うその手つきに、キャロルは小さく唸りながら身をよじった。
「やだ、ジョン。あたし自分でできるよ!」
彼女はハンカチを奪い取ると、自分の顔をゴシゴシ拭いた。でもその仕草がまた子供っぽい。
「お前、ほんとガキだな」
「あたし、もう14になるもん」
キャロルは頬を膨らませて反論しつつ、スプーンを手に持ったままジョンにぐいっと近づいた。
「それに、ジョンだって大人だけど大人じゃないでしょ? 車と女の子とロックンロールしか頭にないんだから!」
「生意気言うなよ。チビ」
生意気なガキの癖に、こんなところはちゃんと図星を突いてくる。
ジョンはキャロルの頭を軽く小突き、ポニーテールを少し乱した。やめてよと抗議する言葉とは裏腹に、笑顔のままだ。
カウンターの向こうから、ブダが新しい客の注文を取る声が聞こえる。店内を彩るロックの音。
少女はふとスプーンを止め、そして、向かいに座る男を見上げて、ちょっと照れたように切り出した。
「ねえ、ジョン。あたし、今日ずっと一緒にいて楽しいよ。バナナスプリット奢ってくれたのも嬉しいし……あたしのこと、ちゃんと見ててくれるんだなって……」
キャロルは微笑んで、バナナスプリットの最後の一口をスプーンですくい、口元に突き出した。
「はい、あーん! 奢ってくれたお礼!」
ジョンは言われるまま渋々口を開けた。アイスとクリームの冷たさと甘ったるさが口に広がる。糖分過多。いささか甘すぎた。慣れないことは、するもんじゃない。
バナナスプリットを食べ終えたキャロルは、満足そうにスプーンを舐めながらジョンを見上げた。
「ねえ。あたし、もっと一緒にいたいな」
「勘弁してくれよ」
ジョンは低く呟いたが、声にはいつもの威勢がない。彼女はやはりそんな様子を見逃さず、自信たっぷりに笑ってさらに近づいた。
「ジョンってさ、かっこいいし車もすごいし、みんなにモテるでしょ? でもあたしのことちゃんと見てくれるの、嬉しいんだから。バナナスプリット奢ってくれたのだって、あたしが特別だからだよね?」
「お前……調子に乗るなよ」
そう言いながらも、子どもの頭を軽く叩く手は、妙に優しい。彼女はその手を掴んで、自分の頬に押し当てた。
「あたし、ジョンと一緒だと安心するんだもん。ねえ、このままドライブ連れてってよ。またクーペに乗せて!」
子供らしい純真な目を輝かせて、ジョンをまっすぐに見上げる。その瞳に映る自分を見て、ジョンは完全に参ってしまう。
どうせ、こいつを送り届けなければならないのだから、同じか。
「乗せてやるから、そんな目で俺を見るな」
「やったー!」
立ち上がり、デュース・クーペの方へ歩き出した。一歩遅れてキャロルが跳ねるように後をついてきて、助手席に飛び乗ると、シートにちょこんと座って彼を見上げた。
愛車のドアを開け、乗れよと顎で合図する。キャロルはやっとあたしの言うこと聞いてくれた! とばかりに得意げに助手席に飛び乗り、シートに座るなりジョンに絡み始めた。
「ねえ、ジョン! あたしとドライブなんて、最高の夜じゃん! ほらっ早くエンジンかけてよ。あたしのことちゃんと楽しませてよね!」
「うちの車は大声禁止だ」
ドライブインの喧騒を貫く、思わず耳を塞ぎたくなるようなキンキン声。手元でキーを回しながら、太い眉をひそめた。
車がハイウェイに滑り出すと、キャロルは窓から身を乗り出してはしゃいだ。
「風気持ちいいー!」
「落ちんなよ、チビ」
ハンドルを軽く握る手に力がこもる。柔らかい茶髪が風に揺れて、あどけない笑い声が夜空に溶けていった。
それからキャロルは助手席で膝立ちになって、ジョンに顔を近づけた。
「ねえ、ジョン。今夜のあたしのこと、どう思う? 可愛いよね? 絶対可愛いって言えよ!」
「可愛いってよりうるさいガキだ。座ってろ、危ねえから」
ジョンは片手でキャロルの首元を引っ掴み、強引にシートに戻した。キャロルは拗ねたように唇をとがらせて連呼する。
「意地悪! 意地悪、意地悪、意地悪!」
「可愛い」
「やったー!」
そんな単純なやり取りが続く中、車はスピードを落とし、人気のない道に入った。夜空には星が瞬き、遠くの町の灯りが小さく見える。ジョンはタバコに火をつけ、窓から煙を吐き出した。
「何? 急に徐行して」
キャロルが不思議そうに聞くと、ジョンはふっと彼女を見た。
「夜道に怖気付いたの?」
「なわけあるか」
「じゃあどうしたの」
「さっきから騒いでばっかで疲れねえのか? ちょっと黙って、見てみろよ」
彼の声は、いつもと違って低く落ち着いている。彼は細く華奢な肩にそっと手を置いて、星空の方を指さしてみせた。
「ほら。綺麗だろ」
一瞬の戸惑いののち、キャロルは急に静かになった。大人の無骨な手が肩にあたって、その体温にどぎまぎしたのか、彼女の頬が少し赤くなる。先ほどまでの勢いが一瞬でしぼんで、目を丸くしてジョンを見上げた。
「ジョンって……こういうとこ連れてきてくれるんだね。なんか、ロマンティック……じゃん……デートみたいで……」
珍しくしおらしい。
「お前がガキっぽく騒ぐからだろ。大人しくしてりゃ、俺だって優しくするさ」
彼はそう言って、キャロルの頭を軽く撫でた。乱暴に髪を乱す仕草が男前だ。キャロルは言葉に詰まり、顔を真っ赤にして俯く……と思われた。
次の瞬間、彼女はハッと顔を上げて、叩いて笑い出す。
「や、やっぱりジョン、あたしのこと好きなんだー!」
調子を取り戻すのが早すぎる。ジョンはタバコを取り落としそうになりながら、呆れ顔を作った。しかしその表情はどこか弾んでもいた。
慣れないことはするもんじゃない。けれどジョンは、この子供っぽい甘さを存外心地よく感じてしまっていた。二つに分かたれたバナナの間の、甘すぎるクリームのような。
タバコを始末し、ハンドルに手をかける。
さあ、ドライブを続けよう。夜はこれからだ。
(2025/03/08)
1/1ページ