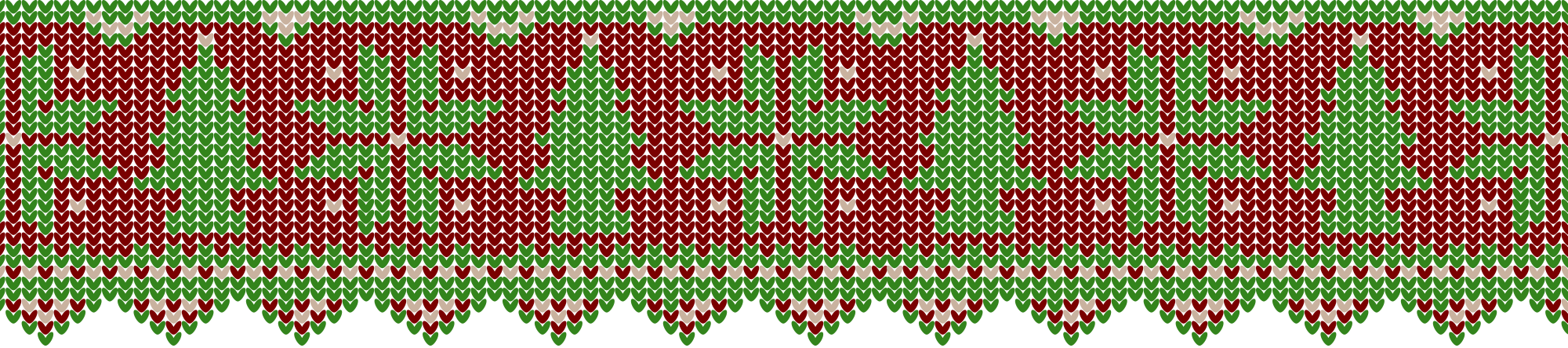📖🏇Uma
空はまだらな曇天で、庭はホワイトチョコレートをかけたみたいに雪が積もっている。教室の窓ガラスは寒暖差で白く曇っていた。トレセン学園にも冬が訪れようとしていた。
クラシック路線や主要なレースが終わり、既に次シーズンへ向けての調整に入っている子も少なくはない。そんなウマ娘達はクリスマスやお正月にそれぞれ胸を高鳴らせているみたいだった。そしてメイショウドトウもその一人で、朋友テイエムオペラオー主催のパーティを手伝うことになったのだ。去年の年末はディナーショーを計画していたが、今年はお偉いさんを集めて特別なパーティを開くらしい。
朝礼前の一番冷え込む時間、メイショウドトウはトレーナー室でクリスマスパーティの準備を手伝っていた。机にはすべすべしたテーブルクロスを敷く。大きなモミの木の枝に色とりどりのリボンを巻き付け、部屋中に電飾を飾りつけると、部屋は繁華街のように明るくなった。
それから段ボール箱を開いてツリー用のオーナメントを取り出した。兵隊やサンタの人形、鈴。小さいながらに精緻な装飾が施されていて、色とりどりで煌びやかだ。軽く払ってから水を含ませた柔らかい布で拭いてやると、埃っぽい匂いはすっかり消えて、かわりに木の香ばしい匂いが鼻腔を満たす。大振りなツリーの枝にひとつひとつ吊り下げてやるのだ。ドジしないように、慎重に。
――こういうのって楽しいですぅ。去年のパーティだって、オペラオーさんは相変わらず元気いっぱいでまぶしくて……。
意図せず口元が弛む。本当に幸せな時間だった。でも、この時間がいつまでも続くわけではないことを、彼女は心のどこかで知っている。いつか終わりが来ることは分かっていたけれど、まだもう少しだけこのままでいたいと願うのはいけないことだろうか。
――だって、私は……。
オーナメントを飾る手が止まる。その先は考えられない。と言うよりむしろ考えたくなかった。
ツリーを半分ほど飾り付けた頃に、部屋の外から足音が聞こえた。誰かが立ち止まる気配。そしてドアを開けたのは、テイエムオペラオーのトレーナーだった。ドトウの姿を身留めて気さくに微笑む。
「お、ドトウじゃないか。今年も手伝ってくれるのか?」
「は、はいぃ……私は今年のパーティには参加しないですけど、準備くらいでもお力になれたらって」
メイショウドトウは視線を落としてもじもじする。オペラオーの力になりたいのは本当。ただそれと同じくらい、憧れの人のそばに居る口実が欲しかった。
「無理しなくていいんだよ? 自分のトレーニングもあるだろう」
「いえっ、大丈夫ですぅ。やりたくてやってることなので……私のトレーナーさんも『息抜きは大切だ』って言ってくれてましたのでぇ」
言葉を返し、慌てて手を振る。しかしよく考えてみたら、パーティを手伝って皆の役に立ちたいと思っていたはずなのに、結局はオペラオーのトレーナーと自分のトレーナーどちらにも気を使わせてしまっているのではないだろうか。ああ、本当に考えなし……。
固まっている彼女をよそに、オペラオーのトレーナーは笑って礼を言った。
「そうなんだ、ありがとう。あの覇王のアイデアを全部一人で実現させるなんて大変だったから助かるよ」
彼は持っていた段ボール箱を机に置いた。中から資料を取り出してひとつひとつ広げながら、
「そういえば、クリスマスプレゼント何を用意したんだ? オペラオー、すごく楽しみにしてたみたいだから」
「ええっ……?」
細い声で言い淀む。オペラオーが自分からのプレゼントを楽しみにしているなんて、頭が沸騰しそうで思考がまとまらない。
「オペラオーさんがそんな事を言っていたんですか〜?」
「うん? そうだよ」
トレーナーは、資料ファイルをあさりながら生返事を返す。
トレーナーの言葉に、メイショウドトウは顔を赤くしてうつむくばかりである。プレゼントのこと、忘れていたわけではなくて最初から全く考えていなかった。
「オペラオーは人からもらった贈り物なら何でも喜んでくれるタイプだろ? でもやけに楽しみにしてたから。今年は何をあげるつもりなんだ?」
しかし問いかけから数秒経ってもドトウの返事はなかった。代わりに凄まじい衝撃音が響き渡り、部屋中の備品やらが一斉に床へ落ちた。何が起きたのか分からないトレーナーは振り返り、それから呆然とした。部屋の中央にツリーが倒れてオーナメントが散乱し、メイショウドトウがX字のポーズで伸びている。
「あわわわわわ、すみませんすみませんっ……」
彼女は慌てて床から立ち上がる。狼狽してオーナメントを引っ張った調子にツリーを丸ごと倒してしまったのだ。顔から血の気が引いてゆき、膝から力が抜けてゆくが、床に散らばったオーナメントを一つ一つ拾っていく。
彼女は恐る恐る顔を上げる。オペラオーのトレーナーはメイショウドトウの顔を見るなりにっこりと微笑んでくれた。怒っていないのだろうか。それとも優しい人だから、何も言わずに許してくれたのだろうか。
「あ……あの、本当にごめんなさいぃ……。せっかくみなさんのために準備していたのにぃ……」
桃色の大きな瞳に涙が浮かぶ。オペラオーのトレーナーは、床に散らばった飾りを拾いながら彼女を宥めてくれた。別にオーナメントも机も壊れていないから大丈夫。それは不安を取り除くのには十分な行動だった。
◆
食堂は賑やかだった。お昼ご飯を食べ終わって、メイショウドトウは浅くため息を漏らした。
――プレゼントはどうしようか。自分のあげたいものと、オペラオーの求めているものが同じであればいいと思う。それを迷いなく探し当てられる自信はないけれど、パズルの最後のピースを探すように、お互いの心が一致するまで考えていたいという感情ならある。オペラオーさんは私の憧れだから。いつまでも見つめていたい人だから。
隣に座っていたウマ娘……マチカネフクキタルは、ドトウの異変を見逃さない。耳をぴくぴくさせながら人差し指を真っ直ぐ立てて、助手に詰め寄った。
「ため息をつくと『福』が逃げていきますよ? 何かお悩みでもあるのですか!?」
「ふぇっ? いえっ、別にそんなわけではぁ……」
「もしも悩みがあるなら、このフクキタルにお任せください! きっとあなたのお役に立てることでしょう!」
「そ、そんな、大したことじゃないですしぃ……」
「遠慮なさらずに!」
ドトウはおどおどと首を振っていたが、フクキタルの勢いに押されて、やがて肩をすぼめた。そして躊躇いがちにつぶやいた。
「実はぁ……オペラオーさんが、私からのクリスマスプレゼントをすごく楽しみにしてくれているとお聞きしたんですぅ。けれど私、オペラオーさんに相応しいプレゼントなんて、選べる自信がなくてぇ……」
話していくうちに、声量はどんどん小さくなって語尾は涙声になっていく。そしてこめかみに両手をあててぐりぐりしながら、また悩み始めてしまった。しかしフクキタルの方は、ドトウとは対照的に、胸を張って自信ありげな笑みを浮かべる。
「わかりましたっ! 確かに、大切な人への贈り物を選ぶのは至難の業。ならば私が占ってさしあげましょう!」
「えええっ!? そんなことできるんですかぁ~?」
「もちろんです、お任せ下さい!」
言うやいなや、フクキタルは、懐から水晶玉を取り出して手をかざした。あの制服のどこに水晶なんか隠していたんだろう。とにかく彼女は何やら呪文のようなものを唱え始め、数分間ふんにゃかはんにゃかと唸った後、完全に硬直した。
「出ましたっ、今年のクリスマスの運勢は大吉! ……しかしプレゼント運は大凶!? な、何を選んでもだめ? むむっ……」
「救いはないのですかぁ〜?」
「シラオキ様のお告げに間違いはありません。どうします、ドトウさん?」
それが分からないからフクキタルに聞いたのだが。メイショウドトウは不安げに耳を伏せてへなへなと椅子に崩れ落ちてしまったが、やがて気を取り直して口を開いた。
「そ、それでも……オペラオーさんが楽しみにしてくださっているので……頑張って用意してみますぅ」
占いの結果が『何を選んでも駄目』なら、逆に何を選んだって「もっと上手くやれたかも」なんて考えなくてもいいっていうことだ。それなら、与えられた選択肢の中で精一杯納得できるものを選びたい。
「そうですね! では私もラッキーアイテムを探してみますっ」
占い少女がまた水晶に手をかざし、私服に似合うようなシックな小物が良いだろうと絞り出した。それならカラーリングはどうしようか、彼女にはどんな色が似合うだろうか。ドトウはまた考え込む。
思い出すのはやはりレース場の景色だった。
焦がれは膨張する。渇望がターフを蹴る。観客席を満たす歓声とは対照的に、狭いゲートの中は水を打ったように静かだ。出走準備のぴりっと張り詰めた空気は嫌いじゃない。芝は良バ場、蹄鉄が地面を噛み締めて、緊張しながらスタートの合図を待ち望む。自ずと筋肉に力が入って感覚が研ぎ澄まされていく。しなやかな身体の中で穏やかに燃える情熱、充血を思わせるピンクの瞳。私とあなたを繋ぐ色。
◆
12月24日、いよいよクリスマスがやってきた。パーティが終了した頃には空はもう黒銀に変わっていて、カシオペア座が燦燦と輝いている。
トレーナーは事務方との手続きのために出かけていったようだ。その間ドトウは、テイエムオペラオーと共に部屋の片付けを行うことになっていた。ストーブで乾燥した空気、二人きりの部屋の中で深呼吸して切り出した。プレゼントを用意していることを言わなくちゃ。
「あのぅ、オペラオーさん……」
「どうしたドトウ?」
「これ、私の気持ちですぅ! ……受け取ってくださいぃ……」
顔を真っ赤にして差し出された紙袋。オペラオーはそれを見留めて小さく、しかし仰々しく息を飲む。驚愕を知らせるように全身でポーズをとった。
「ハッ! 忠実なる臣下ドトウよ、これはボクへの捧げ物かい? とても綺麗な包みじゃないか。ボクのために選んでくれたのかい?」
「はいぃ……って、あぁっ!」
箱を渡そうとしたはずみに、ドトウはカーペットを踏んで滑り、バランスを崩した。手前に立っていたオペラオーが支えてくれたおかげでなんとか倒れなかったものの、その拍子にプレゼントの箱は手から滑り落ちてしまった。放物線を描いて床に叩きつけられ、家具に引っかかってボロボロに崩れてしまった。
「ああっ……プレゼントがあっ……」
見るも無惨な姿だった。用意したアクセサリーの鎖は千々に引きちぎれ、ペンダントトップは罅が入って三つに割れている。もう取り返しがつかない。
「ああっ……! ご、ごめんなさいごめんなさいごめんなさいいぃ! わ、私がドジなせいでぇっ……」
メイショウドトウは今にも泣き出してしまいたかった。いつもこう。良かれと思ってやったことが全て裏目に出てしまう。落ち込んでいる様子を見たオペラオーはしかし、唇を優しく綻ばせる。
「ドトウ、なぜ泣いているんだい」
「だって……私のせいで、せっかくのプレゼントがめちゃめちゃに……」
「割れてしまっても輝きは変わっていないさ。むしろ困難を経てなお輝くという美しきドラマが付与されたと言っていい。身につけさせられないというのなら、部屋に飾ればいい!」
そう言って彼女は、手袋越しにペンダントトップの欠片を拾い上げて机に置いた。淡い桃色の瞳の中には光が宿っていた。
「キミがこんな素敵なプレゼントを用意してくれたのは、トレーナー君に何か聞かされていたからだろう? けれどボクの望みはね、キミがボクのライバルであり忠実な臣下として、胸を張っていてほしいということだったのさ。だからキミがここにいてくれることが何よりの贈り物だよ」
オペラオーの言葉は、メイショウドトウにとっては魔法の呪文だ。心に張り付いた冷たい恐怖も凍りついた戦慄もゆっくり溶かしてくれる。
初めて会った時からずっと彼女の姿を追いかけていた。どうしようもない逡巡でさえ憧憬に緩やかに飲み込まれて、甘やかな慕情と陶酔を生み出す。そういう瞬間が積み重なって、私の恋は彼女を選んだのだろう。
「私……、私っ」
オペラオーは颯爽と笑って、一輪の薔薇を取り出してドトウの服にさしてくれた。
「さあ、立ちたまえ。すべての宿願は成就された!」
差し出された掌になかばしがみつくようにして立ち上がると、勢いよく肉体が引き上げられてくるりと一回転する。
「ひとつ踊ってはくれないか? レディ」
「はい、もちろんですぅ!」
窓の向こうで雪の結晶がさざめく中、二人の少女は互いに手を取り合い見つめ合った。照れくささより、はしゃいで舞い上がる乙女心が勝る。そっと寄り添って額を寄せ合う。彼女の身体の鮮明な熱が、腕を伸ばして触れ合うよりも早くなだらかに伝わってきた気がした。
メイショウドトウははにかんで笑う。きっと今私たちの頬は、誰が見ても分かるくらいのピンク色に染まっていることだろう。
クラシック路線や主要なレースが終わり、既に次シーズンへ向けての調整に入っている子も少なくはない。そんなウマ娘達はクリスマスやお正月にそれぞれ胸を高鳴らせているみたいだった。そしてメイショウドトウもその一人で、朋友テイエムオペラオー主催のパーティを手伝うことになったのだ。去年の年末はディナーショーを計画していたが、今年はお偉いさんを集めて特別なパーティを開くらしい。
朝礼前の一番冷え込む時間、メイショウドトウはトレーナー室でクリスマスパーティの準備を手伝っていた。机にはすべすべしたテーブルクロスを敷く。大きなモミの木の枝に色とりどりのリボンを巻き付け、部屋中に電飾を飾りつけると、部屋は繁華街のように明るくなった。
それから段ボール箱を開いてツリー用のオーナメントを取り出した。兵隊やサンタの人形、鈴。小さいながらに精緻な装飾が施されていて、色とりどりで煌びやかだ。軽く払ってから水を含ませた柔らかい布で拭いてやると、埃っぽい匂いはすっかり消えて、かわりに木の香ばしい匂いが鼻腔を満たす。大振りなツリーの枝にひとつひとつ吊り下げてやるのだ。ドジしないように、慎重に。
――こういうのって楽しいですぅ。去年のパーティだって、オペラオーさんは相変わらず元気いっぱいでまぶしくて……。
意図せず口元が弛む。本当に幸せな時間だった。でも、この時間がいつまでも続くわけではないことを、彼女は心のどこかで知っている。いつか終わりが来ることは分かっていたけれど、まだもう少しだけこのままでいたいと願うのはいけないことだろうか。
――だって、私は……。
オーナメントを飾る手が止まる。その先は考えられない。と言うよりむしろ考えたくなかった。
ツリーを半分ほど飾り付けた頃に、部屋の外から足音が聞こえた。誰かが立ち止まる気配。そしてドアを開けたのは、テイエムオペラオーのトレーナーだった。ドトウの姿を身留めて気さくに微笑む。
「お、ドトウじゃないか。今年も手伝ってくれるのか?」
「は、はいぃ……私は今年のパーティには参加しないですけど、準備くらいでもお力になれたらって」
メイショウドトウは視線を落としてもじもじする。オペラオーの力になりたいのは本当。ただそれと同じくらい、憧れの人のそばに居る口実が欲しかった。
「無理しなくていいんだよ? 自分のトレーニングもあるだろう」
「いえっ、大丈夫ですぅ。やりたくてやってることなので……私のトレーナーさんも『息抜きは大切だ』って言ってくれてましたのでぇ」
言葉を返し、慌てて手を振る。しかしよく考えてみたら、パーティを手伝って皆の役に立ちたいと思っていたはずなのに、結局はオペラオーのトレーナーと自分のトレーナーどちらにも気を使わせてしまっているのではないだろうか。ああ、本当に考えなし……。
固まっている彼女をよそに、オペラオーのトレーナーは笑って礼を言った。
「そうなんだ、ありがとう。あの覇王のアイデアを全部一人で実現させるなんて大変だったから助かるよ」
彼は持っていた段ボール箱を机に置いた。中から資料を取り出してひとつひとつ広げながら、
「そういえば、クリスマスプレゼント何を用意したんだ? オペラオー、すごく楽しみにしてたみたいだから」
「ええっ……?」
細い声で言い淀む。オペラオーが自分からのプレゼントを楽しみにしているなんて、頭が沸騰しそうで思考がまとまらない。
「オペラオーさんがそんな事を言っていたんですか〜?」
「うん? そうだよ」
トレーナーは、資料ファイルをあさりながら生返事を返す。
トレーナーの言葉に、メイショウドトウは顔を赤くしてうつむくばかりである。プレゼントのこと、忘れていたわけではなくて最初から全く考えていなかった。
「オペラオーは人からもらった贈り物なら何でも喜んでくれるタイプだろ? でもやけに楽しみにしてたから。今年は何をあげるつもりなんだ?」
しかし問いかけから数秒経ってもドトウの返事はなかった。代わりに凄まじい衝撃音が響き渡り、部屋中の備品やらが一斉に床へ落ちた。何が起きたのか分からないトレーナーは振り返り、それから呆然とした。部屋の中央にツリーが倒れてオーナメントが散乱し、メイショウドトウがX字のポーズで伸びている。
「あわわわわわ、すみませんすみませんっ……」
彼女は慌てて床から立ち上がる。狼狽してオーナメントを引っ張った調子にツリーを丸ごと倒してしまったのだ。顔から血の気が引いてゆき、膝から力が抜けてゆくが、床に散らばったオーナメントを一つ一つ拾っていく。
彼女は恐る恐る顔を上げる。オペラオーのトレーナーはメイショウドトウの顔を見るなりにっこりと微笑んでくれた。怒っていないのだろうか。それとも優しい人だから、何も言わずに許してくれたのだろうか。
「あ……あの、本当にごめんなさいぃ……。せっかくみなさんのために準備していたのにぃ……」
桃色の大きな瞳に涙が浮かぶ。オペラオーのトレーナーは、床に散らばった飾りを拾いながら彼女を宥めてくれた。別にオーナメントも机も壊れていないから大丈夫。それは不安を取り除くのには十分な行動だった。
◆
食堂は賑やかだった。お昼ご飯を食べ終わって、メイショウドトウは浅くため息を漏らした。
――プレゼントはどうしようか。自分のあげたいものと、オペラオーの求めているものが同じであればいいと思う。それを迷いなく探し当てられる自信はないけれど、パズルの最後のピースを探すように、お互いの心が一致するまで考えていたいという感情ならある。オペラオーさんは私の憧れだから。いつまでも見つめていたい人だから。
隣に座っていたウマ娘……マチカネフクキタルは、ドトウの異変を見逃さない。耳をぴくぴくさせながら人差し指を真っ直ぐ立てて、助手に詰め寄った。
「ため息をつくと『福』が逃げていきますよ? 何かお悩みでもあるのですか!?」
「ふぇっ? いえっ、別にそんなわけではぁ……」
「もしも悩みがあるなら、このフクキタルにお任せください! きっとあなたのお役に立てることでしょう!」
「そ、そんな、大したことじゃないですしぃ……」
「遠慮なさらずに!」
ドトウはおどおどと首を振っていたが、フクキタルの勢いに押されて、やがて肩をすぼめた。そして躊躇いがちにつぶやいた。
「実はぁ……オペラオーさんが、私からのクリスマスプレゼントをすごく楽しみにしてくれているとお聞きしたんですぅ。けれど私、オペラオーさんに相応しいプレゼントなんて、選べる自信がなくてぇ……」
話していくうちに、声量はどんどん小さくなって語尾は涙声になっていく。そしてこめかみに両手をあててぐりぐりしながら、また悩み始めてしまった。しかしフクキタルの方は、ドトウとは対照的に、胸を張って自信ありげな笑みを浮かべる。
「わかりましたっ! 確かに、大切な人への贈り物を選ぶのは至難の業。ならば私が占ってさしあげましょう!」
「えええっ!? そんなことできるんですかぁ~?」
「もちろんです、お任せ下さい!」
言うやいなや、フクキタルは、懐から水晶玉を取り出して手をかざした。あの制服のどこに水晶なんか隠していたんだろう。とにかく彼女は何やら呪文のようなものを唱え始め、数分間ふんにゃかはんにゃかと唸った後、完全に硬直した。
「出ましたっ、今年のクリスマスの運勢は大吉! ……しかしプレゼント運は大凶!? な、何を選んでもだめ? むむっ……」
「救いはないのですかぁ〜?」
「シラオキ様のお告げに間違いはありません。どうします、ドトウさん?」
それが分からないからフクキタルに聞いたのだが。メイショウドトウは不安げに耳を伏せてへなへなと椅子に崩れ落ちてしまったが、やがて気を取り直して口を開いた。
「そ、それでも……オペラオーさんが楽しみにしてくださっているので……頑張って用意してみますぅ」
占いの結果が『何を選んでも駄目』なら、逆に何を選んだって「もっと上手くやれたかも」なんて考えなくてもいいっていうことだ。それなら、与えられた選択肢の中で精一杯納得できるものを選びたい。
「そうですね! では私もラッキーアイテムを探してみますっ」
占い少女がまた水晶に手をかざし、私服に似合うようなシックな小物が良いだろうと絞り出した。それならカラーリングはどうしようか、彼女にはどんな色が似合うだろうか。ドトウはまた考え込む。
思い出すのはやはりレース場の景色だった。
焦がれは膨張する。渇望がターフを蹴る。観客席を満たす歓声とは対照的に、狭いゲートの中は水を打ったように静かだ。出走準備のぴりっと張り詰めた空気は嫌いじゃない。芝は良バ場、蹄鉄が地面を噛み締めて、緊張しながらスタートの合図を待ち望む。自ずと筋肉に力が入って感覚が研ぎ澄まされていく。しなやかな身体の中で穏やかに燃える情熱、充血を思わせるピンクの瞳。私とあなたを繋ぐ色。
◆
12月24日、いよいよクリスマスがやってきた。パーティが終了した頃には空はもう黒銀に変わっていて、カシオペア座が燦燦と輝いている。
トレーナーは事務方との手続きのために出かけていったようだ。その間ドトウは、テイエムオペラオーと共に部屋の片付けを行うことになっていた。ストーブで乾燥した空気、二人きりの部屋の中で深呼吸して切り出した。プレゼントを用意していることを言わなくちゃ。
「あのぅ、オペラオーさん……」
「どうしたドトウ?」
「これ、私の気持ちですぅ! ……受け取ってくださいぃ……」
顔を真っ赤にして差し出された紙袋。オペラオーはそれを見留めて小さく、しかし仰々しく息を飲む。驚愕を知らせるように全身でポーズをとった。
「ハッ! 忠実なる臣下ドトウよ、これはボクへの捧げ物かい? とても綺麗な包みじゃないか。ボクのために選んでくれたのかい?」
「はいぃ……って、あぁっ!」
箱を渡そうとしたはずみに、ドトウはカーペットを踏んで滑り、バランスを崩した。手前に立っていたオペラオーが支えてくれたおかげでなんとか倒れなかったものの、その拍子にプレゼントの箱は手から滑り落ちてしまった。放物線を描いて床に叩きつけられ、家具に引っかかってボロボロに崩れてしまった。
「ああっ……プレゼントがあっ……」
見るも無惨な姿だった。用意したアクセサリーの鎖は千々に引きちぎれ、ペンダントトップは罅が入って三つに割れている。もう取り返しがつかない。
「ああっ……! ご、ごめんなさいごめんなさいごめんなさいいぃ! わ、私がドジなせいでぇっ……」
メイショウドトウは今にも泣き出してしまいたかった。いつもこう。良かれと思ってやったことが全て裏目に出てしまう。落ち込んでいる様子を見たオペラオーはしかし、唇を優しく綻ばせる。
「ドトウ、なぜ泣いているんだい」
「だって……私のせいで、せっかくのプレゼントがめちゃめちゃに……」
「割れてしまっても輝きは変わっていないさ。むしろ困難を経てなお輝くという美しきドラマが付与されたと言っていい。身につけさせられないというのなら、部屋に飾ればいい!」
そう言って彼女は、手袋越しにペンダントトップの欠片を拾い上げて机に置いた。淡い桃色の瞳の中には光が宿っていた。
「キミがこんな素敵なプレゼントを用意してくれたのは、トレーナー君に何か聞かされていたからだろう? けれどボクの望みはね、キミがボクのライバルであり忠実な臣下として、胸を張っていてほしいということだったのさ。だからキミがここにいてくれることが何よりの贈り物だよ」
オペラオーの言葉は、メイショウドトウにとっては魔法の呪文だ。心に張り付いた冷たい恐怖も凍りついた戦慄もゆっくり溶かしてくれる。
初めて会った時からずっと彼女の姿を追いかけていた。どうしようもない逡巡でさえ憧憬に緩やかに飲み込まれて、甘やかな慕情と陶酔を生み出す。そういう瞬間が積み重なって、私の恋は彼女を選んだのだろう。
「私……、私っ」
オペラオーは颯爽と笑って、一輪の薔薇を取り出してドトウの服にさしてくれた。
「さあ、立ちたまえ。すべての宿願は成就された!」
差し出された掌になかばしがみつくようにして立ち上がると、勢いよく肉体が引き上げられてくるりと一回転する。
「ひとつ踊ってはくれないか? レディ」
「はい、もちろんですぅ!」
窓の向こうで雪の結晶がさざめく中、二人の少女は互いに手を取り合い見つめ合った。照れくささより、はしゃいで舞い上がる乙女心が勝る。そっと寄り添って額を寄せ合う。彼女の身体の鮮明な熱が、腕を伸ばして触れ合うよりも早くなだらかに伝わってきた気がした。
メイショウドトウははにかんで笑う。きっと今私たちの頬は、誰が見ても分かるくらいのピンク色に染まっていることだろう。
1/1ページ