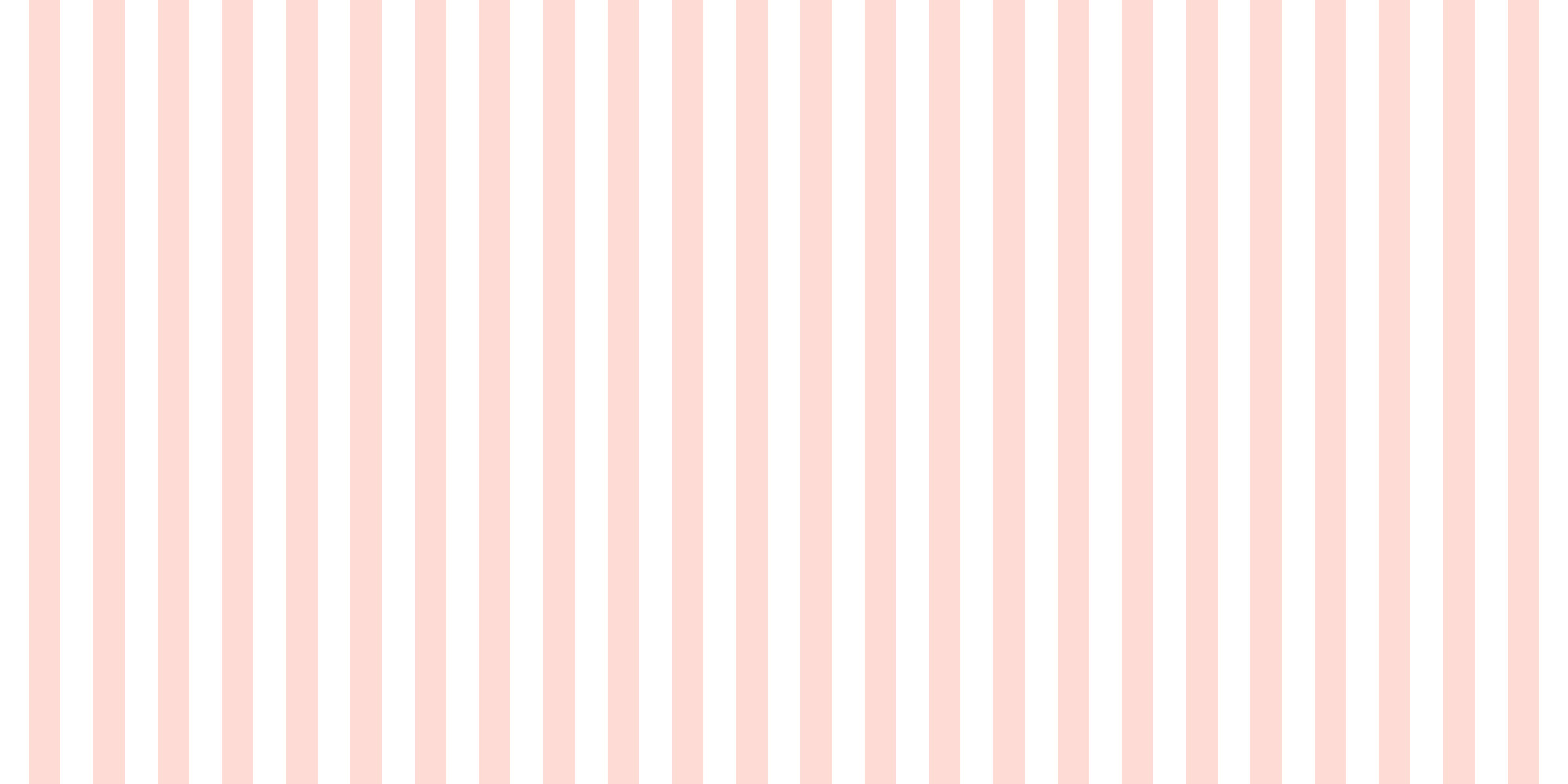twinkle days(白石vs財前/2年生)
name
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
「白石…俺ら、ちょっと離れなあかんかもしれんわ」
休み時間、謙也と廊下を歩いていると、急に立ち止まって真剣な顔で話してきた。
「ん?いきなり何や」
「白石のせいやないねん。でもな…大事な事なんや…!」
「やから、その大事な理由て何て」
「俺が男として一人前になるための一歩なんや」
よくわからないが、何か変なことを誰かに吹き込まれたようだ。
「…なあ、謙也…」
「なんや。俺は心を鬼にしとるで」
「そうか。でもな…いつまでも謙也は俺の親友や。それに…謙也は今のままで充分かっこええで」
「…白石…」
「お前は、男前や」
「…俺は何目を曇らしとったんやろな。…そうやな、俺は俺や。今の俺で勝負やで!ありがとうな、白石!やっぱり俺の親友やわ」
なんや最後までよくわからんかったけど、結果よければええわ。元気でたみたいやし。
「ん?あの子、財前のクラスの子やん」
謙也に言われてそちらをみると、中庭で1人ぼうっとしている彼女が見えた。
「何してるんやろ。もうすぐチャイムなるで」
「…ちょっと声かけとこか」
声をかけようとそちらに向かうと、先に彼女が立ち上がった。まだぼんやりとした様子で足を踏み出したと思ったら、その場で何かに躓く。
「…おお…結構派手に転んだで。あれは、痛いわ」
「ーー謙也。ちょっと俺、遅れるわ。先生に言うといてや」
「ん、ああ」
彼女の所に走る。後ろで謙也が「次、自習やで!」と言うのが聞こえたので、手で返事を返しておいた。
「痛っ…」
「苗字さん、大丈夫か?」
「…っ、白石、先輩」
彼女はこちらを見るととても驚いた顔をしたが、少し痛みが走ったのか顔をしかめた。
見れば膝を擦りむいていて、血がでている。
「立てるか?保健室行くで」
「っ、大丈夫です。洗って、絆創膏貼っておきますから」
「あかん。ちゃんと消毒しとかな、綺麗に治らんで」
「でも…」
「でも、やない。な、素直に聞いとき」
「…ありがとうございます…」
「ええ子や」
保健室の扉をノックし開けると、しん…としていた。先生は不在のようで、今は授業中だからか、いつもより静かに感じる。
「座っとき。先生おらんみたいやから、俺が手当てするわ」
救急箱を棚から取り出し手当ての準備をする。保健委員だから、どこに何があるかは一通り知っているし、手当ての仕方もわかっている。
消毒液を手にとり、視線を彼女の方へ向けると目があった。
「大丈夫やで。手当ては一通りできるし、安心しとき」
「ーあ、ありがとうございます」
消毒液の瓶の蓋をとると、特有の匂いがする。
「…すみません、先輩。授業始まってるのに」
「ええんや。怪我した子を放っとかれん。それに、次、自習やし」
そう笑って言うと、彼女も少しほっとしたのか、控えめに笑う。
「先輩」
「ん?なんや?」
「私、言えなかった事があって」
「うん」
「先輩は、覚えてないかもしれないですけど、入学式の日に同じように手当てしてもらった事があって」
入学式。覚えがあった。2年前の入学式、膝を怪我した女子を手当てした。
…しかも、今日のように派手に躓いていたのを思い出した。
「苗字さんやったんやな、あの時の子。覚えてるで」
そう言うと、彼女は目を丸くしてこちらを見て、でもすぐに俯いて恥ずかしそうに顔を赤らめた。
「あの時も派手に転けとったなあ。痕にならんでよかった」
「…あの時、私ちゃんとお礼を言えなくて。今更なんですけど…ありがとう、ございました」
「ええて、そんな。俺が気になって手当てしたんやし」
「でもっ、嬉しかったので。だから、ありがとうございました」
「…はは、こんな感謝されるとこそばゆいわ。ー…ん、ちょい、滲みるで」
消毒液を塗ると、彼女の肩が少し揺れる。
「…もうちょいやから」
一通りの手当てをして、最後に絆創膏を貼った。
「…よっしゃ、もう大丈夫や。次、気を付けるんやで」
「ありがとうございます」
「……」
「……」
どちらからも話すことなく、静かな空気が流れた。何か、この時間が終わってしまうのが惜しいかのような。
(俺、苗字の事好きなんで)
ふと、後輩の台詞を思い出す。
なんで、今思い出したんやろ。
「ー…っ、すまんな。授業、遅刻させてしもうた。もう行きや」
「ー…あ…。…はい」
彼女はもう一度礼を言い、扉に手をかけた。
そして静かに閉まると、静けさだけが残った。
なんやろ、これ。
「(ー…なんやろ、とちゃう。わかっとるやろ、俺)」
引き返さなあかんやつや。
休み時間、謙也と廊下を歩いていると、急に立ち止まって真剣な顔で話してきた。
「ん?いきなり何や」
「白石のせいやないねん。でもな…大事な事なんや…!」
「やから、その大事な理由て何て」
「俺が男として一人前になるための一歩なんや」
よくわからないが、何か変なことを誰かに吹き込まれたようだ。
「…なあ、謙也…」
「なんや。俺は心を鬼にしとるで」
「そうか。でもな…いつまでも謙也は俺の親友や。それに…謙也は今のままで充分かっこええで」
「…白石…」
「お前は、男前や」
「…俺は何目を曇らしとったんやろな。…そうやな、俺は俺や。今の俺で勝負やで!ありがとうな、白石!やっぱり俺の親友やわ」
なんや最後までよくわからんかったけど、結果よければええわ。元気でたみたいやし。
「ん?あの子、財前のクラスの子やん」
謙也に言われてそちらをみると、中庭で1人ぼうっとしている彼女が見えた。
「何してるんやろ。もうすぐチャイムなるで」
「…ちょっと声かけとこか」
声をかけようとそちらに向かうと、先に彼女が立ち上がった。まだぼんやりとした様子で足を踏み出したと思ったら、その場で何かに躓く。
「…おお…結構派手に転んだで。あれは、痛いわ」
「ーー謙也。ちょっと俺、遅れるわ。先生に言うといてや」
「ん、ああ」
彼女の所に走る。後ろで謙也が「次、自習やで!」と言うのが聞こえたので、手で返事を返しておいた。
「痛っ…」
「苗字さん、大丈夫か?」
「…っ、白石、先輩」
彼女はこちらを見るととても驚いた顔をしたが、少し痛みが走ったのか顔をしかめた。
見れば膝を擦りむいていて、血がでている。
「立てるか?保健室行くで」
「っ、大丈夫です。洗って、絆創膏貼っておきますから」
「あかん。ちゃんと消毒しとかな、綺麗に治らんで」
「でも…」
「でも、やない。な、素直に聞いとき」
「…ありがとうございます…」
「ええ子や」
保健室の扉をノックし開けると、しん…としていた。先生は不在のようで、今は授業中だからか、いつもより静かに感じる。
「座っとき。先生おらんみたいやから、俺が手当てするわ」
救急箱を棚から取り出し手当ての準備をする。保健委員だから、どこに何があるかは一通り知っているし、手当ての仕方もわかっている。
消毒液を手にとり、視線を彼女の方へ向けると目があった。
「大丈夫やで。手当ては一通りできるし、安心しとき」
「ーあ、ありがとうございます」
消毒液の瓶の蓋をとると、特有の匂いがする。
「…すみません、先輩。授業始まってるのに」
「ええんや。怪我した子を放っとかれん。それに、次、自習やし」
そう笑って言うと、彼女も少しほっとしたのか、控えめに笑う。
「先輩」
「ん?なんや?」
「私、言えなかった事があって」
「うん」
「先輩は、覚えてないかもしれないですけど、入学式の日に同じように手当てしてもらった事があって」
入学式。覚えがあった。2年前の入学式、膝を怪我した女子を手当てした。
…しかも、今日のように派手に躓いていたのを思い出した。
「苗字さんやったんやな、あの時の子。覚えてるで」
そう言うと、彼女は目を丸くしてこちらを見て、でもすぐに俯いて恥ずかしそうに顔を赤らめた。
「あの時も派手に転けとったなあ。痕にならんでよかった」
「…あの時、私ちゃんとお礼を言えなくて。今更なんですけど…ありがとう、ございました」
「ええて、そんな。俺が気になって手当てしたんやし」
「でもっ、嬉しかったので。だから、ありがとうございました」
「…はは、こんな感謝されるとこそばゆいわ。ー…ん、ちょい、滲みるで」
消毒液を塗ると、彼女の肩が少し揺れる。
「…もうちょいやから」
一通りの手当てをして、最後に絆創膏を貼った。
「…よっしゃ、もう大丈夫や。次、気を付けるんやで」
「ありがとうございます」
「……」
「……」
どちらからも話すことなく、静かな空気が流れた。何か、この時間が終わってしまうのが惜しいかのような。
(俺、苗字の事好きなんで)
ふと、後輩の台詞を思い出す。
なんで、今思い出したんやろ。
「ー…っ、すまんな。授業、遅刻させてしもうた。もう行きや」
「ー…あ…。…はい」
彼女はもう一度礼を言い、扉に手をかけた。
そして静かに閉まると、静けさだけが残った。
なんやろ、これ。
「(ー…なんやろ、とちゃう。わかっとるやろ、俺)」
引き返さなあかんやつや。