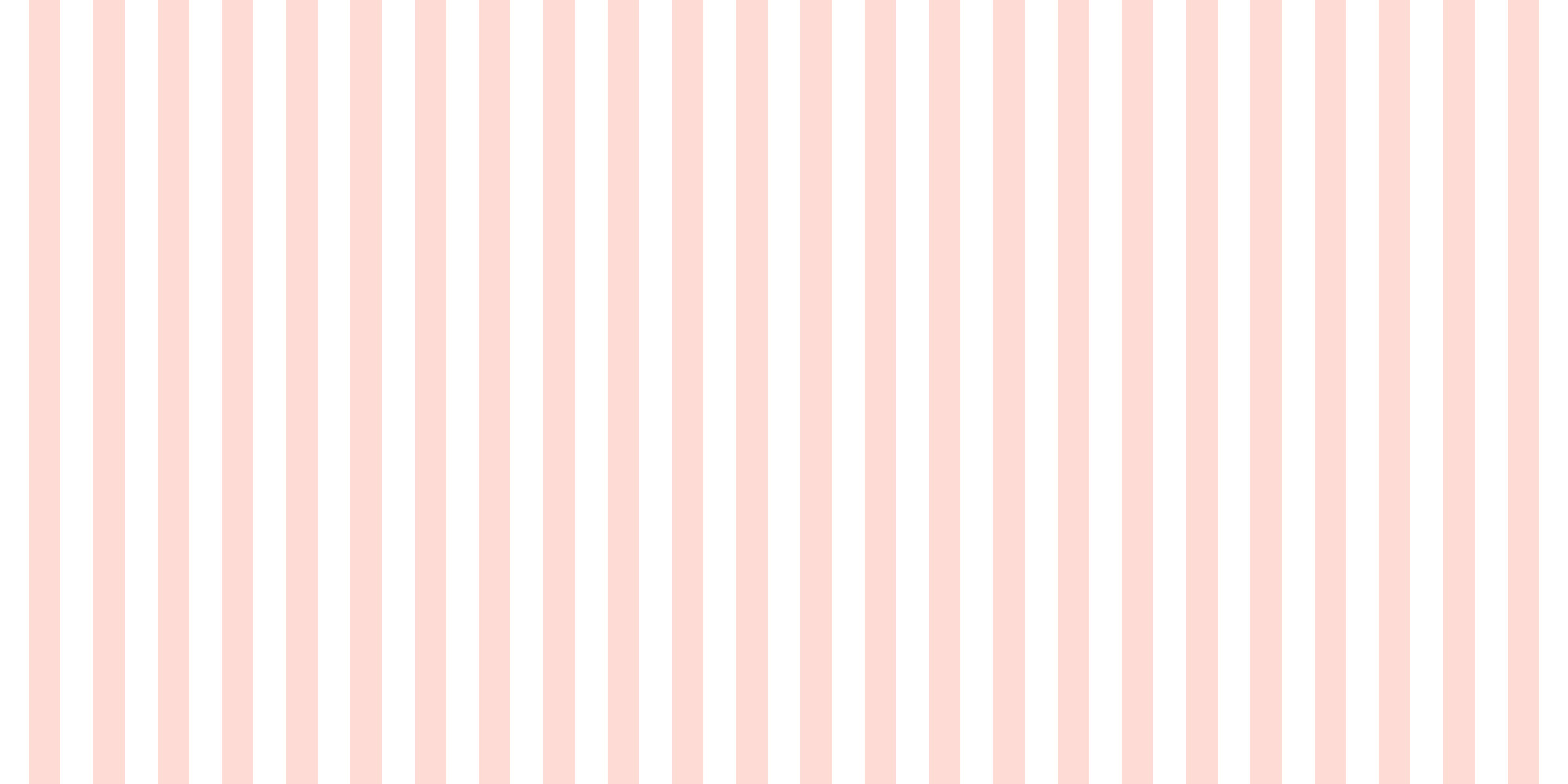twinkle days(白石vs財前/2年生)
name
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
目の前にいる人は誰だろう。
今わかる事といえば、白石先輩の事を知っていて、蔵ノ介くんと呼ぶような親しい関係ということ。
「蔵ノ介くんと打ってる子、何年生?むちゃくちゃやけど、すごいやん!」
「2年です。金ちゃんは西のルーキー言われてますから」
彼女に説明している忍足先輩が、いつもより少し笑顔がぎこちないような気がするのは気のせいだろうか。
「へえー、楽しそうやなあ。あの子、うちの高校入らへんかな」
「随分先やないですか」
「あはは、ホンマやなあ。それに、私卒業しておらんやん!て話やわ」
よく笑う、明るい人。そして美人だ。
話を聞いていれば、どうやら白石先輩と忍足先輩の高校のテニス部のマネージャーさんのようで。前に言っていた美人マネージャーさんというのは、この人の事だったんだと思う。
そんな事を思っていると、じっと見ていたのが伝わってしまったのか、こちらを向いた彼女と目があった。
「…どないしたん?」
彼女はそう言って、綺麗な笑顔で微笑む。同性の私から見てもドキッとする笑顔で、つい見惚れてしまうくらい。
「…あなた、マネージャー?それとも誰かの彼女?」
「え?あ、私は…」
「ーちょっと、ええですか」
話を遮るかのように、知った声がした。そちらを見ると、予想通り財前くんだ。
「すんませんけど、ちょっと打ち合わせあるんで。こいつ連れて行ってもええですか」
「ん?私はかまへんよ」
「ー苗字、行くで」
「あ…うん。すみません、失礼します」
「はーい」
笑顔で送り出してくれる彼女に、会釈をして返す。
奥のコートを見た。
白石先輩と遠山くんの打ち合いは終わったようだった。息を整えながらも、こちらを見た白石先輩と目があう。それだけでも嬉しくて、自然と顔がほころんでしまうのを感じた。
彼も微笑んで何かをこちらに言おうとしたようだったけれど、それを遮るように、目の前の彼女が「蔵ノ介くん!」と声をかけて、そちらへと走っていく。
彼女の存在に気付くとかなり驚いたようで、今度は少し困ったような顔に変わる。
彼女が手に持っていたタオルを白石先輩に渡したところで、ぐ、ともう一度手を引かれた。
「早よ、行くで」
「うん…」
自分の隣に置いていたタオルを一目見てから、財前くんと歩きだす。
後ろから彼女の楽しそうな声が聞こえて、気にならないわけはなくて。でも振り返る勇気はなかった。
「……とりあえず、用事言うたらこのくらいやけど、できる事だけでもしてくれたら助かるわ」
「うん」
部室で明日からの一通りの説明を受けて、メモをとる。書いていて思ったのは、やる事が予想以上に多かったこと。でも、もしマネージャーとしてなら、もっとあったはずだ。
私に出来ること。少なくともさっき言われた事をきちんとして、テニス部の助けになりたい。
「私、頑張るね。ちょっとでも助けになれるように」
「わからんとこあったら、聞いてくれてええから」
「うん、ありがとう」
財前くんは頷くと、部誌を広げて何か考えだした。
私は、先程とったメモを見返す事にした。
部室内は、静かだ。
静かになると、忘れていた光景が思い出された。
「(…まだ、あの人いるのかな。蔵ノ介くんって…言ってた。…あの人は、毎日白石先輩の側で、マネージャーとして支えているんだ)」
つい、メモをめくる手がとまる。
「…何か暗い事考えとるやろ」
「……えっ」
そう話しかけられて、つい上擦った声で返してしまった。
部誌を見ていたはずの彼は、いつの間にか頬杖をついてこちらを見ている。
「ホンマ、わかりやす」
「………」
「…白石先輩の事やから、心配しとるような事にはならんやろ」
「……。そう、だよね。私、ちょっと混乱してたかも」
「…俺もそうなんやろか」
「え?」
そんな事を話していると、部室の扉が開いて。
会いたかった人がいた。
「名前」
少し息が上がっている。もしかして、急いで来てくれた?そう思うと、それだけで嬉しい自分がいる。
白石先輩は財前くんの方を見たあと、こちらに歩いてきた。
「ーマネージャーには、帰ってもろたから」
「え…?」
「不安にさせたんちゃうかて、思ったんやけど…」
…正直、言う通り不安だった。あんなに綺麗なマネージャーさんが、白石先輩の事を"蔵ノ介くん"と呼んで、誰が見ても好意を抱いているとわかる近さで接して、毎日白石先輩の事をマネージャーとしてしっかりサポートしていて…。
私が彼にできることを考えてみるが、どれも小さな事に思えた。
今、目の前の彼は、私に気を使ってくれている。優しい、大好きな人。だから、自分が不安に思っているなんて言ったら心配させてしまうから。
ただでさえ高校でもテニスを続ける以上疲れもするし、休みだってあまりない。勉強だって、そんな中で、私に時間をくれているというのに。
「ーそんな事。大丈夫、ですから」
初めて、白石先輩に嘘をついた。
安心させたい、負担になりたくないが為の嘘。
「そう…か…。よかった」
そして、彼は本当にほっとしたのか、深く息をついた。
「俺が好きなんは、名前だけやから。信じとって欲しい」
「ーはい」
先輩はずるい。このもやもやを、全部取り去ってしまう。もやもやした霧が散ってしまう。
…好き。
「…ちょっと、俺の事みえてます?」
その声にハッとして、急に顔が一気に赤く染まるのを感じた。
「ご、ごごごめん」
「なんやこのプレイて思ったわ」
「おるんは知っとったで」
「…知っとって、この扱いとかないでしょ」
「…すまんな、心配性なんや」
「…へえ、そうなんすか。まあ、それくらいが丁度ええかもしれんですね。油断しとって後悔とかカッコ悪いですから」
「はは、油断はせえへんよ」
「"油断せずに行こう"とか言うかて思いました」
「…すべってもうたな」
話の中白石先輩に、手をぎゅ、と握られて。
彼を見上げると、大好きな笑顔があった。
「一緒に帰ろか?」
「あ…はい。でも、打ち合わせがまだ」
「打ち合わせ?」
白石先輩にはまだ話が伝わっていないようで、なんの事かと思っているようだった。
「謙也さんからきいてないですか?オサムちゃんが苗字に手伝いを頼んだんですけど」
「手伝いて、何の」
「テニス部です」
「マネージャー…いう事?」
「ちゃいます。手伝い、ですわ」
「……そうか…」
「白石、先輩…?」
「ー…あ、すまん。何でも…。打ち合わせ、あるんやろ?俺の事は気にせんでええから」
「打ち合わせならあらかた伝えたんで、今日はもうええですよ。ー苗字、明日からよろしく頼むわ」
「ーうん。わかった」
「ほな俺、皆の様子みてきます」
「…ああ、お疲れさん」
財前くんは開いていた部誌を閉じると、部室から出て行った。
そして白石先輩は、その出て行ったドアを暫く見ていて。
「先輩…?」
どうかしたのだろうかと声をかけると、こちらを向いた彼は私の名前を呼んだ。
「名前」
「どうかしたんですか…?」
「いや…何も。…なあ、抱きしめてもええ?」
「…っ…はい」
なんだか、随分久しぶりのように思えた。
ずっと、そうしたかったから、長く感じたのか。
「…あ…俺、汗臭ない?」
「え?ふふ、そんな事ないです!」
「ホンマ?良かったわ、臭くて幻滅されたら立ち直れんとこやった」
「…先輩からは、いい香りがします」
「… 名前からは、シャンプーの香りがする」
軽く触れるだけのキスが降ってきた。
見つめあうと、どちらからともなく笑顔が溢れた。
好きな人の匂い、抱きしめられた温かさ。
幸せ、だった。
今わかる事といえば、白石先輩の事を知っていて、蔵ノ介くんと呼ぶような親しい関係ということ。
「蔵ノ介くんと打ってる子、何年生?むちゃくちゃやけど、すごいやん!」
「2年です。金ちゃんは西のルーキー言われてますから」
彼女に説明している忍足先輩が、いつもより少し笑顔がぎこちないような気がするのは気のせいだろうか。
「へえー、楽しそうやなあ。あの子、うちの高校入らへんかな」
「随分先やないですか」
「あはは、ホンマやなあ。それに、私卒業しておらんやん!て話やわ」
よく笑う、明るい人。そして美人だ。
話を聞いていれば、どうやら白石先輩と忍足先輩の高校のテニス部のマネージャーさんのようで。前に言っていた美人マネージャーさんというのは、この人の事だったんだと思う。
そんな事を思っていると、じっと見ていたのが伝わってしまったのか、こちらを向いた彼女と目があった。
「…どないしたん?」
彼女はそう言って、綺麗な笑顔で微笑む。同性の私から見てもドキッとする笑顔で、つい見惚れてしまうくらい。
「…あなた、マネージャー?それとも誰かの彼女?」
「え?あ、私は…」
「ーちょっと、ええですか」
話を遮るかのように、知った声がした。そちらを見ると、予想通り財前くんだ。
「すんませんけど、ちょっと打ち合わせあるんで。こいつ連れて行ってもええですか」
「ん?私はかまへんよ」
「ー苗字、行くで」
「あ…うん。すみません、失礼します」
「はーい」
笑顔で送り出してくれる彼女に、会釈をして返す。
奥のコートを見た。
白石先輩と遠山くんの打ち合いは終わったようだった。息を整えながらも、こちらを見た白石先輩と目があう。それだけでも嬉しくて、自然と顔がほころんでしまうのを感じた。
彼も微笑んで何かをこちらに言おうとしたようだったけれど、それを遮るように、目の前の彼女が「蔵ノ介くん!」と声をかけて、そちらへと走っていく。
彼女の存在に気付くとかなり驚いたようで、今度は少し困ったような顔に変わる。
彼女が手に持っていたタオルを白石先輩に渡したところで、ぐ、ともう一度手を引かれた。
「早よ、行くで」
「うん…」
自分の隣に置いていたタオルを一目見てから、財前くんと歩きだす。
後ろから彼女の楽しそうな声が聞こえて、気にならないわけはなくて。でも振り返る勇気はなかった。
「……とりあえず、用事言うたらこのくらいやけど、できる事だけでもしてくれたら助かるわ」
「うん」
部室で明日からの一通りの説明を受けて、メモをとる。書いていて思ったのは、やる事が予想以上に多かったこと。でも、もしマネージャーとしてなら、もっとあったはずだ。
私に出来ること。少なくともさっき言われた事をきちんとして、テニス部の助けになりたい。
「私、頑張るね。ちょっとでも助けになれるように」
「わからんとこあったら、聞いてくれてええから」
「うん、ありがとう」
財前くんは頷くと、部誌を広げて何か考えだした。
私は、先程とったメモを見返す事にした。
部室内は、静かだ。
静かになると、忘れていた光景が思い出された。
「(…まだ、あの人いるのかな。蔵ノ介くんって…言ってた。…あの人は、毎日白石先輩の側で、マネージャーとして支えているんだ)」
つい、メモをめくる手がとまる。
「…何か暗い事考えとるやろ」
「……えっ」
そう話しかけられて、つい上擦った声で返してしまった。
部誌を見ていたはずの彼は、いつの間にか頬杖をついてこちらを見ている。
「ホンマ、わかりやす」
「………」
「…白石先輩の事やから、心配しとるような事にはならんやろ」
「……。そう、だよね。私、ちょっと混乱してたかも」
「…俺もそうなんやろか」
「え?」
そんな事を話していると、部室の扉が開いて。
会いたかった人がいた。
「名前」
少し息が上がっている。もしかして、急いで来てくれた?そう思うと、それだけで嬉しい自分がいる。
白石先輩は財前くんの方を見たあと、こちらに歩いてきた。
「ーマネージャーには、帰ってもろたから」
「え…?」
「不安にさせたんちゃうかて、思ったんやけど…」
…正直、言う通り不安だった。あんなに綺麗なマネージャーさんが、白石先輩の事を"蔵ノ介くん"と呼んで、誰が見ても好意を抱いているとわかる近さで接して、毎日白石先輩の事をマネージャーとしてしっかりサポートしていて…。
私が彼にできることを考えてみるが、どれも小さな事に思えた。
今、目の前の彼は、私に気を使ってくれている。優しい、大好きな人。だから、自分が不安に思っているなんて言ったら心配させてしまうから。
ただでさえ高校でもテニスを続ける以上疲れもするし、休みだってあまりない。勉強だって、そんな中で、私に時間をくれているというのに。
「ーそんな事。大丈夫、ですから」
初めて、白石先輩に嘘をついた。
安心させたい、負担になりたくないが為の嘘。
「そう…か…。よかった」
そして、彼は本当にほっとしたのか、深く息をついた。
「俺が好きなんは、名前だけやから。信じとって欲しい」
「ーはい」
先輩はずるい。このもやもやを、全部取り去ってしまう。もやもやした霧が散ってしまう。
…好き。
「…ちょっと、俺の事みえてます?」
その声にハッとして、急に顔が一気に赤く染まるのを感じた。
「ご、ごごごめん」
「なんやこのプレイて思ったわ」
「おるんは知っとったで」
「…知っとって、この扱いとかないでしょ」
「…すまんな、心配性なんや」
「…へえ、そうなんすか。まあ、それくらいが丁度ええかもしれんですね。油断しとって後悔とかカッコ悪いですから」
「はは、油断はせえへんよ」
「"油断せずに行こう"とか言うかて思いました」
「…すべってもうたな」
話の中白石先輩に、手をぎゅ、と握られて。
彼を見上げると、大好きな笑顔があった。
「一緒に帰ろか?」
「あ…はい。でも、打ち合わせがまだ」
「打ち合わせ?」
白石先輩にはまだ話が伝わっていないようで、なんの事かと思っているようだった。
「謙也さんからきいてないですか?オサムちゃんが苗字に手伝いを頼んだんですけど」
「手伝いて、何の」
「テニス部です」
「マネージャー…いう事?」
「ちゃいます。手伝い、ですわ」
「……そうか…」
「白石、先輩…?」
「ー…あ、すまん。何でも…。打ち合わせ、あるんやろ?俺の事は気にせんでええから」
「打ち合わせならあらかた伝えたんで、今日はもうええですよ。ー苗字、明日からよろしく頼むわ」
「ーうん。わかった」
「ほな俺、皆の様子みてきます」
「…ああ、お疲れさん」
財前くんは開いていた部誌を閉じると、部室から出て行った。
そして白石先輩は、その出て行ったドアを暫く見ていて。
「先輩…?」
どうかしたのだろうかと声をかけると、こちらを向いた彼は私の名前を呼んだ。
「名前」
「どうかしたんですか…?」
「いや…何も。…なあ、抱きしめてもええ?」
「…っ…はい」
なんだか、随分久しぶりのように思えた。
ずっと、そうしたかったから、長く感じたのか。
「…あ…俺、汗臭ない?」
「え?ふふ、そんな事ないです!」
「ホンマ?良かったわ、臭くて幻滅されたら立ち直れんとこやった」
「…先輩からは、いい香りがします」
「… 名前からは、シャンプーの香りがする」
軽く触れるだけのキスが降ってきた。
見つめあうと、どちらからともなく笑顔が溢れた。
好きな人の匂い、抱きしめられた温かさ。
幸せ、だった。