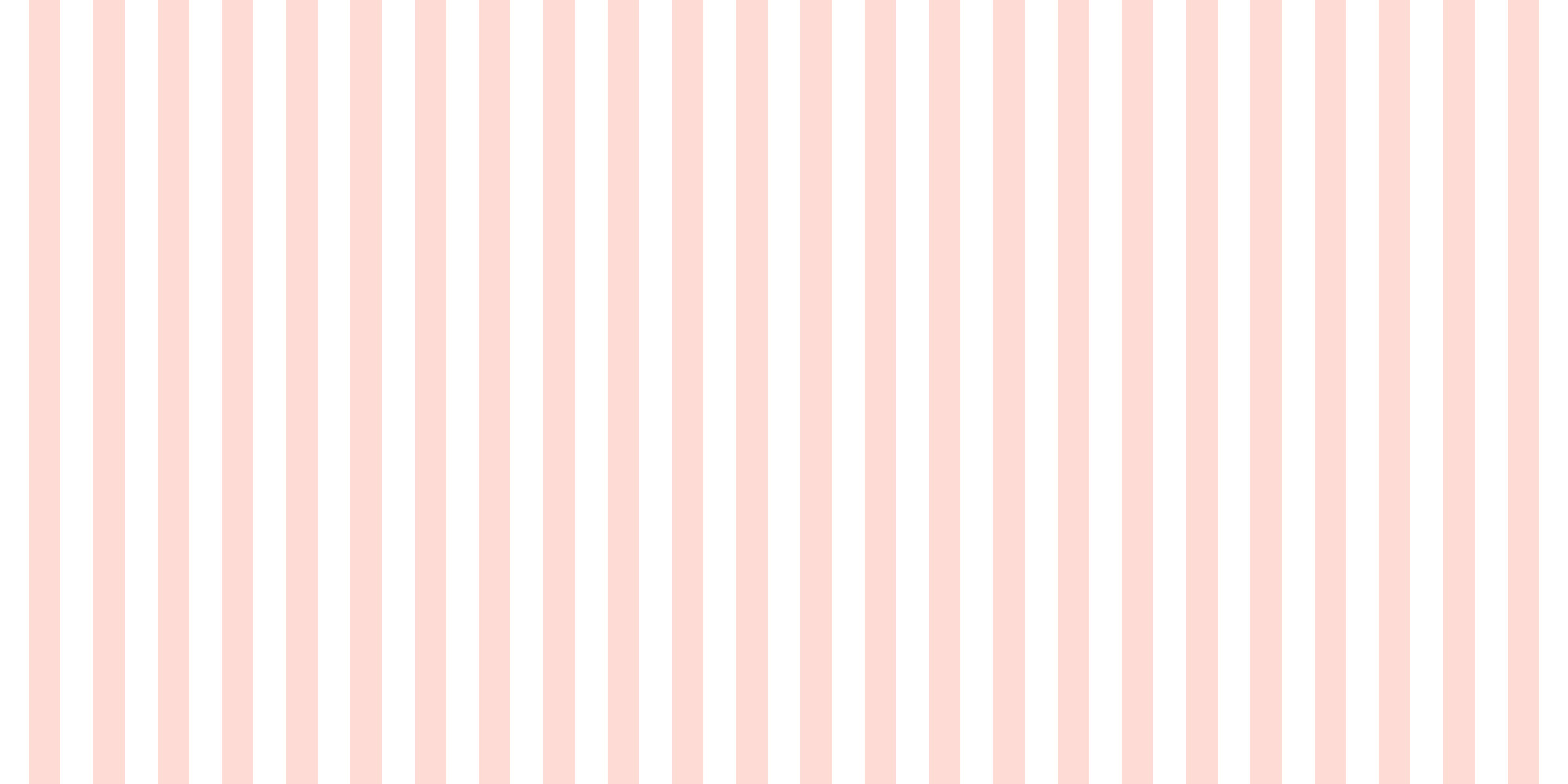Give me all your love(仁王vs丸井/同級生)
name
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
あれから、自然と屋上で3人で昼ごはんを食べるようになった。
苗字とブン太が仲良くなるのは早かった。昼休みだけじゃなく、休み時間も料理の話なんかをよくしている。
「お、そのハンバーグ旨そうだな!」
「食べる?結構うまくできたんだ」
「やりい!」
「仁王くんも玉子焼きどうぞ」
「…ん、ありがとさん」
玉子焼きを手で摘んで、口に放り込む。
「うま「うっま‼︎なんだこのハンバーグ!めっちゃうまい!」
うまい、という言葉がブン太によってかき消されると、続きの言葉を改めていう気にはならない。
「なあ、名前、今度作り方教えてくれね?」
"名前"
その言葉に苗字も少し驚いていたが、またすぐ笑って、「うん、いいよ」と答えた。
自分の中が、ざわざわと騒がしい。
周りがざわついているのもあまり好きではないが、自分の中となるともっとだ。
シャットアウトすればいい、そう身体が反応して、すっと中が冷めていく。
その場を立つと、2人がこちらを見た。
「何だよ仁王、どうした?」
「…ちょっと、用事じゃ」
「ふーん、ならこの玉子焼きいらねぇの?」
ブン太が指差したのは、俺の為にちょっと多めに作ってくれているものだ。
今までは、昼ごはんを食べるより屋上で昼寝、苗字と出会ってからは昼寝のかわりに作ってきてくれた玉子焼きを摘んで食べるようになった。最初に食べたそれがうまかったから。
「もういらんから、ブンちゃんが食べんしゃい」
「お、マジか。じゃ、いっただき!」
本当に旨そうに食べる。偏食の自分からしたら、こんな風に食事をする事などないだろう。
ブン太の隣の彼女を見ると目があったが、視線を逸らして屋上のドアノブに手をかけた。
次の日からは、昼休みに屋上に行かなかった。
ある日も、チャイムが鳴ると席を立った。身体がだるい。さて、どこで昼寝をするか。
教室を出て行こうとすると後ろから呼び止められて、赤い髪が目に飛び込んでくる。
「なあ、今日も来ねえの?」
「…そうじゃな、昼寝せんと力がでんからの」
「それ、昼飯食わねぇからじゃね」
「昼寝が栄養なんじゃ」
「折角名前が昼飯作ってくれてんのに。……。なあ、ちょっと相談があるんだけど、耳かしてくんね」
そう言って腕を俺の肩に回してくると、小声で話はじめた。
「…俺さ、名前が好きなんだ」
「…ほう」
「告白しようと思うんだけどさ。脈ありだと思う?」
また自分の中がざわつくのがわかる。
そしてもう1人の自分が囁く。騒がしいものには蓋をしろと。面倒なだけだと。
「お前さんらは話も合うんじゃから、ええんじゃなか」
「お、仁王もそう思う⁈よし、そうと決まればだけど…」
そこまでは笑っていたブン太だったが、真剣な眼差しでこちらを見てくる。
「なあ、仁王。俺、告っていいんだな?…一応、確認するけど」
「…なんじゃ、ブンちゃん。自信ないんか」
「ちげーよ!…聞いときたかっただけ。もう、わかった」
そう言うと、早速彼女のところに歩いて行って「昼飯食いに行こうぜ」と声をかけている。
2人に背を向けて、教室の扉を開けた。
同じやつを好きになるなんてのは、後で面倒だ。さらに部活のチームメイトと同じ相手をときたら、余計に。
それなら、女なんぞ他のやつでもいいと思ってしまう自分がいた。
今思えば、他の女でいいなんて、よく言えたものだと思う。
苗字とブン太が仲良くなるのは早かった。昼休みだけじゃなく、休み時間も料理の話なんかをよくしている。
「お、そのハンバーグ旨そうだな!」
「食べる?結構うまくできたんだ」
「やりい!」
「仁王くんも玉子焼きどうぞ」
「…ん、ありがとさん」
玉子焼きを手で摘んで、口に放り込む。
「うま「うっま‼︎なんだこのハンバーグ!めっちゃうまい!」
うまい、という言葉がブン太によってかき消されると、続きの言葉を改めていう気にはならない。
「なあ、名前、今度作り方教えてくれね?」
"名前"
その言葉に苗字も少し驚いていたが、またすぐ笑って、「うん、いいよ」と答えた。
自分の中が、ざわざわと騒がしい。
周りがざわついているのもあまり好きではないが、自分の中となるともっとだ。
シャットアウトすればいい、そう身体が反応して、すっと中が冷めていく。
その場を立つと、2人がこちらを見た。
「何だよ仁王、どうした?」
「…ちょっと、用事じゃ」
「ふーん、ならこの玉子焼きいらねぇの?」
ブン太が指差したのは、俺の為にちょっと多めに作ってくれているものだ。
今までは、昼ごはんを食べるより屋上で昼寝、苗字と出会ってからは昼寝のかわりに作ってきてくれた玉子焼きを摘んで食べるようになった。最初に食べたそれがうまかったから。
「もういらんから、ブンちゃんが食べんしゃい」
「お、マジか。じゃ、いっただき!」
本当に旨そうに食べる。偏食の自分からしたら、こんな風に食事をする事などないだろう。
ブン太の隣の彼女を見ると目があったが、視線を逸らして屋上のドアノブに手をかけた。
次の日からは、昼休みに屋上に行かなかった。
ある日も、チャイムが鳴ると席を立った。身体がだるい。さて、どこで昼寝をするか。
教室を出て行こうとすると後ろから呼び止められて、赤い髪が目に飛び込んでくる。
「なあ、今日も来ねえの?」
「…そうじゃな、昼寝せんと力がでんからの」
「それ、昼飯食わねぇからじゃね」
「昼寝が栄養なんじゃ」
「折角名前が昼飯作ってくれてんのに。……。なあ、ちょっと相談があるんだけど、耳かしてくんね」
そう言って腕を俺の肩に回してくると、小声で話はじめた。
「…俺さ、名前が好きなんだ」
「…ほう」
「告白しようと思うんだけどさ。脈ありだと思う?」
また自分の中がざわつくのがわかる。
そしてもう1人の自分が囁く。騒がしいものには蓋をしろと。面倒なだけだと。
「お前さんらは話も合うんじゃから、ええんじゃなか」
「お、仁王もそう思う⁈よし、そうと決まればだけど…」
そこまでは笑っていたブン太だったが、真剣な眼差しでこちらを見てくる。
「なあ、仁王。俺、告っていいんだな?…一応、確認するけど」
「…なんじゃ、ブンちゃん。自信ないんか」
「ちげーよ!…聞いときたかっただけ。もう、わかった」
そう言うと、早速彼女のところに歩いて行って「昼飯食いに行こうぜ」と声をかけている。
2人に背を向けて、教室の扉を開けた。
同じやつを好きになるなんてのは、後で面倒だ。さらに部活のチームメイトと同じ相手をときたら、余計に。
それなら、女なんぞ他のやつでもいいと思ってしまう自分がいた。
今思えば、他の女でいいなんて、よく言えたものだと思う。
5/5ページ