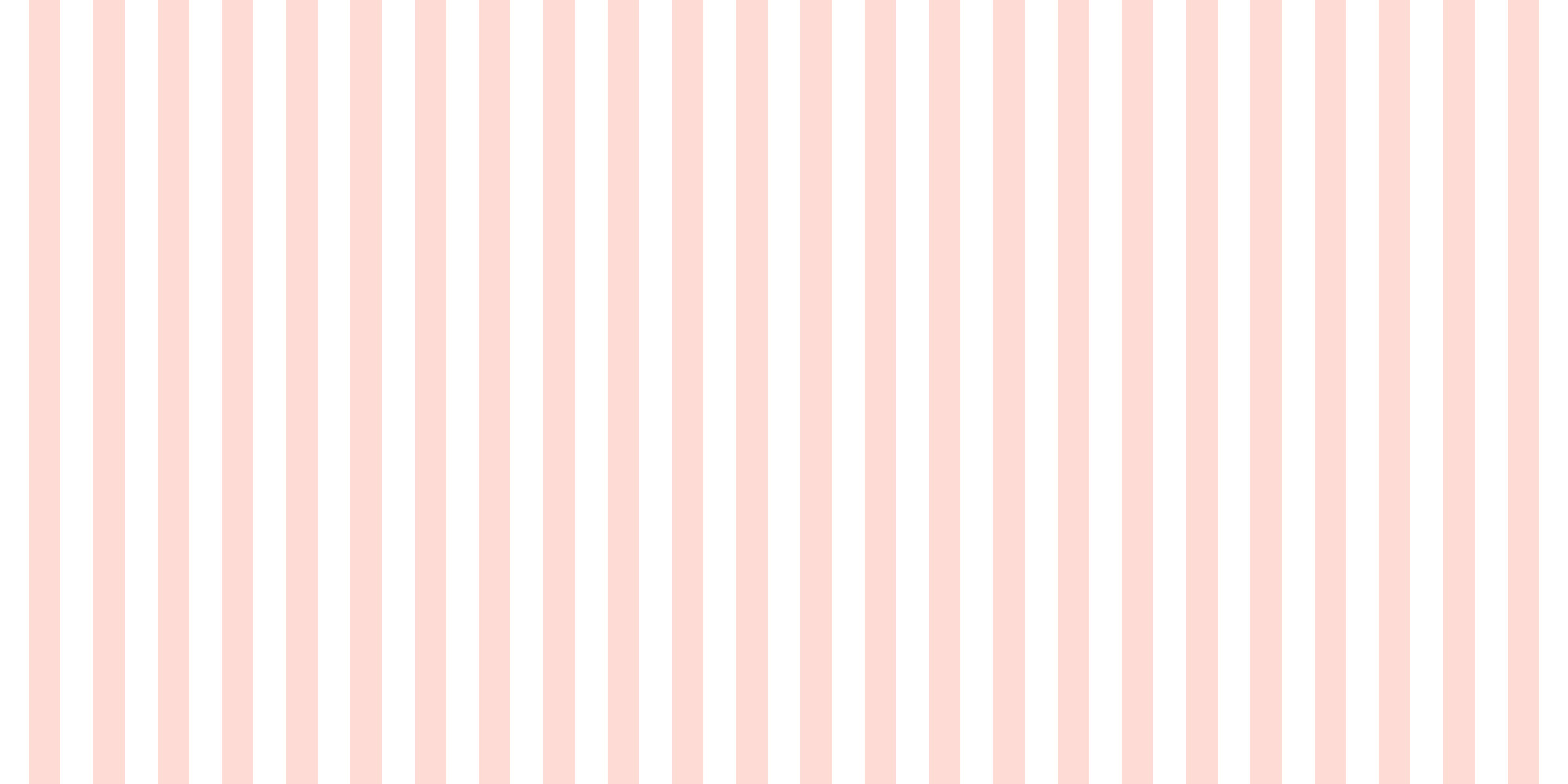Give me all your love(仁王vs丸井/同級生)
name
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
教室に戻る気分じゃなかった。
だから、授業が終わるまで保健室で寝た。
天井を見ながら先ほどの事を思い出した。
悲しませるつもりはなかった。
でも悲しむのはわかっていた。
何してるんじゃ、俺。
あんな顔がみたいわけじゃないのに。
陽春。
昼休みは、塔屋の上で昼寝するのが日課だった。
彼女は同じクラスの転校生で、毎日屋上で昼飯を1人で食べていた。積極的な性格ではなかったから、当時は友達とまだ仲良くなれていなかったのだろう。正直、その時は何も思っていなかった。
彼女がどうしようが、自分の昼寝の時間を邪魔されなければそれでよかった。
ある日、風が少しだけ強くふいていた。
気持ちがいい風だ。
「あっ!」
いきなり素っ頓狂な声が聞こえてきたかと思えば、ふわっとハンカチが俺の顔に落ちてきた。
「(…なんじゃ、これ)」
顔にかかったハンカチを摘んでみると、どうも弁当を包んでいたハンカチのようだ。
上半身を起こすと、下から驚いた声がする。
「ごめんなさい、それ、飛んでいっちゃって…!」
「そんなに慌てると弁当までひっくり返るんじゃなか」
「あ…!」
しっかりと弁当を抱え込む姿を見て、ふと笑ってしまう。
「もう飛ばされんようにな」
塔屋から降りてハンカチを渡してやる。
彼女は返事をしてうなずくと、ありがとうございますと礼を言った。
「…なかなかうまそうな弁当じゃの」
「あ、ありがとう。今日は玉子焼きがうまくできたの」
「そうか」
「…あの、お詫びに、食べる?」
「…じゃ、貰おうかの」
玉子焼きを一つ摘んで食べる。出汁のきいた、好みの味だった。
「うまい。お前さん、なかなかやるのう」
「本当?よかった!」
褒めてやれば笑う。普通の女の子だった。
それからしばらくは、毎日昼寝をし、彼女が来たら何故か玉子焼きをくれるようになった。
「仁王くんはお昼ご飯食べないの?」
「玉子焼きを食べとるよ」
「それはつまんだだけで、お昼ご飯じゃないよ。テニスしてるんでしょ?」
「よく知っとるの」
「さすがに私もテニス部はわかっちゃった。凄い人気だもんね」
「外野が賑やかすぎるんじゃ。でも実際、ウチのテニス部は強いぜよ」
「ずっと優勝してるんだもんね。そのチームのレギュラーとか凄く強いんだろうなあ」
「…無敗の部長に、すぐ鉄拳の副部長、何考えとるんかわからん参謀に、眼鏡の変態紳士、悪魔化するワカメ、お菓子ばっかり食べる子豚に、ブラジルからきたその飼育係…ってとこじゃの」
「え⁈もしかして…その人たちがレギュラー…?」
「おい、お菓子ばっかり食べる子豚ってなんだよ」
後ろを振り向くと、赤い髪のチームメイト。
「どしたんじゃ、ブンちゃん」
「俺子豚みたいに太ってねーっつの」
何も言わずにブン太のわき腹に触れると、少し力をいれてつまんだ。
「ちょ、やめろよ!つまむな!」
ブン太が手をはらってぷりぷり怒っていると、隣からは明るい笑い声が聞こえてきた。
「ご、ごめん…ふふふ。仲がいいんだね」
明るく笑う彼女をみたのは初めてなのか、ブン太もびっくりした表情で苗字を見ている。
「ブンちゃん、何か用があったんじゃなか?」
「…あ!そうだよ!今日部活の初めに大事なミーティングあるから遅れないようにってさ。絶対だぜ」
「面倒じゃの…」
「ぜっったい!遅れんなよ!俺がちゃんと伝えないって怒られちまうだろ!」
「善処はするき」
「ほんと、頼むぜ」
「にしても…お前らいつもココにいるのか?もしかして付き合ってんの」
「苗字にお恵をもらっとるだけじゃよ。付き合っとらん」
「…。うん。たまたま私が屋上で食べてて、そこから成り行きで玉子焼きの仲に」
彼女がそう言うと、ブン太がぶはっと笑って吹き出した。
「何だよ、玉子焼きの仲って!おっかし…ははは!苗字って面白いやつだったんだな」
「え⁈そうかな?」
「そうだよ。つーわけで、ん!」
ブン太は苗字に手を差し出すと、片方の手で差し出した手を指差した。
「仲良くしてくれよなの、握手」
「あ…。うん。こちらこそよろしくお願いします」
「硬いのよそうぜ。もうダチなんだし」
「ーうん。ありがとう」
だから、授業が終わるまで保健室で寝た。
天井を見ながら先ほどの事を思い出した。
悲しませるつもりはなかった。
でも悲しむのはわかっていた。
何してるんじゃ、俺。
あんな顔がみたいわけじゃないのに。
陽春。
昼休みは、塔屋の上で昼寝するのが日課だった。
彼女は同じクラスの転校生で、毎日屋上で昼飯を1人で食べていた。積極的な性格ではなかったから、当時は友達とまだ仲良くなれていなかったのだろう。正直、その時は何も思っていなかった。
彼女がどうしようが、自分の昼寝の時間を邪魔されなければそれでよかった。
ある日、風が少しだけ強くふいていた。
気持ちがいい風だ。
「あっ!」
いきなり素っ頓狂な声が聞こえてきたかと思えば、ふわっとハンカチが俺の顔に落ちてきた。
「(…なんじゃ、これ)」
顔にかかったハンカチを摘んでみると、どうも弁当を包んでいたハンカチのようだ。
上半身を起こすと、下から驚いた声がする。
「ごめんなさい、それ、飛んでいっちゃって…!」
「そんなに慌てると弁当までひっくり返るんじゃなか」
「あ…!」
しっかりと弁当を抱え込む姿を見て、ふと笑ってしまう。
「もう飛ばされんようにな」
塔屋から降りてハンカチを渡してやる。
彼女は返事をしてうなずくと、ありがとうございますと礼を言った。
「…なかなかうまそうな弁当じゃの」
「あ、ありがとう。今日は玉子焼きがうまくできたの」
「そうか」
「…あの、お詫びに、食べる?」
「…じゃ、貰おうかの」
玉子焼きを一つ摘んで食べる。出汁のきいた、好みの味だった。
「うまい。お前さん、なかなかやるのう」
「本当?よかった!」
褒めてやれば笑う。普通の女の子だった。
それからしばらくは、毎日昼寝をし、彼女が来たら何故か玉子焼きをくれるようになった。
「仁王くんはお昼ご飯食べないの?」
「玉子焼きを食べとるよ」
「それはつまんだだけで、お昼ご飯じゃないよ。テニスしてるんでしょ?」
「よく知っとるの」
「さすがに私もテニス部はわかっちゃった。凄い人気だもんね」
「外野が賑やかすぎるんじゃ。でも実際、ウチのテニス部は強いぜよ」
「ずっと優勝してるんだもんね。そのチームのレギュラーとか凄く強いんだろうなあ」
「…無敗の部長に、すぐ鉄拳の副部長、何考えとるんかわからん参謀に、眼鏡の変態紳士、悪魔化するワカメ、お菓子ばっかり食べる子豚に、ブラジルからきたその飼育係…ってとこじゃの」
「え⁈もしかして…その人たちがレギュラー…?」
「おい、お菓子ばっかり食べる子豚ってなんだよ」
後ろを振り向くと、赤い髪のチームメイト。
「どしたんじゃ、ブンちゃん」
「俺子豚みたいに太ってねーっつの」
何も言わずにブン太のわき腹に触れると、少し力をいれてつまんだ。
「ちょ、やめろよ!つまむな!」
ブン太が手をはらってぷりぷり怒っていると、隣からは明るい笑い声が聞こえてきた。
「ご、ごめん…ふふふ。仲がいいんだね」
明るく笑う彼女をみたのは初めてなのか、ブン太もびっくりした表情で苗字を見ている。
「ブンちゃん、何か用があったんじゃなか?」
「…あ!そうだよ!今日部活の初めに大事なミーティングあるから遅れないようにってさ。絶対だぜ」
「面倒じゃの…」
「ぜっったい!遅れんなよ!俺がちゃんと伝えないって怒られちまうだろ!」
「善処はするき」
「ほんと、頼むぜ」
「にしても…お前らいつもココにいるのか?もしかして付き合ってんの」
「苗字にお恵をもらっとるだけじゃよ。付き合っとらん」
「…。うん。たまたま私が屋上で食べてて、そこから成り行きで玉子焼きの仲に」
彼女がそう言うと、ブン太がぶはっと笑って吹き出した。
「何だよ、玉子焼きの仲って!おっかし…ははは!苗字って面白いやつだったんだな」
「え⁈そうかな?」
「そうだよ。つーわけで、ん!」
ブン太は苗字に手を差し出すと、片方の手で差し出した手を指差した。
「仲良くしてくれよなの、握手」
「あ…。うん。こちらこそよろしくお願いします」
「硬いのよそうぜ。もうダチなんだし」
「ーうん。ありがとう」