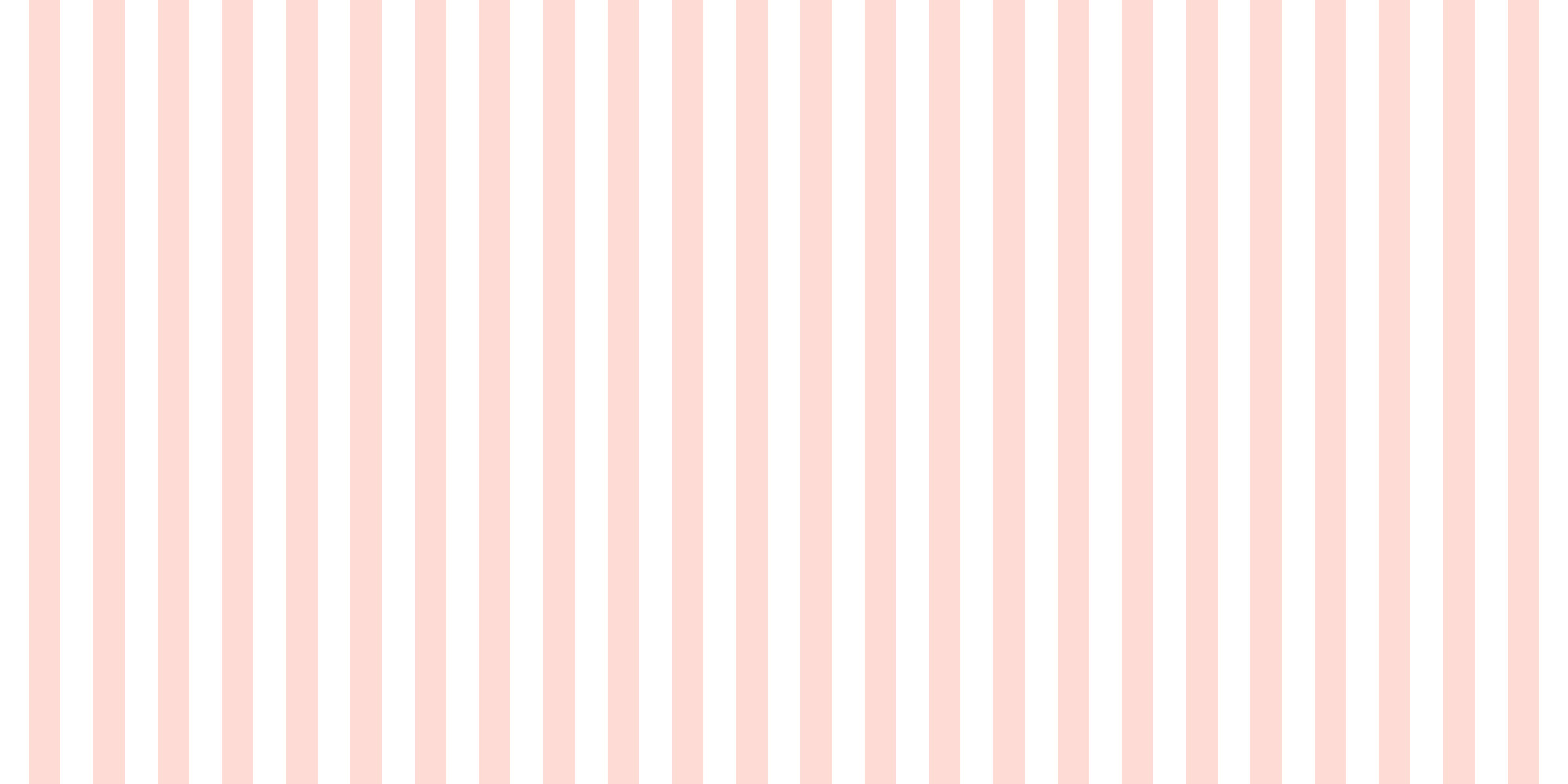twinkle days(白石vs財前/2年生)
name
白石先輩が来ると、皆の様子と場の雰囲気が変わる。
あの人が部長やったとき、誰よりも努力しとるのは知っとった。全国大会でも、努力したら天才にも勝てると証明した、努力の天才。だからあの人にテニスで勝てんかっても、悔しいけど納得ができた。勿論その度に、何があかんかったんやろ次は勝ったる、とも。
けど、今度は自分が部長になってみると、そういう訳にはいかなくて。努力すれば追いつける…むしろ追い越したるて思っとったけど、どれだけやっても、あの人の背中に追いつける気がしない。着地点が見えない。なんでこんなに、遠いんやろ。
…前は、周りから天才とか言われても、別にそれをどうこう思った事はなかった。
でも、今は、そう言われる事がしんどい。
「(天才やないわ。…もう、うっさい)」
焦燥感、もやもやとしたものが膨らんでいく。
テニスって、こんなにしんどかったやろか。
コートから離れた場所で、顔を洗った。ついでに蛇口から流れる水を頭からかぶる。頭が少しでも冷えるといい、と。
タオルで顔を拭いて、深く息をついた。
「ーねえ、あなたテニス部?」
横目で見れば、知らない学校の女生徒だ。
同じ中学生?それにしては大人びているから、高校生かもしれない。
「コートの場所、教えて欲しいんやけど」
「…何か用ですか?」
「高校の後輩がここに来とるて聞いたから、ちょっと様子を見にきたんよ」
「後輩…」
ふいに、謙也さんとの話を思い出した。
多分この人、高校のマネージャーや。
「どないしたん?」
「…すみません。高校の先輩や言うても、部外者は入れん決まりなんですわ」
「え、ホンマに?ちょっとだけもあかん?」
「おーい!財前!」
向こうで謙也さんが呼ぶ声がした。姿はまだ見えないが、どうやら探されているみたいだ。
ホンマ、タイミング悪すぎやろ。人がごまかそうとしてる時に。
そして、その姿が見えた瞬間、隣のマネージャーと思われる人が「あ!」と声をあげた。
「謙也くんやん!ちょうどよかったわ」
「え⁈マネージャー、何でおるんですか?」
「なんでって、今日中学でテニスなんや言うてたやろ?ちょっと様子見に来てみようと思ってな」
「あ、はは…そうなんすか」
「そうや、蔵ノ介くんも来てる?」
さすがの謙也さんも、まずいと思っているのだろう、目が泳いでいる。
「なあ、コートに連れて行ってくれん?」
「う…。ええ、です…けど。せやけど、ちょっと待ってください、コイツとちょっと話あるんで」
「うん、ええよ」
謙也さんに腕を掴まれると、マネージャーから離れたところに連れてこられた。そして小声で「何でやねん」とツッコまれた。
「お前、なんでマネージャーと一緒におんねん」
「何でて…さっき話しかけられただけですけど。大体、マネージャーとか知らんかったし。謙也さんこそどないしたんですか」
「さっき打ち合い途中やったやろ。やから探しに来たんやけど…て、そない言うてる場合やないわ」
謙也さんが肩に腕を回してくると、さらに小声で話しだす。
「なあ、マネージャー、何か言うてた?」
「さっきも言うてた通り、後輩の様子見に来た、って事しか聞いてません」
「…やっぱり、白石と俺の事やんな、それ」
「どう考えても先輩らしかおらんでしょ。…案内、するんですか?」
「いや…行ったら、白石おるやん。今、金ちゃんと打っとるけど。苗字もおるし、苗字の前でいつも通り白石にベタベタなんはさすがにまずいやろ…」
「まあ、そうでしょうね」
「やばい。どないしよ」
「…どないしよ、やないですわ。俺は、部外者は帰って貰おうとしとったのに、謙也さんがタイミング悪く来たせいで台無しや。しかも、なんや案内する流れになってますよね。ほんま、アホですか?」
「アホ言うなや。今はこっからどうするか考えなあかんやろ」
「やったら考えてくださいよ。謙也さんのせいなんやから」
「一緒に考えてくれてもええんやで」
「言い方腹立つんで、はたいてもええですか」
「すまん、一緒に考えてください」
手を合わせてくるものだから、ため息をひとつついてやった。
「…俺が今から苗字を連れてコートから出て行くんで、謙也さんはちょっと遠回りしてコートに戻るんはどうです?それやったら、バッティングは避けられるんちゃいますか」
そう言うと、謙也さんは目を丸くして、「それや!」と大きな声で叫ぶ。
「謙也さん、うっさい」
「それしかないわ。よっしゃ、それで行こ!苗字の方は頼むわ」
「…まあ、ええですけど」
向こうで待つマネージャーの方をちらと見ると、目があった。彼女はにこりと笑ったけれど、俺はすぐに逸らした。
間も無く謙也さんがそちらに走って行くと、2人はコートとは反対に歩き出す。ぐるりと校舎周りをまわってからコート、というところだろう。謙也さんはこちらを振り向かずに、任せとけという事だろうか、親指を立ててみせた。
コートに戻ると、向こうのコートではまだ白石先輩と金ちゃんが打ち合いをしている。謙也さんはうまくやっているようだ、まだ姿は見えない。
「(ーおった)」
先程と同じベンチに座っている彼女を見つけて、そちらまで歩く。あと数メートル。
そこから、名前を呼ぼうとした。
「………」
呼ぼうとしたけど、できなかった。
目の前の彼女の横顔が、ずっと白石先輩を見ていたから。
わかっていることなのに、自分の中のもやもやが、また膨らむのを感じた。
「(俺、何してんやろ)」
「(…そっちばっかり見んなや)」
まだ好きや、とか、キャラやない。
けど、振られたからって、はいそうですか言うて気持ちすっぱり無くなる奴やって普通おらんやろ。
早めに声をかけないととわかっているのに、できない。
「あ、蔵ノ介くん、おるやんか」
後ろから、先程聞いた事がある声が聞こえた。そして、「何してんねん」と焦っているような謙也さんの呟きも。
目の前の彼女が、こちらを向いた。
あの人が部長やったとき、誰よりも努力しとるのは知っとった。全国大会でも、努力したら天才にも勝てると証明した、努力の天才。だからあの人にテニスで勝てんかっても、悔しいけど納得ができた。勿論その度に、何があかんかったんやろ次は勝ったる、とも。
けど、今度は自分が部長になってみると、そういう訳にはいかなくて。努力すれば追いつける…むしろ追い越したるて思っとったけど、どれだけやっても、あの人の背中に追いつける気がしない。着地点が見えない。なんでこんなに、遠いんやろ。
…前は、周りから天才とか言われても、別にそれをどうこう思った事はなかった。
でも、今は、そう言われる事がしんどい。
「(天才やないわ。…もう、うっさい)」
焦燥感、もやもやとしたものが膨らんでいく。
テニスって、こんなにしんどかったやろか。
コートから離れた場所で、顔を洗った。ついでに蛇口から流れる水を頭からかぶる。頭が少しでも冷えるといい、と。
タオルで顔を拭いて、深く息をついた。
「ーねえ、あなたテニス部?」
横目で見れば、知らない学校の女生徒だ。
同じ中学生?それにしては大人びているから、高校生かもしれない。
「コートの場所、教えて欲しいんやけど」
「…何か用ですか?」
「高校の後輩がここに来とるて聞いたから、ちょっと様子を見にきたんよ」
「後輩…」
ふいに、謙也さんとの話を思い出した。
多分この人、高校のマネージャーや。
「どないしたん?」
「…すみません。高校の先輩や言うても、部外者は入れん決まりなんですわ」
「え、ホンマに?ちょっとだけもあかん?」
「おーい!財前!」
向こうで謙也さんが呼ぶ声がした。姿はまだ見えないが、どうやら探されているみたいだ。
ホンマ、タイミング悪すぎやろ。人がごまかそうとしてる時に。
そして、その姿が見えた瞬間、隣のマネージャーと思われる人が「あ!」と声をあげた。
「謙也くんやん!ちょうどよかったわ」
「え⁈マネージャー、何でおるんですか?」
「なんでって、今日中学でテニスなんや言うてたやろ?ちょっと様子見に来てみようと思ってな」
「あ、はは…そうなんすか」
「そうや、蔵ノ介くんも来てる?」
さすがの謙也さんも、まずいと思っているのだろう、目が泳いでいる。
「なあ、コートに連れて行ってくれん?」
「う…。ええ、です…けど。せやけど、ちょっと待ってください、コイツとちょっと話あるんで」
「うん、ええよ」
謙也さんに腕を掴まれると、マネージャーから離れたところに連れてこられた。そして小声で「何でやねん」とツッコまれた。
「お前、なんでマネージャーと一緒におんねん」
「何でて…さっき話しかけられただけですけど。大体、マネージャーとか知らんかったし。謙也さんこそどないしたんですか」
「さっき打ち合い途中やったやろ。やから探しに来たんやけど…て、そない言うてる場合やないわ」
謙也さんが肩に腕を回してくると、さらに小声で話しだす。
「なあ、マネージャー、何か言うてた?」
「さっきも言うてた通り、後輩の様子見に来た、って事しか聞いてません」
「…やっぱり、白石と俺の事やんな、それ」
「どう考えても先輩らしかおらんでしょ。…案内、するんですか?」
「いや…行ったら、白石おるやん。今、金ちゃんと打っとるけど。苗字もおるし、苗字の前でいつも通り白石にベタベタなんはさすがにまずいやろ…」
「まあ、そうでしょうね」
「やばい。どないしよ」
「…どないしよ、やないですわ。俺は、部外者は帰って貰おうとしとったのに、謙也さんがタイミング悪く来たせいで台無しや。しかも、なんや案内する流れになってますよね。ほんま、アホですか?」
「アホ言うなや。今はこっからどうするか考えなあかんやろ」
「やったら考えてくださいよ。謙也さんのせいなんやから」
「一緒に考えてくれてもええんやで」
「言い方腹立つんで、はたいてもええですか」
「すまん、一緒に考えてください」
手を合わせてくるものだから、ため息をひとつついてやった。
「…俺が今から苗字を連れてコートから出て行くんで、謙也さんはちょっと遠回りしてコートに戻るんはどうです?それやったら、バッティングは避けられるんちゃいますか」
そう言うと、謙也さんは目を丸くして、「それや!」と大きな声で叫ぶ。
「謙也さん、うっさい」
「それしかないわ。よっしゃ、それで行こ!苗字の方は頼むわ」
「…まあ、ええですけど」
向こうで待つマネージャーの方をちらと見ると、目があった。彼女はにこりと笑ったけれど、俺はすぐに逸らした。
間も無く謙也さんがそちらに走って行くと、2人はコートとは反対に歩き出す。ぐるりと校舎周りをまわってからコート、というところだろう。謙也さんはこちらを振り向かずに、任せとけという事だろうか、親指を立ててみせた。
コートに戻ると、向こうのコートではまだ白石先輩と金ちゃんが打ち合いをしている。謙也さんはうまくやっているようだ、まだ姿は見えない。
「(ーおった)」
先程と同じベンチに座っている彼女を見つけて、そちらまで歩く。あと数メートル。
そこから、名前を呼ぼうとした。
「………」
呼ぼうとしたけど、できなかった。
目の前の彼女の横顔が、ずっと白石先輩を見ていたから。
わかっていることなのに、自分の中のもやもやが、また膨らむのを感じた。
「(俺、何してんやろ)」
「(…そっちばっかり見んなや)」
まだ好きや、とか、キャラやない。
けど、振られたからって、はいそうですか言うて気持ちすっぱり無くなる奴やって普通おらんやろ。
早めに声をかけないととわかっているのに、できない。
「あ、蔵ノ介くん、おるやんか」
後ろから、先程聞いた事がある声が聞こえた。そして、「何してんねん」と焦っているような謙也さんの呟きも。
目の前の彼女が、こちらを向いた。