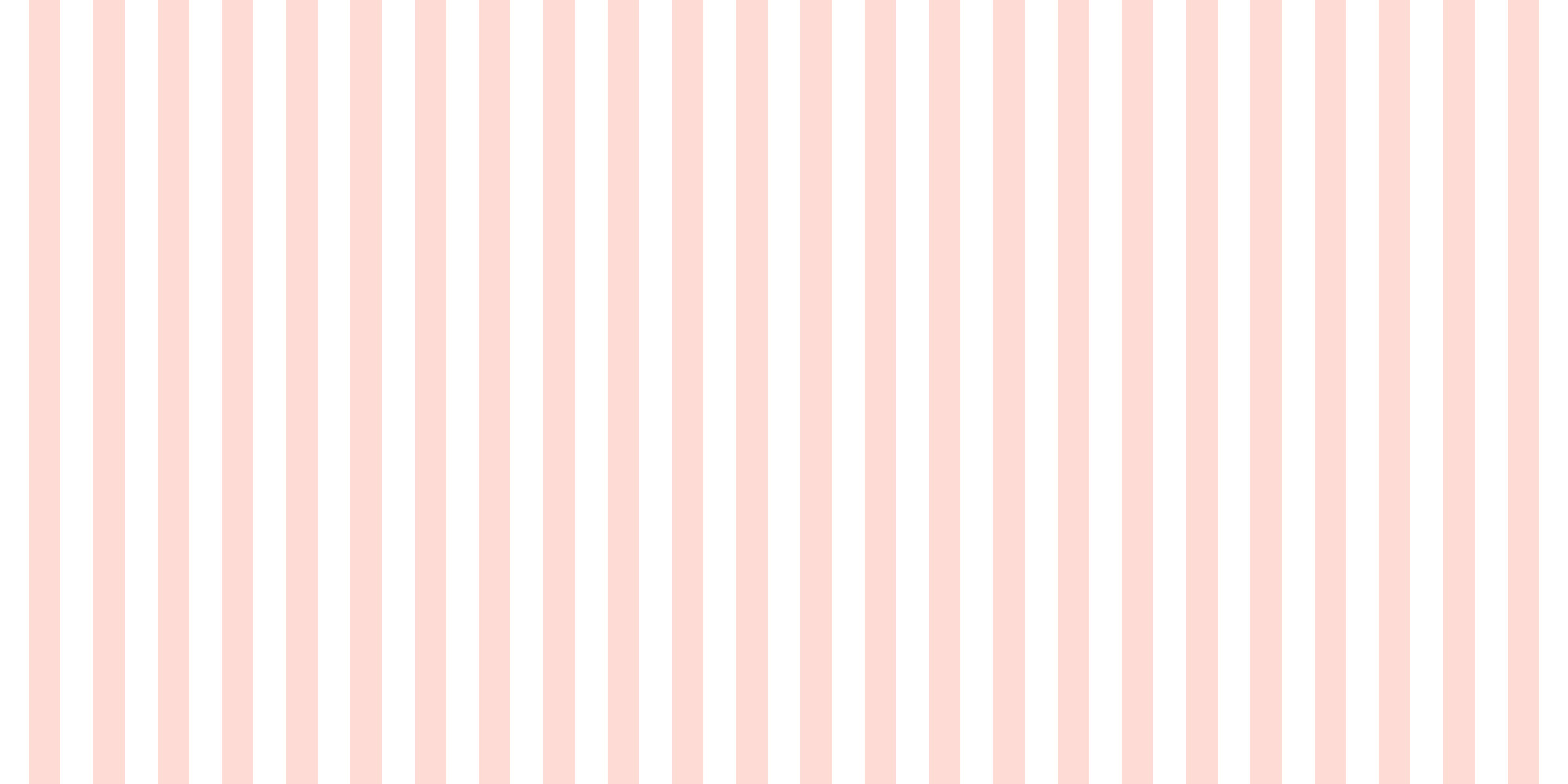twinkle days(白石vs財前/2年生)
name
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
先輩達が卒業してから暫くして、私も3年生になった。
白石先輩とは、学校でこそ会えなくなったけれど、平日にはメールや電話をしたり、休日にはデートもする。
まだ"蔵"と呼ぶには慣れなくて、デートの時につい"白石先輩"と呼んでしまう事も、彼は「少しずつでええよ」と微笑んでくれた。
こんなに幸せだと、今一生分の運を使い切ってるんじゃないかとも思う。
「おーい、苗字、財前。ちょっとええか?」
放課後のチャイムがなると同時に、担任の渡邊先生に呼ばれた。一緒に呼ばれた財前くんとは、3年生にあがっても一緒のクラスになった。
先生に呼ばれても彼は未だ自分の席で、ノートに何かを書くのに集中している。もう一度先生が、「おーい財前、早よ来んと1コケシなくなるで〜」なんて言うと、彼は頭をカシ、と掻いてこちらに歩いてきた。
「お、来たな。よし!なら2人とも、1コケシやろう!」
「いりません。で、何ですか?…あ、練習メニューなら、まだ考え中ですわ」
「何や要らんのかい。相変わらず無愛想くんやなあ。なら苗字に財前の分までコケシやろうな。なんと2コケシやで、嬉しいやろ」
「…えっ⁈あ。ありがとうございます」
「うん、苗字は素直でええ子やわ」
「…俺忙しいんで、何もないなら」
「ちょいちょい!待ちや!そうやで、財前くん。忙しいんやろ?そんなお前にええ話…かもしれん。な、苗字」
話を振られても内容は知らない。どういう事だろう。
「とりあえず、財前。お前は一人で全部やろうとし過ぎな。もうちょい周りに頼らなあかんわ」
「…ほな、オサムちゃんに頼ればええ言う事ですかね」
「いや、俺は無理や」
「ですよね」
「…んんっ、兎に角やな、白石もそうやったけど、抱え込むタイプの部長には周りのサポートがいるんや」
…渡邊先生が言うのは、わかる気がする。
白石先輩も皆の為に様々なものを背負っていた。どんな時だって周りを見ていて、苦しいときでもそんな顔は見せない。
テニス部の仲間はそんな彼の事を知っているから、荷が少しでも軽くなるようにサポートしたりしていた。そして「仲間がいてくれたから、やってこれたんや」と彼は言っていた。
「そこでや。苗字、財前と仲がええみたいやし、テニス部のマネージャーしてくれんかなあ、なんてな。思たりして」
「…えっ⁈」
突然過ぎて、続ける言葉がでてこない。私より先に、隣の財前くんが口を開いた。
「まあ、忙しいんには変わりないですけど…マネージャーとかは、別に大丈夫ですわ」
「財前はそう言うやろ思たけど、苗字はどうや?」
「私は…マネージャーが務まる程テニスに詳しくはないし、逆に面倒をかけてしまいそうなので、正直自信はないです…」
「うーん…、そうか…」
「話終わりましたよね?なら、俺行きますんで」
そう言って先生に背中を向けた財前くんは、"いつも通り"だ。
財前くんは涼しい顔をして、本当にしんどい時は表面に出さないタイプじゃないかと思う。白石先輩と、一緒だ。
彼も部長になったばかりで大変なはずだ。遠山くんがいても、先輩達はいなくなってしまった。
以前は休み時間には音楽を聴いているかスマホと睨めっこだったのに、今はさっきのようにノートに何かを書いたり、疲れているのだろう寝てしまっていたりする。
クラスでは財前くんは面倒くさがり屋とか言われてるけど、部長になってから彼は変わった。
一生懸命、出来る以上の事を頑張っている。
そう思ったら、自然と口が動いていた。
「…でも、マネージャーみたいにはできないですけど、私でも手伝える事があるなら。少しでも…何かできればとは思います」
財前くんが足を止めて、こちらを振り返った。
「そんな無理せんでも「ホンマか!よっしゃ‼︎優しい苗字 には3コケシやろう!おお、やろう!」」
彼の言葉は先生の言葉に遮られて、「声大きすぎやろ」と、ちょっとご機嫌ナナメだ。
「財前、手伝ってもらったらどうや?な、そうしたらええ」
財前くんはこちらを見て何かを言おうとしたけれど、何も言わなかった。そして、ふう、と息をつくと呟いた。
「… 苗字がええんなら」
「よっしゃ!なら決まりや!ほな、2人とも頼むで〜」
先生はそう言って私達の肩をポンポンと叩くと、機嫌良く教室から出て行った。
「…ホンマに手伝いするつもりなん?」
「うん。どれだけ力になれるかわからないけど、私でできる事なら何でもするよ。それでちょっとでも財前くんの助けになれればいいなと。あ…その、出来るだけ面倒はかけないようにするから」
「そうやなくて」
「え?」
「……。…ほな、頼むわ」
「うん」
早速、テニス部に行くと、部員の皆に紹介してくれた。皆や遠山くんが歓迎してくれたのがなんだか嬉しくて、これから頑張ろうと思えてくる。
「ほな、今日の練習やけど」
そう言う財前くんの手には教室で何かを書いていたノートがあって、中の内容を読み上げる。
「ーあと、今日先輩らが来るみたいやから。以上」
卒業した先輩達。頻繁にではないが、先輩達が時間のある時はテニス部に顔をだしてくれる。
昨日白石先輩からメールがきていた事を思い出して、会えるのだと思うと胸がドキドキする。
練習を始めて少しすると、知った声が聞こえた。忍足先輩だ。
「皆、来たでー!」
「…また来たんすか」
「"また"って何や!そんなん言うてホンマは嬉しいんやろ?」
「………はあ」
「ため息!聞こえとるから!」
「来るんはええんですけど、もうちょい早めに連絡くださいよ」
「連絡なら入れたやんか」
「あー…きてましたね。こっちの練習始まる前に"今日皆で行くわ!"…その5分後に、"着いたで!"て。…いやいや、これはないでしょ」
「まあ、スピードスターやからな」
「褒めてないですけど」
賑やかだからか、部員達が集まってきた。皆、先輩達の姿を見て嬉しそうだ。特に、遠山くんなんて凄いスピードで走ってきて、忍足先輩に飛びついた。
「ケーンーヤー‼︎」
「金ちゃん!おー、元気やったか?」
「あったり前や‼︎」
「金太郎さんは相変わらずやねえ。もー、か・わ・え・え♡」
「小春!勿論1番可愛いんは小春やで!」
「やだ、ユウくんたら!」
皆が楽しそうで、自然と笑顔になれた。
忍足先輩がいて、金色先輩に一氏先輩、千歳先輩と、石田先輩、小石川先輩。
「あれ?なあなあ、白石は?どないしたん?」
でも、白石先輩がいない。遠山くんも尚も「白石は?」と忍足先輩に聞いている。
「あー、白石はテニス部の打ち合わせがあるとかで呼ばれて、来れんなってん」
「えー‼︎ワイ、白石と試合したかったのに…」
「…金太郎はん、ならワシとするか?かまわんか、財前はん」
「もうメニューあってないようなモンですから。師範、お願いしてええですか」
「わかった。金太郎はん、あっちのコートで試合しよか」
「銀と試合やな⁈よーし、やるでえー‼︎」
最初は寂しがっていた遠山くんも、石田先輩と試合ができると聞いて元気がでたようで、コートの方に走って行った。
「ほなアタシ達も行こか」
「よっしゃ。今日は俺らのお笑いテニス、じっくり見せたろやないかい」
そのうち、他の先輩達もそれぞれ部員に話しかけて、練習を見てくれている。
私も何かする事はないかと財前くんに聞いたけれど、「今日は先輩達もおるし、見学しといたらええんちゃう」との事だった。
財前くんに教えてもらったベンチに座って、皆が練習している姿を見る。
手伝うとは言ったけれど、思えば、聞かないとできないのではただのお節介に終わってしまう。
「(色々、覚えないとな…。頑張ろう)」
「苗字」
「…あ!はい」
「そこのタオルとってくれへん」
「ええと…これかな?財前くん、どうぞ」
「…ん。ありがとさん」
タオルを渡すと、彼が隣に座る。流れる汗をタオルで拭くと、大きく息をついた。
「財前くんは凄いね。自分の練習もしながら、周りの皆のことも見てって、大変なのに」
「別に、凄くはないやろ」
「そんな事ない。素人目に見ても、誰でもできる事じゃないもの。それに、財前くんが頑張っているからそれが出来てるんじゃないかな」
「……。それでもまだ足りてへん。…あの人の後任とか、ハードル高すぎるし。ーせやけど、比べられる。負けるんとかも癪やし、あの人に追いついたろ思たら、これじゃアカン」
「財前くん…」
白石先輩は確かに凄い人だと思う。けど、白石先輩には先輩の、財前くんには財前くんの。それぞれのいい面があると思う。だったら、財前くんのオリジナルでいいんじゃないか。そう思うけど、簡単には言えない。
少なくとも今の私が言える言葉じゃなくて。
「あー、あっつ!ちょお、休憩や、休憩!」
声がした方を見ると、忍足先輩が制服をパタパタさせながら歩いてきて、一つ隣のベンチに座った。見ると彼も汗が流れ落ちている。
タオルを手に席を立つと、忍足先輩にそれを差し出した。
「忍足先輩、お疲れさまです。タオルどうぞ」
「お、ありがとうな!なんや苗字、マネージャーみたいやな」
「マネージャーではないですけど…テニス部の手伝いをさせてもらおうかと…」
「え⁈何それ、ホンマに?」
「はい」
「く〜マジか!なんや、俺らの時は女マネとかおらんかったのに!財前…お前は羨ましいヤツやなあ」
「おらんかったんは俺のせいちゃうし、苗字もマネージャーとはちゃいますよ」
「女の子がおるってことがそもそも贅沢やわ!」
「あー…はいはい。…せやけど、高校のテニス部こそマネージャーおるんちゃうんですか」
「ん?ああ、まあ…実はな。女マネええなあ…て毎日思っとるところや」
「へえ。なんや謙也さんが言うたらいやらしいですね」
「そうか?…て、どこがいやらしいねん!いやらしないわ!」
「連呼せんとってくれますか。恥ずかしいんで」
「お前がさせたんやろ…」
「人のせいにせんとってください」
「それに、あんな美人マネージャー、白石クラスやないと振り向いてもらえんちゅーねん」
「……」
美人マネージャー。その言葉が頭に残る。
「…あ。いや、その。変な意味ちゃうんやで」
「あ…はい。わかってますから」
「そうそう!白石は苗字にしか興味あらへんからな。…うん。大丈夫やて!」
何故か忍足先輩の様子が不自然だ。
「忍足先輩、どうかしたんですか?」
「いや、なんもせえへんで。…よっしゃ、休憩もしたし、練習戻るわ!」
「あ…はい。頑張ってくださいね」
「…俺も行きますわ」
「ん?おお、なら行こか」
「財前くんも、頑張ってね」
「ん。謙也さん、行きましょ」
コートへ戻って行く2人の背中を見ていると、以前のようだ。皆いて。楽しそうにテニスしてた。
白石先輩も、いて。
…ちょっと会えなかっただけで寂しいって感じたら駄目だ。高校でもテニスをするというのはそういう事だと、わかっていた事だから。それに、テニスをしている白石先輩が好きだから、大丈夫。
「…で、なんで謙也さんだけ来てるんですか?」
「ん?何や?」
「とぼけるん腹立つんでやめてくれますか」
「…な、なんやねん…」
「白石部長と同じテニス部でしょ。打ち合わせ行かんでよかったんですか」
「…あ〜、せやな……」
「言い訳考えるん、いりませんから」
「…別に、お前が知らんでもええ事やんか」
「じゃあ俺が知っててもええ事でもありますよね」
「…あー、もう、何なんやお前は。ぐいぐいくるけど。…苗字には言わんといてや。白石は別に何でもないし、いらん心配させんでもええんやから」
「わかってます」
「…白石な、さっきの美人マネージャーにめっちゃアプローチうけてんねん。打ち合わせも、なんや白石が今日予定ある言うても、半ば無理矢理連れて行かれてもうた」
「…へえ。そうやったんですか」
「白石は苗字が好きやから大丈夫やろけど、こんなん苗字が聞いたら不安になるやろ。やから、本気で言うたらあかんで」
「言いませんよ、そんなん」
「なら、ええけど」
「……あ、謙也さん。ちょっと練習付き合ってくれますか」
「ん?もちろんええで!」
「ありがとうございます」
「…なんやえらいお前にしては素直やん…」
「本気でしたい時は謙也さんが1番なんすわ。ちょっとぶつけても頑丈やし」
「イヤイヤ!なんやその理由…。…やっぱり財前は財前やわ…」
白石先輩とは、学校でこそ会えなくなったけれど、平日にはメールや電話をしたり、休日にはデートもする。
まだ"蔵"と呼ぶには慣れなくて、デートの時につい"白石先輩"と呼んでしまう事も、彼は「少しずつでええよ」と微笑んでくれた。
こんなに幸せだと、今一生分の運を使い切ってるんじゃないかとも思う。
「おーい、苗字、財前。ちょっとええか?」
放課後のチャイムがなると同時に、担任の渡邊先生に呼ばれた。一緒に呼ばれた財前くんとは、3年生にあがっても一緒のクラスになった。
先生に呼ばれても彼は未だ自分の席で、ノートに何かを書くのに集中している。もう一度先生が、「おーい財前、早よ来んと1コケシなくなるで〜」なんて言うと、彼は頭をカシ、と掻いてこちらに歩いてきた。
「お、来たな。よし!なら2人とも、1コケシやろう!」
「いりません。で、何ですか?…あ、練習メニューなら、まだ考え中ですわ」
「何や要らんのかい。相変わらず無愛想くんやなあ。なら苗字に財前の分までコケシやろうな。なんと2コケシやで、嬉しいやろ」
「…えっ⁈あ。ありがとうございます」
「うん、苗字は素直でええ子やわ」
「…俺忙しいんで、何もないなら」
「ちょいちょい!待ちや!そうやで、財前くん。忙しいんやろ?そんなお前にええ話…かもしれん。な、苗字」
話を振られても内容は知らない。どういう事だろう。
「とりあえず、財前。お前は一人で全部やろうとし過ぎな。もうちょい周りに頼らなあかんわ」
「…ほな、オサムちゃんに頼ればええ言う事ですかね」
「いや、俺は無理や」
「ですよね」
「…んんっ、兎に角やな、白石もそうやったけど、抱え込むタイプの部長には周りのサポートがいるんや」
…渡邊先生が言うのは、わかる気がする。
白石先輩も皆の為に様々なものを背負っていた。どんな時だって周りを見ていて、苦しいときでもそんな顔は見せない。
テニス部の仲間はそんな彼の事を知っているから、荷が少しでも軽くなるようにサポートしたりしていた。そして「仲間がいてくれたから、やってこれたんや」と彼は言っていた。
「そこでや。苗字、財前と仲がええみたいやし、テニス部のマネージャーしてくれんかなあ、なんてな。思たりして」
「…えっ⁈」
突然過ぎて、続ける言葉がでてこない。私より先に、隣の財前くんが口を開いた。
「まあ、忙しいんには変わりないですけど…マネージャーとかは、別に大丈夫ですわ」
「財前はそう言うやろ思たけど、苗字はどうや?」
「私は…マネージャーが務まる程テニスに詳しくはないし、逆に面倒をかけてしまいそうなので、正直自信はないです…」
「うーん…、そうか…」
「話終わりましたよね?なら、俺行きますんで」
そう言って先生に背中を向けた財前くんは、"いつも通り"だ。
財前くんは涼しい顔をして、本当にしんどい時は表面に出さないタイプじゃないかと思う。白石先輩と、一緒だ。
彼も部長になったばかりで大変なはずだ。遠山くんがいても、先輩達はいなくなってしまった。
以前は休み時間には音楽を聴いているかスマホと睨めっこだったのに、今はさっきのようにノートに何かを書いたり、疲れているのだろう寝てしまっていたりする。
クラスでは財前くんは面倒くさがり屋とか言われてるけど、部長になってから彼は変わった。
一生懸命、出来る以上の事を頑張っている。
そう思ったら、自然と口が動いていた。
「…でも、マネージャーみたいにはできないですけど、私でも手伝える事があるなら。少しでも…何かできればとは思います」
財前くんが足を止めて、こちらを振り返った。
「そんな無理せんでも「ホンマか!よっしゃ‼︎優しい苗字 には3コケシやろう!おお、やろう!」」
彼の言葉は先生の言葉に遮られて、「声大きすぎやろ」と、ちょっとご機嫌ナナメだ。
「財前、手伝ってもらったらどうや?な、そうしたらええ」
財前くんはこちらを見て何かを言おうとしたけれど、何も言わなかった。そして、ふう、と息をつくと呟いた。
「… 苗字がええんなら」
「よっしゃ!なら決まりや!ほな、2人とも頼むで〜」
先生はそう言って私達の肩をポンポンと叩くと、機嫌良く教室から出て行った。
「…ホンマに手伝いするつもりなん?」
「うん。どれだけ力になれるかわからないけど、私でできる事なら何でもするよ。それでちょっとでも財前くんの助けになれればいいなと。あ…その、出来るだけ面倒はかけないようにするから」
「そうやなくて」
「え?」
「……。…ほな、頼むわ」
「うん」
早速、テニス部に行くと、部員の皆に紹介してくれた。皆や遠山くんが歓迎してくれたのがなんだか嬉しくて、これから頑張ろうと思えてくる。
「ほな、今日の練習やけど」
そう言う財前くんの手には教室で何かを書いていたノートがあって、中の内容を読み上げる。
「ーあと、今日先輩らが来るみたいやから。以上」
卒業した先輩達。頻繁にではないが、先輩達が時間のある時はテニス部に顔をだしてくれる。
昨日白石先輩からメールがきていた事を思い出して、会えるのだと思うと胸がドキドキする。
練習を始めて少しすると、知った声が聞こえた。忍足先輩だ。
「皆、来たでー!」
「…また来たんすか」
「"また"って何や!そんなん言うてホンマは嬉しいんやろ?」
「………はあ」
「ため息!聞こえとるから!」
「来るんはええんですけど、もうちょい早めに連絡くださいよ」
「連絡なら入れたやんか」
「あー…きてましたね。こっちの練習始まる前に"今日皆で行くわ!"…その5分後に、"着いたで!"て。…いやいや、これはないでしょ」
「まあ、スピードスターやからな」
「褒めてないですけど」
賑やかだからか、部員達が集まってきた。皆、先輩達の姿を見て嬉しそうだ。特に、遠山くんなんて凄いスピードで走ってきて、忍足先輩に飛びついた。
「ケーンーヤー‼︎」
「金ちゃん!おー、元気やったか?」
「あったり前や‼︎」
「金太郎さんは相変わらずやねえ。もー、か・わ・え・え♡」
「小春!勿論1番可愛いんは小春やで!」
「やだ、ユウくんたら!」
皆が楽しそうで、自然と笑顔になれた。
忍足先輩がいて、金色先輩に一氏先輩、千歳先輩と、石田先輩、小石川先輩。
「あれ?なあなあ、白石は?どないしたん?」
でも、白石先輩がいない。遠山くんも尚も「白石は?」と忍足先輩に聞いている。
「あー、白石はテニス部の打ち合わせがあるとかで呼ばれて、来れんなってん」
「えー‼︎ワイ、白石と試合したかったのに…」
「…金太郎はん、ならワシとするか?かまわんか、財前はん」
「もうメニューあってないようなモンですから。師範、お願いしてええですか」
「わかった。金太郎はん、あっちのコートで試合しよか」
「銀と試合やな⁈よーし、やるでえー‼︎」
最初は寂しがっていた遠山くんも、石田先輩と試合ができると聞いて元気がでたようで、コートの方に走って行った。
「ほなアタシ達も行こか」
「よっしゃ。今日は俺らのお笑いテニス、じっくり見せたろやないかい」
そのうち、他の先輩達もそれぞれ部員に話しかけて、練習を見てくれている。
私も何かする事はないかと財前くんに聞いたけれど、「今日は先輩達もおるし、見学しといたらええんちゃう」との事だった。
財前くんに教えてもらったベンチに座って、皆が練習している姿を見る。
手伝うとは言ったけれど、思えば、聞かないとできないのではただのお節介に終わってしまう。
「(色々、覚えないとな…。頑張ろう)」
「苗字」
「…あ!はい」
「そこのタオルとってくれへん」
「ええと…これかな?財前くん、どうぞ」
「…ん。ありがとさん」
タオルを渡すと、彼が隣に座る。流れる汗をタオルで拭くと、大きく息をついた。
「財前くんは凄いね。自分の練習もしながら、周りの皆のことも見てって、大変なのに」
「別に、凄くはないやろ」
「そんな事ない。素人目に見ても、誰でもできる事じゃないもの。それに、財前くんが頑張っているからそれが出来てるんじゃないかな」
「……。それでもまだ足りてへん。…あの人の後任とか、ハードル高すぎるし。ーせやけど、比べられる。負けるんとかも癪やし、あの人に追いついたろ思たら、これじゃアカン」
「財前くん…」
白石先輩は確かに凄い人だと思う。けど、白石先輩には先輩の、財前くんには財前くんの。それぞれのいい面があると思う。だったら、財前くんのオリジナルでいいんじゃないか。そう思うけど、簡単には言えない。
少なくとも今の私が言える言葉じゃなくて。
「あー、あっつ!ちょお、休憩や、休憩!」
声がした方を見ると、忍足先輩が制服をパタパタさせながら歩いてきて、一つ隣のベンチに座った。見ると彼も汗が流れ落ちている。
タオルを手に席を立つと、忍足先輩にそれを差し出した。
「忍足先輩、お疲れさまです。タオルどうぞ」
「お、ありがとうな!なんや苗字、マネージャーみたいやな」
「マネージャーではないですけど…テニス部の手伝いをさせてもらおうかと…」
「え⁈何それ、ホンマに?」
「はい」
「く〜マジか!なんや、俺らの時は女マネとかおらんかったのに!財前…お前は羨ましいヤツやなあ」
「おらんかったんは俺のせいちゃうし、苗字もマネージャーとはちゃいますよ」
「女の子がおるってことがそもそも贅沢やわ!」
「あー…はいはい。…せやけど、高校のテニス部こそマネージャーおるんちゃうんですか」
「ん?ああ、まあ…実はな。女マネええなあ…て毎日思っとるところや」
「へえ。なんや謙也さんが言うたらいやらしいですね」
「そうか?…て、どこがいやらしいねん!いやらしないわ!」
「連呼せんとってくれますか。恥ずかしいんで」
「お前がさせたんやろ…」
「人のせいにせんとってください」
「それに、あんな美人マネージャー、白石クラスやないと振り向いてもらえんちゅーねん」
「……」
美人マネージャー。その言葉が頭に残る。
「…あ。いや、その。変な意味ちゃうんやで」
「あ…はい。わかってますから」
「そうそう!白石は苗字にしか興味あらへんからな。…うん。大丈夫やて!」
何故か忍足先輩の様子が不自然だ。
「忍足先輩、どうかしたんですか?」
「いや、なんもせえへんで。…よっしゃ、休憩もしたし、練習戻るわ!」
「あ…はい。頑張ってくださいね」
「…俺も行きますわ」
「ん?おお、なら行こか」
「財前くんも、頑張ってね」
「ん。謙也さん、行きましょ」
コートへ戻って行く2人の背中を見ていると、以前のようだ。皆いて。楽しそうにテニスしてた。
白石先輩も、いて。
…ちょっと会えなかっただけで寂しいって感じたら駄目だ。高校でもテニスをするというのはそういう事だと、わかっていた事だから。それに、テニスをしている白石先輩が好きだから、大丈夫。
「…で、なんで謙也さんだけ来てるんですか?」
「ん?何や?」
「とぼけるん腹立つんでやめてくれますか」
「…な、なんやねん…」
「白石部長と同じテニス部でしょ。打ち合わせ行かんでよかったんですか」
「…あ〜、せやな……」
「言い訳考えるん、いりませんから」
「…別に、お前が知らんでもええ事やんか」
「じゃあ俺が知っててもええ事でもありますよね」
「…あー、もう、何なんやお前は。ぐいぐいくるけど。…苗字には言わんといてや。白石は別に何でもないし、いらん心配させんでもええんやから」
「わかってます」
「…白石な、さっきの美人マネージャーにめっちゃアプローチうけてんねん。打ち合わせも、なんや白石が今日予定ある言うても、半ば無理矢理連れて行かれてもうた」
「…へえ。そうやったんですか」
「白石は苗字が好きやから大丈夫やろけど、こんなん苗字が聞いたら不安になるやろ。やから、本気で言うたらあかんで」
「言いませんよ、そんなん」
「なら、ええけど」
「……あ、謙也さん。ちょっと練習付き合ってくれますか」
「ん?もちろんええで!」
「ありがとうございます」
「…なんやえらいお前にしては素直やん…」
「本気でしたい時は謙也さんが1番なんすわ。ちょっとぶつけても頑丈やし」
「イヤイヤ!なんやその理由…。…やっぱり財前は財前やわ…」