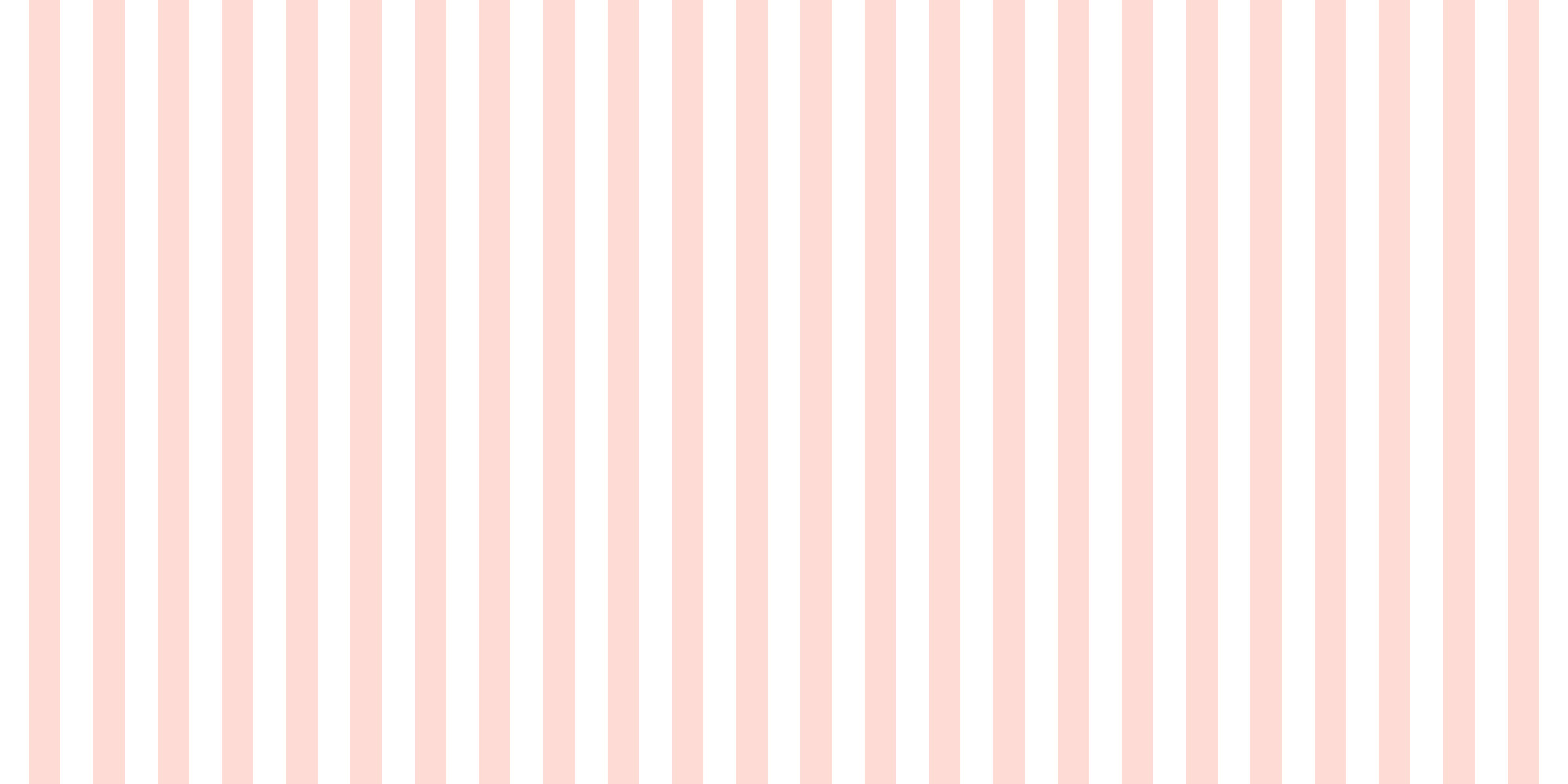twinkle days(白石vs財前/2年生)
name
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
「遅れてすんません」
部活が始まって暫くすると、財前が来た。
慌てることもなく、いつも通り怠そうに歩く。
「どないしたんや?もう部活始まってんで」
「すんません。はずせん用やったんで」
「そうか。せや、来て早々に悪いんやけど、早めに準備してやってくれるか?今日は謙也と組んでもらおうと思てたから、アイツあっちで痺れきらしとるんや」
「ー……部長」
「ん?なんや」
「俺、ちゃんと謝りましたから」
"謝る"で思い当たるのは一つだけだ。
「ー…俺にしとけばええのに、他に好きな奴おるらしいすわ」
「…え?」
「誰やと思います?」
「…財前は知っとるんか?」
「…聞くんはズルいんちゃいますか」
「そう、やな」
確かに、人伝いに聞くなんてナシだ。
でも、"好きな人がいる"。それだけで、頭を殴られたみたいにガンガンする。
「…部長でも動揺するんすね。面白いもん見れましたわ」
「そら…するやろ。俺を何やと思てんねん」
「…それに、おんなじ顔やし」
「何が」
「部長にも好きな奴おるって言ったときの顔とおんなじですわ」
「……え?」
「これ以上言うんはなんや腹たつんで、準備してきます」
「まだ、校舎におるんちゃいますか」
「ーーっ、財ぜ…「財前‼︎」」
そうしているうちに、財前を見つけた謙也がすごい速さで走ってきて。
「ちょ、遅いっちゅーねん!待ちくたびれたわ!はよ、練習するで〜」
「いやいや、来たばっかりなんですけど」
「ダブルスお前と組むんやから、そらちょっとでも時間惜しんで練習せなあかんやろ。俺らも一心同体っちゅー話や」
「…はあ。言いたいことはわかるんすけど、言い方がきもいっすわ」
「お前、先輩にきもいとか言い方っちゅーもんがあるやろ」
「あー、ハイハイ」
「ハイは1回で腹一杯や!」
そんな話をしながら、2人はこちらに背を向けて歩いて行く。
「ーー財前!謙也!ちょっと暫く抜けるわ!」
2人に向かって大きめの声で伝えると、ユニフォームのまま、校舎の方に走る。
放課後に財前の言うような話をする場所なんて限られとる。
校舎の裏とちゃう。
教室でもない。
「(ーー次)」
屋上に続く階段を駆け上ると、扉をあけた。
あけた瞬間、彼女がいた。
「ーーおった」
「えっ…白石先輩?どうしたんですか?」
彼女を目の前にすると、咄嗟に何も台詞がでてこなかった。越前くんとちゃうけど、自分もまだまだだな、と思う。
「先輩?」
「…ーあのな。苗字さんに言わなあかん事があるんや」
「…私、ですか?」
「…さっき財前と話したと思うんやけど…」
そう言うと、彼女は目を丸くした。
どうして話していた事を知っているのかと言うような表情だ。
「誤解されたなくて」
「誤解、ですか?」
「…あいつ、俺に好きな子おるって言うたやろ?」
「………、はい……」
「確かに好きな子はおるんや」
「…………」
「優しくて、面白い子なんやけど」
「ーおばあちゃんみたいな飴ちゃんばっかもってんねん。中学生がこのチョイスとか渋すぎてめっちゃおもろかったわ」
「ーあとは、おっちょこちょいでな。入学式で転んだ思たら、最近も結構派手にいっとったなあ…」
「……それって、」
「いつの間にか、心の中にその子がおって」
「いつの間にか、好きになっとった」
「ーー俺な。苗字さんの事が好きや。」
彼女は驚いた顔で何も言わずに固まっている。暫くすると自分の頬を手でつねり出したので、今度は自分がびっくりして、つねっていた手を取り、やめさせた。
「いやいや、アカンて!…ほら、赤くなってるわ…」
「ーーっ、ありえないって、私寝てるのかと思って…つねってみたんですけど…」
「どうやった?」
「痛かったです…」
「せやろ。それにありえないって…そんな事ないで」
「だって、白石先輩だから。私を好きになってくれるなんて想像もしないし、ー…ずっと、片想いでいいって思ってて…」
「…ずっと、片想い…してくれてたん?」
「あ…。…っ……はい…」
「ー…嬉しいわ。ありがとうな」
「ーでも、片思いじゃ足らへんみたいや」
手にとっていた彼女の手が熱い。いや、自分の手が熱いのかもしれない。
「これからは、"両思い"になってくれへんかな」
「俺と、付き合ってください」
彼女は真っ赤な顔をして俯いた後、また顔をあげるとはにかむように笑って。
「…私でよければ、よろしくお願いします…」
それを聞いて、身体が先に動いていた。
手をそっと引いて抱きしめると、シャンプーの香りがする。
「ーーありがとう。…あかん、めっちゃ嬉しいわ」
「…私もです」
「大切にする」
「ーー"名前"」
「っ…、はい」
「好きやで」
部活が始まって暫くすると、財前が来た。
慌てることもなく、いつも通り怠そうに歩く。
「どないしたんや?もう部活始まってんで」
「すんません。はずせん用やったんで」
「そうか。せや、来て早々に悪いんやけど、早めに準備してやってくれるか?今日は謙也と組んでもらおうと思てたから、アイツあっちで痺れきらしとるんや」
「ー……部長」
「ん?なんや」
「俺、ちゃんと謝りましたから」
"謝る"で思い当たるのは一つだけだ。
「ー…俺にしとけばええのに、他に好きな奴おるらしいすわ」
「…え?」
「誰やと思います?」
「…財前は知っとるんか?」
「…聞くんはズルいんちゃいますか」
「そう、やな」
確かに、人伝いに聞くなんてナシだ。
でも、"好きな人がいる"。それだけで、頭を殴られたみたいにガンガンする。
「…部長でも動揺するんすね。面白いもん見れましたわ」
「そら…するやろ。俺を何やと思てんねん」
「…それに、おんなじ顔やし」
「何が」
「部長にも好きな奴おるって言ったときの顔とおんなじですわ」
「……え?」
「これ以上言うんはなんや腹たつんで、準備してきます」
「まだ、校舎におるんちゃいますか」
「ーーっ、財ぜ…「財前‼︎」」
そうしているうちに、財前を見つけた謙也がすごい速さで走ってきて。
「ちょ、遅いっちゅーねん!待ちくたびれたわ!はよ、練習するで〜」
「いやいや、来たばっかりなんですけど」
「ダブルスお前と組むんやから、そらちょっとでも時間惜しんで練習せなあかんやろ。俺らも一心同体っちゅー話や」
「…はあ。言いたいことはわかるんすけど、言い方がきもいっすわ」
「お前、先輩にきもいとか言い方っちゅーもんがあるやろ」
「あー、ハイハイ」
「ハイは1回で腹一杯や!」
そんな話をしながら、2人はこちらに背を向けて歩いて行く。
「ーー財前!謙也!ちょっと暫く抜けるわ!」
2人に向かって大きめの声で伝えると、ユニフォームのまま、校舎の方に走る。
放課後に財前の言うような話をする場所なんて限られとる。
校舎の裏とちゃう。
教室でもない。
「(ーー次)」
屋上に続く階段を駆け上ると、扉をあけた。
あけた瞬間、彼女がいた。
「ーーおった」
「えっ…白石先輩?どうしたんですか?」
彼女を目の前にすると、咄嗟に何も台詞がでてこなかった。越前くんとちゃうけど、自分もまだまだだな、と思う。
「先輩?」
「…ーあのな。苗字さんに言わなあかん事があるんや」
「…私、ですか?」
「…さっき財前と話したと思うんやけど…」
そう言うと、彼女は目を丸くした。
どうして話していた事を知っているのかと言うような表情だ。
「誤解されたなくて」
「誤解、ですか?」
「…あいつ、俺に好きな子おるって言うたやろ?」
「………、はい……」
「確かに好きな子はおるんや」
「…………」
「優しくて、面白い子なんやけど」
「ーおばあちゃんみたいな飴ちゃんばっかもってんねん。中学生がこのチョイスとか渋すぎてめっちゃおもろかったわ」
「ーあとは、おっちょこちょいでな。入学式で転んだ思たら、最近も結構派手にいっとったなあ…」
「……それって、」
「いつの間にか、心の中にその子がおって」
「いつの間にか、好きになっとった」
「ーー俺な。苗字さんの事が好きや。」
彼女は驚いた顔で何も言わずに固まっている。暫くすると自分の頬を手でつねり出したので、今度は自分がびっくりして、つねっていた手を取り、やめさせた。
「いやいや、アカンて!…ほら、赤くなってるわ…」
「ーーっ、ありえないって、私寝てるのかと思って…つねってみたんですけど…」
「どうやった?」
「痛かったです…」
「せやろ。それにありえないって…そんな事ないで」
「だって、白石先輩だから。私を好きになってくれるなんて想像もしないし、ー…ずっと、片想いでいいって思ってて…」
「…ずっと、片想い…してくれてたん?」
「あ…。…っ……はい…」
「ー…嬉しいわ。ありがとうな」
「ーでも、片思いじゃ足らへんみたいや」
手にとっていた彼女の手が熱い。いや、自分の手が熱いのかもしれない。
「これからは、"両思い"になってくれへんかな」
「俺と、付き合ってください」
彼女は真っ赤な顔をして俯いた後、また顔をあげるとはにかむように笑って。
「…私でよければ、よろしくお願いします…」
それを聞いて、身体が先に動いていた。
手をそっと引いて抱きしめると、シャンプーの香りがする。
「ーーありがとう。…あかん、めっちゃ嬉しいわ」
「…私もです」
「大切にする」
「ーー"名前"」
「っ…、はい」
「好きやで」