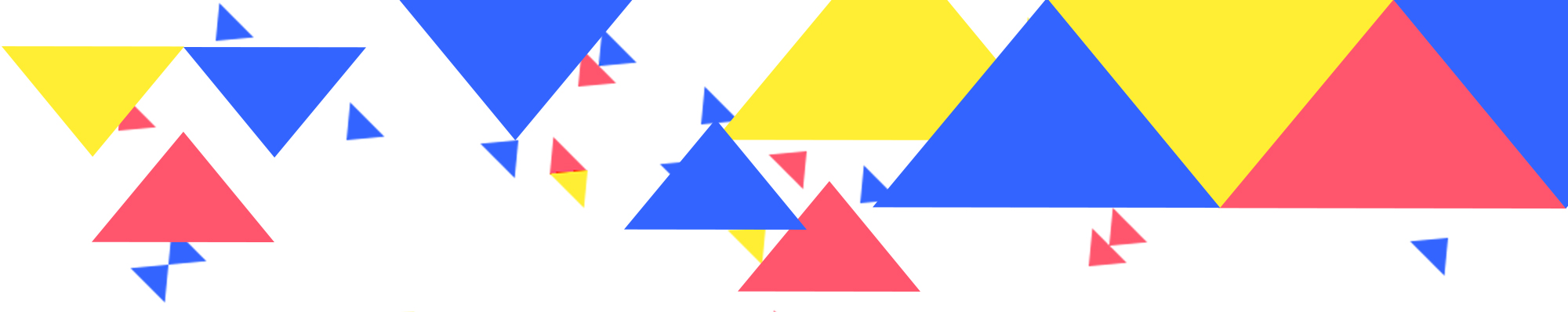Ver.1
たまには外食しないか、というダンテの誘いがあった。断る理由も無いので、バージルは了承した。かくして、双子は近くのカフェに足を向けたのだった。
「…昼食を摂りに来たものだと思っていたのだが?」
「ストロベリーサンデーが昼飯にならないなんて法律はないぜ、お兄ちゃん。」
テラス席で意気揚々と白と赤の山を頬張るダンテに、バージルが一言。そもそもダンテは食べ物にあまり執着しない。ストロベリーサンデーとピザが好物のようだが、実際はそれらが美味しいから食べているというより、ほかのものを食べようとするのが面倒だから、というあたりが妥当だろう。(もちろん好みの味だから、というのもあるだろうが。)他人の食物などどうでも良いと思っていたバージルでさえも、さすがに見かねる偏食ぶりだった。
「よくそんな砂糖の塊のようなものが胃に入るな。」
「あんたからしたら甘い物って全部そうだろ。」
軽く会話しながらバージルはクロックムッシュを齧る。ダンテの山は瞬く間に削られてゆき、あとは残り一口ほどになった当たりだろうか 。
「なんだよ、そんなに見つめて。」
何の気なしに食べる様子を見ていたバージルにダンテが気づいた。
「特に意味は無い。早く食ってしまえ。」
自分の分をすでに片付けたバージルは答える。しばしじっとバージルに目を向けていたダンテは、ふいに笑みを浮かべた。
「…ははん、分かった。…あんたもこれが欲しくなったんだろ。」
にやにやしながら確信を得たり、とさらに独りごちる様子のダンテに、すいとバージルは冷めた視線を贈る。先ほど砂糖の塊、と自ら形容したものが、どうして欲しくなるだろうか。それに甘い物自体あまりバージルの好むところではない。いつも事務所の中に絶えず立ち込めているクリームやバニラの匂いにさえ軽く胃もたれを起こしているというのに。まさかそれらを直に味わうなど、冗談も良いところだ。
「つまらんことを。いいから早く食え。」
「照れんなって、ほら、最後の一口あんたにやるよ。」
「違うと言っているだろう。」
額に手を当て露骨にうんざりとして見せても、ダンテは我関せずとばかりにスプーンで器の中の残りを掬って差し出す。本当に自分が欲しがっていると思っているのか、はたまたからかいの延長なのか。軽くバージルが苛立ち始めたことにも感心が無いようで、ダンテはあくまで楽しげに食べることを勧めてくる。その嫌味な程に邪気のない様子に、バージルの中のなにかがプツリと切れた。
「貸せ。」
ダンテの手からスプーンを取り上げ、望み通り口へ運んでやる。すでに溶けかかっていたそれはすぐにどろりと舌の上で形を無くし、不愉快な甘さを残してやろうと口の中にへばりついてくる。やはり飲み込めたものではないな、とバージルは思った。
…そうだとすれば、どう処理するのか。答えは一つしかない。
テーブルから身を乗り出し、目の前で様子を見ていたダンテの口へ己のそれを重ねた。きっと飛び退くだろうと踏んで彼の頭の後ろへ手をあてがい、逃げるに逃げられない状況を作る。冷えた舌で触れると、やけに相手の唇が熱く感じられた。
「ん…」
口が合わさると、ダンテは反射のように甘く鳴く。そのまま舌を差し込み唇を開かせてやり、自分も薄く口を開ける。そうすると、自ずから口の中のものが相手の口内へとろとろと流れ落ちる。一応、これはあくまでただの「口移し」。愛撫はしない。大人しく口の中のものが無くなるまでじっと待つ。しばらくそうしていると大方移し終えてしまった。予想とは裏腹に、ダンテは大人しく喉を鳴らしてバージルからの甘味を飲み下している。髪に指を差し込んで梳いてやると、重なっている口元が微かに笑んだ気がした。さて、もう終わったかとバージルが離れようとすれば、突然ダンテの舌が動いてぬるり、とバージルの口に入ってきた。そのまま舌同士が触れ合う。いつの間にかダンテの腕はバージルの首筋へと回っており、今度はこちらが囲われる形となっていた。まだ足りないとばかりに、じゅう、と吸われると、バージルの中の意地の悪い気がじわり、起き上がる。
「…お前、ここは家の中じゃない。」
もうすっかりその気になっているダンテに冷や水を浴びせるような声で囁くと、一瞬だけびくりと肩が跳ねた。視線をちらりと横に流して、周りを見るように促す。幸い隅の方の席で店舗の陰になっているとは言え、屋外は屋外。いくら目先のことだけのダンテと言えど、そこまで鈍くはない。先程からずっとこちらを見ていた女がそそくさと去っていったことも確認できたはずだ。
「…さんざん煽っといてそれはないだろ…。」
ダンテは体を椅子の背もたれに預けてバージルから離れた。その顔は明らかに拗ねた子供のそれだ。
「お前はもう少し、節度を持つということを学んだ方が良い。見られて減るものでもないが、気分が良いわけでもないだろう。」
「…じゃあ、家ならいいのか?」
多分に色を含んだ目が合う。諌められた直後だというのに、ダンテは頬杖をついて視線を投げかけてくる。どうあっても引かない、ともすれば子供じみた行動に、流石のバージルも苦笑した。もう駄々をこねていい歳はとっくの昔に過ぎているはずなのだが、それを可愛らしいと思ってしまう自分もきっと同罪なのだろう。
「ああ。好きなだけ、好きにすると良い。」
「…じゃ、早く帰ろうぜ。」
早々に席を立つダンテ。自分から連れ出したくせに、今度は早く帰ろうと急かしているという矛盾に気づいているのだろうか。やれやれとバージルは二度めの苦笑だ。
「家に着いたら、うがいなり歯を磨くなりしろ。そのままだと甘ったるくて敵わん。」
「げ、そういうこと言う?それ無粋って言うんだぜオニーチャン。」
もともと甘いものは苦手なのだ。顔をわかりやすくしかめて見せる片割れに、甘いのはお前自身だけで充分だと内心そっと呟いてみせた。
「…昼食を摂りに来たものだと思っていたのだが?」
「ストロベリーサンデーが昼飯にならないなんて法律はないぜ、お兄ちゃん。」
テラス席で意気揚々と白と赤の山を頬張るダンテに、バージルが一言。そもそもダンテは食べ物にあまり執着しない。ストロベリーサンデーとピザが好物のようだが、実際はそれらが美味しいから食べているというより、ほかのものを食べようとするのが面倒だから、というあたりが妥当だろう。(もちろん好みの味だから、というのもあるだろうが。)他人の食物などどうでも良いと思っていたバージルでさえも、さすがに見かねる偏食ぶりだった。
「よくそんな砂糖の塊のようなものが胃に入るな。」
「あんたからしたら甘い物って全部そうだろ。」
軽く会話しながらバージルはクロックムッシュを齧る。ダンテの山は瞬く間に削られてゆき、あとは残り一口ほどになった当たりだろうか 。
「なんだよ、そんなに見つめて。」
何の気なしに食べる様子を見ていたバージルにダンテが気づいた。
「特に意味は無い。早く食ってしまえ。」
自分の分をすでに片付けたバージルは答える。しばしじっとバージルに目を向けていたダンテは、ふいに笑みを浮かべた。
「…ははん、分かった。…あんたもこれが欲しくなったんだろ。」
にやにやしながら確信を得たり、とさらに独りごちる様子のダンテに、すいとバージルは冷めた視線を贈る。先ほど砂糖の塊、と自ら形容したものが、どうして欲しくなるだろうか。それに甘い物自体あまりバージルの好むところではない。いつも事務所の中に絶えず立ち込めているクリームやバニラの匂いにさえ軽く胃もたれを起こしているというのに。まさかそれらを直に味わうなど、冗談も良いところだ。
「つまらんことを。いいから早く食え。」
「照れんなって、ほら、最後の一口あんたにやるよ。」
「違うと言っているだろう。」
額に手を当て露骨にうんざりとして見せても、ダンテは我関せずとばかりにスプーンで器の中の残りを掬って差し出す。本当に自分が欲しがっていると思っているのか、はたまたからかいの延長なのか。軽くバージルが苛立ち始めたことにも感心が無いようで、ダンテはあくまで楽しげに食べることを勧めてくる。その嫌味な程に邪気のない様子に、バージルの中のなにかがプツリと切れた。
「貸せ。」
ダンテの手からスプーンを取り上げ、望み通り口へ運んでやる。すでに溶けかかっていたそれはすぐにどろりと舌の上で形を無くし、不愉快な甘さを残してやろうと口の中にへばりついてくる。やはり飲み込めたものではないな、とバージルは思った。
…そうだとすれば、どう処理するのか。答えは一つしかない。
テーブルから身を乗り出し、目の前で様子を見ていたダンテの口へ己のそれを重ねた。きっと飛び退くだろうと踏んで彼の頭の後ろへ手をあてがい、逃げるに逃げられない状況を作る。冷えた舌で触れると、やけに相手の唇が熱く感じられた。
「ん…」
口が合わさると、ダンテは反射のように甘く鳴く。そのまま舌を差し込み唇を開かせてやり、自分も薄く口を開ける。そうすると、自ずから口の中のものが相手の口内へとろとろと流れ落ちる。一応、これはあくまでただの「口移し」。愛撫はしない。大人しく口の中のものが無くなるまでじっと待つ。しばらくそうしていると大方移し終えてしまった。予想とは裏腹に、ダンテは大人しく喉を鳴らしてバージルからの甘味を飲み下している。髪に指を差し込んで梳いてやると、重なっている口元が微かに笑んだ気がした。さて、もう終わったかとバージルが離れようとすれば、突然ダンテの舌が動いてぬるり、とバージルの口に入ってきた。そのまま舌同士が触れ合う。いつの間にかダンテの腕はバージルの首筋へと回っており、今度はこちらが囲われる形となっていた。まだ足りないとばかりに、じゅう、と吸われると、バージルの中の意地の悪い気がじわり、起き上がる。
「…お前、ここは家の中じゃない。」
もうすっかりその気になっているダンテに冷や水を浴びせるような声で囁くと、一瞬だけびくりと肩が跳ねた。視線をちらりと横に流して、周りを見るように促す。幸い隅の方の席で店舗の陰になっているとは言え、屋外は屋外。いくら目先のことだけのダンテと言えど、そこまで鈍くはない。先程からずっとこちらを見ていた女がそそくさと去っていったことも確認できたはずだ。
「…さんざん煽っといてそれはないだろ…。」
ダンテは体を椅子の背もたれに預けてバージルから離れた。その顔は明らかに拗ねた子供のそれだ。
「お前はもう少し、節度を持つということを学んだ方が良い。見られて減るものでもないが、気分が良いわけでもないだろう。」
「…じゃあ、家ならいいのか?」
多分に色を含んだ目が合う。諌められた直後だというのに、ダンテは頬杖をついて視線を投げかけてくる。どうあっても引かない、ともすれば子供じみた行動に、流石のバージルも苦笑した。もう駄々をこねていい歳はとっくの昔に過ぎているはずなのだが、それを可愛らしいと思ってしまう自分もきっと同罪なのだろう。
「ああ。好きなだけ、好きにすると良い。」
「…じゃ、早く帰ろうぜ。」
早々に席を立つダンテ。自分から連れ出したくせに、今度は早く帰ろうと急かしているという矛盾に気づいているのだろうか。やれやれとバージルは二度めの苦笑だ。
「家に着いたら、うがいなり歯を磨くなりしろ。そのままだと甘ったるくて敵わん。」
「げ、そういうこと言う?それ無粋って言うんだぜオニーチャン。」
もともと甘いものは苦手なのだ。顔をわかりやすくしかめて見せる片割れに、甘いのはお前自身だけで充分だと内心そっと呟いてみせた。
1/1ページ