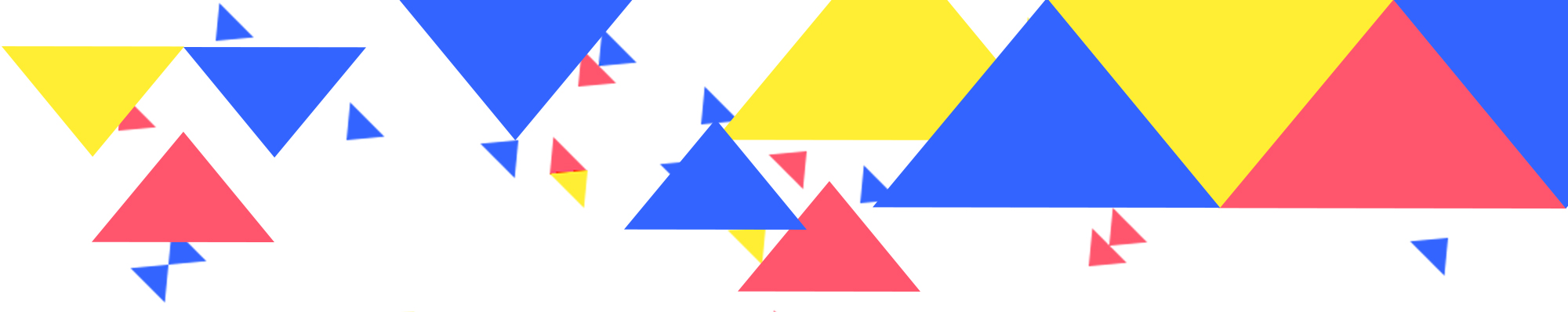A morning
ゆっくりと、真っ暗だった視界がぼやけ始める。意識はだいぶ前からあったものの、まぶたを持ち上げることすら億劫だった。それほどまでに昨夜は気力も体力も使い果たしたのだ。朝を告げる鋭い日差しはまだ掛かったままのカーテンによって中和され、目に心地よい程度の光が届く。起き抜けの気だるい体をゆるゆると動かすのは、朝に弱いダンテも案外好きだったりする。力を入れずに寝返りを打つと、シーツと一体化できるような錯覚に陥る。寝起きの火照った肌と冷たい布地が擦れて、とろとろに蕩けてしまいそうなくらいに気持ちがいい。独り寝の時はこのままだらだらと二度寝に持ち込むのがベターだ。が、生憎今朝は同伴者がいる。そんな貴重な時間を浪費するようなことは、いくら無精なダンテといえどできるはずはない。
「ん、おはよ、バージル」
己よりはやく目を覚ましてベッドの淵に腰を下ろしている片割れの傍に、シーツを伝い手を這わす。すると、当たり前のように自分のより少しだけ大きな手が重ねられた。双子の兄、バージルの体温は人のそれより低めだ。その手に温度の高い自分の肌をなぞられ包まれるのがたまらなく好きだとダンテは思う。肌と肌が直に触れ合うことで、伝わる思いもあるのだと彼に学ばされた。言葉少なに語るバージルは、誰よりも熱を秘めている。撫でて、なぞって、舐って、噛んで…。思い出される動きの一つ一つが熱く焦がれるよう。体温が低いのは彼の熱い熱い内面とバランスを取るためなのではないのだろうか。その点、静物のシーツなど目ではない。回らない頭で取り留めもなく思いを巡らせる。親指で爪先を弄られながら、その擽ったさ、ともすれば快感に繋がりかねない感覚にダンテはくふ、と鼻を鳴らす。
「爪が、伸びたな。」
バージルが呟く。元々官能的な声の持ち主なのだが、朝という時間帯特有の掠れ方がそれに一層磨きをかける。散々愛し合った後だというのに、この声にはどうも敏感に反応してしまう。
「っ、…そうだな。…切ってくれるか?オニーチャン。」
「ほざけ。一体お前はいくつだ。」
爪先から指の背を辿り、手の甲までくすぐってくる指を、ダンテがその触れられていた手で絡めとって甘える。すると微かに夜の雰囲気を察したバージルは軽くダンテの手の甲を抓った。つれないなと笑ってダンテはバージルににじり寄り、腰に腕を回して抱き着いた。色っぽい声音になってしまったと思うが一応、淫魔でもないので今すぐ夜に逆戻りしたい訳でも無い。これはダンテのある種厄介なクセのようなもので、自分でも知らず知らずのうちにやらかしてしまう。いつものようにそっけなく返され、なんだかなあ、と再び笑ってダンテは回す腕の力を強めた。つれない返答に一々めげていたらこの人物の恋人などやっていられない。恋愛とは精神力がものをいう。つくづく実感させられる。バージルはこれがデフォルトなだけで、自分に冷めたわけでも飽きたわけでもないことをダンテはよく知っていた。むしろある程度突き放された方が、こちらも誘惑のしがいがあるというものだ。甘えたい気分が尾を引いていたので、もぞもぞと体を起こしてぴったりと後ろから兄の背に体を重ねる。
「んー…」
ダンテより一足先にシャワーを済ませて一応の身だしなみを整えたバージルからは、ソープや、洗剤や、彼自身の匂いなどが複雑に混じった香りがする。もっと胸いっぱいに吸い込みたくて、肩口から前に腕を回し、すう、と深呼吸する。すると、
「…また煙草かよ、」
ダンテを幸せへ導いてくれる香りに混じって、煙たい邪魔な臭いが一つ。蕩けてぼやけた視界と嗅覚では捕えられなかったが、バージルは喫煙の真っ最中だったらしい。
「やはりバレたか…。」
くすくすと笑う声。そのどこか楽しげな声に反比例するかのようにダンテの機嫌はぐんぐん下がっていく。
「やめろって何回も言ってんのに、聞く耳持たねえよな、アンタ。」
むすくれてそのまま額を背にくっつける。煙草の煙たさと独特の眉間が痛くなるような臭いが嫌いだった。もっと言えば、そんなものにかまけてさっきから全くこちらを見ようともしないバージルの事も気に入らなかった。煙草は神経の塊のような兄を無心にするようで、彼は長く節ばった指で細いそれを挟み、空を見つめて深い息をする。元々読みづらい性格な上に、この間は余計に彼の考えが読めなくなる。構われたがりのダンテからしてみれば、煙草は恋人の関心を奪う恋敵にほかならないのだ。バージルが細く紫煙を吐く様は非常に魅力的だが、それとこれとは別の話。
「一応、臭いの少ないものを嗜んでいるつもりなのだがな。」
言い訳がましいバージルの言葉に、ダンテはそういう問題じゃない、と抗議の意を込めて彼のまだ新しい白いシャツの襟を人差し指で引っ掛けて下ろし、むき出しになった頚椎をがじがじと甘噛みする。
「お前もどうだ。」
ずい、と唐突につい今まで彼がかまけていた紙巻きが目の前に差し出される。げ、とダンテは内心顔をしかめた。…バージルは当然、ダンテが煙草の副流煙が苦手なだけでなくそれ自体嗜めないことを知っている。これは彼からの、結果をわかっていながらの意地の悪い誘いだ。何が面白いのか、ふとした時にこうして勧めてくる。煙で苦しがる弟を見て、彼は滅多に動かない口角を上げるのだ。ダンテは我が兄ながら、これはいかがなものか、と思う。そしてそういう時はもれなく手ずから勧められるものだから、いくら嫌いなものとは言えど無下にできない。相変わらず目線はかち合わないが、声音と雰囲気からバージルが薄く笑っているのがわかる。なんだか無性に悔しくなって、ちくしょうと心の中で悪態を一つ、いっきに口に咥える。フィルターの部分は、彼の唾液で少し湿っていた。
「……!?っ、は、げほっ…!おぇ…」
案の定、少し吸い込んだだけで盛大にむせる。気管の至るところが絞られるようだ。じわりと目の奥が熱を持ち、眼前が醜く歪む。せっかく良い気分で目覚めたのに、朝っぱらからなぜこんな目に遭わされなければならないのか。
「どうだ。」
「っ、は、さいっあく…アンタよくんなもん好き好んで吸えるよな。」
「まあな。」
嫌だと散々言っていることを、半ば強引にやらされたダンテの機嫌はさらに急降下し、底につこうとしていた。自他ともに認める気分屋なので、感情をコロコロと入れ替えるのは得意中の得意だ。さっきまでの良い気分など、すべて苛つきで帳消しにされた。そしてやはり、ダンテの気分が下がるとバージルのそれが上がるような仕組みになっているのか、彼の方からはこの上ないほど機嫌が良いのが伝わってくる。自分の行動が弟の気分の底をぶち破るには充分すぎるというのを、いい加減この悪魔的な兄は分かっているのだろうか。
「っとこの性悪が…。」
シャワーでも浴びて最高に悪い気分を文字通り水に流そうと、ダンテはバージルから離れてベッドを降りた。振り返ればきっと、薄い唇に悪役めいた笑みを載せて不敵にこちらを見つめる悪魔の姿があるだろう。
「まあ、待て。」
宥めるような声に呼び止められて振り返る。ほぼ反射のような自分の反応に、内心苦笑せざるを得ない。そのまま行くことも出来たが、その選択肢はダンテの頭の中には浮かばない。そういうふうに、一緒に居るうちに躾られてしまったようだ。バージルから呼ばれたならば必ず応える。選択の余地などはなから無いのと同然だ。だが、いくら己が好く躾られた弟だとはいえ、まだ不機嫌なのも事実。眉根を寄せてなんだ、と言外にその次を促す。情けないが、不機嫌を露骨に表すくらいがダンテのできる精一杯の抵抗だ。バージルが左手で再び煙草を口に運び、右手の人差し指をくい、くい、と2、3度。「来い」という意味らしい。どこまでも傲慢な態度。そしてダンテはそれに抗うことなく、ごく従順に、言われた通りに行動してしまう。まったく、これでは「Devil May Cry」の看板が泣いてしまうだろう。惚れた弱みとはつくづく怖い。
「はぁ…なんだよ、…っ!?」
綽々と座っているバージルの目の前に、嫌々来てやった雰囲気を醸しつつダンテが戻ってきたなら、いきなり片腕をぐいと強く引っ張られてバランスを崩した。その勢いをそのままにバージルが後ろへ倒れるので、ダンテも相手の身体に乗り上げる形でベッドへ倒れ込む。
「っおい、何しやがん…っ、」
急で少々荒っぽい行為に抗議しようとした唇は、もう一つのそれで塞がれて黙らされた。朝起きたばかりの霞がかった頭では理解が追いつかず、行動が遅れる。とっさに離れるためもがこうとしたが、時すでに遅し。首筋は広い手の平でがっちりと抑えられ、腰には腕が回っていた。
「…んっ、ふ、ぁ…!?」
舌先で強引にこじ開けらた唇から、口の中に何かが入り込んでくる。強烈な苦味とともに襲いかかってくるダンテの一等嫌う、煙たくて、頭のグラグラするような感覚。それは煙草の煙で間違いなかった。
「っ…、は、ん…」
なす術なく、バージルからの口付けを受け入れる。その間、彼の口内にあった煙の粒子は彼の舌と共に次々にダンテの唇から入ってきて舌を侵し、喉を刺激し通り過ぎていく。その感覚が不快で堪らないはずなのに、くちゅ、ちゅ、といやに響く水音がそれを認めさせない。貪られ、舐られ、徐々に快楽が引きずり出されていく。
「っぐ、かはっ…ぁ、や、…んぅ…っ」
今すぐ噎せて煙を追い出したいが食らいつく唇と舌で邪魔されて叶わず、熱烈なキスに溺れるにも鬱陶しい煙による喉の痛みと息が詰まるのとで叶わない。バージルは、ダンテがどこをどう扱われると悦ぶのかをよく理解している。舌を吸われ、上顎を舐め上げられるとぞくぞくと背中を甘い疼きが這い上がる。苦しい、気持ちいい、嫌だ、もっと…。相反する思考に何が何だかもう分からなくなって、体に力が入らなくなってくる。もはやなされるがまま。早くこの訳の分からない感覚から解放してくれ、救ってくれと強く望むのみ。ダンテは、もうどうにでもしろ、とぼんやりと思った。ベッドに突き立てるようにして体を支えていた両腕がくにゃりと力を失う。瞬間、ふわりとした浮遊感に襲われた。態勢が逆になったのだ。つまり、バージルが上、今度はダンテがシーツに沈む形となった。
「…げほ、げほっ、は…っあ、んたなぁ…っ…!」
一旦唇が離れたことでつかえが取れて、無理に抑え込まれていた咳が止まらなくなる。その不快感に腹が立ってきて、さすがに文句の一つでも言ってやろうと思った。が、息も絶え絶えに今更抗議しても迫力など皆無であろうし、見上げた相手の顔は、引っ込んだはずがまたもや出てきた涙のせいで輪郭が滲み、まともに捉えることすら出来ない。結局、ダンテは黙って体内に入り込んだ異物を追い出すことに専念するしかなかった。
「うっ、ぐ…かはっ、げほっ…くっ、…っ」
いつの間にか煙草を処分したバージルによって両手はシーツに縫とめられていたので、口を覆うことが出来ない。煙に弱って苦しがっているところをそのまま相手に晒すのが癪で、顔を横に背ける。どれくらいの間そうしていたのか、一分程度だったかもしれないし、一時間はかかったのかもしれない。大袈裟じゃなく、本当にそういう感覚だった。いずれにせよ、咳が治まる頃にはダンテはぐったりと疲れていた。酸素を求め、胸を上下させて喘ぐ弟を、兄はじっと見下ろす。
「っ、…はぁ。気は済んだかよ。」
一区切りついたところで、バージルを睨んで寄越す。すると、その目は青から赤に変わり、とろりと熱を孕んで確かな愛と欲とで己を見ている事に気がついた。
「はは、…」
ダンテは、ずるい、と思った。そんな目で見られては、もう怒るのも馬鹿らしくなってしまうではないか。
「…んだよ、いじめられてる俺ってそんなにかわいい?」
すっかり赤い瞳の熱さにあてられたダンテは背けていた顔を戻し、正面からバージルを見上げる。お互いの視線が絡み合い、徐々に熱が伝染していくのが分かる。バージルが右手を解放し頬に触れてきたので、ダンテは放された右手を相手の首に回した。
「愚問だな。」
口の端を釣り上げて、バージルが答えた。
「俺は可愛いと思ったものしか苛めない。」
頬を撫でられながらそんなことを囁かれたら、きっと誰だって陥落してしまう。言い渡された言葉の意味をじわりじわりと噛み締めながら、ダンテはいつの間にか手首から移動し絡んでいたもう片方の手指を、きゅっと握り笑った。
「ひでえ、じゃあ俺はずっとあんたにいじめられ続けるわけだ。」
「不満があるのか?」
「ねえよ、そういうことなら大歓迎だ。」
ちゅ、と音を立ててキスをする。こういったバージルのサド的な言動にときめいてしまうなど、自分も相当な物好きだとダンテは独りごちる。触れるだけだった唇をひと舐めしてやって、また目を合わせた。
「ふふ、バージル好きだぜ。愛してる。」
「ああ、俺も愛してるぞ、ダンテ。」
再び穏やかな気分が戻ってきて、さあ、起き上がろうとした途端、下腹部に不穏な気配を察知した。
「えっ、ちょ、なにしてんだよ!」
何も着ていない上半身を、バージルの手がするすると滑っていく。夜の名残でまだ敏感な腹のあたりを少し押しながら撫でられると、微かに甘い疼きが蘇ってくる。
「んっ、…やめろって、ほんと、その気になっちまうから…」
他でもないバージルからの愛撫だ。煽られないわけが無い。身をよじらせ止めるよう訴えると、しれっと当人から言葉が返ってきた。
「その気にさせるつもりだが?」
顔を見上げると、バージルは男のダンテからしてもゾッとするような色気を帯びていた。やられた、と思った。この顔のバージルからは、どうあがいても逃げられない。大人しく喰われる他ないのだ。完全に被食者の立場となってしまったダンテは、諦めと期待とがない交ぜの気分で笑う。
「…じゃあ、キスからもう一回。さっきみたいに苦いのはヤだぜ。とびきり甘いのにしてくれ。」
だが、喰われる側の愉しみもなかなかどうしてクセになるものだ。どうせ喰われるのなら、こちらも喰われるなりの楽しみ方をする方がいいに決まっている。ダンテはせいぜい食べ残さないようにな、と挑発も込めて、愛しい人の口に噛み付いた。
「ん、おはよ、バージル」
己よりはやく目を覚ましてベッドの淵に腰を下ろしている片割れの傍に、シーツを伝い手を這わす。すると、当たり前のように自分のより少しだけ大きな手が重ねられた。双子の兄、バージルの体温は人のそれより低めだ。その手に温度の高い自分の肌をなぞられ包まれるのがたまらなく好きだとダンテは思う。肌と肌が直に触れ合うことで、伝わる思いもあるのだと彼に学ばされた。言葉少なに語るバージルは、誰よりも熱を秘めている。撫でて、なぞって、舐って、噛んで…。思い出される動きの一つ一つが熱く焦がれるよう。体温が低いのは彼の熱い熱い内面とバランスを取るためなのではないのだろうか。その点、静物のシーツなど目ではない。回らない頭で取り留めもなく思いを巡らせる。親指で爪先を弄られながら、その擽ったさ、ともすれば快感に繋がりかねない感覚にダンテはくふ、と鼻を鳴らす。
「爪が、伸びたな。」
バージルが呟く。元々官能的な声の持ち主なのだが、朝という時間帯特有の掠れ方がそれに一層磨きをかける。散々愛し合った後だというのに、この声にはどうも敏感に反応してしまう。
「っ、…そうだな。…切ってくれるか?オニーチャン。」
「ほざけ。一体お前はいくつだ。」
爪先から指の背を辿り、手の甲までくすぐってくる指を、ダンテがその触れられていた手で絡めとって甘える。すると微かに夜の雰囲気を察したバージルは軽くダンテの手の甲を抓った。つれないなと笑ってダンテはバージルににじり寄り、腰に腕を回して抱き着いた。色っぽい声音になってしまったと思うが一応、淫魔でもないので今すぐ夜に逆戻りしたい訳でも無い。これはダンテのある種厄介なクセのようなもので、自分でも知らず知らずのうちにやらかしてしまう。いつものようにそっけなく返され、なんだかなあ、と再び笑ってダンテは回す腕の力を強めた。つれない返答に一々めげていたらこの人物の恋人などやっていられない。恋愛とは精神力がものをいう。つくづく実感させられる。バージルはこれがデフォルトなだけで、自分に冷めたわけでも飽きたわけでもないことをダンテはよく知っていた。むしろある程度突き放された方が、こちらも誘惑のしがいがあるというものだ。甘えたい気分が尾を引いていたので、もぞもぞと体を起こしてぴったりと後ろから兄の背に体を重ねる。
「んー…」
ダンテより一足先にシャワーを済ませて一応の身だしなみを整えたバージルからは、ソープや、洗剤や、彼自身の匂いなどが複雑に混じった香りがする。もっと胸いっぱいに吸い込みたくて、肩口から前に腕を回し、すう、と深呼吸する。すると、
「…また煙草かよ、」
ダンテを幸せへ導いてくれる香りに混じって、煙たい邪魔な臭いが一つ。蕩けてぼやけた視界と嗅覚では捕えられなかったが、バージルは喫煙の真っ最中だったらしい。
「やはりバレたか…。」
くすくすと笑う声。そのどこか楽しげな声に反比例するかのようにダンテの機嫌はぐんぐん下がっていく。
「やめろって何回も言ってんのに、聞く耳持たねえよな、アンタ。」
むすくれてそのまま額を背にくっつける。煙草の煙たさと独特の眉間が痛くなるような臭いが嫌いだった。もっと言えば、そんなものにかまけてさっきから全くこちらを見ようともしないバージルの事も気に入らなかった。煙草は神経の塊のような兄を無心にするようで、彼は長く節ばった指で細いそれを挟み、空を見つめて深い息をする。元々読みづらい性格な上に、この間は余計に彼の考えが読めなくなる。構われたがりのダンテからしてみれば、煙草は恋人の関心を奪う恋敵にほかならないのだ。バージルが細く紫煙を吐く様は非常に魅力的だが、それとこれとは別の話。
「一応、臭いの少ないものを嗜んでいるつもりなのだがな。」
言い訳がましいバージルの言葉に、ダンテはそういう問題じゃない、と抗議の意を込めて彼のまだ新しい白いシャツの襟を人差し指で引っ掛けて下ろし、むき出しになった頚椎をがじがじと甘噛みする。
「お前もどうだ。」
ずい、と唐突につい今まで彼がかまけていた紙巻きが目の前に差し出される。げ、とダンテは内心顔をしかめた。…バージルは当然、ダンテが煙草の副流煙が苦手なだけでなくそれ自体嗜めないことを知っている。これは彼からの、結果をわかっていながらの意地の悪い誘いだ。何が面白いのか、ふとした時にこうして勧めてくる。煙で苦しがる弟を見て、彼は滅多に動かない口角を上げるのだ。ダンテは我が兄ながら、これはいかがなものか、と思う。そしてそういう時はもれなく手ずから勧められるものだから、いくら嫌いなものとは言えど無下にできない。相変わらず目線はかち合わないが、声音と雰囲気からバージルが薄く笑っているのがわかる。なんだか無性に悔しくなって、ちくしょうと心の中で悪態を一つ、いっきに口に咥える。フィルターの部分は、彼の唾液で少し湿っていた。
「……!?っ、は、げほっ…!おぇ…」
案の定、少し吸い込んだだけで盛大にむせる。気管の至るところが絞られるようだ。じわりと目の奥が熱を持ち、眼前が醜く歪む。せっかく良い気分で目覚めたのに、朝っぱらからなぜこんな目に遭わされなければならないのか。
「どうだ。」
「っ、は、さいっあく…アンタよくんなもん好き好んで吸えるよな。」
「まあな。」
嫌だと散々言っていることを、半ば強引にやらされたダンテの機嫌はさらに急降下し、底につこうとしていた。自他ともに認める気分屋なので、感情をコロコロと入れ替えるのは得意中の得意だ。さっきまでの良い気分など、すべて苛つきで帳消しにされた。そしてやはり、ダンテの気分が下がるとバージルのそれが上がるような仕組みになっているのか、彼の方からはこの上ないほど機嫌が良いのが伝わってくる。自分の行動が弟の気分の底をぶち破るには充分すぎるというのを、いい加減この悪魔的な兄は分かっているのだろうか。
「っとこの性悪が…。」
シャワーでも浴びて最高に悪い気分を文字通り水に流そうと、ダンテはバージルから離れてベッドを降りた。振り返ればきっと、薄い唇に悪役めいた笑みを載せて不敵にこちらを見つめる悪魔の姿があるだろう。
「まあ、待て。」
宥めるような声に呼び止められて振り返る。ほぼ反射のような自分の反応に、内心苦笑せざるを得ない。そのまま行くことも出来たが、その選択肢はダンテの頭の中には浮かばない。そういうふうに、一緒に居るうちに躾られてしまったようだ。バージルから呼ばれたならば必ず応える。選択の余地などはなから無いのと同然だ。だが、いくら己が好く躾られた弟だとはいえ、まだ不機嫌なのも事実。眉根を寄せてなんだ、と言外にその次を促す。情けないが、不機嫌を露骨に表すくらいがダンテのできる精一杯の抵抗だ。バージルが左手で再び煙草を口に運び、右手の人差し指をくい、くい、と2、3度。「来い」という意味らしい。どこまでも傲慢な態度。そしてダンテはそれに抗うことなく、ごく従順に、言われた通りに行動してしまう。まったく、これでは「Devil May Cry」の看板が泣いてしまうだろう。惚れた弱みとはつくづく怖い。
「はぁ…なんだよ、…っ!?」
綽々と座っているバージルの目の前に、嫌々来てやった雰囲気を醸しつつダンテが戻ってきたなら、いきなり片腕をぐいと強く引っ張られてバランスを崩した。その勢いをそのままにバージルが後ろへ倒れるので、ダンテも相手の身体に乗り上げる形でベッドへ倒れ込む。
「っおい、何しやがん…っ、」
急で少々荒っぽい行為に抗議しようとした唇は、もう一つのそれで塞がれて黙らされた。朝起きたばかりの霞がかった頭では理解が追いつかず、行動が遅れる。とっさに離れるためもがこうとしたが、時すでに遅し。首筋は広い手の平でがっちりと抑えられ、腰には腕が回っていた。
「…んっ、ふ、ぁ…!?」
舌先で強引にこじ開けらた唇から、口の中に何かが入り込んでくる。強烈な苦味とともに襲いかかってくるダンテの一等嫌う、煙たくて、頭のグラグラするような感覚。それは煙草の煙で間違いなかった。
「っ…、は、ん…」
なす術なく、バージルからの口付けを受け入れる。その間、彼の口内にあった煙の粒子は彼の舌と共に次々にダンテの唇から入ってきて舌を侵し、喉を刺激し通り過ぎていく。その感覚が不快で堪らないはずなのに、くちゅ、ちゅ、といやに響く水音がそれを認めさせない。貪られ、舐られ、徐々に快楽が引きずり出されていく。
「っぐ、かはっ…ぁ、や、…んぅ…っ」
今すぐ噎せて煙を追い出したいが食らいつく唇と舌で邪魔されて叶わず、熱烈なキスに溺れるにも鬱陶しい煙による喉の痛みと息が詰まるのとで叶わない。バージルは、ダンテがどこをどう扱われると悦ぶのかをよく理解している。舌を吸われ、上顎を舐め上げられるとぞくぞくと背中を甘い疼きが這い上がる。苦しい、気持ちいい、嫌だ、もっと…。相反する思考に何が何だかもう分からなくなって、体に力が入らなくなってくる。もはやなされるがまま。早くこの訳の分からない感覚から解放してくれ、救ってくれと強く望むのみ。ダンテは、もうどうにでもしろ、とぼんやりと思った。ベッドに突き立てるようにして体を支えていた両腕がくにゃりと力を失う。瞬間、ふわりとした浮遊感に襲われた。態勢が逆になったのだ。つまり、バージルが上、今度はダンテがシーツに沈む形となった。
「…げほ、げほっ、は…っあ、んたなぁ…っ…!」
一旦唇が離れたことでつかえが取れて、無理に抑え込まれていた咳が止まらなくなる。その不快感に腹が立ってきて、さすがに文句の一つでも言ってやろうと思った。が、息も絶え絶えに今更抗議しても迫力など皆無であろうし、見上げた相手の顔は、引っ込んだはずがまたもや出てきた涙のせいで輪郭が滲み、まともに捉えることすら出来ない。結局、ダンテは黙って体内に入り込んだ異物を追い出すことに専念するしかなかった。
「うっ、ぐ…かはっ、げほっ…くっ、…っ」
いつの間にか煙草を処分したバージルによって両手はシーツに縫とめられていたので、口を覆うことが出来ない。煙に弱って苦しがっているところをそのまま相手に晒すのが癪で、顔を横に背ける。どれくらいの間そうしていたのか、一分程度だったかもしれないし、一時間はかかったのかもしれない。大袈裟じゃなく、本当にそういう感覚だった。いずれにせよ、咳が治まる頃にはダンテはぐったりと疲れていた。酸素を求め、胸を上下させて喘ぐ弟を、兄はじっと見下ろす。
「っ、…はぁ。気は済んだかよ。」
一区切りついたところで、バージルを睨んで寄越す。すると、その目は青から赤に変わり、とろりと熱を孕んで確かな愛と欲とで己を見ている事に気がついた。
「はは、…」
ダンテは、ずるい、と思った。そんな目で見られては、もう怒るのも馬鹿らしくなってしまうではないか。
「…んだよ、いじめられてる俺ってそんなにかわいい?」
すっかり赤い瞳の熱さにあてられたダンテは背けていた顔を戻し、正面からバージルを見上げる。お互いの視線が絡み合い、徐々に熱が伝染していくのが分かる。バージルが右手を解放し頬に触れてきたので、ダンテは放された右手を相手の首に回した。
「愚問だな。」
口の端を釣り上げて、バージルが答えた。
「俺は可愛いと思ったものしか苛めない。」
頬を撫でられながらそんなことを囁かれたら、きっと誰だって陥落してしまう。言い渡された言葉の意味をじわりじわりと噛み締めながら、ダンテはいつの間にか手首から移動し絡んでいたもう片方の手指を、きゅっと握り笑った。
「ひでえ、じゃあ俺はずっとあんたにいじめられ続けるわけだ。」
「不満があるのか?」
「ねえよ、そういうことなら大歓迎だ。」
ちゅ、と音を立ててキスをする。こういったバージルのサド的な言動にときめいてしまうなど、自分も相当な物好きだとダンテは独りごちる。触れるだけだった唇をひと舐めしてやって、また目を合わせた。
「ふふ、バージル好きだぜ。愛してる。」
「ああ、俺も愛してるぞ、ダンテ。」
再び穏やかな気分が戻ってきて、さあ、起き上がろうとした途端、下腹部に不穏な気配を察知した。
「えっ、ちょ、なにしてんだよ!」
何も着ていない上半身を、バージルの手がするすると滑っていく。夜の名残でまだ敏感な腹のあたりを少し押しながら撫でられると、微かに甘い疼きが蘇ってくる。
「んっ、…やめろって、ほんと、その気になっちまうから…」
他でもないバージルからの愛撫だ。煽られないわけが無い。身をよじらせ止めるよう訴えると、しれっと当人から言葉が返ってきた。
「その気にさせるつもりだが?」
顔を見上げると、バージルは男のダンテからしてもゾッとするような色気を帯びていた。やられた、と思った。この顔のバージルからは、どうあがいても逃げられない。大人しく喰われる他ないのだ。完全に被食者の立場となってしまったダンテは、諦めと期待とがない交ぜの気分で笑う。
「…じゃあ、キスからもう一回。さっきみたいに苦いのはヤだぜ。とびきり甘いのにしてくれ。」
だが、喰われる側の愉しみもなかなかどうしてクセになるものだ。どうせ喰われるのなら、こちらも喰われるなりの楽しみ方をする方がいいに決まっている。ダンテはせいぜい食べ残さないようにな、と挑発も込めて、愛しい人の口に噛み付いた。
1/1ページ