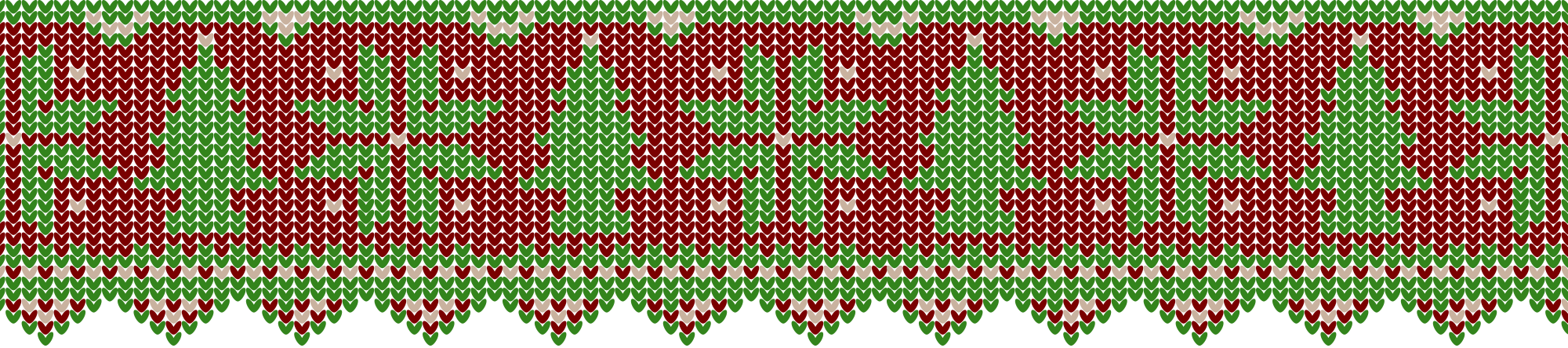情熱スキャンダル
明日、休み取ってます
恋人に耳元で囁かれ、赤井は俄然張り切った。
一度、デートがキャンセルされた後、今日の待ち合わせも恋人の都合で時間が遅らされたものだから、多分、埋め合わせのつもりでそう言ったのだろう。
待てをさせられた哀れな恋人へのご褒美だ。
それは分かっている。
「明日は、ずっと離れないで過ごしたいな」
だが、そんな台詞を可愛い素振りで言われては、たまった物じゃない。
赤井は、疲れて帰ってきた恋人を風呂に入れてやり頭から爪先まで泡だらけにして洗い、ホカホカの彼にちょっとした食事を用意して、それを手ずから食べさせると、すぐに自分の寝床に連れ込んだ。
「ずっと、放っておいてごめん」
恋人の降谷が申し訳なさそうに謝った。
デートのキャンセルが二週間前。その前も三週間会えなかった。もう、かれこれ一ヶ月以上も、会えなかったのだ。
赤井は痛感した。
好きな子に会えないのは、本当につまらない。本当に面白くない。本当に、寂しいと。
「会いたかった」
赤井が言いたかった言葉は、降谷が言った。
「俺もだよ」
こっちの方が会いたかった。こっちの方が飢えてる。こんなに放っておくなんて、なんて意地悪なんだ。
赤井は、格好付けの大人なので、そんなことは言わない。
代わりに恭しくキスして、疲れた降谷の頬を撫でる。
「愛してるよ」
そして、愛の言葉を捧げた。
会えたのが久しぶりだから、その夜は随分と燃え上がった。何が燃え上がったのかと言えば、色々と言いようがあるが、強いて言うなら愛だろう。
降谷は疲れているだろうにギラギラしていて、即物的に赤井の性器に触れたがったし、前戯もそこそこに挿入をねだった。会えなかった寂しさから甘えているのか、ただの疲れナントカかは分からないが、悪い気はしなかった。
散々に抱いてから、明日が休みなら、二人で出かけたかっただろうか。なんて気が付いた。その時には、もう降谷は手も足もぐったりして動かせない状態だった。
「降谷くん、降谷くん」
何度か呼びかけても眠そうにぐずるので、赤井はまた降谷を風呂に入れてやって、清潔なシーツのベッドに寝かした。
降谷のお世話なんて、させてもらえた事がなかったから、新鮮な経験だった。
安らかな寝顔を眺めてから、赤井も目を閉じた。
「放っておかれたことなんて、怒ってないさ」
眠る耳元に囁いて、己も深い眠りに就いた。
ガチャ
ドアの音で目を覚ます。
「…降谷くん?」
寝起きで声は掠れた。
「あ、起きなくていいです。まだ寝てて」
目をこじ開けて見れば、降谷がスーツ姿で部屋を出ていく所だった。
「どこに行くんだ?」
「ちょっと、呼び出しが。いえ、すぐに戻りますから。本当に」
「君、今日は休みだと」
「ちょっとだけ仕事して、すぐに戻りますから」
降谷はごめんと手を合わせて困り顔になった。
ベッドサイドの時計は、まだ朝の七時前だ。
「正気か?」
「すみません」
思わず出た呟きに謝罪で返された。
責めたいわけではなかった。
降谷は忙しい男だと知っていて付き合っている。その男が仕事以外の時間の全てを捧げてくれているのも分かっている。
時間だけじゃ無い。不器用な愛や、細やかな気遣いや、無防備な身体も、赤井に捧げてくれている。
こっそり出て行こうとしたのは、赤井を起こさずに、あわよくば寝ている間に戻ってこようとしたのだろう。
そういう奇妙な気遣いをする男なのだ。
「送るよ」
だが、赤井の方は、恋人には甘えて欲しいと思う男だった。
「え、いいです。自分で行けます」
「いや、昨日は、君がトぶまで抱いてしまったから、体が辛いだろ?」
「え!いや…そんな。うん、平気、です」
長く付き合って、お互いに足の裏まで知り尽くした仲なのに、降谷は昨夜の性行為への言及には恥じらった。
「本当に?」
「ちょっと怠いけど、平気です」
「踏ん張りが効かないだろ?ずっと突っ込んでたから、腰が怠い筈だ」
「つ…ごほん。でも、現場に出るわけでは無いので、平気」
頬を真っ赤にして、俯く。
それから、降谷はこそっと呟いた。
「昨日は、貴方に会いたくて、ちょっと急ぎ過ぎちゃったんです。書類が足りないって連絡が来て…。周りに迷惑を掛けてしまいました」
降谷がそんなミスをしたと聞くのは初めてだった。普段の彼ときたら、痺れる程にできる男なのだ。
赤井はベッドから起き出し、降谷を抱きしめた。
「俺を待たせてるから焦った?」
「会いたくてって言いました。貴方のせいじゃない」
「本当に?そんなに会いたかった?」
「だから、早く終わらせて、貴方のベッドに戻りたいんです」
引き留めないでくれという言葉とは裏腹に、降谷の手は赤井の背中をぎゅっと抱き返した。
離れ難いのは、お互い様だ。
やっぱり、無茶してでも、もっと早く会いに行けば良かった。
赤井は大人しく待てをさせられていた自分を後悔した。
誰に咎められても、降谷本人に叱られても、会いに行って、攫ってしまえばよかった。
ほんの一時間でも、顔を見て触れ合って、キスして抱き合えたなら、それだけで満たさせる。他の瑣末なごたごたなんて、気にもならないだろう。
「やっぱり送らせてくれ。そのまま、待ってるから」
赤井は腕の中の降谷の前髪を撫でつつ、言った。
「貴方を待たせるなんて」
降谷は赤井のことをスーパースターか何にかだと思っているのか、何よりその時間を使わせることには慎重なのだ。
「少しでも側に居たいのさ、健気な犬だからな」
けれども、赤井はスターではなく忠実な獣なので、自分の自由な時間くらいは愛に捧げたい。
「本当に?」
「あぁ、許してくれるなら、君のオフィスにも付き従って行きたい」
「それは、ダメ」
降谷はそれを冗談だと受け止めて、面白そうに笑った。
でも、本当にそうしたい。
不都合や偏見や、妬みややっかみや。降谷の周りには敵ばかりだ。
「君の近くに居たいんだ」
降谷は強い。でも、それでも、赤井は彼に降り注ぐ火の粉や矢を振り払ってやりたい。
「じゃあ、お願いしようかな」
「任せてくれ。一時間後には、君をこのベッドに戻してあげよう」
そのまま肩を抱いて降谷を玄関へエスコートする。
ピタ
降谷は足を止めた。
「あ、ちゃんとシャツを着てください」
それから、上半身裸のままの赤井の胸をつついたのだった。
「おっと」
「他の誰かに裸を見せるなんて、嫉妬させたいんですか?」
「いいね、情熱的だ」
「ふふ」
降谷は艶っぽく笑って赤井の胸元にしなだれかかった。
「僕の情熱はそんなもんじゃないですよ。会えなかった分の愛が暴れ回ってるんですから」
頬を染め、じっと赤井を見つめる目には燃えるような情が込められていた。
昨日、赤井が燃やした例の愛という奴だ。
「ふむ、昨日はがっつき過ぎたと反省していたんだが」
会えない時間に情を募らせていたのはお互い様か。
赤井は遠慮なく降谷にキスした。
おはようのキスか、行ってらっしゃいのキスか。どちらにしても、朝から情熱的なことに変わり無い。
赤井は決意した。
降谷が怒ろうと、職場で問題になろうと、二人の仲は公にしてしまおうと。
手始めに、やはり、今朝は、彼のオフィスまでエスコートしてしまおう。
赤井は密かに決意したのであった。
恋人に耳元で囁かれ、赤井は俄然張り切った。
一度、デートがキャンセルされた後、今日の待ち合わせも恋人の都合で時間が遅らされたものだから、多分、埋め合わせのつもりでそう言ったのだろう。
待てをさせられた哀れな恋人へのご褒美だ。
それは分かっている。
「明日は、ずっと離れないで過ごしたいな」
だが、そんな台詞を可愛い素振りで言われては、たまった物じゃない。
赤井は、疲れて帰ってきた恋人を風呂に入れてやり頭から爪先まで泡だらけにして洗い、ホカホカの彼にちょっとした食事を用意して、それを手ずから食べさせると、すぐに自分の寝床に連れ込んだ。
「ずっと、放っておいてごめん」
恋人の降谷が申し訳なさそうに謝った。
デートのキャンセルが二週間前。その前も三週間会えなかった。もう、かれこれ一ヶ月以上も、会えなかったのだ。
赤井は痛感した。
好きな子に会えないのは、本当につまらない。本当に面白くない。本当に、寂しいと。
「会いたかった」
赤井が言いたかった言葉は、降谷が言った。
「俺もだよ」
こっちの方が会いたかった。こっちの方が飢えてる。こんなに放っておくなんて、なんて意地悪なんだ。
赤井は、格好付けの大人なので、そんなことは言わない。
代わりに恭しくキスして、疲れた降谷の頬を撫でる。
「愛してるよ」
そして、愛の言葉を捧げた。
会えたのが久しぶりだから、その夜は随分と燃え上がった。何が燃え上がったのかと言えば、色々と言いようがあるが、強いて言うなら愛だろう。
降谷は疲れているだろうにギラギラしていて、即物的に赤井の性器に触れたがったし、前戯もそこそこに挿入をねだった。会えなかった寂しさから甘えているのか、ただの疲れナントカかは分からないが、悪い気はしなかった。
散々に抱いてから、明日が休みなら、二人で出かけたかっただろうか。なんて気が付いた。その時には、もう降谷は手も足もぐったりして動かせない状態だった。
「降谷くん、降谷くん」
何度か呼びかけても眠そうにぐずるので、赤井はまた降谷を風呂に入れてやって、清潔なシーツのベッドに寝かした。
降谷のお世話なんて、させてもらえた事がなかったから、新鮮な経験だった。
安らかな寝顔を眺めてから、赤井も目を閉じた。
「放っておかれたことなんて、怒ってないさ」
眠る耳元に囁いて、己も深い眠りに就いた。
ガチャ
ドアの音で目を覚ます。
「…降谷くん?」
寝起きで声は掠れた。
「あ、起きなくていいです。まだ寝てて」
目をこじ開けて見れば、降谷がスーツ姿で部屋を出ていく所だった。
「どこに行くんだ?」
「ちょっと、呼び出しが。いえ、すぐに戻りますから。本当に」
「君、今日は休みだと」
「ちょっとだけ仕事して、すぐに戻りますから」
降谷はごめんと手を合わせて困り顔になった。
ベッドサイドの時計は、まだ朝の七時前だ。
「正気か?」
「すみません」
思わず出た呟きに謝罪で返された。
責めたいわけではなかった。
降谷は忙しい男だと知っていて付き合っている。その男が仕事以外の時間の全てを捧げてくれているのも分かっている。
時間だけじゃ無い。不器用な愛や、細やかな気遣いや、無防備な身体も、赤井に捧げてくれている。
こっそり出て行こうとしたのは、赤井を起こさずに、あわよくば寝ている間に戻ってこようとしたのだろう。
そういう奇妙な気遣いをする男なのだ。
「送るよ」
だが、赤井の方は、恋人には甘えて欲しいと思う男だった。
「え、いいです。自分で行けます」
「いや、昨日は、君がトぶまで抱いてしまったから、体が辛いだろ?」
「え!いや…そんな。うん、平気、です」
長く付き合って、お互いに足の裏まで知り尽くした仲なのに、降谷は昨夜の性行為への言及には恥じらった。
「本当に?」
「ちょっと怠いけど、平気です」
「踏ん張りが効かないだろ?ずっと突っ込んでたから、腰が怠い筈だ」
「つ…ごほん。でも、現場に出るわけでは無いので、平気」
頬を真っ赤にして、俯く。
それから、降谷はこそっと呟いた。
「昨日は、貴方に会いたくて、ちょっと急ぎ過ぎちゃったんです。書類が足りないって連絡が来て…。周りに迷惑を掛けてしまいました」
降谷がそんなミスをしたと聞くのは初めてだった。普段の彼ときたら、痺れる程にできる男なのだ。
赤井はベッドから起き出し、降谷を抱きしめた。
「俺を待たせてるから焦った?」
「会いたくてって言いました。貴方のせいじゃない」
「本当に?そんなに会いたかった?」
「だから、早く終わらせて、貴方のベッドに戻りたいんです」
引き留めないでくれという言葉とは裏腹に、降谷の手は赤井の背中をぎゅっと抱き返した。
離れ難いのは、お互い様だ。
やっぱり、無茶してでも、もっと早く会いに行けば良かった。
赤井は大人しく待てをさせられていた自分を後悔した。
誰に咎められても、降谷本人に叱られても、会いに行って、攫ってしまえばよかった。
ほんの一時間でも、顔を見て触れ合って、キスして抱き合えたなら、それだけで満たさせる。他の瑣末なごたごたなんて、気にもならないだろう。
「やっぱり送らせてくれ。そのまま、待ってるから」
赤井は腕の中の降谷の前髪を撫でつつ、言った。
「貴方を待たせるなんて」
降谷は赤井のことをスーパースターか何にかだと思っているのか、何よりその時間を使わせることには慎重なのだ。
「少しでも側に居たいのさ、健気な犬だからな」
けれども、赤井はスターではなく忠実な獣なので、自分の自由な時間くらいは愛に捧げたい。
「本当に?」
「あぁ、許してくれるなら、君のオフィスにも付き従って行きたい」
「それは、ダメ」
降谷はそれを冗談だと受け止めて、面白そうに笑った。
でも、本当にそうしたい。
不都合や偏見や、妬みややっかみや。降谷の周りには敵ばかりだ。
「君の近くに居たいんだ」
降谷は強い。でも、それでも、赤井は彼に降り注ぐ火の粉や矢を振り払ってやりたい。
「じゃあ、お願いしようかな」
「任せてくれ。一時間後には、君をこのベッドに戻してあげよう」
そのまま肩を抱いて降谷を玄関へエスコートする。
ピタ
降谷は足を止めた。
「あ、ちゃんとシャツを着てください」
それから、上半身裸のままの赤井の胸をつついたのだった。
「おっと」
「他の誰かに裸を見せるなんて、嫉妬させたいんですか?」
「いいね、情熱的だ」
「ふふ」
降谷は艶っぽく笑って赤井の胸元にしなだれかかった。
「僕の情熱はそんなもんじゃないですよ。会えなかった分の愛が暴れ回ってるんですから」
頬を染め、じっと赤井を見つめる目には燃えるような情が込められていた。
昨日、赤井が燃やした例の愛という奴だ。
「ふむ、昨日はがっつき過ぎたと反省していたんだが」
会えない時間に情を募らせていたのはお互い様か。
赤井は遠慮なく降谷にキスした。
おはようのキスか、行ってらっしゃいのキスか。どちらにしても、朝から情熱的なことに変わり無い。
赤井は決意した。
降谷が怒ろうと、職場で問題になろうと、二人の仲は公にしてしまおうと。
手始めに、やはり、今朝は、彼のオフィスまでエスコートしてしまおう。
赤井は密かに決意したのであった。
1/1ページ