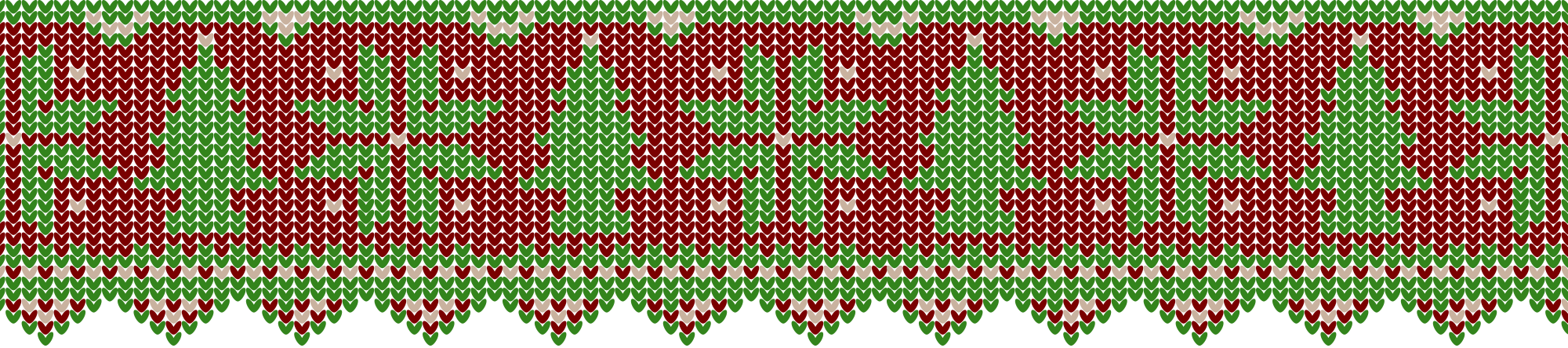七月七日
七月七日、七夕。
降谷は店員として潜伏している喫茶店の店先に、竹を一本、飾った。
「よし」
しっかりと支柱に括って倒れる事がないと確かめる。それから、飾られている常連達が書いた短冊を眺めた。
宝くじが当たりますように
神頼みとしては定番だ。
〇〇君と両思いになりたいです
とても可愛らしい願いだ。
世界平和
これは、降谷が書いた。
他にも願いはあったが、まぁ、それらは己の努力で叶うものだ。こういうところでは大袈裟な物を書くべきだろう。
「おや、七夕飾りですか」
そこに、因縁の大学院生、中身は他国の捜査官が、可愛い小学生探偵を伴って現れた。
「こ、こんには」
江戸川少年は、何度も大人二人の顔を確かめつつそう言った。
「いらっしゃいませ。どうぞ」
降谷は、喫茶店のアルバイトである安室の顔をして、二人のために店のドアを開けた。
「どうしたんです、あれ」
大学院生、沖矢は、店から外の七夕飾りを眺めて言った。
「あぁ、お客様に短冊を書いてもらってたんですけど、昨日まで雨だったから外に出せなくて」
「ほぉ、風流ですね」
沖矢は、そのままカウンター席に座った。
「え?」
「あぁ、坊やは背が届かないか。気が利かずすみません」
連れの小学生探偵は抱っこでスツールに乗せられる。
少年の戸惑いは仕方ない。まさか、安室がいる時にわざわざカウンター席に座ると思わなかったのだろう。
沖矢の中身の赤井と安室の正体である降谷は犬猿の仲。先日、お互いの腹を割って話す場を設けられたものの、表はともかく、まだまだ感情的には複雑であろう。というのが、この江戸川少年の考えの筈だ。
まさか、顔を合わせても取っ組み合いにならないとは。江戸川少年が言いたいことは、口に出さずとも分かる。
何故なら、安室本人もそうだからだ。自分の中の赤井への感情の目まぐるしい変化に、まだついていけてない。
「あのさぁ、仲直りしたならそう言ってよね。沖矢さんがポアロに行くって言うから、大喧嘩になるかと思ったよ」
江戸川少年は、不満げに口を尖らせた。
「一時休戦」
安室はウインクして、二人の前にお冷のコップを置いた。
「コナンくんはアイス?」
「うん」
いつも通りの注文だ。この小学生はチビっこの癖にコーヒー党なのだ。
「今日は暑いからね。沖矢さんも、冷たいのにしますか?」
「いや、ブレンドをスペシャルな方で」
沖矢も、いつもと同じ物を注文した。
「スペシャル?」
「裏メニューです。知りませんか?」
「知らないよ、何それ」
常連の江戸川少年が訝しむ。
「あぁ…」
「あーっ、コナンくん、そう言えば、蘭さんの短冊見た?晴れますようにって、変わったお願いだよね」
安室は沖矢が何か言うのを遮って、少年の前にアイスコーヒーを置いた。
「あ、うん、雨続きだったから、七夕は晴れてほしいって書いてたよ」
「そうなんだ」
「彦星と織姫は一年に一度しか会えないのに、雨だったら可哀想だからね」
「へぇ、優しいな、蘭さん」
「うん」
少年は自分が褒めらたみたいに誇らしげに頷いた。
恋のときめきがキラキラして、とても微笑ましい。
「ふむ。だが、どうでしょう。雨でも二人は会っているのではないでしょうか」
隣の沖矢がポツンと言った。
「え?そうかな」
「寧ろ、雨で誰にも見られない分、堂々と会えますよ。デートを見張られないで済む」
「確かに。雨が理由で会えないなんて、おかしな話だもんね」
「それどころか、我々の知らない所では、しょっちゅう会ってる可能性もあるのでは」
変な話になってきた。
余計な事を言うな。
安室は沖矢を睨みつけたが、分厚い面の皮を被った男には通じなかった。
「元は七日毎にデートしようって約束だったそうですよ。それを聞き違えた男が七月七日にだけ会いに来たとか。そんな勘違い、すぐに正されるでしょう」
「確かに」
確かに、じゃない。これは、なかなか会えない恋人同士のロマンチックな恋の話だ。そんな、普通の付き合いじゃ物語にならないだろうが。
安室は突っ込みたいのを我慢する。墓穴を掘るのが目に見えていたからだ。
「それに、恋人同士が一年に一度きりの逢瀬で耐えられるわけがない。どんな困難も乗り越えて会いに行きますよ」
私ならね。
沖矢はウインクした。バッチリ安室に向けて。
余計なことをするな!
睨む目に力を込めたが、軽くいなされる。
本当に憎たらしい大学院生である。
「織姫だって案外お転婆ですから、恋人の家に忍び込むのなんかお手のものですよ」
「んん?」
江戸川少年が首を傾げた。
やばい、気取られる。
「ブレンド、お待たせですっっ!!!」
ガシャン
ソーサーとカップが音を立てるくらいに慌てて沖矢の前にコーヒーを置いた。
本当に!余計な事を言うなよ!
そう念を込めて置いたのだ。
「やぁ、ありがとう」
沖矢はにこりと柔和に微笑んだ。
「ねぇ、スペシャルブレンドって、レギュラーのブレンドとどう違うの?」
少年が沖矢のコーヒーを覗き込む。
「メニューにあるのはここのマスターのブレンドですが、こちらは安室さんのブレンドなんですよ」
「へぇ、そうなの?」
「えぇ、香りが華やかで、苦味と酸味がガツンと来るんです」
「赤井さん好みだね」
ガシャーン
「し、失礼しました」
安室の手からステンレス製のトレイが落ちた。
クヮンクヮン
それが足元で数回跳ねる。
「まぁ、家で飲むコーヒーも美味しいんですけど、ここで安室さんのエプロン姿を見るのが楽しみで、つい通い詰めてしまいます」
「そうなんだ」
トレイを拾うが、もう、顔を上げる勇気がない。
クソッタレ沖矢が好きな事を言うから、恥ずかしくて仕方ない。
トレイで顔を隠した安室に、少年はニコッとあどけなく笑った。
「ボク、この件については、深く追及しないことにするね」
「うぅ」
安室は、トレイをひん曲げるほどの悔しさと恥ずかしさを味わった。
なにが恥ずかしいって、少年が危ぶむ程に憎んでいた男と、あっという間に懇ろになったと知られてしまった事だ。どれだけちょろい男と思われたか。
降谷だって理解できない。あれほど憎んでいたのに。なんの反動だ?馬鹿なのか?
自分でも自分を嗜めたが、恋は嵐だ。
それに飲み込まれて、もみくちゃなのだ。
「とにかく、今夜は晴れそうで良かったね」
少年はこれまで通りに接してくれる。大人だ。とても大人の対応だ。
「…うん、そうだね」
だが、安室は、まともに顔を合わせられなかった。
「あ、安室さん、今日は、うちにいらっしゃいますか?」
「行くわけないだろっ!」
沖矢の図々しいお伺いには、怒鳴ってやった。
「いいか?お前の織姫は、これっきり恋人の家に忍び込んだりはしない」
「え?そんな」
胡散臭い大学院生が慌ててももう遅い。
降谷の怒りはそんじゃそこらじゃ収まらないほどに、燃え盛ってしまった。
すっかり拗ねてしまった安室と、ご機嫌を取ろうとあれこれ話しかける沖矢を傍目に、江戸川少年は窓から外を眺めた。
空は、今夜の恋人達の逢瀬を約束するように晴れ渡っていた。
降谷は店員として潜伏している喫茶店の店先に、竹を一本、飾った。
「よし」
しっかりと支柱に括って倒れる事がないと確かめる。それから、飾られている常連達が書いた短冊を眺めた。
宝くじが当たりますように
神頼みとしては定番だ。
〇〇君と両思いになりたいです
とても可愛らしい願いだ。
世界平和
これは、降谷が書いた。
他にも願いはあったが、まぁ、それらは己の努力で叶うものだ。こういうところでは大袈裟な物を書くべきだろう。
「おや、七夕飾りですか」
そこに、因縁の大学院生、中身は他国の捜査官が、可愛い小学生探偵を伴って現れた。
「こ、こんには」
江戸川少年は、何度も大人二人の顔を確かめつつそう言った。
「いらっしゃいませ。どうぞ」
降谷は、喫茶店のアルバイトである安室の顔をして、二人のために店のドアを開けた。
「どうしたんです、あれ」
大学院生、沖矢は、店から外の七夕飾りを眺めて言った。
「あぁ、お客様に短冊を書いてもらってたんですけど、昨日まで雨だったから外に出せなくて」
「ほぉ、風流ですね」
沖矢は、そのままカウンター席に座った。
「え?」
「あぁ、坊やは背が届かないか。気が利かずすみません」
連れの小学生探偵は抱っこでスツールに乗せられる。
少年の戸惑いは仕方ない。まさか、安室がいる時にわざわざカウンター席に座ると思わなかったのだろう。
沖矢の中身の赤井と安室の正体である降谷は犬猿の仲。先日、お互いの腹を割って話す場を設けられたものの、表はともかく、まだまだ感情的には複雑であろう。というのが、この江戸川少年の考えの筈だ。
まさか、顔を合わせても取っ組み合いにならないとは。江戸川少年が言いたいことは、口に出さずとも分かる。
何故なら、安室本人もそうだからだ。自分の中の赤井への感情の目まぐるしい変化に、まだついていけてない。
「あのさぁ、仲直りしたならそう言ってよね。沖矢さんがポアロに行くって言うから、大喧嘩になるかと思ったよ」
江戸川少年は、不満げに口を尖らせた。
「一時休戦」
安室はウインクして、二人の前にお冷のコップを置いた。
「コナンくんはアイス?」
「うん」
いつも通りの注文だ。この小学生はチビっこの癖にコーヒー党なのだ。
「今日は暑いからね。沖矢さんも、冷たいのにしますか?」
「いや、ブレンドをスペシャルな方で」
沖矢も、いつもと同じ物を注文した。
「スペシャル?」
「裏メニューです。知りませんか?」
「知らないよ、何それ」
常連の江戸川少年が訝しむ。
「あぁ…」
「あーっ、コナンくん、そう言えば、蘭さんの短冊見た?晴れますようにって、変わったお願いだよね」
安室は沖矢が何か言うのを遮って、少年の前にアイスコーヒーを置いた。
「あ、うん、雨続きだったから、七夕は晴れてほしいって書いてたよ」
「そうなんだ」
「彦星と織姫は一年に一度しか会えないのに、雨だったら可哀想だからね」
「へぇ、優しいな、蘭さん」
「うん」
少年は自分が褒めらたみたいに誇らしげに頷いた。
恋のときめきがキラキラして、とても微笑ましい。
「ふむ。だが、どうでしょう。雨でも二人は会っているのではないでしょうか」
隣の沖矢がポツンと言った。
「え?そうかな」
「寧ろ、雨で誰にも見られない分、堂々と会えますよ。デートを見張られないで済む」
「確かに。雨が理由で会えないなんて、おかしな話だもんね」
「それどころか、我々の知らない所では、しょっちゅう会ってる可能性もあるのでは」
変な話になってきた。
余計な事を言うな。
安室は沖矢を睨みつけたが、分厚い面の皮を被った男には通じなかった。
「元は七日毎にデートしようって約束だったそうですよ。それを聞き違えた男が七月七日にだけ会いに来たとか。そんな勘違い、すぐに正されるでしょう」
「確かに」
確かに、じゃない。これは、なかなか会えない恋人同士のロマンチックな恋の話だ。そんな、普通の付き合いじゃ物語にならないだろうが。
安室は突っ込みたいのを我慢する。墓穴を掘るのが目に見えていたからだ。
「それに、恋人同士が一年に一度きりの逢瀬で耐えられるわけがない。どんな困難も乗り越えて会いに行きますよ」
私ならね。
沖矢はウインクした。バッチリ安室に向けて。
余計なことをするな!
睨む目に力を込めたが、軽くいなされる。
本当に憎たらしい大学院生である。
「織姫だって案外お転婆ですから、恋人の家に忍び込むのなんかお手のものですよ」
「んん?」
江戸川少年が首を傾げた。
やばい、気取られる。
「ブレンド、お待たせですっっ!!!」
ガシャン
ソーサーとカップが音を立てるくらいに慌てて沖矢の前にコーヒーを置いた。
本当に!余計な事を言うなよ!
そう念を込めて置いたのだ。
「やぁ、ありがとう」
沖矢はにこりと柔和に微笑んだ。
「ねぇ、スペシャルブレンドって、レギュラーのブレンドとどう違うの?」
少年が沖矢のコーヒーを覗き込む。
「メニューにあるのはここのマスターのブレンドですが、こちらは安室さんのブレンドなんですよ」
「へぇ、そうなの?」
「えぇ、香りが華やかで、苦味と酸味がガツンと来るんです」
「赤井さん好みだね」
ガシャーン
「し、失礼しました」
安室の手からステンレス製のトレイが落ちた。
クヮンクヮン
それが足元で数回跳ねる。
「まぁ、家で飲むコーヒーも美味しいんですけど、ここで安室さんのエプロン姿を見るのが楽しみで、つい通い詰めてしまいます」
「そうなんだ」
トレイを拾うが、もう、顔を上げる勇気がない。
クソッタレ沖矢が好きな事を言うから、恥ずかしくて仕方ない。
トレイで顔を隠した安室に、少年はニコッとあどけなく笑った。
「ボク、この件については、深く追及しないことにするね」
「うぅ」
安室は、トレイをひん曲げるほどの悔しさと恥ずかしさを味わった。
なにが恥ずかしいって、少年が危ぶむ程に憎んでいた男と、あっという間に懇ろになったと知られてしまった事だ。どれだけちょろい男と思われたか。
降谷だって理解できない。あれほど憎んでいたのに。なんの反動だ?馬鹿なのか?
自分でも自分を嗜めたが、恋は嵐だ。
それに飲み込まれて、もみくちゃなのだ。
「とにかく、今夜は晴れそうで良かったね」
少年はこれまで通りに接してくれる。大人だ。とても大人の対応だ。
「…うん、そうだね」
だが、安室は、まともに顔を合わせられなかった。
「あ、安室さん、今日は、うちにいらっしゃいますか?」
「行くわけないだろっ!」
沖矢の図々しいお伺いには、怒鳴ってやった。
「いいか?お前の織姫は、これっきり恋人の家に忍び込んだりはしない」
「え?そんな」
胡散臭い大学院生が慌ててももう遅い。
降谷の怒りはそんじゃそこらじゃ収まらないほどに、燃え盛ってしまった。
すっかり拗ねてしまった安室と、ご機嫌を取ろうとあれこれ話しかける沖矢を傍目に、江戸川少年は窓から外を眺めた。
空は、今夜の恋人達の逢瀬を約束するように晴れ渡っていた。
1/1ページ