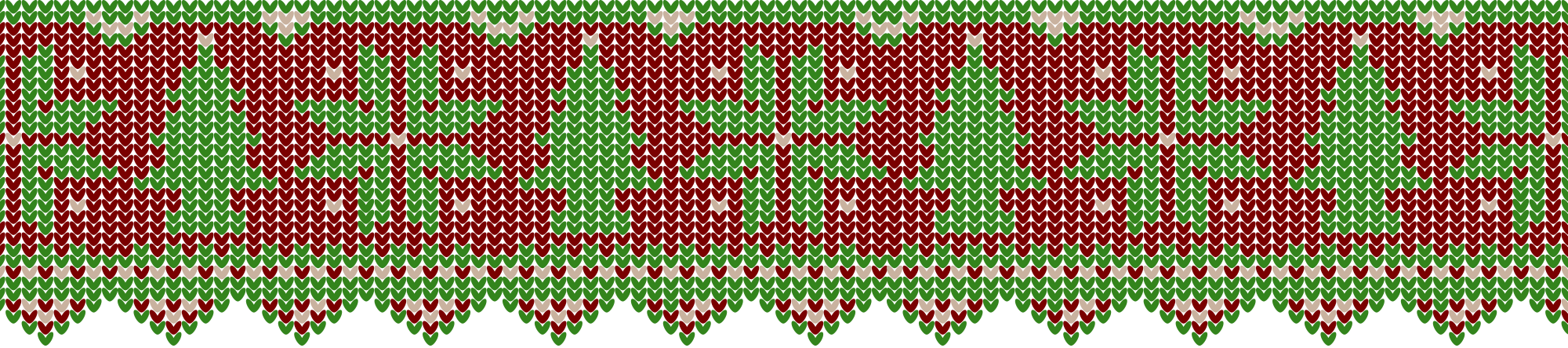千載一遇
六月某日。大安。しかも梅雨の晴れ間。
文句の付けようがないほどの吉日である。
この日、降谷は、紋付袴姿で、都内のとある神社に居た。
「もっと寄ってください」
カメラマンの指示で、隣の男が降谷にぐっと近付く。
「はい、にっこり」
にっこり
笑顔は引きつった。
反対に、隣で実に華麗に微笑んでいる赤井秀一ときたら、元がハンサムだから、まるでモデルみたいだ。
彼も紋付袴姿で、番傘を持ち、それを降谷に差し掛けている。所謂、相合傘である。
何故、こんな格好で、こんな不自然なポーズを写真に撮っているのか。それは、これが、降谷と赤井の結婚式の一環だからである。
どうして、こんなことになったのか。
降谷は、いまだに理解できない。
「良いですね。次は、傘は置いて、見つめ合ってみましょうか。手を取り合って」
そんな降谷を置いてきぼりに、カメラマンのテンションは爆上がりだ。
赤井は傘を置いて、降谷の両手を取った。
「緊張してるのかな?」
ニヤリ。悪戯な笑顔。その顔を見ると、ついついへの字口になってしまう。
「降谷さん、笑顔でーす」
カメラマンの指示が飛んできた。慌てて笑顔を作る。不細工な笑顔だという自覚はあった。
本日、降谷は、華燭の典を挙げる。
神前式は、赤井の希望だ。式を挙げる者は一般公開していない本殿に入れると聞いて、ワクワクしているのだ。日本文化に興味津々なのは感心だが、普通の結婚式場でもよかったのに、とは思う。
降谷の方はと言うと、実のところ、不安が勝ってしまっていた。
昨今の風潮で、同性婚も表立って非難はされなくなった。寧ろ、差別は無くすべきという空気すらある。
今回の、赤井と降谷の結婚も、お互いの組織には大騒動を巻き起こしつつ、祝福された。
祝福されてしまった。
「笑顔ですよ。笑顔。うん、素敵ですよ。降谷さん、綺麗だ」
パシャパシャパシャパシャ
連写だ。
隣で赤井がふっと笑う気配。「綺麗?この乱暴な男が?」とでも思っているのだろう。
間違っても、結婚相手を自慢に思ってのことではない。
何故なら、降谷と赤井は、恋人同士ですら無かったからだ。これっぽっちも愛情なんてない結婚なのだ。
いや、本当のことを言うと、降谷の方には情がある。赤井に前から密かに惚れていた。
でなければ、うっかりプロポーズなんてしない。
降谷は何かの弾みでうっかりと求婚して、赤井は面白そうだと受け入れた。
そんなのはおかしい。しかし、少しだけ、婚約者として扱われてみたい。降谷はそうやって、赤井を手放してやるタイミングを逃し、今日に至ったのだ。
あぁ、すぐさま離婚なんて事になったら、赤井との仲も気まずくなりそうだ。
周りにも心配をかける。それに、皆んなは、二人のことを大恋愛の末の結婚だと思ってくれているのだ。
本当のことを知ったら、どれほどがっかりするだろう。
あれこれを心配し過ぎて、ここのところ毎日、胃が痛む。
「はーい、頬を寄せ合ってみましょうか」
カメラマンの指示がどんどん熱くなっていく。多分、ドアップを撮られた。
もう、さすがに疲れてしまった。写真を理由に、これまでに無く赤井と接近してしまって、気が気でないのだ。
「そろそろ、お式の準備に向かいましょうっ」
そのタイミングで、ウェディングプランナーが本殿へと促す。この厳かな神社に不似合いな程、彼女もハイテンションである。
「本当に、絵になりますっ。今日のお式、絶対に成功させますので!」
「いやぁ、二人ともハンサムだから撮り甲斐がありますよ」
カメラマンも張り切っている。まだ式前なのに、何百枚と写真を撮られた。お陰で、見知らぬ参拝客にまで祝福される始末だ。
二人でこっそり式を挙げるつもりだったのに。
降谷は溜息を吐いた。この、晴れの日に溜息はよろしく無いとは、分かっていた。
先を行くプランナーの彼女が振り返る。
「皆様もお揃いですよ」
「え?」
降谷はぎょっと声を上げた。
挙式は、親族だけの筈だ。つまり、赤井の家族だけだと、そう聞いていた。
「本殿が広いから、希望者は入れるそうだ」
赤井は「聞いてないのか?」という顔だ。
「え?」
「披露宴会場でお声掛けしたら、皆さん、いらして頂けると」
プランナーは、にこにこと言った。
良かれと思ってのことだろうが、降谷の胸はズンズン重くなっていく。
神を欺く重罪に加え、親愛なる友人知人にまで、大嘘を吐くのか?
あぁ、罰が当たるのは自分だけでありますように。
降谷は痛む胃を押さえた。
式はお互いの上司に媒酌人を頼んだ。特に、降谷の上司には、先に謝っておいた。面倒に巻き込んでしまって申し訳ないと。上司は豪快に笑っていた。
ところが、今、降谷の上司はカチカチに緊張しているではないか。
「い、良いか、降谷、俺が付いてる。何も心配するな」
「はぁ」
ガサ入れか?いや、ガサ入れなら、抜かるなよの一言しか言わない人だ。
顰めっ面に汗を浮かべて、何故が手の平に人人人と書き始めた。
ただ、式を見届けるだけなのに、随分と責任を感じてくれてる。
胃が、また痛んだ。
チョン
赤井が降谷の肩を突いた。それから、後ろの方を指で示した。
「見てご覧」
媒酌人の後方には、参列者が並んでいる。
「君の親族列はいっぱいだ」
「あ…毛利さん」
親族列の一番には毛利探偵がドカンと仁王立ちしていた。横には訪問着姿の夫人もいる。それから、娘さんと、その彼氏の名探偵。驚くことに、高木刑事と佐藤警部補まで並んでいた。そして、何故か皆、祝い事というには気合の入った顔つきなのだ。
やっぱりガサ入れみたいだ。
降谷は、首を傾げた。
もしかして、何かの事件が近くで起こったのか?皆んな、やけに鼻息が荒い。
無理に式に出席させてしまっただろうか。
「彼らは、気合十分だな」
「はぁ」
「毛利探偵が、是非にと声を掛けていた。君の親族席を空けたくないと」
「え?先生が」
意外だった。
毛利探偵とは仮初の師弟関係であった縁で、今も付き合いを続けさせてもらっている。警察の先輩でもあるし、頼れる存在だ。だから、何かの折に、実は天涯孤独の身で、と言った気がする。
心配かけてしまったな。
申し訳ないような嬉しいような、くすぐったい気持ちだ。
「君は、この結婚を後悔してるように見える」
赤井が言った。
ドキッとした。
とうとう、何か告げられるのか?
いや、覚悟はできてる。…筈だ。
「俺は後悔してない」
だが、赤井は覚悟とは逆のことを言った。
「君からのプロポーズ、とても驚いたよ」
「あの時は本当に唐突で、すみませんでした」
「君は、あの時、失敗したと言う顔をしたな」
「…あんなこと言うつもりじゃ無かったから」
「そうだろうな」
降谷は今も考える。どうして、あの時、口から求婚の言葉が出てしまったのか。
あの時は、珍しく、赤井がほんの少し弱い所を見せてくれて、それが降谷の愛を衝動的に突き動かしたのだ。
言うべきでは無かった言葉だ。でも、そのお陰で、近付いた距離を嬉しいと思ってしまった。
「その後も、ずっと不安そうだった。大方、俺が周りを巻き込んで悪戯を楽しんでいるとでも思ったんだろう」
赤井は、降谷の葛藤を知っていた。
「そのうちネタばらしして、婚約なんて嘘だったと言うと?」
「貴方、分かってて」
「そりゃ分かるさ、ずっと君を見てきたんだから」
「僕は貴方のこと、掴みきれてないですけど」
「君は、本当に真っ直ぐだからなぁ」
赤井は、彼独特の皮肉げで、ちょっと意地悪な笑い方をして見せた。
「悪い大人に目をつけられる」
赤井の指が降谷の頬を撫でた。
意地悪な笑顔は、甘く緩んだ。優しい指が、頬を数度撫でて、顎まで滑った。まるで、降谷は犬が猫みたいに、撫でられるのを受け入れてしまうのだった。
「俺が君の孤独を埋めよう。それが俺の愛だ」
これが、赤井の愛?
では、この結婚は愛のあるものだと?
「普通の夫婦と違うと君は心配してるらしいが、どこの夫婦も他とは違う。俺は、君への愛を誇れるが?」
降谷はすっかり舞い上がってしまって、媒酌人の上司が聞き耳を立てている事にも気が付かなかった。
「ずっと君のことを愛してる」
「へ?」
「予定では、来年の春ごろに俺からプロポーズする筈だったが、随分と予定が早まったな。いや、構わんよ、遅くなるよりよほど良い」
「は?」
「新婚生活が楽しみだ」
降谷が友人に毛が生えた程度の仲だと思っていた二人が、唐突に夫婦になる?不自然だ。だが、そこに、何やらの情があるなら?
赤井が目の前で、パチンとウインクした。
「熱烈な新婚生活にしよう」
パチパチ
何故か、媒酌人の上司二人からささやかな拍手が送られた。
「ハネムーンに長期休暇を取りなさい」
赤井の上司は、うんうんと頷いた。
「お前も、漸く人並みの幸せを掴んだな、降谷」
降谷の上司は自分も独身のくせに、そんなふうに言ったものだから、突っ込みたいのを我慢する羽目になった。
「ご入場です」
プランナーが二人の背中を押した。
巫女の先導で本殿へと進む。
結婚式だ。本当に、結婚するのだ。
「こんな俺でも、結婚してくれるかな?」
赤井がこっそり囁く。
「忘れてるんですか?先に申し込んだのは僕の方です」
「あぁ、そうだったな。あの時は痺れたよ。千載一遇の光栄だったさ」
何が「痺れたよ」だ。真っ白になるくらい驚いていたくせに。
そうか、あれは、嬉しいと、思ってくれていたのか。
そうか。
かしこみかしこみ
この日、二人は、天の原の神々と、親愛なる友人たちに夫夫として迎えられたのであった。
まことに。人生とは、奇なるものである。
文句の付けようがないほどの吉日である。
この日、降谷は、紋付袴姿で、都内のとある神社に居た。
「もっと寄ってください」
カメラマンの指示で、隣の男が降谷にぐっと近付く。
「はい、にっこり」
にっこり
笑顔は引きつった。
反対に、隣で実に華麗に微笑んでいる赤井秀一ときたら、元がハンサムだから、まるでモデルみたいだ。
彼も紋付袴姿で、番傘を持ち、それを降谷に差し掛けている。所謂、相合傘である。
何故、こんな格好で、こんな不自然なポーズを写真に撮っているのか。それは、これが、降谷と赤井の結婚式の一環だからである。
どうして、こんなことになったのか。
降谷は、いまだに理解できない。
「良いですね。次は、傘は置いて、見つめ合ってみましょうか。手を取り合って」
そんな降谷を置いてきぼりに、カメラマンのテンションは爆上がりだ。
赤井は傘を置いて、降谷の両手を取った。
「緊張してるのかな?」
ニヤリ。悪戯な笑顔。その顔を見ると、ついついへの字口になってしまう。
「降谷さん、笑顔でーす」
カメラマンの指示が飛んできた。慌てて笑顔を作る。不細工な笑顔だという自覚はあった。
本日、降谷は、華燭の典を挙げる。
神前式は、赤井の希望だ。式を挙げる者は一般公開していない本殿に入れると聞いて、ワクワクしているのだ。日本文化に興味津々なのは感心だが、普通の結婚式場でもよかったのに、とは思う。
降谷の方はと言うと、実のところ、不安が勝ってしまっていた。
昨今の風潮で、同性婚も表立って非難はされなくなった。寧ろ、差別は無くすべきという空気すらある。
今回の、赤井と降谷の結婚も、お互いの組織には大騒動を巻き起こしつつ、祝福された。
祝福されてしまった。
「笑顔ですよ。笑顔。うん、素敵ですよ。降谷さん、綺麗だ」
パシャパシャパシャパシャ
連写だ。
隣で赤井がふっと笑う気配。「綺麗?この乱暴な男が?」とでも思っているのだろう。
間違っても、結婚相手を自慢に思ってのことではない。
何故なら、降谷と赤井は、恋人同士ですら無かったからだ。これっぽっちも愛情なんてない結婚なのだ。
いや、本当のことを言うと、降谷の方には情がある。赤井に前から密かに惚れていた。
でなければ、うっかりプロポーズなんてしない。
降谷は何かの弾みでうっかりと求婚して、赤井は面白そうだと受け入れた。
そんなのはおかしい。しかし、少しだけ、婚約者として扱われてみたい。降谷はそうやって、赤井を手放してやるタイミングを逃し、今日に至ったのだ。
あぁ、すぐさま離婚なんて事になったら、赤井との仲も気まずくなりそうだ。
周りにも心配をかける。それに、皆んなは、二人のことを大恋愛の末の結婚だと思ってくれているのだ。
本当のことを知ったら、どれほどがっかりするだろう。
あれこれを心配し過ぎて、ここのところ毎日、胃が痛む。
「はーい、頬を寄せ合ってみましょうか」
カメラマンの指示がどんどん熱くなっていく。多分、ドアップを撮られた。
もう、さすがに疲れてしまった。写真を理由に、これまでに無く赤井と接近してしまって、気が気でないのだ。
「そろそろ、お式の準備に向かいましょうっ」
そのタイミングで、ウェディングプランナーが本殿へと促す。この厳かな神社に不似合いな程、彼女もハイテンションである。
「本当に、絵になりますっ。今日のお式、絶対に成功させますので!」
「いやぁ、二人ともハンサムだから撮り甲斐がありますよ」
カメラマンも張り切っている。まだ式前なのに、何百枚と写真を撮られた。お陰で、見知らぬ参拝客にまで祝福される始末だ。
二人でこっそり式を挙げるつもりだったのに。
降谷は溜息を吐いた。この、晴れの日に溜息はよろしく無いとは、分かっていた。
先を行くプランナーの彼女が振り返る。
「皆様もお揃いですよ」
「え?」
降谷はぎょっと声を上げた。
挙式は、親族だけの筈だ。つまり、赤井の家族だけだと、そう聞いていた。
「本殿が広いから、希望者は入れるそうだ」
赤井は「聞いてないのか?」という顔だ。
「え?」
「披露宴会場でお声掛けしたら、皆さん、いらして頂けると」
プランナーは、にこにこと言った。
良かれと思ってのことだろうが、降谷の胸はズンズン重くなっていく。
神を欺く重罪に加え、親愛なる友人知人にまで、大嘘を吐くのか?
あぁ、罰が当たるのは自分だけでありますように。
降谷は痛む胃を押さえた。
式はお互いの上司に媒酌人を頼んだ。特に、降谷の上司には、先に謝っておいた。面倒に巻き込んでしまって申し訳ないと。上司は豪快に笑っていた。
ところが、今、降谷の上司はカチカチに緊張しているではないか。
「い、良いか、降谷、俺が付いてる。何も心配するな」
「はぁ」
ガサ入れか?いや、ガサ入れなら、抜かるなよの一言しか言わない人だ。
顰めっ面に汗を浮かべて、何故が手の平に人人人と書き始めた。
ただ、式を見届けるだけなのに、随分と責任を感じてくれてる。
胃が、また痛んだ。
チョン
赤井が降谷の肩を突いた。それから、後ろの方を指で示した。
「見てご覧」
媒酌人の後方には、参列者が並んでいる。
「君の親族列はいっぱいだ」
「あ…毛利さん」
親族列の一番には毛利探偵がドカンと仁王立ちしていた。横には訪問着姿の夫人もいる。それから、娘さんと、その彼氏の名探偵。驚くことに、高木刑事と佐藤警部補まで並んでいた。そして、何故か皆、祝い事というには気合の入った顔つきなのだ。
やっぱりガサ入れみたいだ。
降谷は、首を傾げた。
もしかして、何かの事件が近くで起こったのか?皆んな、やけに鼻息が荒い。
無理に式に出席させてしまっただろうか。
「彼らは、気合十分だな」
「はぁ」
「毛利探偵が、是非にと声を掛けていた。君の親族席を空けたくないと」
「え?先生が」
意外だった。
毛利探偵とは仮初の師弟関係であった縁で、今も付き合いを続けさせてもらっている。警察の先輩でもあるし、頼れる存在だ。だから、何かの折に、実は天涯孤独の身で、と言った気がする。
心配かけてしまったな。
申し訳ないような嬉しいような、くすぐったい気持ちだ。
「君は、この結婚を後悔してるように見える」
赤井が言った。
ドキッとした。
とうとう、何か告げられるのか?
いや、覚悟はできてる。…筈だ。
「俺は後悔してない」
だが、赤井は覚悟とは逆のことを言った。
「君からのプロポーズ、とても驚いたよ」
「あの時は本当に唐突で、すみませんでした」
「君は、あの時、失敗したと言う顔をしたな」
「…あんなこと言うつもりじゃ無かったから」
「そうだろうな」
降谷は今も考える。どうして、あの時、口から求婚の言葉が出てしまったのか。
あの時は、珍しく、赤井がほんの少し弱い所を見せてくれて、それが降谷の愛を衝動的に突き動かしたのだ。
言うべきでは無かった言葉だ。でも、そのお陰で、近付いた距離を嬉しいと思ってしまった。
「その後も、ずっと不安そうだった。大方、俺が周りを巻き込んで悪戯を楽しんでいるとでも思ったんだろう」
赤井は、降谷の葛藤を知っていた。
「そのうちネタばらしして、婚約なんて嘘だったと言うと?」
「貴方、分かってて」
「そりゃ分かるさ、ずっと君を見てきたんだから」
「僕は貴方のこと、掴みきれてないですけど」
「君は、本当に真っ直ぐだからなぁ」
赤井は、彼独特の皮肉げで、ちょっと意地悪な笑い方をして見せた。
「悪い大人に目をつけられる」
赤井の指が降谷の頬を撫でた。
意地悪な笑顔は、甘く緩んだ。優しい指が、頬を数度撫でて、顎まで滑った。まるで、降谷は犬が猫みたいに、撫でられるのを受け入れてしまうのだった。
「俺が君の孤独を埋めよう。それが俺の愛だ」
これが、赤井の愛?
では、この結婚は愛のあるものだと?
「普通の夫婦と違うと君は心配してるらしいが、どこの夫婦も他とは違う。俺は、君への愛を誇れるが?」
降谷はすっかり舞い上がってしまって、媒酌人の上司が聞き耳を立てている事にも気が付かなかった。
「ずっと君のことを愛してる」
「へ?」
「予定では、来年の春ごろに俺からプロポーズする筈だったが、随分と予定が早まったな。いや、構わんよ、遅くなるよりよほど良い」
「は?」
「新婚生活が楽しみだ」
降谷が友人に毛が生えた程度の仲だと思っていた二人が、唐突に夫婦になる?不自然だ。だが、そこに、何やらの情があるなら?
赤井が目の前で、パチンとウインクした。
「熱烈な新婚生活にしよう」
パチパチ
何故か、媒酌人の上司二人からささやかな拍手が送られた。
「ハネムーンに長期休暇を取りなさい」
赤井の上司は、うんうんと頷いた。
「お前も、漸く人並みの幸せを掴んだな、降谷」
降谷の上司は自分も独身のくせに、そんなふうに言ったものだから、突っ込みたいのを我慢する羽目になった。
「ご入場です」
プランナーが二人の背中を押した。
巫女の先導で本殿へと進む。
結婚式だ。本当に、結婚するのだ。
「こんな俺でも、結婚してくれるかな?」
赤井がこっそり囁く。
「忘れてるんですか?先に申し込んだのは僕の方です」
「あぁ、そうだったな。あの時は痺れたよ。千載一遇の光栄だったさ」
何が「痺れたよ」だ。真っ白になるくらい驚いていたくせに。
そうか、あれは、嬉しいと、思ってくれていたのか。
そうか。
かしこみかしこみ
この日、二人は、天の原の神々と、親愛なる友人たちに夫夫として迎えられたのであった。
まことに。人生とは、奇なるものである。
2/2ページ