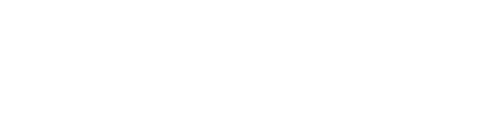第1章
❄︎ ❄︎ ❄︎
「竈門炭治郎、十二鬼月ト遭遇!!」
鎹烏から知らせを受けた鳴子は、一瞬大きく目を見開いた。
竈門炭次郎とは、確か今回の選別で生き残った隊士だったか。顔を見たことはないが、入ったばかりで十二鬼月に遭遇するとは運の悪い。
同情するかの様に目を伏せた彼女の肩に、一匹の烏がそっと降り立った。
「…下弦なの、上弦なの?」
「下弦ノ鬼ダ!!」
「そう、不幸中の幸いね」
鳴子はふっと微笑むと、肩に止まっている鎹烏の喉元を優しく撫でた。気持ちよさそうに目を細めた烏を見つめながら、彼女は再び口を開いた。
「誰が応援に行くの?私はお呼びじゃないのでしょう?」
「富岡義勇、胡蝶しのぶガ参戦スル!!」
「…そう。間に合うと良いわね」
少し物悲しげな笑顔でそう言う彼女の視線の先には、震えながら涙を流す幼い少年の姿があった。そして彼女の足元には、鬼のものと見受けられる胴体が転がっていた。首を跳ねられてからさほど時間が経ってないのだろう、その体は少しずつ消えかかっていた。
「…さ、坊や。こんな時間に出歩くのは感心しないわ。何があったのか知らないけど、家があるのなら帰りましょう。お姉ちゃんが送ってあげる」
鳴子は、少年と目線を合わすためその場に膝まずいた。しかし、彼女が優しく笑いかけても、少年はカタカタと歯をならして首を横に振り続けるだけだった。
そんな少年に、鳴子は少し考える様な素振りをしたが、すぐに微笑むとギュッと彼を抱きしめた。
「大丈夫、もう怖くないよ。お姉ちゃんが守ってあげるからね」
鼻の奥にこびり付いたと思っていた血生臭さが、彼女の甘く優しい匂いに打ち消され、幼い少年は徐々に落ち着きを取り戻し始めた。
「…う、あれ、人を食べてた…!!」
ようやく言葉を発した少年は、まだ怯えている様だった。ほとんど消えてしまったその姿を指差し、震えながら鳴子にしがみつく。
「そうね、嫌なもの見ちゃったわね。人喰い鬼は夜に活動するから、これからは夜出歩かないようにね」
助けられなかった命もあるけど、幼い彼の命が守れて良かった。彼の心には大きな傷が残っただろうが、命があるだけマシだろう。
「家までの道、分かる?」
悲惨な状況にも関わらず、月明かりに照らされた少女は雪のように白くて美しい。そんな彼女の姿を見て安心したのか、少年は小さく頷いた。
「うん、いい子ね」
「師範」
鳴子が彼の小さな頭に手を乗せたと同時に、彼女の背後から抑揚のない声がした。彼女が驚いた顔で振り向くと、黒い隊服に身を包んだ髪の長い少年が立っていた。
「あら、無一郎。向こうは片付いたのね」
何故いるのかとでも言いたげな彼女の表情を見て、無一郎は胃のあたりがムカッとする様な感覚を覚えた。
「何で、そんな子どもがここにいるの?夜なのに、こんな人気のないとこ出歩くなんて危機管理能力が低過ぎるよね。君、いったい何を考えてるの?」
突然現れたかと思ったら、次から次へと厳しい言葉を投げつけてくる。正論とは言えども容赦ない物言いに、幼い少年の目から再び涙が零れ落ちる。
「やめなさい無一郎。まだ小さいんだもの、鬼のことなんて知らないのよ。…ごめんね坊や。あのお兄ちゃん、口が悪いだけで本当は心配しているの。だから怖がらなくて良いのよ」
「いや、僕は心配なんてしてないよ。ただその子どもの軽率すぎる行動に呆れてるだけ」
「無一郎」
泣いている少年を抱きしめ、咎めるかの様に鋭い視線を向けてきた鳴子を見て、無一郎は更に胃の辺りがムカムカしてくるのを感じた。
しかし、これ以上はまずいと思ったのだろう。深くため息をつくと彼女等から視線を逸らした。
「さあ、帰りましょう。お父さんとお母さんも心配してるわ」
おどおどしている少年の手を握ると、鳴子は無一郎の方に顔だけ向けるとにっこり笑った。
「私、取り敢えずこの子を送り届けてくるから、次の任務先で合流しましょう」
じゃあね、と謎に片目を閉じた彼女に、無一郎は再び大きなため息をつく。何故だか分からないけど、腹が立って仕方ない。
「あの人が帰ってくる前に、片付けてやる」
黒髪の少年は微かに顔を歪めると、すっとその場から姿を消した。
「竈門炭治郎、十二鬼月ト遭遇!!」
鎹烏から知らせを受けた鳴子は、一瞬大きく目を見開いた。
竈門炭次郎とは、確か今回の選別で生き残った隊士だったか。顔を見たことはないが、入ったばかりで十二鬼月に遭遇するとは運の悪い。
同情するかの様に目を伏せた彼女の肩に、一匹の烏がそっと降り立った。
「…下弦なの、上弦なの?」
「下弦ノ鬼ダ!!」
「そう、不幸中の幸いね」
鳴子はふっと微笑むと、肩に止まっている鎹烏の喉元を優しく撫でた。気持ちよさそうに目を細めた烏を見つめながら、彼女は再び口を開いた。
「誰が応援に行くの?私はお呼びじゃないのでしょう?」
「富岡義勇、胡蝶しのぶガ参戦スル!!」
「…そう。間に合うと良いわね」
少し物悲しげな笑顔でそう言う彼女の視線の先には、震えながら涙を流す幼い少年の姿があった。そして彼女の足元には、鬼のものと見受けられる胴体が転がっていた。首を跳ねられてからさほど時間が経ってないのだろう、その体は少しずつ消えかかっていた。
「…さ、坊や。こんな時間に出歩くのは感心しないわ。何があったのか知らないけど、家があるのなら帰りましょう。お姉ちゃんが送ってあげる」
鳴子は、少年と目線を合わすためその場に膝まずいた。しかし、彼女が優しく笑いかけても、少年はカタカタと歯をならして首を横に振り続けるだけだった。
そんな少年に、鳴子は少し考える様な素振りをしたが、すぐに微笑むとギュッと彼を抱きしめた。
「大丈夫、もう怖くないよ。お姉ちゃんが守ってあげるからね」
鼻の奥にこびり付いたと思っていた血生臭さが、彼女の甘く優しい匂いに打ち消され、幼い少年は徐々に落ち着きを取り戻し始めた。
「…う、あれ、人を食べてた…!!」
ようやく言葉を発した少年は、まだ怯えている様だった。ほとんど消えてしまったその姿を指差し、震えながら鳴子にしがみつく。
「そうね、嫌なもの見ちゃったわね。人喰い鬼は夜に活動するから、これからは夜出歩かないようにね」
助けられなかった命もあるけど、幼い彼の命が守れて良かった。彼の心には大きな傷が残っただろうが、命があるだけマシだろう。
「家までの道、分かる?」
悲惨な状況にも関わらず、月明かりに照らされた少女は雪のように白くて美しい。そんな彼女の姿を見て安心したのか、少年は小さく頷いた。
「うん、いい子ね」
「師範」
鳴子が彼の小さな頭に手を乗せたと同時に、彼女の背後から抑揚のない声がした。彼女が驚いた顔で振り向くと、黒い隊服に身を包んだ髪の長い少年が立っていた。
「あら、無一郎。向こうは片付いたのね」
何故いるのかとでも言いたげな彼女の表情を見て、無一郎は胃のあたりがムカッとする様な感覚を覚えた。
「何で、そんな子どもがここにいるの?夜なのに、こんな人気のないとこ出歩くなんて危機管理能力が低過ぎるよね。君、いったい何を考えてるの?」
突然現れたかと思ったら、次から次へと厳しい言葉を投げつけてくる。正論とは言えども容赦ない物言いに、幼い少年の目から再び涙が零れ落ちる。
「やめなさい無一郎。まだ小さいんだもの、鬼のことなんて知らないのよ。…ごめんね坊や。あのお兄ちゃん、口が悪いだけで本当は心配しているの。だから怖がらなくて良いのよ」
「いや、僕は心配なんてしてないよ。ただその子どもの軽率すぎる行動に呆れてるだけ」
「無一郎」
泣いている少年を抱きしめ、咎めるかの様に鋭い視線を向けてきた鳴子を見て、無一郎は更に胃の辺りがムカムカしてくるのを感じた。
しかし、これ以上はまずいと思ったのだろう。深くため息をつくと彼女等から視線を逸らした。
「さあ、帰りましょう。お父さんとお母さんも心配してるわ」
おどおどしている少年の手を握ると、鳴子は無一郎の方に顔だけ向けるとにっこり笑った。
「私、取り敢えずこの子を送り届けてくるから、次の任務先で合流しましょう」
じゃあね、と謎に片目を閉じた彼女に、無一郎は再び大きなため息をつく。何故だか分からないけど、腹が立って仕方ない。
「あの人が帰ってくる前に、片付けてやる」
黒髪の少年は微かに顔を歪めると、すっとその場から姿を消した。