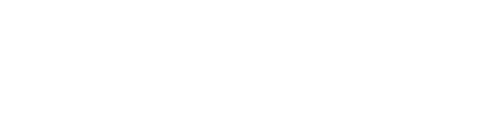第1章
❄︎ ❄︎ ❄︎
とある屋敷の庭で、1人の少年が木刀を振り回していた。その少年の動きはしなやかで無駄がない。次から次へと的を切り倒していく。
一通り終わった後、少年は涼しい顔で空を見上げた。そして、不意に何かに気が付いたのか視線を門の方へと向けた。
「お疲れ様、頑張ってるわね」
微笑を浮かべて手を振ってくる人物を捕らえた少年の瞳が、微かに動いた。自分と同じ、黒い隊服を身に纏った少女は、彼にとって特別な存在だった。
「…師範」
少年の表情は乏しくて、どこか生気が感じられない。発せられるその声も、淡々としていて全く感情が読み取れない。
そんな少年とは対照的に、色白の肌にくっきりとした顔立ちが印象的な女性──氷向鳴子からは、上機嫌な様子がひしひしと伝わってくる。
「あら、私はもう貴方の師じゃないわよ?…ま、それはどうでも良いわ。そんなことより、特訓もひと段落したみたいだし少し休憩しない?良いもの買ってきたのよ」
楽しそうに少年の方へと近付く彼女の手には、花柄の風呂敷が抱えられていた。
「さっきね、実弥さんと逢引きしてたのよ。それで、可愛い無一郎にお土産買ってきたの」
「…逢引き?」
無一郎と呼ばれた少年は、相変わらずぼんやりとした表情のまま首を傾げた。そんな彼を見て、少女は「ああ」と頷くと、再び言葉を続けた。
「今日の午前中、風柱様と手合わせしてたんだけどね、ただやり合うだけじゃ面白くないからゲームしたのよ。先に一本取られた方が相手の言うこと聞くってゲーム」
風柱である不死川実弥は、確かな実力の持ち主だ。純粋に力だけで言えば、彼は鳴子より上だった。しかし、雪柱の座に着いている氷向鳴子は、動きが迅速かつ正確な上に頭の回転までも速い。そのため、総合的な実力で言うと二人は互角だった。
「今日はね、運良く私が勝ったんだ。だからあの人に昼食奢ってもらったの。…それで、ついでに貴方へのお土産も買ってもらったのよ」
鳴子は、その時の光景を思い出したのかクスクスと楽しそうに笑った。綺麗な顔立ちに似合わず、その笑顔は小さな子どもが悪戯に成功した時のそれに似ていた。
「…ふうん」
無一郎はしばらく鳴子の顔を見つめていたが、つまらなくなったのか彼女に背を向けるとすたすたと歩き出した。
「ねえ、これ何だと思う?」
少年の背中に、鳴子の明るい声が降り注ぐ。彼は少し気怠そうにため息を吐いたが、首を微かに回して視線だけ彼女に戻した。
「知らないよ。寧ろ、何で僕がその中身を知ってると思うの?その場に居なかったんだから、知る訳ないだろう」
やや棘のある物言いの彼だが、鳴子はそんなこと気にする様子もなく「厳しいなぁ」と眉を八の字にして笑った。
「おやつに丁度いいと思って、三色団子買ってきたの。ね、一緒に食べましょう?」
「…さっきお昼食べたんじゃなかったの?」
どこまでも、無邪気な人だ。その近寄り難い程に美しい容姿からは想像もできない。西洋の彫刻にありそうな顔立ちの彼女が、しつこいとも言えるほど人懐っこい性格をしているなど、誰が想像できるだろう。
相変わらず上機嫌な彼女に、無一郎はやれやれとでも言いたげな表情でため息を吐いた。
「そんなにため息ばかり吐いてると幸せが逃げるわよ?いいの、おやつは別腹だから問題ない!」
彼女は無一郎の腕に自分の腕を絡ませると、グイッと彼の身体を引っ張り半ば強引に縁側へ座らせた。
「稽古も大事だけど、息抜きも大切よ。たまには街に顔を出して、羽を伸ばすのも楽しいわよ」
手際良く風呂敷を解いていく鳴子の横顔を、少年はぼうっとした様な顔で見つめていた。毎日の様に自分の元へやって来るこの女性は一体何を考えているのか、理解しようとしているのだ。
「…僕が貴方の弟子だったから、構ってくれるの?」
「それもあるわね。…でも私は、単純に貴方が好きだから毎日遊びに来てるのよ。」
優しげな笑みを浮かべてそう答えた彼女に、無一郎はますます訳が分からないといった顔をして首を傾げた。
そんな彼に、鳴子は少し考えるかの様に視線を横へ流したが、すぐに彼の方へ視線を戻すと再び微笑んだ。
「貴方のことが気がかりだから、毎日来てるのよ」
「…気がかり?心配ってこと?…何で、赤の他人の僕のことを心配するの?それに、貴方に心配されるほど僕は弱くないよ?」
更に質問を畳み掛けてくる彼に、鳴子は思わず苦笑いの様な表情を浮かべた。
時透無一郎という少年は、訳あって人としての何かが欠けている。決して彼自身に悪気があるわけではないのだが、人によっては嫌な顔をする者も出てくるだろう。
「そうね、貴方の言ってることは正しいわ。…でもね、人の心って不思議なものなのよ。きっと貴方にも、分かる日がくるわ」
彼だけを特別視している訳ではない。それでも、やはり贔屓してしまうのは事実だ。それは、彼女の中に閉じ込められた悲しい思い出から引き起こされる衝動的な行動でもあった。
「…僕が貴方の弟と同い年だから?」
不意に発せられたその言葉に、鳴子は団子を口に運んでいた手を止めた。そして、怪訝そうな表情で無一郎の顔を凝視した。
「…何故それを?私、貴方にそんな話した?」
紅色の瞳が、真っ直ぐに少年の姿を捉えている。その美しい瞳に捕われた少年は、しばらく黙って彼女の瞳を見つめていたが、やがてすっと視線を逸らすと手に持っていた団子を口へと運んだ。
「別に、何かそんな気がしただけだよ。…よく分からないけど、そんな気がしたんだ」
彼の表情からは、感情が読み取れない。彼が発した言葉も、嘘なのか本当なのかは分からない。でも、鳴子はそれが本当であるということが分かっていた。
「そっか。…そういう事もあるよね」
鳴子はふっと微笑むと、三色団子をパクリと頬張った。とろける様な甘さが口の中に広がるのを感じながら、彼女は視線を頭上へと移動させた。
「今年の最終選別、5人も受かったそうよ。…貴方と歳が近い子ばかりだから、友達になれると良いわね」
「どうでも良いよ」という無一郎の淡々とした返事を聞きながら、鳴子は2つ目の団子に手を伸ばすのだった。
❄︎ ❄︎ ❄︎
とある屋敷の庭で、1人の少年が木刀を振り回していた。その少年の動きはしなやかで無駄がない。次から次へと的を切り倒していく。
一通り終わった後、少年は涼しい顔で空を見上げた。そして、不意に何かに気が付いたのか視線を門の方へと向けた。
「お疲れ様、頑張ってるわね」
微笑を浮かべて手を振ってくる人物を捕らえた少年の瞳が、微かに動いた。自分と同じ、黒い隊服を身に纏った少女は、彼にとって特別な存在だった。
「…師範」
少年の表情は乏しくて、どこか生気が感じられない。発せられるその声も、淡々としていて全く感情が読み取れない。
そんな少年とは対照的に、色白の肌にくっきりとした顔立ちが印象的な女性──氷向鳴子からは、上機嫌な様子がひしひしと伝わってくる。
「あら、私はもう貴方の師じゃないわよ?…ま、それはどうでも良いわ。そんなことより、特訓もひと段落したみたいだし少し休憩しない?良いもの買ってきたのよ」
楽しそうに少年の方へと近付く彼女の手には、花柄の風呂敷が抱えられていた。
「さっきね、実弥さんと逢引きしてたのよ。それで、可愛い無一郎にお土産買ってきたの」
「…逢引き?」
無一郎と呼ばれた少年は、相変わらずぼんやりとした表情のまま首を傾げた。そんな彼を見て、少女は「ああ」と頷くと、再び言葉を続けた。
「今日の午前中、風柱様と手合わせしてたんだけどね、ただやり合うだけじゃ面白くないからゲームしたのよ。先に一本取られた方が相手の言うこと聞くってゲーム」
風柱である不死川実弥は、確かな実力の持ち主だ。純粋に力だけで言えば、彼は鳴子より上だった。しかし、雪柱の座に着いている氷向鳴子は、動きが迅速かつ正確な上に頭の回転までも速い。そのため、総合的な実力で言うと二人は互角だった。
「今日はね、運良く私が勝ったんだ。だからあの人に昼食奢ってもらったの。…それで、ついでに貴方へのお土産も買ってもらったのよ」
鳴子は、その時の光景を思い出したのかクスクスと楽しそうに笑った。綺麗な顔立ちに似合わず、その笑顔は小さな子どもが悪戯に成功した時のそれに似ていた。
「…ふうん」
無一郎はしばらく鳴子の顔を見つめていたが、つまらなくなったのか彼女に背を向けるとすたすたと歩き出した。
「ねえ、これ何だと思う?」
少年の背中に、鳴子の明るい声が降り注ぐ。彼は少し気怠そうにため息を吐いたが、首を微かに回して視線だけ彼女に戻した。
「知らないよ。寧ろ、何で僕がその中身を知ってると思うの?その場に居なかったんだから、知る訳ないだろう」
やや棘のある物言いの彼だが、鳴子はそんなこと気にする様子もなく「厳しいなぁ」と眉を八の字にして笑った。
「おやつに丁度いいと思って、三色団子買ってきたの。ね、一緒に食べましょう?」
「…さっきお昼食べたんじゃなかったの?」
どこまでも、無邪気な人だ。その近寄り難い程に美しい容姿からは想像もできない。西洋の彫刻にありそうな顔立ちの彼女が、しつこいとも言えるほど人懐っこい性格をしているなど、誰が想像できるだろう。
相変わらず上機嫌な彼女に、無一郎はやれやれとでも言いたげな表情でため息を吐いた。
「そんなにため息ばかり吐いてると幸せが逃げるわよ?いいの、おやつは別腹だから問題ない!」
彼女は無一郎の腕に自分の腕を絡ませると、グイッと彼の身体を引っ張り半ば強引に縁側へ座らせた。
「稽古も大事だけど、息抜きも大切よ。たまには街に顔を出して、羽を伸ばすのも楽しいわよ」
手際良く風呂敷を解いていく鳴子の横顔を、少年はぼうっとした様な顔で見つめていた。毎日の様に自分の元へやって来るこの女性は一体何を考えているのか、理解しようとしているのだ。
「…僕が貴方の弟子だったから、構ってくれるの?」
「それもあるわね。…でも私は、単純に貴方が好きだから毎日遊びに来てるのよ。」
優しげな笑みを浮かべてそう答えた彼女に、無一郎はますます訳が分からないといった顔をして首を傾げた。
そんな彼に、鳴子は少し考えるかの様に視線を横へ流したが、すぐに彼の方へ視線を戻すと再び微笑んだ。
「貴方のことが気がかりだから、毎日来てるのよ」
「…気がかり?心配ってこと?…何で、赤の他人の僕のことを心配するの?それに、貴方に心配されるほど僕は弱くないよ?」
更に質問を畳み掛けてくる彼に、鳴子は思わず苦笑いの様な表情を浮かべた。
時透無一郎という少年は、訳あって人としての何かが欠けている。決して彼自身に悪気があるわけではないのだが、人によっては嫌な顔をする者も出てくるだろう。
「そうね、貴方の言ってることは正しいわ。…でもね、人の心って不思議なものなのよ。きっと貴方にも、分かる日がくるわ」
彼だけを特別視している訳ではない。それでも、やはり贔屓してしまうのは事実だ。それは、彼女の中に閉じ込められた悲しい思い出から引き起こされる衝動的な行動でもあった。
「…僕が貴方の弟と同い年だから?」
不意に発せられたその言葉に、鳴子は団子を口に運んでいた手を止めた。そして、怪訝そうな表情で無一郎の顔を凝視した。
「…何故それを?私、貴方にそんな話した?」
紅色の瞳が、真っ直ぐに少年の姿を捉えている。その美しい瞳に捕われた少年は、しばらく黙って彼女の瞳を見つめていたが、やがてすっと視線を逸らすと手に持っていた団子を口へと運んだ。
「別に、何かそんな気がしただけだよ。…よく分からないけど、そんな気がしたんだ」
彼の表情からは、感情が読み取れない。彼が発した言葉も、嘘なのか本当なのかは分からない。でも、鳴子はそれが本当であるということが分かっていた。
「そっか。…そういう事もあるよね」
鳴子はふっと微笑むと、三色団子をパクリと頬張った。とろける様な甘さが口の中に広がるのを感じながら、彼女は視線を頭上へと移動させた。
「今年の最終選別、5人も受かったそうよ。…貴方と歳が近い子ばかりだから、友達になれると良いわね」
「どうでも良いよ」という無一郎の淡々とした返事を聞きながら、鳴子は2つ目の団子に手を伸ばすのだった。
❄︎ ❄︎ ❄︎