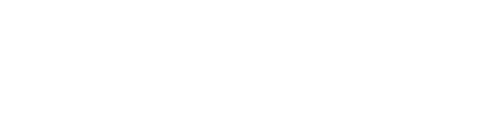第1章
団子が食べたい。町を散策していた鳴子は、不意にそんな欲に駆られた。弟の墓参りを済ませ、お館様と別れた彼女は、そのまま屋敷に戻る気にもなれずふらふらと町まで降りて来たのだった。
鳴子は和菓子屋の前で歩みを止めると、店主に挨拶をした。
「三色団子、3つ下さい」
「おう、お姉さんまた来てくれたのかい」
すっかり常連になった彼女に、店主の男性が嬉しそうな顔で団子の乗った皿を渡す。
「ここのお団子は美味しいから、ついつい来ちゃうんです」
笑顔で店主に会釈すると、鳴子は長椅子に腰掛けた。そして暫くの間、赤、白、緑の三色が綺麗に並べられた皿を見つめていたが、やがてゆっくりと視線を上に向けた。
「良い天気ね…。一人で居るのが寂しくなるわ」
どこまでも続く青。雲がない分、余計に広く感じてしまう。広く感じてしまうから、ここには自分以外誰もいないのではないかと思ってしまう。
「…一人は、寂しい」
彼女の口から溢れたその言葉は、街行く人々の足音に飲み込まれ消えていった。
周囲は賑わっているはずなのに、彼女の目には誰一人として写っていない。彼女の耳にも、周囲の楽しげな笑い声は届いていなかった。
「あら、鳴。どうしたのです?」
無音だった彼女の世界に突然聞こえてきたその声は、穏やかで美しかった。鳴子は声の主の方に視線を向けると、ほっとした様な表情を浮かべた。
「しのぶ…。ああ良かった!ちょうど良いところに来てくれたわ。団子買いすぎちゃったから、一緒に食べましょう?」
3本の三色団子が並んだ皿を顔の高さまで持ち上げ、明るい声でそう言う鳴子を、しのぶは数秒間黙って見つめていた。しかし、すぐに綺麗な笑みを浮かべると、ふんわりとした声で返事をした。
「あら、それは嬉しいですね。遠慮なくいただきます」
「どうぞどうぞ!」
隣に腰掛けたしのぶに皿を差し出すと、しのぶは「ありがとう」と微笑みながら団子を1本口に運んだ。それにつられる様に、鳴子も団子を口に入れる。
口の中に広がる甘さが、体中を癒してくれる。鳴子は、その瞬間が好きだった。
「…やっぱり、美味しいものは誰かと一緒に食べた方が良いわ」
団子を飲み込み、伏せ目がちにそう言う彼女の表情はどこか悲しげだった。そんな彼女に、しのぶは「そうですね」とだけ相槌を打った。
頬を撫でるように吹いている穏やかな風が一瞬強まり、彼女らの髪を揺らした。
「鳴は毎年、この時期になると寂しそうな顔をしますね」
しのぶの言葉に、鳴子は少し困った様な笑みを浮かべて首を傾げた。彼女の白い手に、しのぶの小さな手が重なる。
「分かります、貴方の気持ち。…だから、私の前では強がらなくて良いんですよ」
それを聞いた鳴子は、一瞬大きく目を見開いた。そしてゆっくりとその目を閉じ、再び紅の瞳を開くと、穏やかな笑顔を浮かべた。
「ありがとう、しのぶ。…しのぶも、私の前では無理しなくて良いのよ?」
その言葉に、今度はしのぶの瞳が大きく見開かれる。どくん、と鼓動が大きく鳴ったのを感じながら、彼女は鳴子から目をそらした。
「…貴方は意地が悪いわ」
少し不満げにそう言った彼女を見て、鳴子は楽しそうな笑い声を上げた。
「しのぶにだけは言われたくないなぁ…」
しのぶは少し拗ねた様な表情で鳴子の顔を見つめていたが、楽しげな彼女につられたのか小さく吹き出した。
賑やかな昼間の町に、二人の少女の軽快な笑い声が響き渡った。