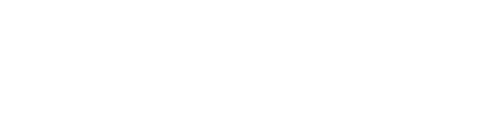第1章
胸が締め付けられるようだった。幸せそうなあの親子を見ていると、己の家族が生きていた日々を思い出して苦しくなる。決して、妬んでいるわけではない。ただ羨ましいだけだった。
「どうか、幸せなまま生きて下さい。私が、守りますから」
静寂の中に、鈴の音の様な声が響き渡る。柔らかく、それでも凛としたその声は、夜空に浮かぶ月へと吸い込まれていく。
月明かりに照らされる少女の横顔は、この世のものとは思えぬ程美しく、今にも消えてしまいそうな程儚げだった。
「…さて、あの子はどうなったかしら」
儚げだった少女の顔が、キリッとした凛々しい顔立ちへと変わる。彼女の容姿によく似合う、気の強そうな笑みを浮かべて目的地へと降り立った。
「まあ、もう片付いたのね!さすが霞柱様だわ」
消えゆく鬼の身体の前で、日輪刀を腰に納めている少年に、鳴子は明るい声で話しかけた。
その声を聞いた少年は、微かに首を捻り彼女の方に目を向けた。相変わらず正気の感じられない瞳に、鳴子の白くて美しい顔が映っている。
「私の仕事、無くなっちゃったね。貴方と一緒だと楽ができて嬉しいわ」
鳴子はにこやかな表情で少年に近付くと、自分とほぼ同じ位置にある彼の頭に手を置いた。
少年の瞳が一瞬大きく見開かれたが、直ぐに普段通りの表情に戻りパッと彼女の手を振り払った。
「貴方があんな子どもに構ってるからでしょ?わざわざ送り届けなくても隠がどうにかしてたよ」
相変わらず刺々しい口調で正論を振りかざす彼に、鳴子は「厳しいなぁ」と苦笑いの様な表情で首を傾げた。
「何も厳しくなんてないよ。僕は普通の事を言ってるだけ」
彼が毒舌なのはいつものことだが、今日は一段と当たりが強く感じる。
機嫌が悪いのか、と視線を逸らしたその先に、一輪の白い花が月の光を求めるかの如く咲いていた。
「…月下美人」
思わず、胸に手を当てた。何という偶然だろう。先程の幼い少年が探していた、満月の夜しか咲かないと云われる希少な花が、目の前に咲き誇っているのだ。
「…何?」
突然驚きの表情を浮かべた鳴子に、少年が怪訝そうな顔で彼女の視線の先を辿る。
「…っ!!」
少年は、自分の鼓動が大きく波打つのを感じた。常に霧がかっていた脳内が、急に晴れたような不思議な感覚を覚えた。
「…月下、美人…」
ゆっくりと、花の名前を口にする。その名前に、その白く上品な佇まいに覚えがあった。
目を見開いたまま動かなくなった彼を不思議に思った鳴子は、「どうしたの?」と彼の顔を覗き込んだ。
少年の瞳がゆっくりと彼女の姿をとらえた。その姿は、月下に咲き誇る花のように白く美しい。
「…知ってる。僕、貴方のこと知ってる!」
突然、少年が勢いよく鳴子の肩を掴んだ。常に霞がかっていた彼の瞳に、一点の光が灯される。
突拍子ない彼の言葉に、鳴子は面食らってしまった。そして次の瞬間、彼の行動が意味することに気付いた。
「そりゃ知ってるでしょう。一緒に任務する仲だもの」
何を言っているの、とでも言いたげに眉を下げて笑う彼女だが、内心穏やかではなかった。閉ざされていた彼の記憶が戻りかけてしまったことに、焦りを覚えていた。
「違う!もっと前から、貴方のこと…」
「竈門炭治郎、竈門禰豆子拘束!!」
鎹烏の声が、少年の言葉を遮った。2人は弾かれたように烏の方に目を向ける。
「あら、どうしたのかしら」
鳴子は微かに顔をしかめたが、理由はどうあれこの状況を打開してくれた鎹烏の知らせに感謝した。
しらばっくれる事なら幾らでもできるが、その後の罪悪感を思うと辛かった。
「気になるわね…。無一郎のおかげで任務も終わったことだし、行きましょうか」
差し出された白く細い手を、少年は無言で見つめていた。晴れたはずの霧が、再び彼の頭の中を埋め尽くしていく。
──あれ、何だったっけ?
つい先程まで、彼女に何か言いたいことがあったはずなのに忘れてしまった。何か、大切なことを思い出したような気がしたのに忘れてしまった。
無一郎がそっと目を閉じると、いつも通り霧のかかった世界が姿を表す。
──まあ、いいか
どうせ、考えても分からないのだ。きっと、然程大事なことではなかったのだろう。
「貸し一つね。今度何かお礼してよ」
無一郎は淡々とした表情で、目の前の少女にそう言った。差し出されていた手は取らず、彼女に背を向ける。
「喜んで。貴方の望みなら何でも叶えてあげる」
鳴子はにこやかに微笑むと、少し先を歩く無一郎の背中をじっと見つめた。その背中はまだまだ子どもで、何故こんな小さな子が戦わなければならないのかと悲しいような悔しいような気持ちになる。かつて守れなかった幼い弟と同い年の彼が、刃を握って鬼の頸を切るこの状況はどう考えても異常だ。
「私がもっと強ければ…」
そう言いかけて口をつぐむ。自分の良くない癖が出てきたと静かに首を横に振れば、ずっと前を歩いていたはずの少年が立ち止まって鳴子の方を見ていた。鳴子は少し驚いてニ、三度瞬きしたが、すぐに彼の元へ近寄るといたずらっ子の様に顔を覗き込んだ。
「なぁに?何か欲しいものでもあるの?」
「…さっき、何か言った?」
「いいえ何も。私に一人で喋る趣味はないわ」
「…何か、聞こえた気がしたんだけど」
「気のせいでしょう。よくあることだわ」
優しい眼差しに何度も射抜かれ、なんとも形容し難い気持ちを抱いては捨ててきたことを、彼女は知る由もないのだ。
少年は空を見上げた。真上にあった月は、いつの間にか西の空へと移動していた。
❄︎ ❄︎ ❄︎
7/7ページ