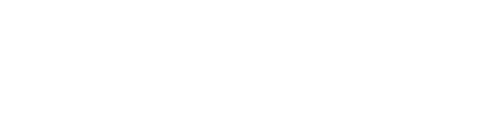第1章
「ねえ坊や。どうして夜遅く出歩いていたの?」
少年の手を引きながら、鳴子は優しく彼に問いかけた。少年は暫くおどおどしていたが、鳴子の顔を見上げると意を決した様に言葉を発した。
「お母さんにね、お花を摘んで帰りたかったの。…夜にしか咲かない、白くて綺麗なお花」
それを聞いた鳴子の顔がほんの少し強張った。何故なら彼女は、同じような台詞を過去に聞いたことがあるからだ。忘れもしない、まるで今日をなぞるような月の綺麗な夜のことだった。
──お姉ちゃんに、見せてあげたかったの
──鳴さんに、似合うなと思って
そう言って目を見張るくらいに美しい白く優雅な花を差し出してくれたのは、はるか昔に亡くなった弟と、弟のように可愛がっていた男の子だ。優しく哀しい記憶だが、決して忘れたくない、忘れられるはずのない大切な記憶だった。
「…そっかぁ、優しいのねぇ。でも、貴方が死んでしまったらお母さん悲しむわ」
鳴子は悲しげな微笑みを浮かべて少年の頭を撫でる。ついさっき会ったばかりの小さな子どもの行動が、決して忘れられない記憶と重なったことに戸惑いながらも懐かしく感じ、幸せだった日々を思い出して泣きそうになった。
でも、今の彼女は鬼殺隊の柱だ。穏やかで心優しい少女であることに変わりはないが、柱になった4年前から私情で心を乱されることがないよう気をつけていた。
「お母さんはね、貴方が生きてるだけで幸せなのよ。だから、今度からはお昼に咲く綺麗な花を贈ってあげたら良いわ」
コクリと頷いた少年の頭をもう一度撫でると、鳴子はゆっくり視線を上方に向けた。藍色の空に、青白い満月が見事に輝いている。
「…ああ、今日は気持ちの良い夜ね。貴方に取っては辛い夜だったかもしれないけど、どうかこの日を忘れないで」
──鬼という存在を忘れないで
──彼らに奪われた哀れな命を忘れないで
──そんな鬼を密かに狩る人間がいることを忘れないで
──人々の命を守るために自らの命を懸けている人間がいること、どうか覚えていて
「うん、忘れない。…お姉ちゃんのこと、絶対忘れない」
彼女の心の声が聞こえたのだろうか、少年は凛とした表情で鳴子の瞳を見つめた。繋いでいた手の力が強くなったのを感じた鳴子は、ふっと優しく笑った。
「うん、ありがとう」
少年の小さな手が、亡くなった弟の手と重なる。旭もちょうど、この少年と同じくらいの歳だった。旭も自分のことを、「お姉ちゃん」と呼んでいた。
「奏多!!」
過去を思い出していた鳴子の耳に、突然大きな声が届いた。酷く狼狽したような、甲高い声だった
「奏多…!!貴方どこに行ってたの!!」
前方から駆けてくるその女性は、恐らく少年の母親だろう。結い上げた黒髪と、質素な着物が乱れている。
「お母さんに、お花をあげたかったんですって」
穏やかな声でそう言う鳴子を、女性は驚いた顔で見つめた。我が息子が見慣れない少女と一緒にいることに混乱しているのか、瞳が大きく揺らいでいる。
「優しい息子さんですね。…でも、夜は鬼が出ます。この子も危なかったんですよ。だからどうか、今後は気を付けて」
それを聞いた女性は、「まあっ!」と怯えた様な顔をした。そして、鳴子の隣に立っている少年を抱きしめると、「良かった」と繰り返すのだった。
「家はこの近くですか?」
心温まる親子のやり取りを見ていた鳴子は、微笑みを浮かべ彼らに問いかけた。
「はい。直ぐそこでございます。…本当に、何とお礼を申し上げたら良いか」
女性はそう言うと、彼女に深々と頭を下げた。それを見た鳴子は、ゆっくりと首を横に振る。
「いいえ、私は当然のことをしただけです。それでは、失礼しますね。…奏多くん、お母さんを大切にね」
鳴子はそっと少年の頭を撫でると、くるりと彼らに背を向けた。
「お姉ちゃん、ありがとう!!」
背後から聞こえてきた可愛らしい声に、自然と頬が緩む。鳴子は振り返ると、親子に大きく手を振りその場から姿を消したのだった。
❄︎ ❄︎ ❄︎