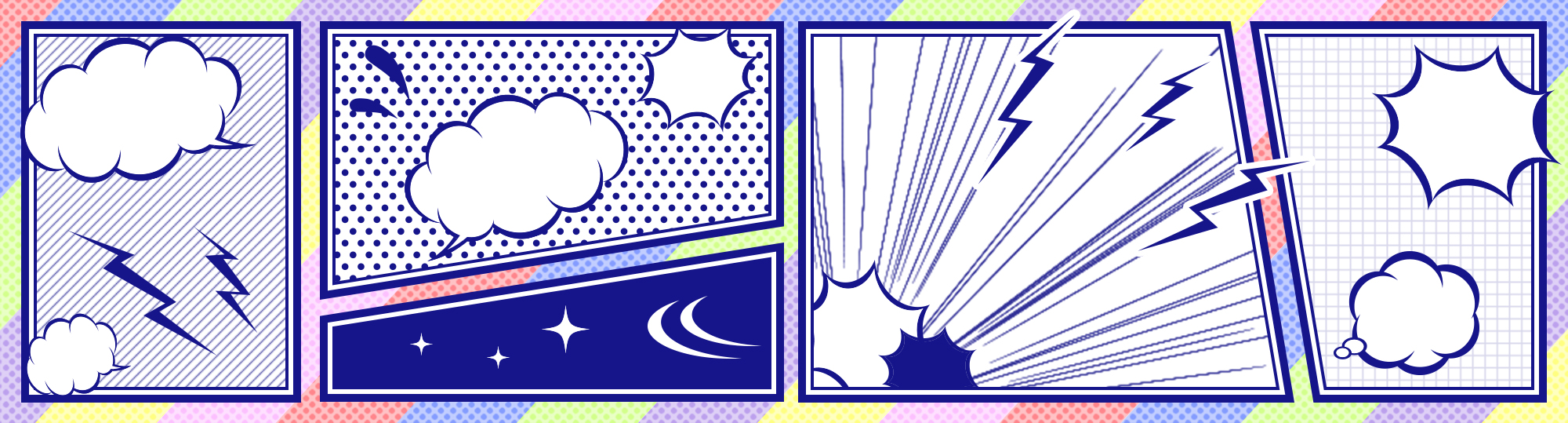COMMANDE
夢小説設定
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
1
切羽詰まっていたとはいえ、先を急ぎ過ぎていたと冷静になった今では思う。
しかしもう遅いのだ。
私はもう…
此処の一部なのだから。
=レストラン・ワグナリア=
授業が終わり、部活が終わると同時に履歴書と鞄を片手に学校を飛び出した。
生まれて十七年、まさか自分がバイトをする日がこようとは……はっきり言って思いもしなかった。
今まで小遣いの額には満足していたし、趣味が読書程度しか無いから小遣いだけでも十分やっていけていた。
けれど無理になった。
本を読めば読む程本を読む速度は増し、ひと月に本の為に消費する金も増え続けた。
増えに増えて…はっきり言って小遣いじゃ足りなくなった。
だからバイトをする事にした。
『ホールスタッフ希望…宮本 京、高三の十七です』
「そうか」
履歴書の入った封筒を見ながらそう呟いた此処、レストラン“ワグナリア”の店長、白藤 杏子は空いていた手で己の腹を押さえながら京を見据えた。
「腹減った。お前何か持ってないか?」
『……クッキーでよければ』
何事かと思いながらも京は鞄から可愛らしい包みを取り出し、杏子に差し出した。
杏子はその包みを開けると黙々とクッキーを食べ続けた。そして空になった包みを京に差し出す。
「…美味かった」
『後輩がくれたんです』
差し出された包みを“要らないです”と返すと、杏子は包みをゴミ箱に捨てながら納得した様に二・三度頷いた。
自分だけで納得されても困る。こっちには何に納得したのかさえ分からない。
「うむ、採用」
『は?』
何か…変な言葉を聞いた気がする。
履歴書を渡しただけ…因みに出会って二分で、店長は履歴書を目の前の机の上に置いただけで目も通して無い。
それなのに……採用?
「採用だ、採用。ホールスタッフに採用だ。着替えろ」
差し出された制服は確かにワグナリアの物だった。
店長は…いやもうあの人を店長だとは思え無い。杏子さんは制服を手渡すとさっさと部屋を出て行ってしまった。
バイトの面接に来て早、五分…
“もう仕事始めんのかよ”という思いと“こんなんで此の店大丈夫なのか”という考えを無かった事にして京はその場で制服に着替えた。
誰もいないし別に良いだろ。面倒臭いし別に支障は無いのでベストの上から制服を着た。
帯を締めながら部屋を出ると、杏子さんが壁に凭れ掛かって待っていた。
『お待たせしました』
「良し、行くぞ」
廊下の真ん中をヒールの音を立てて堂々と歩く杏子さんの後を唯着いて行った。
ホールに行くのかと思ったら、ホールよりも手前にあるキッチンに連れて行かれた。
「佐藤、相馬」
そう呼ばれて、キッチンに居た二人の男のうち背の低い方は振り返ったが、金髪の長身は振り返りもしない。
「あぁ、店ちょ」
「食いもんは無いぞ」
背の低い方…優男の様な奴の言葉を遮ってそう言う金髪の言葉が引っ掛かった。
…食いもんは無いぞ?
「いや佐藤、あるだろう…こんなに沢山」
「これは全部客のもんだ」
そりゃそうだ。
“何だこのやり取りは”と傍観していると、優男…相馬さんがニッコリと笑った。
「店長、用があったんじゃないですか?」
“この子誰ですか?”と言う優男に、杏子さんは小さく唸った。
「新しく入った奴だ」
随分簡潔で…
『宮本 京です、宜しく』
「新人さんか」
「“物好き”だろ」
「やだなぁ、佐藤くん~犠牲者と言えるかもしれないよ」
アハハと楽しそうに笑った相馬さんは“で?”と首を傾げた。
「君は何でそれ着てるの?」
『ぇ…キッチンに連れてこられましたが、キッチンではなくホールスタッフなので』
「…へぇ、じゃあさ~」
「佐藤、飯」
「だからお前にやる食いもんは無ぇつっでんだろ」
「何か作ってくれ」
「作らない」
「腹減って死ぬ」
「知るか!」
「杏子さ~ん」
そう第三者の声がして振り返ると、ホールスタッフの制服を着た女の人が、パフェを手にキッチンに入って来る所だった。
面接の為にこの店に入って、一番最初に目に入り、声を掛けた人だった。
……って…んん?何だあれ。
「杏子さんにパフェ作ったんです」
「でかした、八千代」
片手でパフェを受け取って上機嫌で女の人の頭を撫でる杏子さんは、どこか生意気な子供の様だ。
そして…恋でもしている様に頬を赤く染めているあの女の人は一体…
「八千代、そいつにかまってないで仕事しろ」
「ウフフ、全部終わっちゃったのよ…今日は人手が多いし、今はお客さんもいないのよ、さとーくん」
客が居ないから店長にパフェ作るってどういう事よ?
って言うか…ほんと何あれ…
気になる。物凄くこの人が気になる。
『ぁ…』
「気にしなくていいよ。轟さんは店長が大好きで、店長に尽くすのが生き甲斐な人だから」
いや、そこも少しは気になったが、問題はそこじゃない。
何より気になって仕方が無いのは…
腰に巻き付けているソレだ!
店に入った時はカウンター越しで気付かなかったが、この女の人は、結び付ける様に腰に刀を巻き付けているのだ。
模造刀か本物かは知らないが一体なんで……いや、本物なら銃刀法違反で疾うに捕まっている筈だ…模造刀なんだろう。
………いや、模造刀でも危険物で銃刀法が…じゃなくて、そもそも何であんなもの巻き付け…
「轟さんね、家が金物屋さんなんだって」
『そういう問題じゃ無いだろう』
そこまで口にして、京は不機嫌そうに後退った。
『人の心を読むな』
「読んでないよ~普通、初めて轟さん見たらアレが気になるでしょ」
『せめてきり出し方考えろよ』
「アハハ、ごめんね~」
「山田、お前一日に何枚皿割ったら気が済むんだ!!」
瞬間、一際大きな声が聞こえた。
別にキッチンが静かだったわけじゃないのに、その声はやたらと響いた。
“あ~ぁ、またやったんだ山田さん”と言う相馬さんの呟きからするに、いつもの事なのだろう。
「ま…まあまあ、カタナシくん」
「そうです、山田は可愛い~新人ですよ、小鳥遊さん」
「葵ちゃ…」
「入ってから随分経ったが?」
「カタナシく…」
「山田はいつまでも皆に愛される可愛い~新人です!!」
「今日だけで皿七枚に、カップ二個も割っといてよくそんな事言えるな」
“素直にあやまれよ”と言う男の声に思わず“全くだ”と頷いてしまった。
第一、どうやったらそんなに割れるんだ……京がそう考える中、声の主である三人の足音は段々とキッチンに近付いてきていた。
「フッフッフッ…まだまだですね、小鳥遊さん」
「は?」
「パフェグラスも割りました!!」
「やかましい、えばるな!」
「もう、葵ちゃん!か、カタナシくん、落ち着いて!」
「いくら可愛い先輩の頼みであっても無理です!」
「小鳥遊さん、ひどい!」
「お前は黙ってろ、山田!」
……会話から察するに…
ヤマダ アオイ(女)が日常的に食器類を割り、タカナシ(或いはカタナシ)が怒り、一番年上であろう先輩(女)が宥めている、と…
ヤマダは茶目っ気のある問題児、タカナシ(或いはカタナシ)は真面目でしっかり者か短気、先輩は平和的タイプって所かな…
「凄い分析してるねぇ」
『だから人の心を読むなと言った…でしょう』
「読んでないよ~、難しい顔してるからそうかと思っただけ。ぁ、別に敬語使わなくて良いからね」
京が深く溜め息をついた瞬間、三人がなだれ込む様にキッチンに入って来た。
「店長、山田が…!って、あれ…どちら様ですか?」
「新しく入った奴だ」
『宮本 京です、宜しく』
「私、種島 ぽぷらだよ!」
「小鳥遊 宗太です、よろしくおねがいします」
中学生…下手すれば小学生にも見えそうな小さくて可愛らしい少女と眼鏡の少年に挨拶されて“やっぱり小鳥遊だったか”そう思った瞬間、切り揃えられた長い黒髪に釣り目の少女に両手を握られた。
「山田のお兄さんになって下さい!!」
『…は?』
意味が分からない。
と言うか君がヤマダ アオイなのか。
「宮本さんかっこいいです!!佐藤さんみたいに意地悪ではなさそうですし、ぜひ山田の家族に!!」
「おい、一言余計だ」
「山田の素敵家族計画がまた一歩前進しました!」
嬉しそうに抱き付かれ、京は困った様に山田の頭を撫でた。
まだ了承してないんだけどな…
「ふっふ~、やっぱり予想通り宮本さんは優しいです!山田を甘やかしてくれる人がまた増えました!」
甘やか…それでいいのか?
「で、宮本さんは何でそっちの服着てるの?」
『だから、ホールスタッフだからって言ってるでしょ』
何故、何度も聞く。
「あぁ、キッチン人数少ないですよね」
「相馬さんとさとーさんだけだもんねぇ」
「ホールは人多いですよね、賑やかで山田は好きです!あ、でもどうしてもと言うなら、山田がキッチンを手伝ってあげなくもないですよ!」
「お前なんぞ要らん」
「ひどい!」
自分の言葉に涙目になった山田を無視し、佐藤は京に目を向けた。
「小鳥遊か宮本なら…まあ良い」
佐藤さんの言葉に、杏子さんはパフェを食べながら小さく唸った。
「小鳥遊は伊波と山田の担当だしな…宮本、お前キッチンになるか」
『遠慮します』
ホールを志願して採用。ホールの制服も着てるのに、何もしないでキッチンに回されるなんて嫌だ。
「ぁ、じゃ、じゃあ杏子さん、私が…」
「八千代、お前はチーフだろ」
『…チーフなんですか?!』
杏子さんが店長で、帯刀してる八千代さんがチーフって…オーナー、何考えてるの?
「えぇ、そうなのよ私…」
「それに八千代がいないとパフェが食えなくて困る」
「きょーこさん!私、ずっとホールにいますね!!」
実際目には見えないが…大量のハートを飛ばしながら八千代さんはそう言って杏子さんに寄り添った。
「食べなくていいんです!チーフも餌与えないで下さい!!」
小鳥遊の言う通りだ。
何なのこの二人。
『あの、佐藤さん…』
「何だ」
『これ…もしかして日常茶飯事なんですか?』
「あぁ、ここの…」
「あ、あの…!」
佐藤さんの言葉はそう焦った声に遮られた。
と言うか、その声が聞こえた瞬間、佐藤さんが黙って相馬さんと同時に数歩後退った。
キッチンの入り口を見れば、ヘアピンを付けたショートカットの少女が顔を覗かせていた。
「皆こっちに来ちゃったら困るよ~せっかくお客さん来たのに、私じゃ男のお客さん接客出来な‥…」
そこまで口にして、ヘアピンの少女は目を見開いた。
「京先輩?!なな、何でココに…!!」
『…あぁ、うちの高校の子?』
固まってがっつり見られたから、一瞬何かと思った。
『ホールバイトの面接に来てね…面接だけのつもりが何故か即、初日開始だよ』
「えぇ?!」
「………ぇ…え、宮本さん、伊波ちゃんの学校の人なの?!」
種島の言葉に、小鳥遊と佐藤は首を傾げた。
「……あれ?伊波さんって女子高じゃなかったですっけ?」
「そ、そうだよ?」
「男嫌いなんだから共学なわけ無ぇよな…」
「って事は…」
小鳥遊と佐藤が京に目を向ける中、今度は種島と轟が首を傾げた。
「え、何々?」
「…いいですか?宮本さんは“女子高に通ってる伊波さん”の先輩なんですよ」
「…は、山田分かりました!!!」
「伊波ちゃんの先輩……ぁ!」
「まひるちゃんの……ぁ!」
「「宮本さん(くん)、女の子なの?!」」
種島と轟がそれに気付いた瞬間、相馬が楽しそうに笑った。
「だからさっき言ったじゃない。“何でそっちの服着てるの?”って」
『あぁ、そういう意味だったの』
「はっきり言って下さいよ、相馬さん。失礼な話ですが…男性だと思ってましたよ」
言い辛そうにそう口にした小鳥遊の隣で、杏子は食べ終わったパフェのグラスを作業台に置くと、フンと鼻を鳴らした。
「こいつ、制服ズボン履いてたぞ」
『部活の後、直ぐ来たんで』
「先輩は演劇部員なんです。うちは女子高なんで、男役は殆ど京先輩がやってるんですよ」
「お前、履歴書はどうした」
「貰ったが見てない」
「アホか」
「あぁ、だから店長は間違えたんだね。俺は胸が無いから少し迷ったよ」
“アハハ”と楽しそうに笑う相馬を佐藤が手にしていたお玉で殴り、山田は目を輝かせた。
「伊波さん、お仲間ですね!」
「山田さん!!」
「宮本さん、何カップですか?」
「や、山田さ…」
涙目だった伊波の表情が青く染まる中、京は山田に耳打ちした。
「……そうは見えません」
『あぁ、胸潰すベスト着てるから』
「伊波さん、お仲間じゃなかったです!」
「…山田さん……」
すっかり落ち込んだ彼女は、胸の大きさで悩んでるんだろうか?
可愛らしいが…可哀想に、今のは痛手だろう。
「最近のベストは有能です!」
「え、そんなにあるの?」
「相馬さん、セクハラです」
仄かに頬を赤く染めた小鳥遊が困った様にそう口にし、佐藤が今度はフライパンで相馬を殴った。
「紛らわしい」
不機嫌そうな佐藤を前に、京は困った様に笑った。
『場当たりがおして…約束の面接時間に間に合わなそうだったんで、鞄だけ持って衣装のまんま来ちゃいました』
「何で、女だと言わない」
『間違えられてるとは思わず』
「ホールの制服は」
『あんまり深く考えてませんでした』
呆れた様に溜め息をついた佐藤さんは“おい”と杏子さんに声を掛けた。
「客が誤解する…制服、女もん出してやれ」
「あぁ、そうだな」
「おい、着替えて来い」
『因みに…これウィッグなんですが』
「全部取って来い」
ピ──ン、ポ────ン…
決して静かでは無かったキッチンに、今度はそう聞き覚えのある音が響いた。
ピンポーンって…
「「「「お客さん!!!」」」」
青くなってそう叫んだホールスタッフの四人は、口々に何かを口にしながらホールへと走って行った。何て慌しい…
『そういえば、さっき男性客がどうのって言ってましたね』
「あぁ」
『この店大丈夫なんですか?』
「ダメだな」
佐藤は言い切った。
そして京は、困った様に小さく乾いた笑いをもらした。
なんだかな…
ここは考えていたものと大分違う気がする…
切羽詰まっていたとはいえ、先を急ぎ過ぎていたと冷静になった今では思う。
しかしもう遅いのだ。
私はもう…
此処の一部なのだから。
=レストラン・ワグナリア=
授業が終わり、部活が終わると同時に履歴書と鞄を片手に学校を飛び出した。
生まれて十七年、まさか自分がバイトをする日がこようとは……はっきり言って思いもしなかった。
今まで小遣いの額には満足していたし、趣味が読書程度しか無いから小遣いだけでも十分やっていけていた。
けれど無理になった。
本を読めば読む程本を読む速度は増し、ひと月に本の為に消費する金も増え続けた。
増えに増えて…はっきり言って小遣いじゃ足りなくなった。
だからバイトをする事にした。
『ホールスタッフ希望…宮本 京、高三の十七です』
「そうか」
履歴書の入った封筒を見ながらそう呟いた此処、レストラン“ワグナリア”の店長、白藤 杏子は空いていた手で己の腹を押さえながら京を見据えた。
「腹減った。お前何か持ってないか?」
『……クッキーでよければ』
何事かと思いながらも京は鞄から可愛らしい包みを取り出し、杏子に差し出した。
杏子はその包みを開けると黙々とクッキーを食べ続けた。そして空になった包みを京に差し出す。
「…美味かった」
『後輩がくれたんです』
差し出された包みを“要らないです”と返すと、杏子は包みをゴミ箱に捨てながら納得した様に二・三度頷いた。
自分だけで納得されても困る。こっちには何に納得したのかさえ分からない。
「うむ、採用」
『は?』
何か…変な言葉を聞いた気がする。
履歴書を渡しただけ…因みに出会って二分で、店長は履歴書を目の前の机の上に置いただけで目も通して無い。
それなのに……採用?
「採用だ、採用。ホールスタッフに採用だ。着替えろ」
差し出された制服は確かにワグナリアの物だった。
店長は…いやもうあの人を店長だとは思え無い。杏子さんは制服を手渡すとさっさと部屋を出て行ってしまった。
バイトの面接に来て早、五分…
“もう仕事始めんのかよ”という思いと“こんなんで此の店大丈夫なのか”という考えを無かった事にして京はその場で制服に着替えた。
誰もいないし別に良いだろ。面倒臭いし別に支障は無いのでベストの上から制服を着た。
帯を締めながら部屋を出ると、杏子さんが壁に凭れ掛かって待っていた。
『お待たせしました』
「良し、行くぞ」
廊下の真ん中をヒールの音を立てて堂々と歩く杏子さんの後を唯着いて行った。
ホールに行くのかと思ったら、ホールよりも手前にあるキッチンに連れて行かれた。
「佐藤、相馬」
そう呼ばれて、キッチンに居た二人の男のうち背の低い方は振り返ったが、金髪の長身は振り返りもしない。
「あぁ、店ちょ」
「食いもんは無いぞ」
背の低い方…優男の様な奴の言葉を遮ってそう言う金髪の言葉が引っ掛かった。
…食いもんは無いぞ?
「いや佐藤、あるだろう…こんなに沢山」
「これは全部客のもんだ」
そりゃそうだ。
“何だこのやり取りは”と傍観していると、優男…相馬さんがニッコリと笑った。
「店長、用があったんじゃないですか?」
“この子誰ですか?”と言う優男に、杏子さんは小さく唸った。
「新しく入った奴だ」
随分簡潔で…
『宮本 京です、宜しく』
「新人さんか」
「“物好き”だろ」
「やだなぁ、佐藤くん~犠牲者と言えるかもしれないよ」
アハハと楽しそうに笑った相馬さんは“で?”と首を傾げた。
「君は何でそれ着てるの?」
『ぇ…キッチンに連れてこられましたが、キッチンではなくホールスタッフなので』
「…へぇ、じゃあさ~」
「佐藤、飯」
「だからお前にやる食いもんは無ぇつっでんだろ」
「何か作ってくれ」
「作らない」
「腹減って死ぬ」
「知るか!」
「杏子さ~ん」
そう第三者の声がして振り返ると、ホールスタッフの制服を着た女の人が、パフェを手にキッチンに入って来る所だった。
面接の為にこの店に入って、一番最初に目に入り、声を掛けた人だった。
……って…んん?何だあれ。
「杏子さんにパフェ作ったんです」
「でかした、八千代」
片手でパフェを受け取って上機嫌で女の人の頭を撫でる杏子さんは、どこか生意気な子供の様だ。
そして…恋でもしている様に頬を赤く染めているあの女の人は一体…
「八千代、そいつにかまってないで仕事しろ」
「ウフフ、全部終わっちゃったのよ…今日は人手が多いし、今はお客さんもいないのよ、さとーくん」
客が居ないから店長にパフェ作るってどういう事よ?
って言うか…ほんと何あれ…
気になる。物凄くこの人が気になる。
『ぁ…』
「気にしなくていいよ。轟さんは店長が大好きで、店長に尽くすのが生き甲斐な人だから」
いや、そこも少しは気になったが、問題はそこじゃない。
何より気になって仕方が無いのは…
腰に巻き付けているソレだ!
店に入った時はカウンター越しで気付かなかったが、この女の人は、結び付ける様に腰に刀を巻き付けているのだ。
模造刀か本物かは知らないが一体なんで……いや、本物なら銃刀法違反で疾うに捕まっている筈だ…模造刀なんだろう。
………いや、模造刀でも危険物で銃刀法が…じゃなくて、そもそも何であんなもの巻き付け…
「轟さんね、家が金物屋さんなんだって」
『そういう問題じゃ無いだろう』
そこまで口にして、京は不機嫌そうに後退った。
『人の心を読むな』
「読んでないよ~普通、初めて轟さん見たらアレが気になるでしょ」
『せめてきり出し方考えろよ』
「アハハ、ごめんね~」
「山田、お前一日に何枚皿割ったら気が済むんだ!!」
瞬間、一際大きな声が聞こえた。
別にキッチンが静かだったわけじゃないのに、その声はやたらと響いた。
“あ~ぁ、またやったんだ山田さん”と言う相馬さんの呟きからするに、いつもの事なのだろう。
「ま…まあまあ、カタナシくん」
「そうです、山田は可愛い~新人ですよ、小鳥遊さん」
「葵ちゃ…」
「入ってから随分経ったが?」
「カタナシく…」
「山田はいつまでも皆に愛される可愛い~新人です!!」
「今日だけで皿七枚に、カップ二個も割っといてよくそんな事言えるな」
“素直にあやまれよ”と言う男の声に思わず“全くだ”と頷いてしまった。
第一、どうやったらそんなに割れるんだ……京がそう考える中、声の主である三人の足音は段々とキッチンに近付いてきていた。
「フッフッフッ…まだまだですね、小鳥遊さん」
「は?」
「パフェグラスも割りました!!」
「やかましい、えばるな!」
「もう、葵ちゃん!か、カタナシくん、落ち着いて!」
「いくら可愛い先輩の頼みであっても無理です!」
「小鳥遊さん、ひどい!」
「お前は黙ってろ、山田!」
……会話から察するに…
ヤマダ アオイ(女)が日常的に食器類を割り、タカナシ(或いはカタナシ)が怒り、一番年上であろう先輩(女)が宥めている、と…
ヤマダは茶目っ気のある問題児、タカナシ(或いはカタナシ)は真面目でしっかり者か短気、先輩は平和的タイプって所かな…
「凄い分析してるねぇ」
『だから人の心を読むなと言った…でしょう』
「読んでないよ~、難しい顔してるからそうかと思っただけ。ぁ、別に敬語使わなくて良いからね」
京が深く溜め息をついた瞬間、三人がなだれ込む様にキッチンに入って来た。
「店長、山田が…!って、あれ…どちら様ですか?」
「新しく入った奴だ」
『宮本 京です、宜しく』
「私、種島 ぽぷらだよ!」
「小鳥遊 宗太です、よろしくおねがいします」
中学生…下手すれば小学生にも見えそうな小さくて可愛らしい少女と眼鏡の少年に挨拶されて“やっぱり小鳥遊だったか”そう思った瞬間、切り揃えられた長い黒髪に釣り目の少女に両手を握られた。
「山田のお兄さんになって下さい!!」
『…は?』
意味が分からない。
と言うか君がヤマダ アオイなのか。
「宮本さんかっこいいです!!佐藤さんみたいに意地悪ではなさそうですし、ぜひ山田の家族に!!」
「おい、一言余計だ」
「山田の素敵家族計画がまた一歩前進しました!」
嬉しそうに抱き付かれ、京は困った様に山田の頭を撫でた。
まだ了承してないんだけどな…
「ふっふ~、やっぱり予想通り宮本さんは優しいです!山田を甘やかしてくれる人がまた増えました!」
甘やか…それでいいのか?
「で、宮本さんは何でそっちの服着てるの?」
『だから、ホールスタッフだからって言ってるでしょ』
何故、何度も聞く。
「あぁ、キッチン人数少ないですよね」
「相馬さんとさとーさんだけだもんねぇ」
「ホールは人多いですよね、賑やかで山田は好きです!あ、でもどうしてもと言うなら、山田がキッチンを手伝ってあげなくもないですよ!」
「お前なんぞ要らん」
「ひどい!」
自分の言葉に涙目になった山田を無視し、佐藤は京に目を向けた。
「小鳥遊か宮本なら…まあ良い」
佐藤さんの言葉に、杏子さんはパフェを食べながら小さく唸った。
「小鳥遊は伊波と山田の担当だしな…宮本、お前キッチンになるか」
『遠慮します』
ホールを志願して採用。ホールの制服も着てるのに、何もしないでキッチンに回されるなんて嫌だ。
「ぁ、じゃ、じゃあ杏子さん、私が…」
「八千代、お前はチーフだろ」
『…チーフなんですか?!』
杏子さんが店長で、帯刀してる八千代さんがチーフって…オーナー、何考えてるの?
「えぇ、そうなのよ私…」
「それに八千代がいないとパフェが食えなくて困る」
「きょーこさん!私、ずっとホールにいますね!!」
実際目には見えないが…大量のハートを飛ばしながら八千代さんはそう言って杏子さんに寄り添った。
「食べなくていいんです!チーフも餌与えないで下さい!!」
小鳥遊の言う通りだ。
何なのこの二人。
『あの、佐藤さん…』
「何だ」
『これ…もしかして日常茶飯事なんですか?』
「あぁ、ここの…」
「あ、あの…!」
佐藤さんの言葉はそう焦った声に遮られた。
と言うか、その声が聞こえた瞬間、佐藤さんが黙って相馬さんと同時に数歩後退った。
キッチンの入り口を見れば、ヘアピンを付けたショートカットの少女が顔を覗かせていた。
「皆こっちに来ちゃったら困るよ~せっかくお客さん来たのに、私じゃ男のお客さん接客出来な‥…」
そこまで口にして、ヘアピンの少女は目を見開いた。
「京先輩?!なな、何でココに…!!」
『…あぁ、うちの高校の子?』
固まってがっつり見られたから、一瞬何かと思った。
『ホールバイトの面接に来てね…面接だけのつもりが何故か即、初日開始だよ』
「えぇ?!」
「………ぇ…え、宮本さん、伊波ちゃんの学校の人なの?!」
種島の言葉に、小鳥遊と佐藤は首を傾げた。
「……あれ?伊波さんって女子高じゃなかったですっけ?」
「そ、そうだよ?」
「男嫌いなんだから共学なわけ無ぇよな…」
「って事は…」
小鳥遊と佐藤が京に目を向ける中、今度は種島と轟が首を傾げた。
「え、何々?」
「…いいですか?宮本さんは“女子高に通ってる伊波さん”の先輩なんですよ」
「…は、山田分かりました!!!」
「伊波ちゃんの先輩……ぁ!」
「まひるちゃんの……ぁ!」
「「宮本さん(くん)、女の子なの?!」」
種島と轟がそれに気付いた瞬間、相馬が楽しそうに笑った。
「だからさっき言ったじゃない。“何でそっちの服着てるの?”って」
『あぁ、そういう意味だったの』
「はっきり言って下さいよ、相馬さん。失礼な話ですが…男性だと思ってましたよ」
言い辛そうにそう口にした小鳥遊の隣で、杏子は食べ終わったパフェのグラスを作業台に置くと、フンと鼻を鳴らした。
「こいつ、制服ズボン履いてたぞ」
『部活の後、直ぐ来たんで』
「先輩は演劇部員なんです。うちは女子高なんで、男役は殆ど京先輩がやってるんですよ」
「お前、履歴書はどうした」
「貰ったが見てない」
「アホか」
「あぁ、だから店長は間違えたんだね。俺は胸が無いから少し迷ったよ」
“アハハ”と楽しそうに笑う相馬を佐藤が手にしていたお玉で殴り、山田は目を輝かせた。
「伊波さん、お仲間ですね!」
「山田さん!!」
「宮本さん、何カップですか?」
「や、山田さ…」
涙目だった伊波の表情が青く染まる中、京は山田に耳打ちした。
「……そうは見えません」
『あぁ、胸潰すベスト着てるから』
「伊波さん、お仲間じゃなかったです!」
「…山田さん……」
すっかり落ち込んだ彼女は、胸の大きさで悩んでるんだろうか?
可愛らしいが…可哀想に、今のは痛手だろう。
「最近のベストは有能です!」
「え、そんなにあるの?」
「相馬さん、セクハラです」
仄かに頬を赤く染めた小鳥遊が困った様にそう口にし、佐藤が今度はフライパンで相馬を殴った。
「紛らわしい」
不機嫌そうな佐藤を前に、京は困った様に笑った。
『場当たりがおして…約束の面接時間に間に合わなそうだったんで、鞄だけ持って衣装のまんま来ちゃいました』
「何で、女だと言わない」
『間違えられてるとは思わず』
「ホールの制服は」
『あんまり深く考えてませんでした』
呆れた様に溜め息をついた佐藤さんは“おい”と杏子さんに声を掛けた。
「客が誤解する…制服、女もん出してやれ」
「あぁ、そうだな」
「おい、着替えて来い」
『因みに…これウィッグなんですが』
「全部取って来い」
ピ──ン、ポ────ン…
決して静かでは無かったキッチンに、今度はそう聞き覚えのある音が響いた。
ピンポーンって…
「「「「お客さん!!!」」」」
青くなってそう叫んだホールスタッフの四人は、口々に何かを口にしながらホールへと走って行った。何て慌しい…
『そういえば、さっき男性客がどうのって言ってましたね』
「あぁ」
『この店大丈夫なんですか?』
「ダメだな」
佐藤は言い切った。
そして京は、困った様に小さく乾いた笑いをもらした。
なんだかな…
ここは考えていたものと大分違う気がする…
1/1ページ