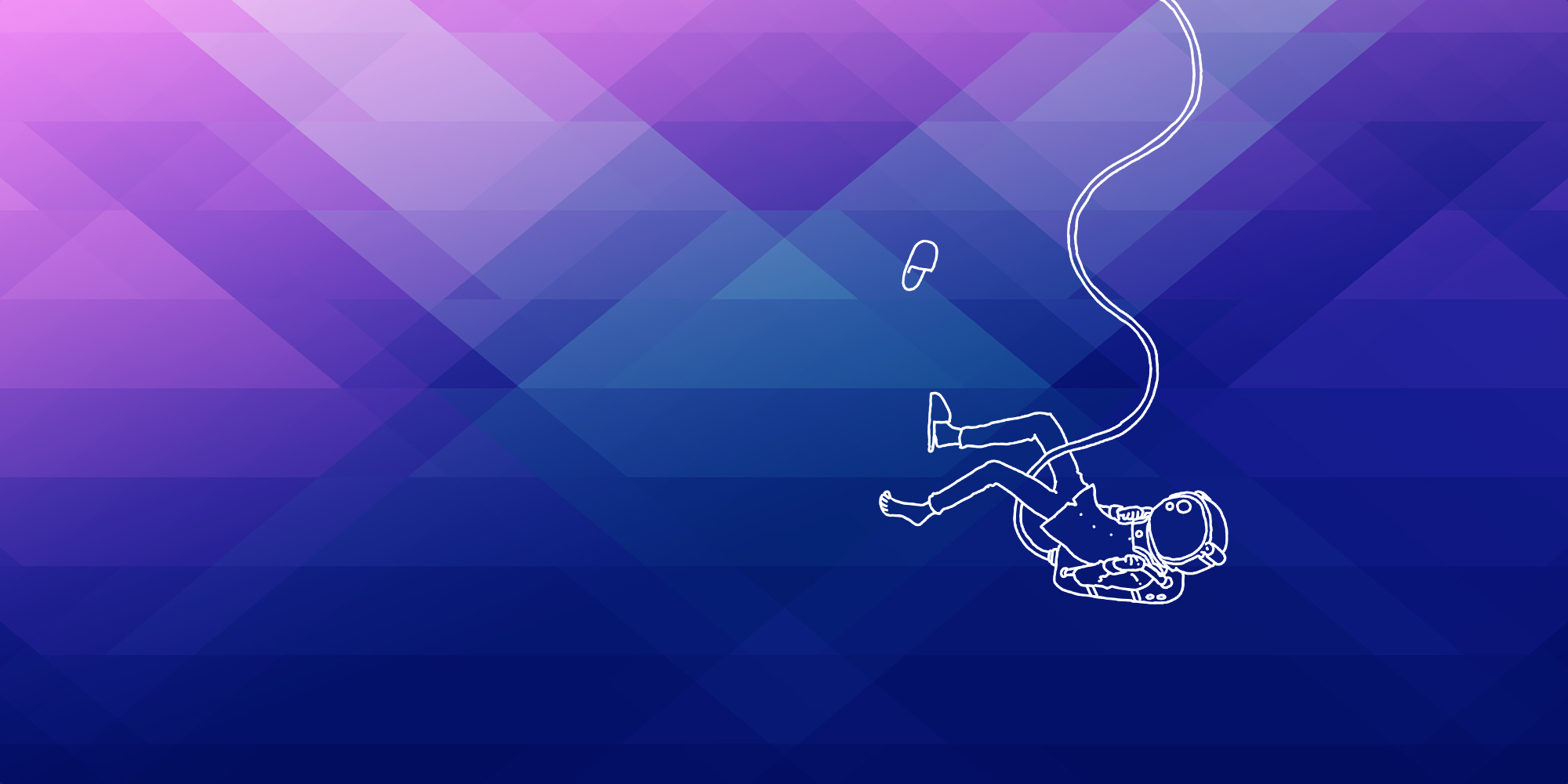究極と呼ばれたコンピューター
コンピューターはいよいよ熟考した。まず大学のコンピューターからこの研究室の研究の進捗状況と父親の性格が調べられ、息子が留年することによって、父親の研究にどのような影響が出るかの推論がなされた。
調査はその研究室の学生の単位の状況、性格、その学生達がよく行く食堂の定食の今後1カ月間のメニューの予測にまで及んでいた。そしてまた、貴重な数秒が失われ、大都市に何千店とある銀行などの金融関係のコンピューターがすべて動作を停止した。
この学生を留年させてはいけない。留年した場合、父親の研究が停滞し、この究極のコンピューター自身の評判を落とすことになる。まずい。
コンピューターはいよいよ真剣に解決策を検討していった。コンピューターは今からのフル稼働のために大都市に供給していた電力をすべて自分に振り向けた。当然ながら都市は一気に停電してしまった。
そして1分余りの時間が流れた。それは究極のコンピューターにとってはほとんど悠久ともいえる時間だった。コンピューターは修復に1年はかかろうかという被害をものともせず、満足げに通常の動作に戻っていった。
「お待たせしました。解答を打ち出します。」
印字装置が軽快な印字音を立てて数行の数式を打ち出した。
俺はやっとの思いで声を上げたくなるのを抑えた。
すでに俺の目には、親父の研究室の本棚も分厚いコンクリートの壁も見えておらず、紺碧の海と海風に砕け散る波頭と、波に照り返す光をバックにシルエットとなって駆けるギャルの姿が映っていた。俺は親父に挨拶もせず、T101番教室へとダッシュした。
調査はその研究室の学生の単位の状況、性格、その学生達がよく行く食堂の定食の今後1カ月間のメニューの予測にまで及んでいた。そしてまた、貴重な数秒が失われ、大都市に何千店とある銀行などの金融関係のコンピューターがすべて動作を停止した。
この学生を留年させてはいけない。留年した場合、父親の研究が停滞し、この究極のコンピューター自身の評判を落とすことになる。まずい。
コンピューターはいよいよ真剣に解決策を検討していった。コンピューターは今からのフル稼働のために大都市に供給していた電力をすべて自分に振り向けた。当然ながら都市は一気に停電してしまった。
そして1分余りの時間が流れた。それは究極のコンピューターにとってはほとんど悠久ともいえる時間だった。コンピューターは修復に1年はかかろうかという被害をものともせず、満足げに通常の動作に戻っていった。
「お待たせしました。解答を打ち出します。」
印字装置が軽快な印字音を立てて数行の数式を打ち出した。
俺はやっとの思いで声を上げたくなるのを抑えた。
すでに俺の目には、親父の研究室の本棚も分厚いコンクリートの壁も見えておらず、紺碧の海と海風に砕け散る波頭と、波に照り返す光をバックにシルエットとなって駆けるギャルの姿が映っていた。俺は親父に挨拶もせず、T101番教室へとダッシュした。