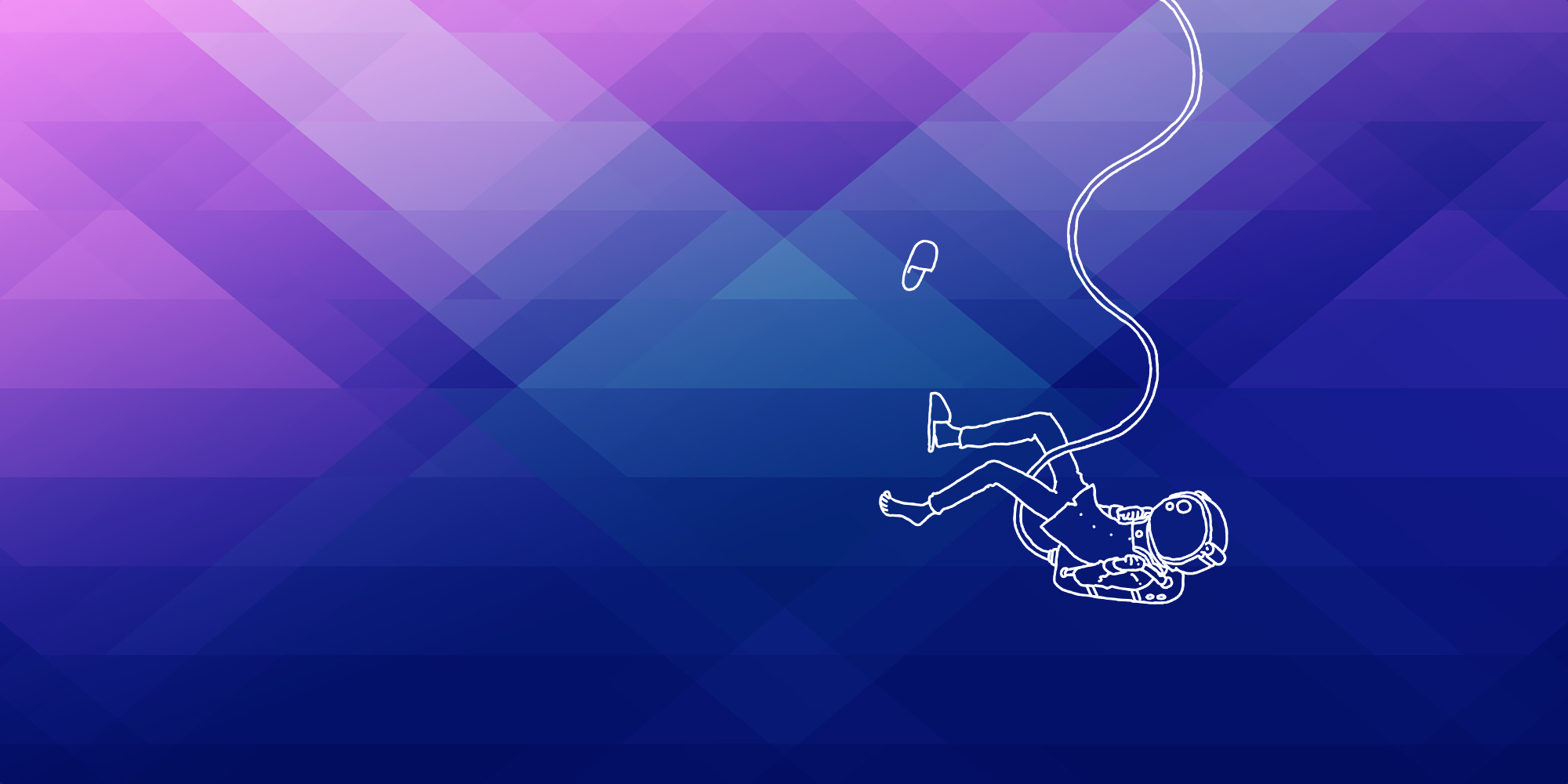ビクトリーラーメンマンシリーズ第1弾 誕生
「これはおれの大好物だ。学生の時からずっと食べていた。ほかの種類のデザートも相当食ったが、特にゼリーは好きでね。会社でもこの甘いものへの執着と舌を買われて、今は食品会社の調査課にいる。あんた、こんな缶詰を自然食品と偽って商売していたら手が後ろに回るよ。早くやめることだな。」
甲斐はゼリーを食べ終え、満足そうにゲップをして「料理はうまいけどね」と、ぶつぶつ言いながらボーイを眺めた。ボーイはがっくりと肩を落として一回り小さくなったように見えた。
「すみません。許してください。当然お代は頂きませんし、お土産も差し上げますから、どうぞ警察には言わないでください。」
ボーイは今にも泣き出しそうな顔になって頼んだ。甲斐はボーイがかわいそうに思え、いやむしろ料理がうまかったので気が大きくなっていたためかも知れない。
「ああ、別に迷惑を被ったわけでもないし、黙っといてやるよ。」と投げやりに答えた。
ボーイはおいおいと泣き崩れながら、付け加えた。
「しかし、こうも見事に見破られたのは、この店を開いて以来初めてです。さぞ優れた会社の方なのでしょう。よろしければどちらの会社の方から教えいただけませんか。」
甲斐は褒められたので気分を良くし、やや紅潮して答えた。
「あまり口外してもらうと困るのだが、まあいいか。VRMマークでおなじみ、ビクトリー・ラーメン食品産業さ。今度からうちの会社のも使ってほしいな。」
ボーイは、ははーっとひれ伏しながら、「必ず使わせてもらいます。」とつぶやいていた。
甲斐はゼリーを食べ終え、満足そうにゲップをして「料理はうまいけどね」と、ぶつぶつ言いながらボーイを眺めた。ボーイはがっくりと肩を落として一回り小さくなったように見えた。
「すみません。許してください。当然お代は頂きませんし、お土産も差し上げますから、どうぞ警察には言わないでください。」
ボーイは今にも泣き出しそうな顔になって頼んだ。甲斐はボーイがかわいそうに思え、いやむしろ料理がうまかったので気が大きくなっていたためかも知れない。
「ああ、別に迷惑を被ったわけでもないし、黙っといてやるよ。」と投げやりに答えた。
ボーイはおいおいと泣き崩れながら、付け加えた。
「しかし、こうも見事に見破られたのは、この店を開いて以来初めてです。さぞ優れた会社の方なのでしょう。よろしければどちらの会社の方から教えいただけませんか。」
甲斐は褒められたので気分を良くし、やや紅潮して答えた。
「あまり口外してもらうと困るのだが、まあいいか。VRMマークでおなじみ、ビクトリー・ラーメン食品産業さ。今度からうちの会社のも使ってほしいな。」
ボーイは、ははーっとひれ伏しながら、「必ず使わせてもらいます。」とつぶやいていた。