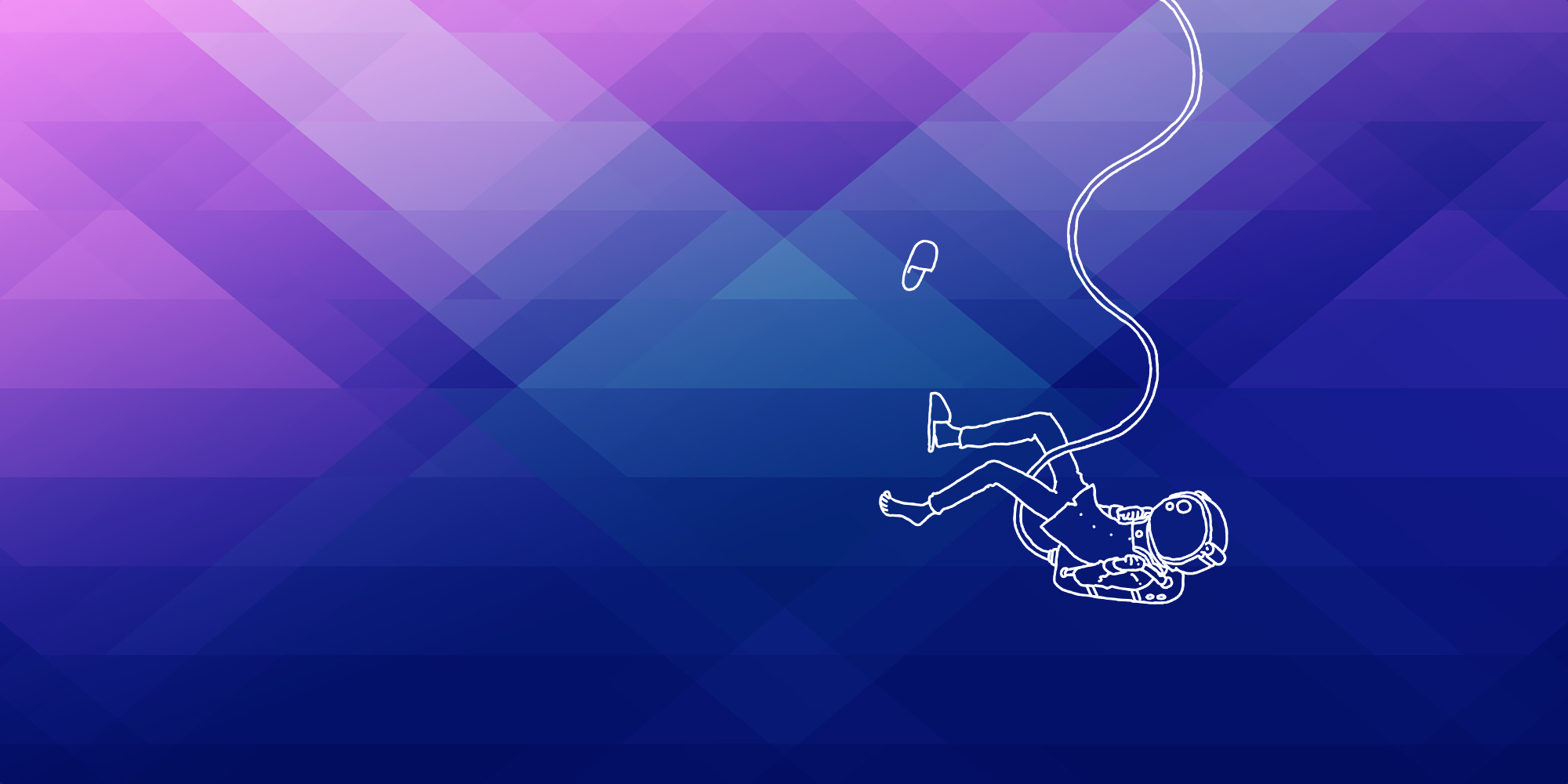ビクトリーラーメンマンシリーズ第5弾 渡り鳥
俺は、わずかな肉をかじり終わり、さて店主になんと御礼を言ったものかと逡巡していると、突然、景色が一変した。俺はなぜか屋外にいて、目の前にはどこかで見たことのある、ローマ彫刻が中央にある噴水の前のベンチに座っていた。
「ここはどこだ・・・。居酒屋で飲んでいたはずなのに・・・。」
俺はあまりのことに言葉を失った。これは夢ではないだろうかと思ったが、噴水の周りを歩く人々ははっきり見え、噴水の音も夢とは思えなかった。そして、俺はこの場所のことを思い出した。ここは俺が学生時代を過ごしたキャンパスだ。しかもこのベンチ、忘れもしない。彼女から別れを告げられたベンチだ。俺は、彼女に呼び出されてこのベンチで待っていたのだ。そして、彼女は少し遅れてやってきて、別れを告げたのだ。青春時代の苦い思い出だった。
「待った。ごめんね。」
彼女だ。記憶の通り、ポニーテールにニットを来た彼女がやってきた。久しぶりに見たが、やはりかわいい。しかし、記憶の通りならこれは別れを告げられたシーンだ。なぜこんなシーンを見ているのだろう。やはり夢なのだろうか。俺には全く理解できなかった。しかし、俺は理解できないまま、俺の意思とは関係なく彼女に答えていた。
「いや、今来たところだから。それより大事な話って何。」
俺は大事な話が何かはよく知っている。彼女は俺が優柔不断だからもう付き合えないと言うのだ。
「そうだね。もったいぶってもいけないので、単刀直入に言うね。甲斐君とは何回かデートして、少し仲良くなったって思ってるんだけどさ、私って優柔不断でしょ。でも、甲斐君も優柔不断じゃない。二人でいると楽しいんだけど、このまま楽しい時間だけが過ぎていくようで、先が見えないんだよね。だからこれ以上深入りせず、前のように友達に戻ったほうがいいんじゃないかと思ってさ。どう。」
彼女は「どう」と言っているが、彼女の中では結論は出ていたはずだ。ここで俺が何か言っても無駄なだけだ。当時はそう思ったし、今もその判断が変わるわけではない。彼女と別れるのは俺にとっては残念で大変悲しいことだったが、当時はその素振りを見せることも何か格好が悪いと思っていた。今の俺なら、格好悪くても、交際を続けるよう頼んでみるかもしれない。
「そうだねー。そのほうがいいかもしれないね。二人でいても色んなことが決められないもんね。」
俺は心と裏腹な返事をした。平静を装っていたが、心の中では大泣きしていた。
「良かったー。なんか、ごめんね。でも、嫌いになったわけじゃないからね。また、みんなで遊ぼうね。じゃあね。」
彼女は明るく去っていった。彼女にとって、俺はその程度ものだったのだろう。俺は、ベンチに座ってうつむいたまま涙を流していた。
「ここはどこだ・・・。居酒屋で飲んでいたはずなのに・・・。」
俺はあまりのことに言葉を失った。これは夢ではないだろうかと思ったが、噴水の周りを歩く人々ははっきり見え、噴水の音も夢とは思えなかった。そして、俺はこの場所のことを思い出した。ここは俺が学生時代を過ごしたキャンパスだ。しかもこのベンチ、忘れもしない。彼女から別れを告げられたベンチだ。俺は、彼女に呼び出されてこのベンチで待っていたのだ。そして、彼女は少し遅れてやってきて、別れを告げたのだ。青春時代の苦い思い出だった。
「待った。ごめんね。」
彼女だ。記憶の通り、ポニーテールにニットを来た彼女がやってきた。久しぶりに見たが、やはりかわいい。しかし、記憶の通りならこれは別れを告げられたシーンだ。なぜこんなシーンを見ているのだろう。やはり夢なのだろうか。俺には全く理解できなかった。しかし、俺は理解できないまま、俺の意思とは関係なく彼女に答えていた。
「いや、今来たところだから。それより大事な話って何。」
俺は大事な話が何かはよく知っている。彼女は俺が優柔不断だからもう付き合えないと言うのだ。
「そうだね。もったいぶってもいけないので、単刀直入に言うね。甲斐君とは何回かデートして、少し仲良くなったって思ってるんだけどさ、私って優柔不断でしょ。でも、甲斐君も優柔不断じゃない。二人でいると楽しいんだけど、このまま楽しい時間だけが過ぎていくようで、先が見えないんだよね。だからこれ以上深入りせず、前のように友達に戻ったほうがいいんじゃないかと思ってさ。どう。」
彼女は「どう」と言っているが、彼女の中では結論は出ていたはずだ。ここで俺が何か言っても無駄なだけだ。当時はそう思ったし、今もその判断が変わるわけではない。彼女と別れるのは俺にとっては残念で大変悲しいことだったが、当時はその素振りを見せることも何か格好が悪いと思っていた。今の俺なら、格好悪くても、交際を続けるよう頼んでみるかもしれない。
「そうだねー。そのほうがいいかもしれないね。二人でいても色んなことが決められないもんね。」
俺は心と裏腹な返事をした。平静を装っていたが、心の中では大泣きしていた。
「良かったー。なんか、ごめんね。でも、嫌いになったわけじゃないからね。また、みんなで遊ぼうね。じゃあね。」
彼女は明るく去っていった。彼女にとって、俺はその程度ものだったのだろう。俺は、ベンチに座ってうつむいたまま涙を流していた。