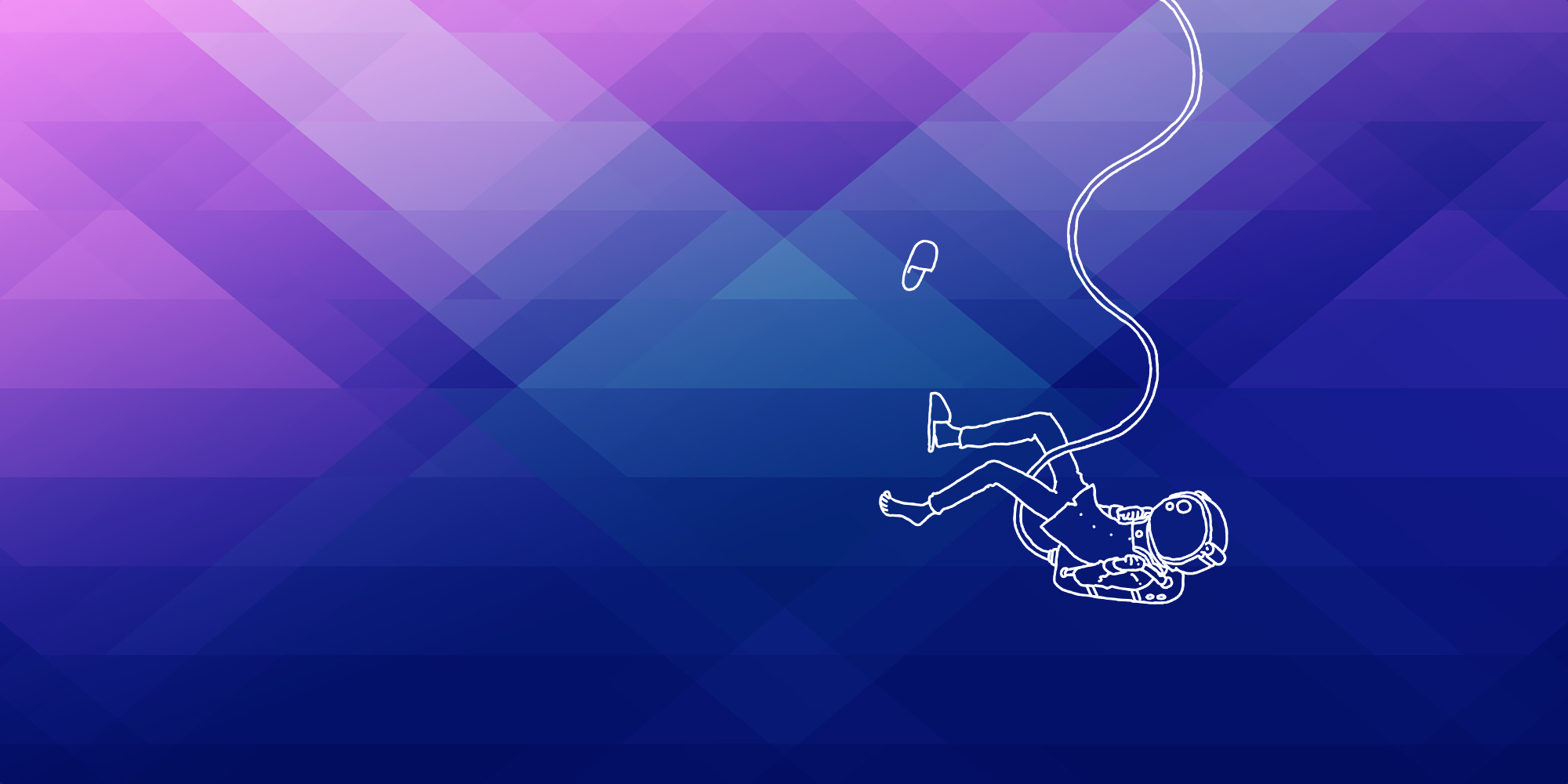ビクトリーラーメンマンシリーズ第4弾 火鍋ドラゴン
「はい、いらっしゃい。」
店主は人のよさそうな老人で威勢よく出向えてくれた。店構えこそ他の店と同じような感じだったが、店内はキッチンスタジアムのように、奥の方の少し低いところにあるオープンキッチンが、8つほどのすべてのテーブルから見えるように作られていた。いくつかのテーブルにはすでに客が座っており、湯気の上がった熱々の真っ赤なスープを食べている。
「お客さん、何にするね。お勧めは当店一推しのドラゴンスープだよ。」
店主はキッチンから出ることなく、こちらに話しかけてきた。
「じゃ、それを1つお願いします。」
俺は迷うことなく店主のお勧めに従った。まずはオーソドックスな料理を食べて、徐々に珍しい食材がないか探っていくのが常套手段だ。
キッチンには3つのコンロがあり、すべて火がついているようだった。店主はその1つに大きな鍋を置き、次々と食材を投げ込んでいった。そして鍋ふりをすると鍋縁から大きく炎が上がった。また同時に、使っていないコンロからも天井に向かって数メートル火柱が上がった。
「おー!」
なんと派手な。熱気で頬が熱くなる。他の客もこの炎の演出を楽しみながら、食事をしているようだ。熱い炎を感じつつ、辛い鍋を食べて汗をかく。これぞ火鍋の醍醐味ということだろう。何回かのファイヤーの後、テーブルに持って来られた、まだグツグツ言っているドラゴンスープに俺は挑んだ。
「辛ーっ!」
予想にたがわず、辛さは相当なものだった。調理の炎ですでに顔が熱くなっていたが、スープを飲むとすべての汗腺から汗が噴き出すようだった。しかし、辛美味いというのか、辛さの中にも他のスパイスや出汁も感じられてなかなかの味であった。
店主は人のよさそうな老人で威勢よく出向えてくれた。店構えこそ他の店と同じような感じだったが、店内はキッチンスタジアムのように、奥の方の少し低いところにあるオープンキッチンが、8つほどのすべてのテーブルから見えるように作られていた。いくつかのテーブルにはすでに客が座っており、湯気の上がった熱々の真っ赤なスープを食べている。
「お客さん、何にするね。お勧めは当店一推しのドラゴンスープだよ。」
店主はキッチンから出ることなく、こちらに話しかけてきた。
「じゃ、それを1つお願いします。」
俺は迷うことなく店主のお勧めに従った。まずはオーソドックスな料理を食べて、徐々に珍しい食材がないか探っていくのが常套手段だ。
キッチンには3つのコンロがあり、すべて火がついているようだった。店主はその1つに大きな鍋を置き、次々と食材を投げ込んでいった。そして鍋ふりをすると鍋縁から大きく炎が上がった。また同時に、使っていないコンロからも天井に向かって数メートル火柱が上がった。
「おー!」
なんと派手な。熱気で頬が熱くなる。他の客もこの炎の演出を楽しみながら、食事をしているようだ。熱い炎を感じつつ、辛い鍋を食べて汗をかく。これぞ火鍋の醍醐味ということだろう。何回かのファイヤーの後、テーブルに持って来られた、まだグツグツ言っているドラゴンスープに俺は挑んだ。
「辛ーっ!」
予想にたがわず、辛さは相当なものだった。調理の炎ですでに顔が熱くなっていたが、スープを飲むとすべての汗腺から汗が噴き出すようだった。しかし、辛美味いというのか、辛さの中にも他のスパイスや出汁も感じられてなかなかの味であった。