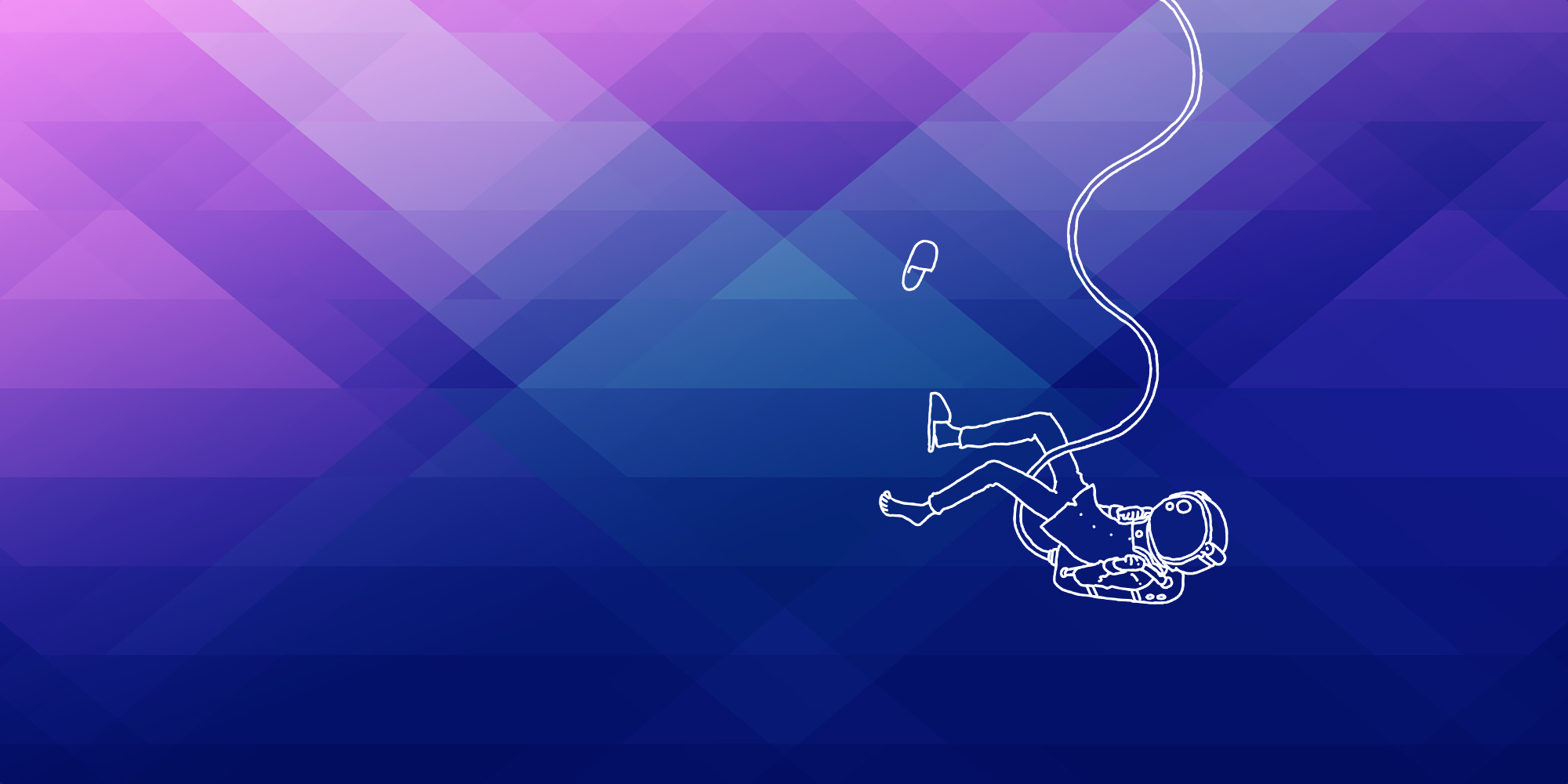虹の贈り物
この植民星CDF294の首都にいる惑星代表あるいは移民管理局、警察でも何でもいいが、とにかく連絡が取れればいいんだ。これ以上危険を冒して、わざわざその場所に出向く必要はない。
「通信機ってなあに?」
少年はかなり近くまでよってきて、イリウスを見上げながら尋ねた。
「ネットワーク端末とか、電話とか、トランシーバーとか、無線とか、見たことないかい。」
「知らない。」
少年はあっけなく答えた。
イリウスは、しばし遅れて事態の深刻さに気付いた。少年は通信機もトランシーバーも、電話でさえも知らない。物事のわからない年齢ではないと思われるので、たぶん家にないのだろう。まさか、通信手段がないとは……。イリウスはあきらめずに質問を続けた。
「お友達とか、誰か持っていないのか?」
「持ってない。」
さて、どうしたものか、イリウスは途方に暮れた。とりあえず、少年の親にここまで来てもらうか。しかし、少年の言葉が正しければ、少年の村に通信手段は一切ない。シャトルの通信機が使えればこんな苦労はないのだが…。しかしそれをいうなら、母船の通信機が使えれば、そもそもシャトルでこの星に着陸する必要もなかったのだ。
「困ったな。」
イリウスは思わず心のうちを言葉にしてしまった。
「おじさん一人で来たの。」
少年はまだ摩擦熱の冷め切っていないシャトルの外壁をちょっと触ってみながら、顔を上げずに尋ねた。
「いや、もう一人いるよ。二人できたんだ。お空にはもっと多くの友達がいるんだよ。」
「ふーん。もう一人の人はどこ。」
「シャトルの中にいるよ。呼んで来ようか。ちょっと待っててくれるかな。どこにも行かないでね。」
イリウスは少年がかすかにうなづいたのを見届けて、エアロックの外扉を閉めた。エアロックは構造的に外扉が完全に閉じないと内扉は開かない。
再び外扉を開けた時に少年がいてくれることを願って、イリウスはアカバを呼びに行くことにしたのだ。少年と話してみたが、現在手詰まりであり、解決の糸口が見えない。
こんなときにアカバなら、何かいい知恵を出してくれるに違いない。そして仮にも船長であるアカバに出てきてもらう絶好の機会でもある。相手が子供であろうと、何であろうと船長が第一に話すのが規則であった。
「通信機ってなあに?」
少年はかなり近くまでよってきて、イリウスを見上げながら尋ねた。
「ネットワーク端末とか、電話とか、トランシーバーとか、無線とか、見たことないかい。」
「知らない。」
少年はあっけなく答えた。
イリウスは、しばし遅れて事態の深刻さに気付いた。少年は通信機もトランシーバーも、電話でさえも知らない。物事のわからない年齢ではないと思われるので、たぶん家にないのだろう。まさか、通信手段がないとは……。イリウスはあきらめずに質問を続けた。
「お友達とか、誰か持っていないのか?」
「持ってない。」
さて、どうしたものか、イリウスは途方に暮れた。とりあえず、少年の親にここまで来てもらうか。しかし、少年の言葉が正しければ、少年の村に通信手段は一切ない。シャトルの通信機が使えればこんな苦労はないのだが…。しかしそれをいうなら、母船の通信機が使えれば、そもそもシャトルでこの星に着陸する必要もなかったのだ。
「困ったな。」
イリウスは思わず心のうちを言葉にしてしまった。
「おじさん一人で来たの。」
少年はまだ摩擦熱の冷め切っていないシャトルの外壁をちょっと触ってみながら、顔を上げずに尋ねた。
「いや、もう一人いるよ。二人できたんだ。お空にはもっと多くの友達がいるんだよ。」
「ふーん。もう一人の人はどこ。」
「シャトルの中にいるよ。呼んで来ようか。ちょっと待っててくれるかな。どこにも行かないでね。」
イリウスは少年がかすかにうなづいたのを見届けて、エアロックの外扉を閉めた。エアロックは構造的に外扉が完全に閉じないと内扉は開かない。
再び外扉を開けた時に少年がいてくれることを願って、イリウスはアカバを呼びに行くことにしたのだ。少年と話してみたが、現在手詰まりであり、解決の糸口が見えない。
こんなときにアカバなら、何かいい知恵を出してくれるに違いない。そして仮にも船長であるアカバに出てきてもらう絶好の機会でもある。相手が子供であろうと、何であろうと船長が第一に話すのが規則であった。