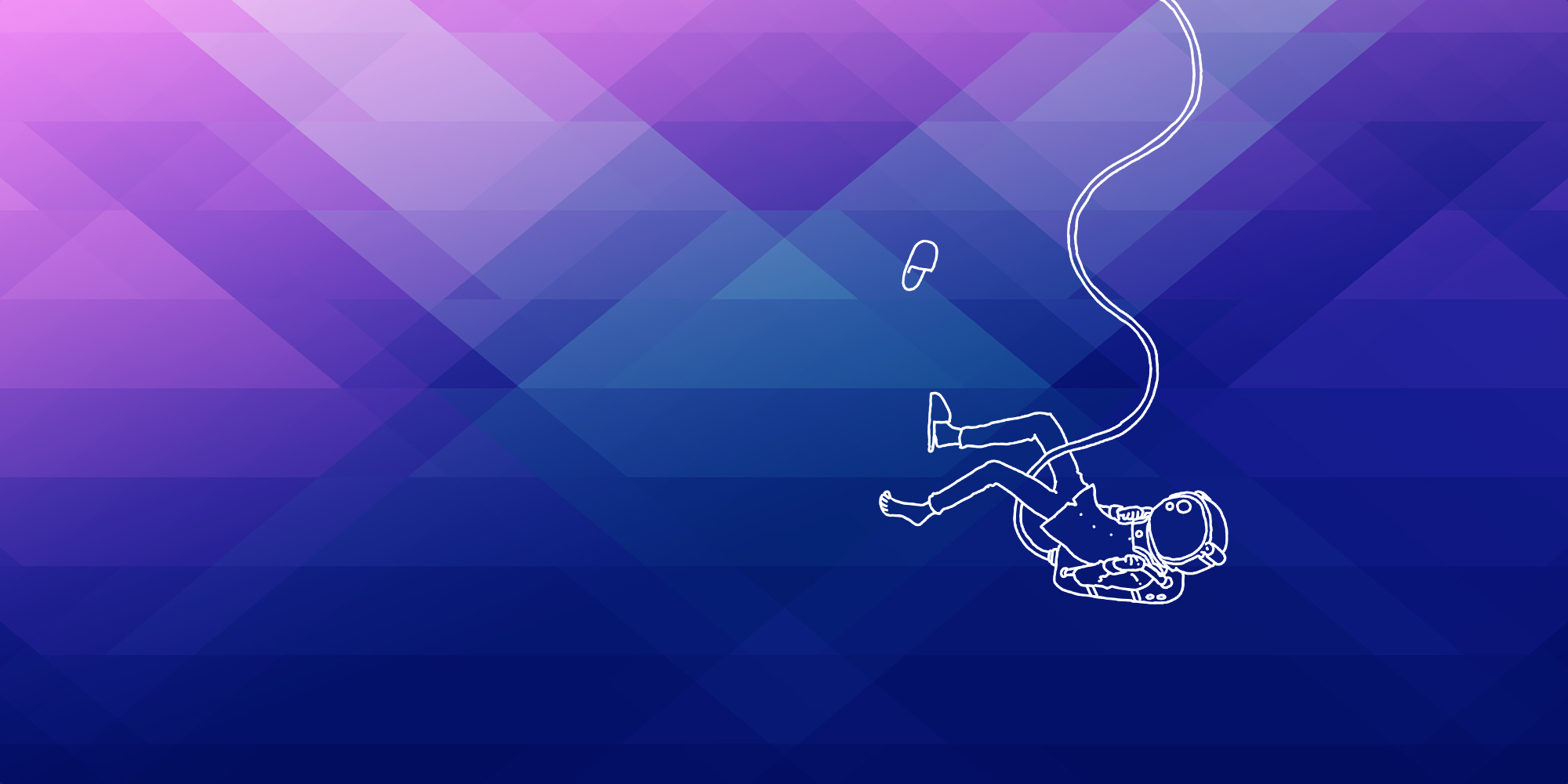虹の贈り物
しばらく時間が経過した後、アカバはコクピットの中の異様な静けさの中で気がついた。コクピットはわずかな赤色の非常燈が灯り、ほのかに見渡すことができた。すでに対衝撃姿勢は解除されて、風船は自動的に格納され、操縦席も機関士席も通常の状態に戻っていた。
「イリウス、大丈夫か?」
「うーん。何とか生きてるようだ。そっちこそ怪我はないか?船長。」
イリウスも同じころ目覚めたようで、力なく答えた。
「こっちも大丈夫のようだ。まだ運命の女神は俺たちを見捨ててないようだ。」
アカバはシャトルの計器類を見渡しながらつぶやいた。
「あんなにひどく着陸した割には損傷はほとんどないようだな。たいした宇宙船だ。まあ、俺も数年前に学校の講義で何回かシュミレーション着陸しただけだから、実際の着陸がどのようなものかは知らないが…。」
移民用大型航宙船においては、産業や科学の発達というものはほとんど皆無だったが、代わりにすべての乗組員は生涯さまざまな学習を行うことが義務付けられていた。
乗組員の文化や技術のレベルを落とさないことと、モラルを下げないことが移民の最大の課題だった。それぞれの乗組員は学者としてまた技術者としていくつかの分野のスペシャリストとなることが義務づけられ、殊に母船やシャトルの操縦と整備は全員の必須科目であった。
「イリウス、大丈夫か?」
「うーん。何とか生きてるようだ。そっちこそ怪我はないか?船長。」
イリウスも同じころ目覚めたようで、力なく答えた。
「こっちも大丈夫のようだ。まだ運命の女神は俺たちを見捨ててないようだ。」
アカバはシャトルの計器類を見渡しながらつぶやいた。
「あんなにひどく着陸した割には損傷はほとんどないようだな。たいした宇宙船だ。まあ、俺も数年前に学校の講義で何回かシュミレーション着陸しただけだから、実際の着陸がどのようなものかは知らないが…。」
移民用大型航宙船においては、産業や科学の発達というものはほとんど皆無だったが、代わりにすべての乗組員は生涯さまざまな学習を行うことが義務付けられていた。
乗組員の文化や技術のレベルを落とさないことと、モラルを下げないことが移民の最大の課題だった。それぞれの乗組員は学者としてまた技術者としていくつかの分野のスペシャリストとなることが義務づけられ、殊に母船やシャトルの操縦と整備は全員の必須科目であった。